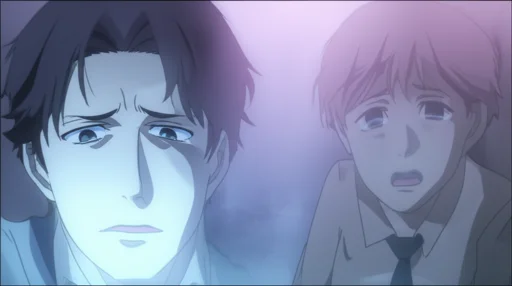第一章 蠢く瑕疵
柏木湊(かしわぎ みなと)の左腕には、誰にも見せたことのない秘密があった。肘から手首にかけての一部分、そこだけが彼の皮膚ではなかった。まるで色の悪い粘土を塗りたくったかのように、肌理(きめ)も毛穴もなく、ぬらりとした光沢を帯びている。それは三年ほど前から、小さな痣のように現れ、徐々にその領域を広げてきた。
医者には行かなかった。行けなかった、と言う方が正しい。なぜなら、それは時折、微かに蠢くのだ。筋肉の痙攣とは明らかに違う、内側から何かが盛り上がるような、意思を持った蠕動。その感触は、皮膚の下を巨大な蛭が這い回るようで、湊はたびたび鳥肌を立てては、長袖のシャツの袖口を強く握りしめた。
校正者である湊の仕事は、静かで孤独だ。一日中、モニターの光を浴びながら、赤字の入ったゲラと向き合う。キーボードを叩く右手の規則正しい音だけが、時間が流れていることを教えてくれる。左腕は、常に机の下に隠されていた。同僚と昼食をとる時も、打ち合わせの時も、彼は決して左腕をテーブルの上に出さなかった。夏でも長袖を着続ける彼を、同僚たちは奇異の目で見ていたが、誰もその理由を問いただしはしなかった。湊が自ら、人を遠ざける壁を築いていたからだ。
その夜、湊はいつものように一人、蛍光灯が白々と照らす部屋で夕食を済ませていた。レトルトのカレーは、味気なく舌の上を滑り落ちていく。静寂の中、不意に左腕が大きく脈打った。びくん、と。それは今までで最も強い動きだった。思わずスプーンを取り落とし、床に甲高い音を立てる。
湊は恐る恐る、シャツの袖をまくり上げた。
粘土のような皮膚が、波打っていた。中央がゆっくりと隆起し、小さな窪みを作る。まるで、それが「眼」を開けようとしているかのように。湊は息を呑んだ。恐怖で声も出ない。それは病気などではない。自分の身体の一部が、自分のものでなくなっていく。未知の何かに乗っ取られていく、絶対的な恐怖。
汗がこめかみを伝う。瑕疵(かし)と呼んでいたそれは、もはや瑕疵などという生易しいものではなかった。それは、湊の内で育ち続ける、悪性の「何か」だった。彼はその「何か」に心当たりがあった。三年前のあの日、彼が口にした、取り返しのつかない嘘。彼の人生を、そしてもう一人の人間の人生を、根底から歪めてしまった、あの黒い言葉。その記憶が蘇るたびに、腕の蠢きは激しくなるような気がしていた。
第二章 後悔の胚胎
粘土質の領域は、さらにその範囲を広げていた。今や手首を越え、指の付け根にまで達しようとしている。そして、その表面には 희미하게、人の顔のような凹凸が浮かび始めていた。閉じられた瞼、固く結ばれた唇。それは苦悶の表情を浮かべているように見えた。
湊は夜ごと、同じ夢にうなされた。才能豊かで、太陽のように笑う親友、圭介の夢だ。彼らは同じデザイン事務所で働いていた。圭介の才能は群を抜いており、誰もが彼の未来を疑わなかった。湊もその一人だったはずだ。しかし、心の奥底で燻っていたのは、焦がれるような嫉妬だった。
決定的な出来事は、ある大きなコンペで起きた。圭介の提出したデザイン案は画期的で、誰もが彼の勝利を確信していた。しかし、湊は締め切り前夜、圭介のデータを盗み見て、そこに致命的な欠陥があるかのように見せかける偽の情報を、匿名でクライアントにリークしたのだ。「彼のデザインは、他社の未公開特許を侵害している」――それは、湊が作り上げた完全な嘘だった。
結果、圭介の案は選考から外され、彼は業界内で盗作の疑いをかけられた。説明しようにも、湊が巧妙に仕組んだ状況証拠が彼の首を締め、圭介は誰にも信じてもらえなかった。憔悴しきった彼は、やがて事務所を辞め、故郷に帰ると言って湊の前から姿を消した。それ以来、連絡は取れていない。
「お前のせいじゃない。俺が未熟だっただけだ」
最後に圭介が絞り出した言葉が、今も湊の耳にこびりついている。その優しさこそが、最も鋭い刃となって湊の良心を切り刻み続けていた。
湊は、震える手でパソコンを開いた。「嘘」「肉体」「変質」――そんな支離滅裂な単語を検索窓に打ち込む。いくつものオカルトサイトや都市伝説のフォーラムがヒットした。その中に、一つの記述を見つけた。
『偽肉(ぎにく)。古くから伝わる呪いの一種。人がついた重大な嘘や、それによって生まれた強い後悔の念が、その者の肉体の一部を蝕み、やがて分離する。嘘が他者を深く傷つけるものであればあるほど、偽肉はより醜悪で、明確な形を取るという。それは、嘘の重さを物理的に背負わせるための、逃れられない罰なのだ』
――罰。
湊は画面を睨みつけ、全身から血の気が引いていくのを感じた。左腕の蠢きが、まるでその記述に応えるかのように、一層激しくなった。これは呪いだ。自分が犯した罪の、物理的な顕現なのだ。腕に浮かび上がった苦悶の表情が、圭介のそれに重なって見えた。このままでは、この腕は、完全に圭介の顔をした「何か」になってしまうのではないか。そして、その時、自分はどうなってしまうのだろう。恐怖が、冷たい霧のように部屋を満たしていく。
第三章 分離する良心
嵐の夜だった。窓ガラスを叩きつける雨音と、遠くで轟く雷鳴が、湊の心臓の鼓動と重なっていた。左腕が、焼け付くように熱い。見れば、粘土質の皮膚が激しく脈動し、その表面が引き裂かれようとしていた。皮膚と肉の境界から、じわりと血が滲む。
「う、ああ……っ!」
激痛に耐えきれず、湊は床に蹲った。肉が裂ける生々しい音。骨がきしむような鈍い痛み。まるで、自分の腕が無理やり引き千切られていくかのようだ。彼は絶叫し、意識が遠のきかけた。
どれくらいの時間が経っただろうか。嵐が嘘のように静まり、部屋には雨だれの音だけが響いていた。恐る恐る目を開けた湊の視界に、信じられない光景が飛び込んできた。
床の上に、「それ」がいた。
肘から先ほどの大きさで、歪な人型をしていた。表面はやはり生乾きの粘土のようで、圭介の面影を宿した顔は、深い苦悩に歪んでいる。それは、湊が想像したような、襲いかかってくる怪物ではなかった。ただ、部屋の隅で小さく丸まり、か細く震えているだけだった。
湊は自分の左腕を見た。そこには、生々しい傷跡だけが残り、あの不気味な蠢きは消え失せていた。代わりに、失われた腕の重みが、幻肢痛のようにずしりとのしかかる。
恐怖と安堵と混乱が入り混じる中、湊はゆっくりと「それ」に近づいた。床を濡らすのは、湊の腕から流れた血と、そして「それ」が流しているらしい、粘り気のある涙だった。
その時、か細い声が聞こえた。湊の頭の中に直接響くような、思念の声だった。
『……たすけて』
湊は息を呑んだ。声の主は、目の前の「偽肉」だった。それは、怒りや憎しみではなく、ただ純粋な救いを求める声だった。
『くるしい……。あの人が、くるしんでいる』
湊は悟った。雷に打たれたような衝撃とともに、全てを理解した。
これは、罰ではあった。しかし、単なる罰ではなかった。この偽肉は、湊が嘘によって傷つけた圭介の「苦しみ」そのものを映し出す鏡であり、同時に、湊自身の心の奥底に押し込められていた「罪悪感」と「贖罪の念」――彼の失われた良心そのものだったのだ。
恐怖の対象だと思っていたそれは、怪物などではなかった。それは、湊自身の一部。助けを求める、歪んでしまった彼の良心だった。襲ってくる恐怖ではなく、救いを求める悲痛な叫び。その事実は、湊の価値観を根底から覆した。彼は、自分自身から目を背けてきたのだ。この震える塊こそが、彼が無視し続けた真実の姿だった。
第四章 贖罪の伴侶
湊は、震える「それ」の前に膝をついた。もう恐怖はなかった。あるのは、途方もない後悔と、そして、今ここで向き合わなければならないという、厳粛な覚悟だけだった。
「圭介は……今、どこにいるんだ?」
偽肉は、苦しげに顔を歪ませながら、一つの方向をぼんやりと示した。北の方角だった。圭介の故郷がある方角だ。
『……あいたい。あやまりたい』
それは、偽肉の声であり、湊自身の心の声だった。三年間、ずっと蓋をしてきた本心だった。
湊は立ち上がった。窓の外は、雨上がりの澄んだ空気が漂っていた。彼は、自分の空っぽになった左腕と、床で震えるもう一人の自分を見比べる。これから自分が為すべきことは、一つしかなかった。
彼は部屋に戻ると、簡単な旅支度を始めた。着替え、財布、そして携帯電話。最後に、彼は床に転がっていた大きな布を手に取り、偽肉の前に差し出した。
「行こう。一緒に行くんだ」
偽肉は、おずおずと湊を見上げた。その歪んだ瞳に、一瞬、安堵の色が浮かんだように見えた。湊は、その不格好で、生暖かく湿った塊を、壊れ物を扱うようにそっと布で包み、右手で抱きかかえた。ずしりとした重み。それは、彼がこれから背負っていく罪の重さそのものだった。
ドアを開けると、朝の光が眩しく差し込んできた。世界は何も変わっていない。しかし、湊の中の世界は、完全に変わってしまった。
彼の贖罪の旅が、今、始まる。行方不明の親友を探し出し、この腕に抱いた良心の塊とともに、真実を告げるために。それがどれほど困難で、許されることのない道だとしても、もう彼は逃げないと決めた。恐怖の対象だった偽肉は、今や彼の唯一の「伴侶」だった。左腕の痛みと、腕に抱いた良心の重みだけが、彼の進むべき道を照らす、唯一の道標だった。