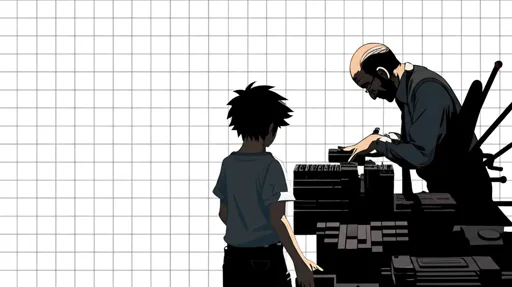第一章 錆びた鳥籠の客
水島湊の世界は、静かで、埃っぽく、そして他人の後悔で満ちていた。
神保町の裏路地にひっそりと佇む古書店『遠近洞(えんきんどう)』。その店主である湊には、秘密があった。彼には、人々が心の奥底に抱える「未練」が、古びたオブジェとして見えるのだ。それは誰の目にも映らず、湊だけが認識できる、いわば魂の澱(おり)のようなものだった。
通勤ラッシュの雑踏を歩くサラリーマンの背中には、使い古された野球のグローブがぶら下がっている。カフェで談笑する若い女性の足元には、割れたガラスの靴が転がっている。それらは実体を伴ってそこにあり、時に湊の足に触れることさえあったが、持ち主も、周囲の誰も、その存在に気づかない。湊はこの奇妙な能力を呪いのように感じ、他人との間に見えない壁を築いて生きてきた。古書に囲まれた静寂だけが、彼の心を慰めてくれるシェルターだった。
その日も、雨が街を灰色に染めていた。店先の軒を打つ雨音を聞きながら、湊がカウンターで古い洋書の修繕をしていると、ドアベルがちりんと鳴った。入ってきたのは、品の良い薄紫色のコートを着た小柄な老婆だった。白髪を綺麗にまとめ、その顔には深い皺が刻まれているが、背筋は凛と伸びている。
「いらっしゃいませ」
湊が顔を上げ、言葉を発した瞬間、息を呑んだ。老婆の胸元、ちょうど心臓のあたりから、古びて赤黒く錆びついた鳥籠が、まるでペンダントのようにぶら下がっていたのだ。それは拳ほどの大きさで、繊細な蔦の意匠が施されているが、その扉は固く閉ざされ、中には何もいない。空っぽの鳥籠は、老婆が呼吸するたびに、ぎしり、と軋むような幻聴を湊の耳に届けた。
これまで湊が見てきた数多の「未練」の中でも、これほどまでに重く、悲痛な存在感を放つものはなかった。彼は思わず目を逸らし、手元の本に視線を落とす。関わってはいけない。見てはいけない。心の警鐘が鳴り響く。
老婆は湊に一瞥もくれず、店内をゆっくりと歩き始めた。彼女の目的地は決まっているようだった。詩集の棚の前で足を止めると、一冊の古い本を手に取った。萩原朔太郎の初版本だ。彼女はそれを買おうとはせず、ただ表紙を撫で、数ページをめくっては、そっと棚に戻した。そして、何も言わずに店を出ていく。
ドアベルが再び鳴り、店内に静寂が戻る。しかし、湊の心には、あの錆びた鳥籠のイメージが焼き付いて離れなかった。空っぽのはずなのに、そこには声なき声で鳴く鳥の姿が見えるような気がした。雨は一層、その勢いを増していた。
第二章 遠い日の詩集
翌日も、その次の日も、老婆――名札から、近藤千代という名前だと湊は知った――は同じ時間にやって来た。そして、同じように萩原朔太郎の詩集を手に取り、静かにページをめくり、そして帰っていく。彼女の胸の鳥籠は、日を追うごとに錆を深め、その重みを増していくように湊には見えた。
三日目のことだった。いつものように詩集を棚に戻した千代が、ふと、カウンターにいる湊に声をかけた。
「このお店は、静かでいいですね」
その声は、澄んだ鈴の音のようだった。湊は驚いて顔を上げた。
「……ありがとうございます」
「あなたがお一人で?」
「ええ、まあ」
人付き合いを避けてきた湊にとって、客との会話は緊張を伴う。だが、千代の穏やかな眼差しは、不思議と彼の警戒心を解いた。
「昔、教師をしておりましてね。国語を教えていたんです」
千代は懐かしむように目を細めた。
「ある生徒が、この詩集が大好きで。放課後になると、いつも私のところにやって来ては、詩について語り合ったものです。才能のある、明るい子でした」
彼女の言葉の端々に、その生徒への深い愛情が滲んでいた。しかし、その愛情が深ければ深いほど、胸の鳥籠はより一層、重く軋むのだった。
「その子は……今も、詩を?」
湊は、尋ねずにはいられなかった。千代の表情が、ふっと曇る。
「さあ……。どうしているかしらね」
彼女はそう言って、寂しそうに微笑んだ。その笑顔は、湊の胸を締め付けた。彼女は何かを隠している。そして、その隠された真実こそが、この錆びた鳥籠の正体なのだと直感した。
湊は、彼女を助けたいと、柄にもなく思い始めていた。この忌まわしい能力が、初めて誰かのために使えるかもしれない。そんな考えが頭をよぎる。それは、数年前に最愛の妹・遥を事故で亡くして以来、凍りついていた彼の心に差し込んだ、微かな光のようだった。妹を失ったあの日から、この能力は始まった。そして、湊自身の胸にも、いつも正体不明の重たい塊が鎮座している。それは、どんな形をしているのか、彼自身にも見ることができなかった。ただ、冷たくて、硬い、錠前のような感触だけがあった。
その夜、湊は店の明かりを落とした後も、一人残って考え込んでいた。千代の「未練」を解き放つには、どうすればいいのか。まずは、彼女が語った「大切な生徒」について知る必要があった。手がかりは、萩原朔太郎の詩集と、「昔の教え子」という曖昧な情報だけだ。無謀な試みかもしれない。だが、湊は突き動かされるように、調査を始める決意を固めた。それは、千代のためであると同時に、自分自身の胸にある冷たい錠前と向き合うための、最初の戦いでもあった。
第三章 交差する追憶
湊の調査は、想像以上に難航した。千代がどの学校で教えていたのかも分からない。手当たり次第に近隣の学校の卒業アルバムを古書店仲間から借り受け、ページをめくる日々が続いた。しかし、手掛かりは一向に見つからない。
焦りが募り始めたある日、湊はふと、原点に立ち返った。萩原朔太郎の詩集だ。千代はなぜ、初版本にこだわっていたのだろう。何か特別な意味があるのかもしれない。彼は、懇意にしている郷土史家のもとを訪ねた。
「この詩集の初版本かい。昔、この近辺の女子校で、教材として使われていたことがあると聞いたことがあるな」
史家はあっさりと、光明となる情報を口にした。その女子校の名前は「私立藤ノ宮女学館」。数年前に廃校になったが、記録は市の公文書館に残っているはずだという。
湊はすぐに公文書館へ向かった。書庫のひんやりとした空気の中、彼は藤ノ宮女学館の職員名簿をめくった。そして、ついに「近藤千代」の名前を見つけ出した。国語科教諭。在職期間は、三十年以上に及ぶ。
次に、彼女が在職していた時期の卒業アルバムを閲覧する。ページをめくる指が、期待と不安で震えた。千代が話していた「才能のある、明るい子」。どんな顔をしているのだろうか。
そして、湊はあるページで、手を止めた。そこに写っていたのは、見間違えるはずもない、彼の妹、水島遥の笑顔だった。
時間が止まった。頭を鈍器で殴られたような衝撃が、全身を貫く。まさか。そんなはずはない。遥が、千代先生の教え子? 湊は震える手で、ページに記された名前を確認する。「水島遥」。間違いない。
遥は、高校二年の秋、下校途中に交通事故で命を落とした。あの日、彼女は少し帰りが遅くなると言っていた。塾の前に、学校で調べ物をすると。その「調べ物」とは、一体何だったのか。湊は今まで、深く考えたことすらなかった。
記憶の断片が、激流となって押し寄せる。詩が好きだった妹。部屋の本棚に、萩原朔太郎の詩集があったこと。時折、「千代先生」という名前を口にしていたこと。すべてが今、一本の線で繋がった。
湊は公文書館の古びた机に突っ伏し、声を殺して嗚咽した。千代の「未練」の正体が、津波のように彼に襲いかかった。あの鳥籠は、遥のことだったのだ。才能に溢れ、これから自由に羽ばたくはずだった妹。その未来を奪われたことへの後悔と自責の念が、あの重く錆びついた鳥籠を形作っていたのだ。
そして、最も残酷な事実が、湊を打ちのめした。千代は、湊がその遥の兄であることに、全く気づいていない。彼女はただ、兄妹とは知らずに、遥の面影が残る湊の古書店に、慰めを求めて通い続けていたのだ。運命のあまりの皮肉に、湊は言葉を失った。自分の胸にある冷たい「錠前」が、ぎりぎりと締め付けられるような激痛を感じた。
第四章 解錠の涙
店に戻った湊は、カウンターの奥で呆然と座り込んでいた。窓の外は、あの日と同じように、冷たい雨が降っている。やがて、ドアベルが鳴り、千代がいつも通りに入ってきた。彼女は湊の異変に気づいたのか、心配そうな顔で近づいてくる。
「どうかなさいましたか、水島さん。顔色が優れませんよ」
その優しい声が、今は刃のように湊の心を抉る。湊はゆっくりと顔を上げた。覚悟を決めなければならない。この真実を、二人で分かち合わなければ、千代の鳥籠も、自分の錠前も、永遠にそのままになってしまう。
「近藤先生」
湊がそう呼ぶと、千代は驚いて目を見開いた。
「私の妹が……遥が、先生には大変お世話になりました」
千代の顔から、さっと血の気が引いた。彼女はよろめき、近くの椅子に崩れるように座り込んだ。震える唇が、か細く言葉を紡ぐ。
「あなたが……遥さんの、お兄さん……?」
湊は静かに頷いた。そして、すべてを語り始めた。自分の能力のこと。彼女の胸に、錆びた鳥籠が見えること。そして、それが遥への後悔の念から生まれたものだと分かったこと。
千代は、堰を切ったように泣き出した。
「あの日……事故のあった日、遥さんは私のところに相談に来るはずだったんです。進路のことで悩んでいて……。でも、私に急な家の用事ができてしまって、『また今度にしてちょうだい』と、断ってしまった……。もし、あの時、私が話を聞いていれば。少しでも引き留めていれば、あの子は事故に遭わなかったかもしれない……! 私が、あの子を……!」
その絶叫と共に、千代の胸の鳥籠が激しく軋み、砕け散るのではないかと思われるほどの悲痛な音を立てた。
湊は、静かに彼女の隣に座り、その皺だらけの冷たい手を握った。
「先生のせいじゃありません」
彼の声は、震えていた。
「妹は、先生のことが大好きでした。いつも家で、先生の話ばかりしていました。『先生みたいになりたい』って。あいつは、先生に会えただけで、幸せだったはずです。あの日、もし会えなくても、きっとまた次の日を楽しみにしていました。だから、自分を責めないでください」
湊の言葉は、彼自身にも向けられていた。妹を守れなかったという罪悪感。誰とも悲しみを分かち合おうとしなかった、独りよがりの後悔。
湊が千代の手を握りしめたその時、奇跡が起こった。千代の胸にあった錆びついた鳥籠が、ふわりと淡い光を放ち始めたのだ。錆は剥がれ落ち、美しい銀色の蔦模様が現れる。そして、固く閉ざされていた扉が、かすかな音を立てて、ゆっくりと開いた。
中から現れたのは、一羽の小さな光の鳥だった。鳥は、二人の周りを優雅に一回りすると、開かれた店のドアから雨上がりの空へと飛び立ち、眩い光の粒子となって消えていった。
鳥籠が消えた千代の胸元は、もう何も見えなかった。彼女の顔には、長年の重荷から解放されたような、穏やかで、透明な微笑みが浮かんでいた。
そして、湊は気づく。自分自身の胸を締め付けていた、あの冷たくて硬い「錠前」。その中心に、小さな亀裂が入り、そこから温かい光が漏れ出しているのを。錠前はまだ消えてはいない。妹を失った悲しみが、完全に癒えることはないだろう。だが、もうそれは、彼を孤独に縛り付けるためのものではなかった。それは、遥が生きていた証であり、彼女を愛した人々と共有できる、追憶の扉を開けるための鍵に変わろうとしていた。
窓の外では雨が上がり、夕暮れの光が街を黄金色に染めていた。湊はカウンターに立ち、ガラス越しに人々が行き交うのを眺める。彼らの胸や背中には、相変わらず様々な形の「未練」が寄り添っている。しかし、もうそれは不気味な呪いには見えなかった。一つ一つが、誰かを愛し、何かを失い、それでも懸命に生きる人々の、かけがえのない物語の欠片に見えた。
湊は、静かに微笑んだ。この世界で、この能力と共に、自分はこれからも生きていく。人々の声なき物語に、そっと耳を澄ませながら。