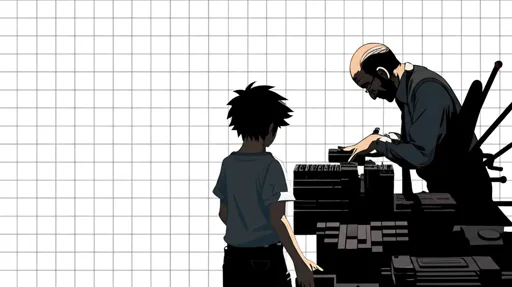第一章 色褪せた街の影法師
俺、レンの眼に映る世界は、常に感情の色で満ち溢れていた。
人々が歩くたび、その足元からは影が伸びる。だがそれは、単なる光の欠落ではない。喜びの絶頂にある者の影は金色の蝶のように舞い、深い悲しみに沈む者の影は藍色の霧となって地面を這う。怒りは、まるで血のような赤い棘を周囲に突き立てる。他者の最も鮮烈な『感情のピーク』が、俺にはそうして視えるのだ。
この街角は、さながら万華鏡だ。カフェの窓辺で恋人が交わす囁きは柔らかな桃色の光を放ち、市場で言い争う男たちの足元では黒ずんだ赤色の影が火花を散らす。俺はそんな色彩の洪水の中を、息を潜めるようにして生きてきた。他人の感情に酔い、時にその毒気に当てられながら。
だが、俺自身の影だけは、どんな時もただの黒だった。感情という絵の具を一切弾く、底なしのインク溜まりのような黒。喜びも、悲しみも、怒りさえも、その不透明な闇は決して映し出すことはない。まるで俺という存在に、心が欠落しているとでも言うかのように。
そして最近、俺と同じ『黒い影』を持つ子供たちが増え始めていた。彼らは『無晶者』と呼ばれている。この世界では、人は皆、過去の人生で最も輝いた『生きた証』を『魂の結晶』として心臓に宿し生まれてくる。だが、『無晶者』たちにはそれがない。彼らの影は俺と同じように色を持たず、その存在は静かな波紋のように世界を侵食していた。彼らが通り過ぎた後、あれほど鮮やかだった人々の感情の影は、まるで水で薄められた絵の具のように色褪せ、時には完全にその色彩を失ってしまうのだ。世界から、感情という名の彩りが、少しずつ、しかし確実に失われつつあった。
第二章 無色の出会い
その日、俺は裏路地の古道具屋で、一枚の奇妙な石板を見つけた。磨かれた黒曜石のようでいて、光を全く反射しない、無機質な『無色』の板。店主は「何の変哲もない石ころさ」と笑ったが、俺は何故か惹きつけられ、なけなしの金でそれを手に入れた。
石板を抱えて広場に出ると、噴水の縁に座る一人の少女が目に入った。年は十歳ほどだろうか。彼女の足元に伸びる影は、俺と同じ、光を飲み込むような黒だった。『無晶者』だ。しかし、他の子たちとはどこか違っていた。彼女の周りだけ、空気が張り詰めたような静寂に包まれている。人々は無意識に彼女を避け、その周囲だけ感情の色彩がごっそりと抜け落ち、モノクロームの空間が生まれていた。
俺が近づくと、少女は無表情のまま、大きな灰色の瞳で俺をじっと見つめた。その視線に射抜かれ、俺は思わず足を止める。
「君も、黒いんだね」
少女――エリアナは、そう呟いた。声に抑揚はなく、風の音に溶けてしまいそうなほどか細い。
俺は言葉を返せず、ただ手にしていた石板を握りしめた。エリアナは俺の持つ石板に目を留め、ゆっくりと立ち上がると、おずおずと小さな手を伸ばしてきた。彼女の指先が石板に触れた瞬間、ただの石ころだったはずの板が、微かに乳白色に曇った。それはほんの一瞬のことで、すぐに元の無色に戻ってしまったが、確かに何かが起きた。俺以外の『黒い影』に、石板が反応したのだ。
その時だった。広場の向こうから、鋭い声が響いた。
「そこな『無晶者』!確保しろ!」
白い制服に身を包んだ『結晶守護隊』の男たちが、俺たちを指差していた。彼らの影は、正義感を履き違えた独善的な、硬質な鋼色の棘となって揺らめいていた。
第三章 石板が映す未来
咄嗟にエリアナの手を掴み、俺は走り出した。入り組んだ路地を駆け抜け、迫り来る足音から逃れる。なぜ、見ず知らずの少女のために?自分でも分からなかった。ただ、彼女の灰色の瞳の奥に、俺と同じ孤独の色を見た気がしたのだ。
追い詰められたのは、古い教会の裏手にある行き止まりの広場だった。守護隊の男たちが、じりじりと距離を詰めてくる。彼らの鋼色の影が、俺たちを刺し貫かんばかりに伸びてくる。
「抵抗は無意味だ。世界の調和を乱す『空白』は我々が管理する」
エリアナが俺の背中に隠れ、その小さな体が震えているのが分かった。守らなければ。その一心で、俺は彼女の前に立ち、無意識に『無色の石板』を盾のように構えた。男たちが一斉に飛びかかってくる。
その瞬間、世界から音が消えた。
俺の掌と、背後のエリアナの体温が、石板を介して一つになった気がした。石板が、閃光と呼ぶにはあまりに静かな、しかし圧倒的な光を放った。それは色を持たない、純粋な『無』の光だった。
石板の表面に、映像が浮かび上がった。それは、誰にも見覚えのない、未来の世界の風景だった。人々と思しき無数の光の点が、輝く線で結ばれ、巨大な一つのネットワークを形成している。そこには個々の影はなく、誰もが繋がり、共鳴し合っていた。悲しみも喜びも、全てが共有された、巨大な一つの生命体のような世界。あまりに美しく、そしてあまりに恐ろしい、モノクロームの未来図。
同時に、俺自身の黒い影が、まるで生き物のように足元から膨れ上がった。それはエリアナの影を優しく包み込むと、次の瞬間、襲いかかってきた守護隊の男たちの鋼色の影へと牙を剥いた。影は、叫び声もなく、彼らの感情の色を喰らい始めた。鋼色は墨汁のように黒に染まり、男たちの顔から一切の表情が抜け落ちる。彼らはただ呆然と立ち尽くし、自分が何をしようとしていたのかさえ忘れてしまったかのように、虚な目で空を見上げていた。
第四章 空白の器の真実
静寂が戻った広場で、俺は自分の足元に広がる、異常なまでに濃い黒の影を見下ろしていた。それはもう、ただの影ではなかった。他者の感情を吸収し、無に還す『空白の器』。
石板が映し出した未来。この黒い影の力。全てが一本の線で繋がった。
『無晶者』は、感情を破壊する存在ではなかった。世界が一度滅びかけた『過去の災厄』で失われ、歪んでしまった感情を、もう一度新しい形で再構築するために生まれた存在なのだ。彼らの黒い影は、あらゆる感情を吸収し、解体し、再構築するための『器』そのものだった。
そして、俺は――俺のこの不透明な黒い影は、その『始祖』。
全ての『無晶者』たちの『器』を集約し、世界の感情を再編する、『感情の編集者』だったのだ。
俺が振り返ると、エリアナが静かに俺を見上げていた。彼女の灰色の瞳には、初めて微かな光が宿っているように見えた。恐怖でも、驚きでもない。それは、長きにわたる旅路の終着点を見出したかのような、安堵の色だった。彼女は、俺という『編集者』を起動させるための『鍵』だったのだ。
俺は選択を迫られていた。このまま、個人の感情が輝き、時にぶつかり合って傷つけ合う、不完全で美しい旧世界を見守るのか。それとも、石板が示した、悲しみも孤独も存在しない代わりに、『個』という概念すら失われる新世界を創造するのか。
俺はエリアナの小さな手を取った。その手は、冷たいようでいて、確かな温もりを持っていた。俺たちの影が、静かに一つに重なり合った。
第五章 感情の終着点
俺は、街で最も高い時計塔の頂上に立っていた。エリアナは、その傍らで静かに空を見上げている。眼下には、色とりどりの感情の影が揺らめく、俺が愛した世界が広がっていた。喜びの金色、悲しみの藍色、愛の桃色。それら一つ一つが、誰かの人生の紛れもない『生きた証』だった。
だが、その輝きはあまりに脆く、孤独だった。
俺は『無色の石板』を空に掲げた。
「始めるよ」
俺の言葉に、エリアナは小さく頷いた。
俺は目を閉じ、意識を足元の影に集中させる。黒い影は、俺の意志に応え、無限に広がっていった。それは街を覆い、国を覆い、やがて全世界を飲み込む巨大な闇の帳となった。
世界中の人々の足元から、感情の影が剥がされていく。金色の蝶が、藍色の霧が、赤い棘が、光の粒子となって俺の影へと吸い込まれていった。人々の心臓に宿る『魂の結晶』が、ガラスの砕けるような微かな音を立てて砕け散り、その最後の輝きもまた、俺という巨大な『空白の器』に注がれていく。
世界から、色が消えた。音が消えた。喜びの歌も、悲しみの嗚咽も、全てが静寂に帰した。
俺の意識は、無数の感情の奔流に飲み込まれそうになった。愛しい人を想う温もり。我が子を失った絶望。目標を達成した歓喜。裏切られた怒り。その全てが、俺の中で一度解体され、混ざり合い、一つの巨大な奔流となっていく。
最後に、俺は掲げた石板に、その全てを注ぎ込んだ。
世界が、白く染まった。
人々を繋ぐ光のネットワークが、新たな世界の骨格として構築されていく。誰もが隣人の喜びを我がことのように感じ、見知らぬ誰かの悲しみに涙を流す。もう孤独に苛まれる者はいない。争いも、憎しみも、共有された理解の中に溶けていく。世界は、完璧な調和を手に入れたのだ。
だが、恋人のためだけにときめく心臓の音も、自分だけの秘密を抱える苦しさも、世界でたった一つの夕焼けに感動する心も、そこにはもうなかった。『個』としての感情の独自性は、永遠に失われた。
俺自身の意識は、その光のネットワークの中に拡散し、溶けていった。俺という『個』は消え、世界の感情そのものとなった。これが、俺が編集した物語の結末。これが、俺が見つけた、唯一の救済。
果たしてこの世界は、幸福なのだろうか。
その答えを知る者は、もうどこにもいない。