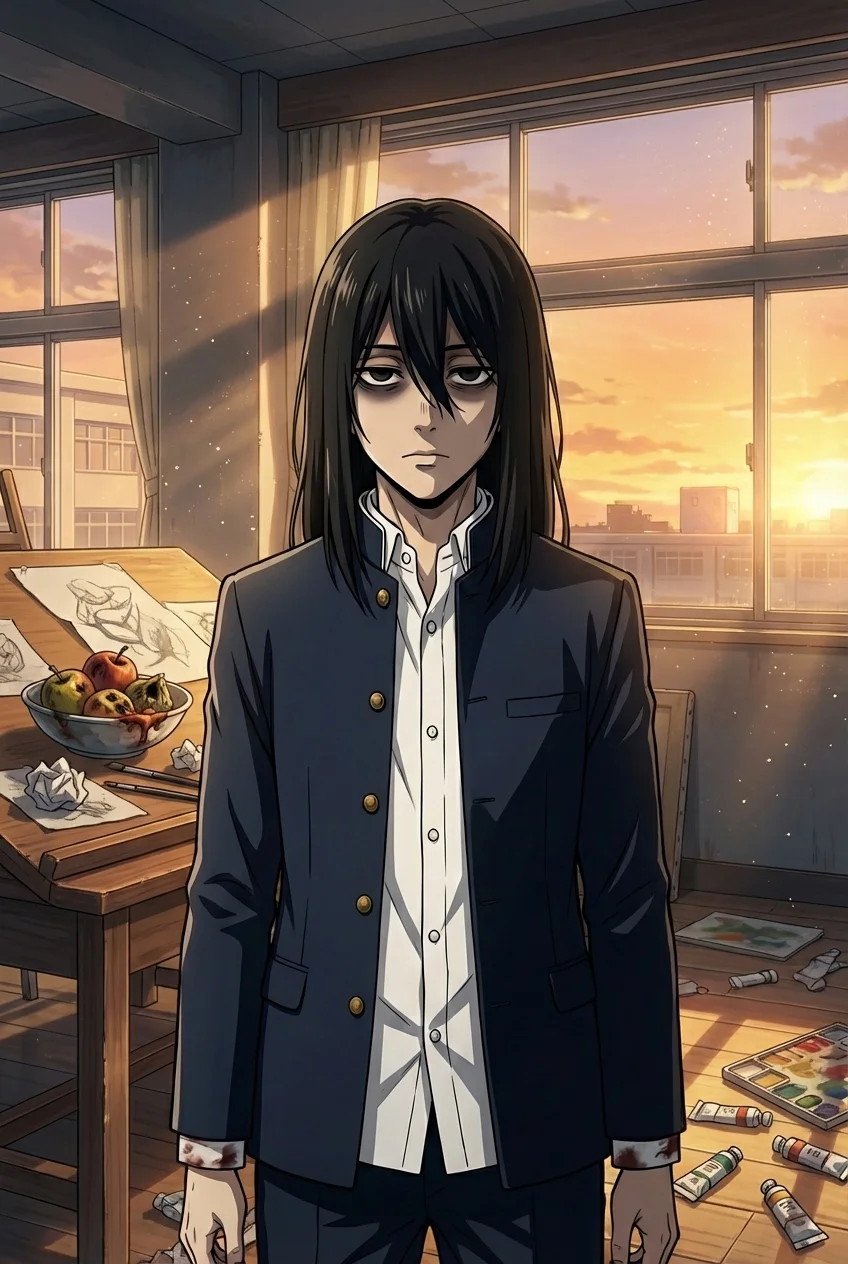第一章 完璧な結晶と音のない言葉
僕たちの通うこの月白(つきしろ)学園では、言葉は、ただの音波の振動ではない。
誰かが何かを口にするとき、その言葉に込められた感情や意図の「重さ」に応じて、物理的な実体となって空間に現れる。他愛ない噂話はシャボン玉のように浮かんで弾け、悪意に満ちた陰口は黒曜石の棘となって床に突き刺さる。そして、心からの感謝は、掌で温かい光を放つ小さな宝石になる。僕たちは、そんな不思議な現象が日常となった世界で生きている。
教室は、常に言葉のオブジェクトで満ち溢れていた。授業中の真剣な問いかけが産み出す硬質な水晶、休み時間の冗談が生む色とりどりの紙吹雪、時折転がっている、誰かを妬む言葉が変質した黒く粘つく泥。僕、水瀬湊(みなせ みなと)は、いつもその教室の隅で、息を潜めるように過ごしていた。
僕が発する言葉は、いつだって不格好だったからだ。どもりがちな声から生まれるのは、泥の塊とも石ころともつかない、歪で小さなオブジェクト。自分の気持ちをうまく形にできない僕は、言葉を発することそのものに臆病になっていた。
そんな僕の視線の先には、いつも朝比奈響(あさひna ひびき)がいた。彼女は、まるで熟練の職人のようだった。彼女の口から紡がれる言葉は、常に完璧なカッティングが施されたプリズムとなって、教室の光を乱反射させた。その美しさに誰もが魅了され、彼女の周りにはいつも、その輝きに惹かれた人だかりができていた。彼女の「おはよう」という挨拶ひとつで、朝の教室に七色の虹がかかるのだ。
僕は、彼女の完璧な結晶を、ただ羨望の眼差しで見つめることしかできなかった。僕の歪な石ころでは、彼女の隣に並ぶことさえ許されない気がした。
その日、事件は起きた。放課後、忘れ物を取りに誰もいない教室に戻った僕は、ふと、隣の音楽室から漏れる微かな気配に気づいた。好奇心に引かれ、そっとドアの隙間から中を覗く。そこにいたのは、朝比奈響だった。
ピアノの前に一人座り、彼女は何かを呟いていた。だが、いつもと様子が違う。彼女の口元から、あの美しい結晶は生まれていなかった。代わりに、まるで陽炎のように、形をなさず、ただ空気をごく微かに揺らすだけの「何か」が、彼女の周りを漂っていた。
それは、「音のない言葉」だった。形にも色にもならない、けれど、そこに存在するだけで胸が締め付けられるような、途方もなく重く、深い悲しみを湛えた沈黙の言葉。完璧な彼女が見せた、初めての亀裂。僕は、見てはいけないものを見てしまったという罪悪感と、それ以上に強い衝撃に、その場で凍り付いていた。
第二章 歪な石ころの在り処
あの日以来、僕の中で朝比奈響という存在は、単なる憧れの対象ではなくなった。完璧なプリズムを生み出す彼女と、音のない言葉に沈む彼女。どちらが本当の彼女なのだろうか。僕は、彼女のことが気になって仕方がなかった。
観察を続けるうちに、僕は一つの事実に気づいた。彼女が生み出す完璧な言葉の結晶は、確かに美しい。非の打ち所がないほどに。しかし、それらはどこか冷たく、まるで精巧なガラス細工のように、人の心の温度を感じさせなかった。彼女は、誰かの期待に応えるように、ただ「正しくて美しい言葉」を生産しているだけなのではないか。そんな疑念が僕の心に芽生えた。
自分の不格用な言葉に思い悩んだ僕は、変わり者と評判の国語教師、田所先生の研究室を訪ねた。古書の匂いと、様々な言葉のオブジェクトの標本が並ぶその部屋で、先生は僕の歪な石ころを手に取り、面白そうに言った。
「水瀬、君は言葉の形ばかりを気にしているな。大事なのはそこじゃない。その言葉に、どれだけ『君自身』を乗せられているかだ。借り物の綺麗な言葉より、不格好でも自分の魂から絞り出した言葉の方が、よっぽど遠くまで届くものだよ」
先生の言葉は、小さな光の球となって僕の掌に落ちた。温かかった。
それから、僕は勇気を出して響に話しかけるようになった。学級委員の仕事を手伝ったり、課題について質問したり。けれど、彼女との間に生まれるのは、相変わらず彼女の冷たく完璧な結晶と、僕の小さく歪な石ころだけだった。距離は一向に縮まらない。それどころか、彼女は僕と話す時、いつもより一層、完璧な言葉の鎧を纏っているように見えた。僕の不器用さが、彼女を警戒させているのかもしれない。無力感が募った。
ある雨の日、僕たちは図書室で鉢合わせた。静寂の中、雨音が窓を叩く。ふと、彼女が読んでいた本のページから、一粒の小さな光がこぼれ落ちた。それは、物語の登場人物に共感した読者の涙が生み出すと言われる、「共感の雫」だった。彼女は慌ててそれを隠したが、僕は見てしまった。冷たい結晶の奥に隠された、彼女の柔らかい心の片鱗を。
「……綺麗な雫だね」
僕が思わず呟いた言葉は、いつもより少しだけ丸みを帯びた、小さなビー玉になって彼女の足元に転がった。彼女は驚いたように目を見開き、そして、何も言わずに俯いてしまった。僕たちの間の沈黙は、雨音に溶けていった。
第三章 魂の溶岩
変化は、学園祭の準備が本格化した頃に訪れた。クラスの出し物を巡って意見が対立し、教室の空気は日増しに悪くなっていった。誰もが自分の意見という名の鋭い言葉の矢を放ち、相手の言葉を打ち落とすことに必死だった。教室の床には、砕かれた言葉の残骸が散らばり、歩くたびにじゃりじゃりと嫌な音を立てた。
そしてついに、決定的な瞬間がやってきた。中心メンバーの一人、佐藤が放った「どうせお前の意見なんて、何の価値もない」という言葉が、黒く鋭い棘となって、懸命に提案を練っていた鈴木の言葉――皆で楽しみたいという願いが込められた、温かい光の球――を無慈悲に貫いたのだ。パリン、と乾いた音が響き、光の球は粉々に砕け散った。鈴木は泣き崩れ、教室は凍りついた。
その時、朝比奈響がすっと立ち上がった。誰もが彼女に期待した。この最悪の状況を、彼女の美しい言葉が救ってくれるはずだと。
「みんな、落ち着いて。感情的になるのはやめましょう。目的は、学園祭を成功させること。その一点に立ち返って、最も合理的で効率的な方法を……」
彼女の口から紡がれる言葉は、いつにも増して理路整然とし、光り輝く巨大なプリズムとなって教室の中央に出現した。その絶対的な美しさと論理性の前に、誰もが反論の言葉を失い、ただ圧倒され、その意見に従いそうになった。
だが、僕だけは駄目だった。その完璧すぎるプリズムが、ひどく空虚で、偽物に見えたからだ。音楽室で見た、あの音のない言葉。図書室で見た、共感の雫。本当の彼女は、こんな冷たい言葉の主じゃない。
僕は、気づいたら叫んでいた。
「それは、あなたの言葉じゃない!」
喉から絞り出した、しゃがれた声。僕の全身からほとばしった想いは、これまで生み出したどんなオブジェクトとも違っていた。それは、不格好で、表面はゴツゴツとしていたが、内側から灼熱の光を放つ、燃える溶岩の塊だった。
僕の魂の溶岩は、まっすぐに響の生み出した巨大なプリズムに激突した。凄まじい音と共に、完璧に見えたプリズムに、蜘蛛の巣のような亀裂が走る。教室中が息を呑んだ。
そして、プリズムの中心にいた響の瞳から、大粒の涙が溢れ出した。彼女は、その場にへたり込み、子供のように声を上げて泣き始めたのだ。
「……そうよ」彼女は嗚咽に途切れながら、告白した。「私の言葉じゃない……。私は、ずっと怖かった。私の本当の言葉なんて、きっと醜くて、歪で、誰も受け入れてくれないって……。だから、本で読んだ綺麗な言葉、誰かが言っていた正しい言葉を真似して、完璧な私を演じてきたの! 本当の私は、空っぽなのよ……!」
完璧な結晶の鎧が、音を立てて崩れ落ちていく。その下から現れたのは、傷つきやすく、不器用な、一人の少女の素顔だった。
第四章 不揃いな僕らのかけら
響の告白は、凍りついた教室の空気を静かに溶かし始めた。彼女の嗚咽から生まれたのは、美しくもなければ、大きくもない、ただ涙の雫のように歪で、けれど内側から淡く優しい光を放つ、小さな小さなオブジェクトだった。それは、彼女が初めて自分自身のために生み出した、本当の言葉だった。
そのか細い光を見て、クラスメイトたちはハッとしたように顔を見合わせた。黒い棘を放ってしまった佐藤も、言葉を砕かれた鈴木も、自分たちがこれまで、言葉の形や美しさ、正しさばかりに囚われていたことに気づいたのだ。一番大切なのは、その奥にある心だということに。
誰かが、ぽつりと「ごめん」と呟いた。それは、いびつな形の謝罪の言葉だった。すると、別の誰かが「私も」と続けた。あちこちで、不器用で、不格好で、けれど温かい、本物の言葉が生まれ始めた。教室は、様々な形、様々な色の、不揃いだが心からの言葉のオブジェクトで、ゆっくりと満たされていった。それはまるで、無数の星が灯った夜空のように、不完全で、だからこそ美しい光景だった。
数日後、僕は響と二人で放課後の屋上にいた。夕焼けが、僕たちの影を長く伸ばしている。
「あの時は、ありがとう」響が静かに言った。彼女の口元から、柔らかな光を帯びた、小さな綿毛のような言葉が生まれた。
「僕こそ、ごめん。あんな言い方しかできなくて」僕の言葉は、角の取れた小さな石ころになって、彼女の綿毛の隣にそっと転がった。
僕たちの間に、もうあの完璧なプリズムも、燃える溶岩も生まれることはなかった。ただ、穏やかで小さな光の粒のような言葉が、静かに行き交うだけ。それで十分だった。いや、それが良かった。完璧な言葉でなくても、不器用なままでも、心は通じ合うことができる。僕は、ようやくそのことに気づけたのだ。
僕たちの世界は、言葉で満ちている。完璧な結晶も、歪な石ころも、すべてが誰かの心のかけらだ。そして僕たちは、その不揃いなかけらを集めて、傷つけ合い、許し合いながら、不器用なまま、明日を作っていく。
夕暮れの空を見上げながら、僕は隣にいる彼女の、本当の言葉から生まれた小さな光を、何よりも愛おしいと思った。