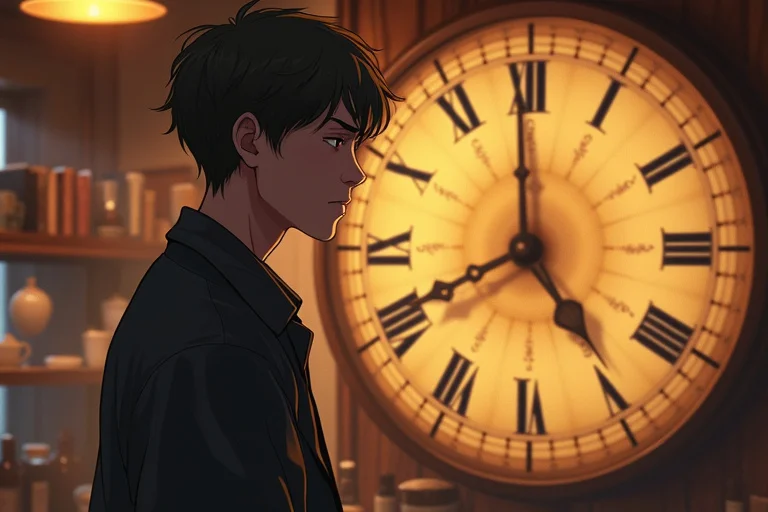第一章 静かな侵食者
水島湊の日常は、古びた紙の匂いと、静寂を区切る柱時計の音で編まれていた。神保町の路地裏にひっそりと佇む古書店『時紡ぎ堂』の二階に住み、店主として客のいない時間を過ごす。世界はひどく色褪せていて、感情の起伏は凪いだ海のように平坦だった。朝、トーストを焼き、コーヒーを淹れ、店を開ける。本を整理し、埃を払い、日が傾けば店を閉める。同じことの繰り返し。その単調さこそが、湊が自らに課した、穏やかで安全な檻だった。
その均衡が、ある朝、音もなく崩れ始めた。
洗面所の鏡に向かった時だった。背後の白い壁に映る自分の影が、ほんのわずかに、湊の動きから遅れたのだ。右手を挙げて顔を洗おうとすると、影の腕は一瞬ためらうように止まり、それから慌てて追いついてくる。湊は手を止め、鏡の中の自分と、壁に映る黒いシルエットを交互に見た。寝不足だろうか。目の錯覚に違いない。彼はそう結論づけ、冷たい水で顔を洗い、意識の隅からその違和感を追い払った。
しかし、「侵食」は続いた。翌日、店番をしながら文庫本を読んでいると、ふと足元に落ちた影が、湊がページをめくる手とは無関係に、指をそっと組み合わせるような形を作った。まるで祈るかのように。その翌日には、昼食のサンドイッチを頬張る湊の影が、壁の上でゆっくりと首を傾げ、どこか遠くを見つめるような仕草をした。
それはもはや気のせいではなかった。湊の影は、湊の知らない意志を持ち始めていた。恐怖よりも先に訪れたのは、深い困惑だった。影は自分自身の一部のはずだ。光があって初めて存在する、従属的な存在。それがなぜ、別の生命体のように振る舞うのか。湊は誰にも相談できず、一人、自分の影を監視するという奇妙な日常を始めることになった。影は言葉を発しない。だがその動きは、日に日に雄弁になっていった。ある時は悲しげにうずくまり、またある時は、店の窓から見える西の空を、焦がれるように指さすのだった。湊の平坦な日常に投げ込まれたその黒い石は、静かに、しかし確実に波紋を広げていた。
第二章 影がささやく断片
影との共同生活は、湊の精神を少しずつ削っていった。彼は自分の影から目が離せなくなり、夜、部屋の明かりを消すことにさえ、微かな躊躇を覚えるようになった。暗闇の中では、影は自分という本体から解放され、どこかへ行ってしまうのではないか。そんな非科学的な妄想に囚われるほどだった。
観察を続けるうち、湊は影の行動に特定のパターンがあることに気づき始めた。影が頻繁に示す方角は、いつも西だった。そして、湊が古いジャズのレコードをかけると、影は決まって、楽しげにステップを踏むような動きを見せる。その曲は、湊自身もなぜ持っているのか思い出せない、古いレコードだった。
ある雨の日、湊は書庫の整理中に、段ボールの奥から一冊の古いアルバムを見つけた。表紙には何も書かれていない。ページをめくると、そこにいたのは今よりもずっと若く、屈託なく笑う自分だった。そして、どの写真にも、彼の隣には柔らかな笑顔を浮かべた一人の女性がいた。陽光のように明るい髪、少し困ったように八の字に曲がる眉。湊はその女性の顔に見覚えがあるような気がしたが、名前も、彼女との関係も、何一つ思い出せなかった。まるで、脳の一部にだけ都合よく分厚い霧がかかっているかのようだ。
その時、背後の壁に映っていた影が、そっと湊の肩に寄り添うような形を作った。アルバムの中の女性が、写真の中でしていたのと同じ仕草だった。ぞくりと背筋が粟立つ。この影は、この女性を知っているのか? そして、なぜ自分は彼女を忘れているのか?
アルバムの最後のページに、一枚だけ、海辺のカフェで撮られた写真が挟まっていた。夕陽を背にした二人の影が、砂浜に長く伸びている。『海猫亭にて』と、丸みを帯びた女性的な文字で書かれている。
「海猫亭……」
湊は呟いた。その名前には聞き覚えがあった。影は、まるでその言葉を待っていたかのように、壁の上で大きく頷き、カフェがあるであろう西の方角を、再び強く指さした。それはもはや、ただの奇妙な現象ではなかった。失われた記憶への、黒い道標だった。湊は、自分の過去と向き合う覚悟を決めなければならないことを悟った。たとえその先に、知りたくない真実が待っていたとしても。彼はアルバムを抱きしめ、重い腰を上げた。
第三章 黄昏に溶けた真実
海沿いの国道を走り、記憶の断片を頼りに車を進めると、果たしてそのカフェ『海猫亭』は存在した。潮風で白く錆びた看板が、傾きかけた陽の光を浴びて物憂げに輝いている。湊が店のドアを開けると、カラン、と澄んだベルの音が鳴り、コーヒー豆の香ばしい匂いが鼻腔をくすぐった。
「いらっしゃい」
カウンターの奥から、白髪の混じった壮年のマスターが顔を上げた。彼は湊の顔を見るなり、少し驚いたように目を見開き、そしてすぐに寂しげな微笑みを浮かべた。
「……久しぶりだね、湊くん。もう、来てくれないかと思っていたよ」
マスターは湊のことを知っていた。湊はアルバムを取り出し、カウンターの上に置いた。「この女性のことを、知っていますか? そして……僕のことも」
マスターは黙って頷き、ゆっくりと語り始めた。湊が忘れていた、三年という空白の時間を埋めるように。写真の女性は、陽菜(ひな)という名の、湊の恋人だったこと。二人がこのカフェの常連で、いつも同じ窓際の席で、他愛ない話をして笑い合っていたこと。そして、三年前の秋、このカフェからの帰り道、二人が乗った車が事故に遭ったこと。
「陽菜さんは、君を庇って……即死だった。君は奇跡的に助かったが、頭を強く打ってね。事故のショックと、あまりの悲しみから、君の心は陽菜さんの記憶に蓋をしてしまったんだ。一種の防衛本能だったんだろう」
湊は、頭を殴られたような衝撃で立ち尽くした。陽菜。その名前を口の中で転がすと、舌の上に懐かしくも切ない味が広がった。そうだ、陽菜だ。僕の、たった一人の……。堰を切ったように、失われた記憶が奔流となって押し寄せる。陽菜の笑い声。陽菜の作る少し甘い卵焼きの味。喧嘩した後の、気まずい沈黙。夕陽の海辺を、手を繋いで歩いた時の、彼女の指の温もり。
全てが、鮮明に蘇った。そして、それらを失った絶望も。
湊は自分の足元に落ちる影を見た。夕陽に照らされて長く伸びた影は、静かに、ただそこにいるだけだった。
「君の影はね」マスターが静かに続けた。「事故の後、時々、陽菜さんの癖をしていたよ。考え事をする時に、髪を指でくるくる巻く癖。君にはそんな癖、なかったからね。不思議だと思っていたんだ」
その瞬間、湊は全てを理解した。なぜ影が奇妙な動きをしていたのか。なぜ西の空を指さしたのか。なぜ古いジャズで踊ったのか。あれは全て、陽菜の記憶、陽菜の想いの断片だったのだ。
彼の影は、湊が失った記憶の代わりをしていたのではない。事故の瞬間、湊を守ろうとした陽菜の強い想いが、光と影の境界線に奇跡のように宿り、彼の影の一部として存在し続けていたのだ。湊が陽菜を忘れ、空っぽの日常を送ることに、影は――陽菜は、耐えられなかった。忘れないで、と。ここにいるよ、と。そう訴え続けていたのだ。
「陽菜……」
湊の口から、嗚咽混じりの声が漏れた。頬を伝う熱い雫が、床に落ちて小さな染みを作る。彼の影が、そっと震えた。それはまるで、ようやく想いが届いたことに安堵し、共に泣いているかのようだった。湊の無機質な日常は、愛と喪失という、あまりにも鮮やかで残酷な色彩を、一瞬にして取り戻した。
第四章 君と歩む影法師
古書店に戻った湊の世界は、以前とは全く違って見えた。本の背表紙の色はより深く、柱時計の音は時の重みを語り、窓から差し込む光には温もりがあった。彼は空っぽではなかった。ただ、最も大切なものを、心の奥底にしまい込んでいただけだったのだ。
湊は自分の影に向き合った。壁に映るそれは、もう不気味な侵食者ではない。愛する人の名残であり、自分自身を支えてくれた、かけがえのない存在だ。
「ごめん、陽菜。ずっと一人にして。寂しかったよな」
湊が語りかけると、影はゆっくりと、まるで抱きしめるかのように、湊自身の影とぴったりと重なった。初めて、影の動きと湊の動きが完全にシンクロした瞬間だった。涙が後から後から溢れたが、それはもう絶望の色ではなかった。再会の喜びと、深い感謝が入り混じった、温かい涙だった。
湊の日常は、静かに、だが確かに変わり始めた。朝、トーストを二枚焼き、陽菜が好きだった苺ジャムを塗った方を、窓際の小さなテーブルに置くようになった。店で客と話す時も、以前より少しだけ口角が上がるようになった。彼は悲しみを乗り越えたわけではない。悲しみは彼の心の一部となり、その痛みごと抱きしめて生きていくと決めたのだ。
影は、もう湊の動きを妨げるようなことはしなかった。しかし、ふとした瞬間に、陽菜の面影を見せることはあった。湊が本に栞を挟む時、影の手が陽菜のようにそっとページを撫でたり、夕焼け空を眺めていると、影が彼の肩にそっと頭を乗せるような形になったり。そのたびに、湊の胸にはチクリとした痛みと、それ以上の愛おしさが込み上げた。彼はもう一人ではなかった。
ある日の夕暮れ時、湊は店を閉め、陽菜とよく歩いた近所の公園まで散歩に出かけた。橙色の光が世界を染め上げ、長く伸びた自分の影が地面に焼き付けられている。彼は立ち止まり、その影を愛おしげに見つめた。
その時、一瞬だけ、本当にほんの一瞬だけ、自分の影の隣に、もう一つ、寄り添うように立つ淡い影が見えたような気がした。それは夕陽が作り出した光の悪戯だったのかもしれない。しかし、湊は確かに感じた。陽菜が微笑みかけてくれているのを。
「帰ろうか、陽菜」
湊は、誰に言うでもなく呟き、再び歩き出した。彼の隣には、彼だけに見える温かい存在を連れて。喪失は決して消えることはない。だがそれは、人を孤独にするためだけにあるのではない。失われた愛しい記憶は、影となって、光となって、残された者の明日をそっと照らし続ける。湊の影法師は、これからも彼と共に、時を紡いでいくのだろう。