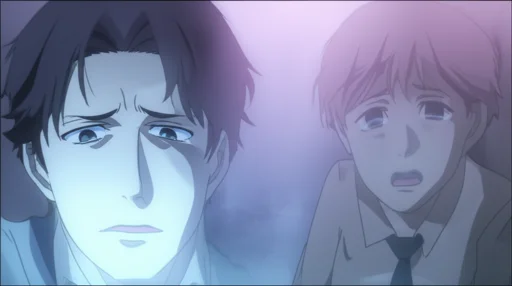第一章 黒い澱み
柏木透の世界は、そこかしこに黒い染みがこびりついていた。それは物理的な汚れではない。人の強い後悔が残した、魂の残滓のようなものだ。古びた神保町の古書店の店主代理である彼にとって、その染みは日常の風景だった。客が手放していった本には、しばしば小さな染みがついていた。「もっと読んでやればよかった」という微かな悔い。「売らなければよかった」という未練。それらは透にとって、背景に溶け込むノイズのようなものだった。
透は幼い頃から、この忌まわしい能力と共に生きてきた。染みは黒く、まるで水面に落とした墨汁のように、輪郭を曖昧に蠢かせている。そして、決して触れてはならない。一度だけ、子供の頃に好奇心から道端の染みに触れてしまったことがある。その瞬間、見ず知らずの男の絶望が、冷たい奔流となって彼の精神を蹂躙した。ギャンブルで全てを失い、家族に顔向けできず、自ら命を絶とうとする男の、焼け付くような後悔。以来、透は人との間に見えない壁を築き、染みから、そしてその源である他人の心から距離を置いて生きてきた。
その日、店の古びたドアベルが、乾いた音を立てた。入ってきたのは、背中の丸まった小柄な老婆だった。手には、褪せた布で丁寧に包まれた一冊の本を抱えている。
「これを…買い取っていただけますか」
しわがれた声で差し出されたのは、革装の分厚い植物図鑑だった。透が受け取ろうと手を伸ばし、そして、息を呑んだ。
本そのものが、これまで見たこともないほど濃く、おぞましい黒い染みに覆われていたのだ。それは単なる染みではなかった。まるで生命を宿した黒い澱みだ。粘性を帯びた闇がゆらめき、本の表面をゆっくりと這い回っている。そこから放たれる冷気は、初夏の店内にあってなお、透の肌を粟立たせた。これは、尋常な後悔ではない。魂の根幹を蝕むような、途方もない絶望が凝縮している。
「…大事な本なのですね」
透は声が震えるのを必死でこらえ、なんとか言葉を絞り出した。老婆は、深く刻まれた皺の奥で、悲しそうに目を細めた。
「ええ。夫の形見でしてね。でも、施設に入るのに、持っていける荷物には限りがあるものですから」
老婆はそう言うと、名残惜しそうに本の背を一度だけ撫で、深々と頭を下げて店を出ていった。
残された本は、カウンターの上で禍々しい存在感を放ち続けている。染みは心なしか、先ほどよりも濃くなっているように見えた。透は恐怖と嫌悪感に駆られ、ゴム手袋をはめると、その本を店の最も奥にある、開かずの書庫の引き出しに叩き込んだ。鍵をかけ、固く閉ざされた扉を見つめる。これでいい。もう見ることもない。そう自分に言い聞かせたが、背筋を這い上がる悪寒は、いつまでも消えなかった。
第二章 囁く残像
老婆の本を封印してから数日、透の日常は静かに狂い始めていた。夜、店を閉めて二階の自室で眠りにつくと、どこからか囁き声が聞こえるのだ。意味のある言葉ではない。ただ、後悔と悲嘆に満ちた、湿っぽい音の断片。それは階下の、あの開かずの書庫から響いてくるようだった。
昼間も気の休まる時はない。店内のあちこちに、あの本の染みと同じ性質の、黒い残像がちらつくようになった。客が立ち去った椅子に、棚の隅に、床の木目に。それらはすぐに消える幻覚だったが、透の神経を確実にすり減らしていく。彼は、あの澱みが店全体を、そして自分の精神を侵食しつつあるのではないかと恐れた。
そんなある日、常連客の女子高生、小野寺美咲がやってきた。彼女は受験勉強の息抜きに、よく文芸書のコーナーを覗きに来る、快活な少女だ。
「柏木さん、こんにちは! 今日は何か面白い本、入ってます?」
屈託のない笑顔を向けられ、透はわずかに緊張を緩める。だが、彼女の肩に、小さな黒い染みが浮かんでいるのを見つけて、再び心臓が冷たく収縮した。できたばかりの、まだ輪郭の淡い染みだ。誰かとの些細な行き違いが生んだ、小さな後悔だろう。
「…別に、いつもと変わりないよ」
透は素っ気なく答え、視線を逸らした。深く関わってはいけない。彼女の心に触れてしまえば、またあの奔流に飲み込まれる。だが、美咲は気にした様子もなく、楽しそうに本棚を眺め始めた。彼女の存在は、この陰鬱な古書店の中では異質なほど明るく、透のささくれた心を、ほんの少しだけ癒してくれるのも事実だった。
その夜、透はまたあの囁き声で目を覚ました。だが、今夜はいつもと違った。囁きに混じって、すすり泣くような音が聞こえる。意を決して階下に下り、開かずの書庫の扉に耳を当てた。間違いない。中からだ。
震える手で鍵を開け、扉を押し開ける。黴と古紙の匂いに満ちた暗闇の中、引き出しの隙間から、黒い光が漏れ出していた。恐る恐る引き出しを開けると、あの植物図鑑が、まるで生きているかのように、禍々しい光を放ちながら脈動していた。表面を覆う黒い染みは、心臓のように規則正しく、しかし不気味に膨張と収縮を繰り返している。それはもはや後悔の残滓などではない。明確な意志を持った、未知の何かだった。
「ひっ…!」
透は短い悲鳴を上げ、その場にへたり込んだ。逃げなければ。これを捨てなければ、自分は取り込まれてしまう。恐怖が理性を麻痺させていく。もう、限界だった。
第三章 偽りの後悔
恐怖は、時に人を無謀にする。このままでは自分が壊れてしまう。そう直感した透は、半ば自暴自棄になって、再び書庫へと向かった。震える手で、脈動する植物図鑑を掴む。そして、意を決して、素手でそのおぞましい染みに触れた。
激しいイメージの奔流を覚悟し、奥歯を食いしばる。だが、予想していた衝撃は訪れなかった。代わりに流れ込んできたのは、驚くほど穏やかで、温かい記憶だった。
――陽光が降り注ぐ庭。若き日の老婆が、夫と共に楽しそうに草花を眺めている。夫が優しい声で、花の名前を教えてくれる。ページをめくる指。インクの匂い。長い年月をかけて、夫婦がこの一冊を慈しんできた、幸福な時間の積み重ね。そこには、一片の後悔も存在しなかった。
混乱する透の脳裏に、次の瞬間、全く異なる光景がフラッシュバックした。
――雨の日の横断歩道。信号を待つ老婆。彼女は、夫との思い出に浸り、穏やかに微笑んでいる。青信号。彼女が一歩踏み出した瞬間、猛スピードで交差点に突っ込んできたトラック。衝撃。悲鳴。そして、老婆を助けようとして、ほんの数歩間に合わなかった若い男性の、絶望に歪んだ顔。彼の魂が引き裂かれるような慟哭。「ああ、なぜ、あの時、手を伸ばせなかったんだ…!」
透は、雷に打たれたように悟った。
これは、後悔の染みではない。
これは、「これから起こる悲劇」の予兆だ。そして、それに伴って生まれるであろう「未来の誰かの後悔」の残像なのだ。老婆自身は、事故の瞬間まで幸せな記憶の中にいる。彼女は後悔しない。後悔するのは、彼女を助けられなかった誰か。あるいは、彼女を施設に入れることになった家族か。だから、こんなにも濃く、おぞましい形をしていたのだ。
全身から血の気が引いていく。今まで自分が見てきた、忌み嫌ってきたあの無数の染みは、一体何だったのか? 道端の染み。あれは本当に男の自殺の後悔だったのか? それとも、これから彼を止められなかった誰かの後悔の予兆だったのか? 見て見ぬふりをしてきた、数えきれないほどの染み。その一つ一つが、防げたはずの悲劇の警告だったとしたら?
「…なんてことだ」
透は呆然と呟いた。自分はただ怖がり、目を背けていただけだった。誰かを救うための、たった一つの可能性から。激しい自己嫌悪が、彼の心を暗く塗りつ潰していく。この力は呪いではなかった。呪いにしていたのは、自分自身だったのだ。
第四章 触れるべき痛み
思考が定まるより先に、透の体は動いていた。店を飛び出し、雨上がりの湿ったアスファルトを駆ける。目指す先は一つ。美咲だ。彼女の肩にあった、あの小さな染み。あれも何かの予兆に違いない。些細な喧嘩などではなかったのだ。
駅前の雑踏をかき分け、透は必死に美咲の姿を探した。記憶の中の彼女の制服、髪型、歩き方を頼りに、人波に目を凝らす。焦りが心臓を締め付ける。もし、間に合わなかったら。また、自分は見て見ぬふりをしたことになる。
「いた!」
前方、商店街のアーケードを抜けようとする美咲の背中を見つけた。彼女は友人との待ち合わせに向かう途中らしく、イヤホンで音楽を聴きながら、軽快な足取りで歩いている。その先には、外壁の改修工事中のビルがあった。足場が組まれ、作業員たちの声が響いている。
透の目に、はっきりと見えた。美咲の肩の染みが、黒い靄のように濃さを増し、不吉に揺らめいている。そして、その染みと重なるように、未来のビジョンが明滅する。落下する一本の鉄パイプ。アスファルトに突き刺さる金属音。そして、それを呆然と見つめる友人の、悲痛な顔。
「危ないっ!」
透は最後の力を振り絞って叫びながら走り、美咲の体にタックルするように突き飛ばした。
「きゃっ!」
もつれ合うようにして二人が歩道に倒れ込む。その直後、凄まじい轟音と共に、彼らがいた場所の数センチ横に、銀色の鉄パイプが深々と突き刺さった。
呆然とする美咲に、作業員たちの怒声や周囲の悲鳴が降り注ぐ。透は、息を切らしながら体を起こした。彼女の肩に目をやる。あの黒い染みは、跡形もなく消え失せていた。
「…大丈夫か」
「え…、は、はい。あの、どうして…」
混乱する美咲に、透は何も説明できなかった。この力のことも、未来のことも。ただ、彼女の無事な顔を見て、心の底から安堵が込み上げてきた。
「ごめん。…ただ、危ないと思ったんだ」
それだけ言うのが精一杯だった。
古書店に戻った透は、カウンターの上に置かれた植物図鑑を、静かに手に取った。染みは、まだ消えていない。老婆の事故は、まだ起きていないのだ。
彼はもう、この染みから目を逸らさない。この力から逃げないと決めた。今まで感じていた恐怖や嫌悪は、使命感へと変わりつつあった。
透は受話器を取り、警察に匿名で通報することも考えた。だが、それはあまりに不確実だ。これは、自分自身が向き合うべき運命なのだ。彼は図鑑の巻末に挟まっていた、老婆が書いたであろう住所のメモを見つめた。
窓の外に広がる街の景色が、以前とはまるで違って見えた。建物の壁に、行き交う人々の肩に、無数の黒い染みが蠢いている。それらはもはや不気味な汚れではなかった。これから生まれる誰かの痛みの、声なき叫びだった。救いを求める、無数の手に見えた。
それは恐ろしく、絶望的な光景のはずなのに、なぜか、ほんの少しだけ美しくさえ感じられた。彼の孤独な戦いが、今、静かに始まろうとしていた。