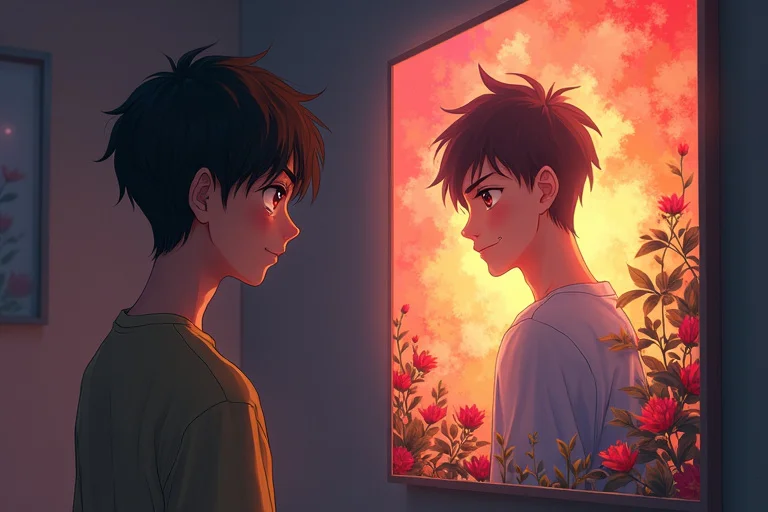第一章 夏至を待つアキラ
アキラにとって、夏至は一年で最も特別な日だった。学校の長い一日が終わり、窓の外はまだ薄明るい夕暮れ。湿気をはらんだ生ぬるい風がカーテンを揺らし、庭の紫陽花が夜露を吸って色濃く見える。今日という日が終われば、あの娘に会える。その期待は、彼の胸を高鳴らせるのと同時に、得体の知れない不安を連れてくる。
毎年夏至の夜、アキラは家の裏手にある古い桜の木の下で、ユイを待った。彼女は、月明かりが枝葉の間から漏れる頃、ふっと、まるで空気の振動が形になったかのように現れる。肌は透けるように白く、光を宿した瞳は吸い込まれそうなほど深い翠色をしていた。現実離れした美しさは、アキラにとって慣れ親しんだ日常の一部だった。ユイはアキラのたった一人の秘密の友人であり、他の誰にもその存在を明かせない、彼だけの宝物だった。
ユイがこの世界に姿を現すのは、夏至から数日間だけ。最初は一週間だった。やがて五日、三日と、その期間は年々短くなっていった。アキラは、その事実をどこか認めまいとしながらも、毎年その変化に怯えていた。
「アキラ!」
桜の木の下でぼんやりと空を見上げていたアキラの耳に、鈴を転がすような、しかし少しだけ掠れた声が届いた。振り返ると、そこにはいつものように、しかしどこか儚げなユイが立っていた。彼女の白いワンピースは、風もないのに微かに揺れている。
「ユイ!今年も来てくれたんだね!」
アキラは駆け寄って、彼女の手を取ろうとした。指先が触れる寸前で、ユイはすっと手を引いた。
「ごめん、アキラ。まだ、ちょっと体が安定しなくて」
寂しげな笑みを浮かべるユイの言葉に、アキラの胸が締め付けられる。毎年、彼女がこの世界に現れる初日は、常に不安定で、すぐに消えてしまいそうな危うさがあった。だが、今年は例年になく、その気配が強い。
アキラは気を取り直して、彼女に最近あった出来事を語り始めた。学校でのこと、クラスメイトとの些細な喧嘩、新しく読んだ本の感動。ユイはいつも、どんな話でも真剣な眼差しで聞いてくれた。そして、時折、アキラが知らない世界のことを教えてくれた。遠い宇宙の星々の話、深い海の底に眠る古代文明、あるいは、時を超えて紡がれる物語。彼女の言葉は、アキラの日常に色鮮やかな夢を描き出し、彼の心を豊かにした。
夜が更け、蝉時雨が遠くで聞こえる頃、ユイはいつものようにアキラの顔を覗き込んだ。
「ねえ、アキラ。私、今年、なんだか体が重いんだ」
「重い?」
「うん。まるで、砂時計の砂が落ちるみたいに、私の時間がどんどん減っていくのを感じる。来年は、もっと短くなるかもしれない」
ユイの声は、今にも消え入りそうだった。その言葉は、アキラの心に冷たい鉛を流し込む。彼はユイを失うことへの恐怖を、毎年募らせていた。来年は、もっと短くなる?その言葉が、アキラの胸に深く刺さり、彼の日常に不穏な影を落とした。ユイの翠色の瞳が、夜の闇に吸い込まれていくように見えた。
第二章 消えゆく影と探求の始まり
ユイとの再会から一日、二日と時間が過ぎるたびに、彼女の存在は確かになっていった。アキラは、今年もユイと共に過ごせる限られた時間を慈しんだ。二人で秘密基地で遊んだり、街の図書館で彼女が教えてくれた世界のことを調べたりした。ユイの知識は、アキラの知的好奇心を刺激し、世界にはまだ見ぬ不思議が満ちていることを教えてくれた。しかし、一方で、彼女の姿は年々薄くなっているように感じられた。声に張りはなくなり、触れることのできない時間が長くなった。
今年、ユイはアキラに、一つの不思議な歌を教えてくれた。それは、言葉にならないようなメロディと、意味不明な単語の羅列でできた、子守唄のような歌だった。ユイは歌い終えると、アキラの頭を優しく撫で、寂しげに微笑んだ。
「この歌、私がお腹の中にいた頃から知ってるんだ。不思議だよね」
ユイの言葉に、アキラは違和感を覚えた。「お腹の中にいた頃」という表現。まるで、彼女が人間であるかのように。しかし、ユイは人間ではない。アキラはそう信じていた。そうでなければ、彼女が毎年消え、そして現れることの説明がつかない。
ユイが「来年はもっと短くなるかもしれない」と言った夜から、アキラの心は落ち着かなかった。なぜ、ユイは実体を持てる期間が短くなるのか。そして、なぜ毎年、アキラは夏至の夜まで彼女の存在を深く考えずに過ごしてしまっていたのか。彼は、まるで夏の終わりの夢のように、ユイの記憶がぼんやりとした輪郭しか持たなかったことに、今更ながらに気づいた。
アキラはユイの正体を探り始めた。図書館で「異界の存在」「期間限定の友」「記憶を失う」といったキーワードで調べた。インターネットでも、様々な都市伝説や民話、哲学的な概念に触れた。しかし、どれもユイの状況にぴったりと当てはまるものは見つからなかった。
ある日、ユイがアキラの古い絵日記を見つけた。それはアキラが幼い頃に描いた、家族との穏やかな日常や、初めて自転車に乗れた日の喜びが綴られたものだった。しかし、あるページを境に、絵日記の内容は急変していた。激しい雨の絵、病院のベッド、そして何よりも、寂しそうなアキラの自画像が繰り返し描かれていた。
「アキラ、この絵は……?」ユイが心配そうに尋ねた。
「ああ、これは……」アキラは言葉を詰まらせた。そこから先の記憶は、曖昧だった。幼い頃、大きな交通事故に遭い、両親を一度に失ったこと。彼自身も生死の境をさまよい、心に深い傷を負ったこと。その後のことは、なぜか明確に思い出せなかった。まるで、大切な記憶が、すっぽりと抜け落ちているかのように。
「この絵の女の子……」ユイは、アキラが描いた小さな女の子の絵を指差した。「私に似ているね」
アキラが描いたその女の子は、ユイによく似ていた。翠色の瞳、白い肌。しかし、その絵は、ユイに出会うよりもずっと前の、アキラがまだ幼かった頃の絵日記に描かれていた。
その瞬間、アキラの胸に言いようのないざわつきが走った。ユイは、本当に「外の世界」から来た存在なのだろうか?それとも……。
ユイは、アキラが戸惑っているのを見て、そっと絵日記を閉じた。
「そろそろ、時間だね」
彼女はそう言って、寂しげに微笑んだ。アキラは、彼女の笑顔が、何かを隠しているように感じられた。そして、今年の夏至の終わりは、例年以上に速く訪れた。ユイはほとんど消えかかった声で、「来年、またね」と囁き、まるで砂のように、彼の目の前で静かに崩れ落ちていった。
第三章 記憶の扉、真実の淵へ
ユイが消えてからの日々は、アキラにとって生きた心地がしなかった。彼の頭の中は、ユイの存在と、なぜ彼女が年々短くなるのかという疑問で埋め尽くされていた。そして、幼い頃の絵日記に描かれた「ユイに似た女の子」の絵が、彼の心を離れなかった。あの空白の記憶。両親を失った後の、彼自身の心の闇。
アキラは、幼い頃から通っていた心療内科のカルテを取り寄せた。そこには、彼の両親が事故で亡くなった後、彼が重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)を患い、長い間、感情の麻痺と現実逃避の状態にあったことが記されていた。そして、彼の心を救うために、当時のカウンセラーが「イマジナリーフレンド」の存在を奨励していたことまで。
「イマジナリーフレンド……?」
アキラは思わず息をのんだ。目の前が真っ白になるような感覚に襲われた。まさか。そんなはずはない。ユイは現実の存在だ。毎年夏至に会いに来てくれる、アキラのたった一人の大切な友人だ。しかし、彼の脳裏には、ユイが語った「お腹の中にいた頃から知ってる歌」という言葉が蘇る。そして、彼の絵日記に描かれた、ユイにそっくりの女の子の絵。
アキラは、失われた記憶を取り戻そうと必死になった。昔の写真を探し、親戚に話を聞いた。祖母は、彼が事故の後、塞ぎ込んでばかりいたが、ある時期から急に活発になり、誰にも言えない秘密の友達と遊んでいると言い出した、と語った。
「あの頃のアキラは、本当に苦しそうだったから、おばあちゃんは、秘密の友達なんていないって、ずっと知っていたけど、何も言わなかったんだよ。その子がアキラを笑顔にしてくれたからね」
祖母の言葉は、アキラの心臓を鷲掴みにした。ユイは、現実の存在ではなかった。彼女は、幼いアキラが、心の傷から逃れるために、無意識のうちに生み出した「理想の友人」だったのだ。
全てのピースが、おぞましいほど完璧にはまり込んでいく。ユイが実体を持てる期間が年々短くなっていたのは、アキラ自身の心が癒え、彼女への依存が減っていくにつれて、彼女の存在意義が薄れていたからだ。彼女は、アキラの「心の傷」が具現化したものであり、彼の心が回復すればするほど、その実体を維持できなくなっていたのだ。
そして、最も残酷な真実がアキラを襲う。
ユイが実体を持てない期間、アキラが彼女を完全に忘れてしまっていたのは、ユイ自身がアキラの記憶に働きかけ、自分の存在を覆い隠していたからだった。彼女は、アキラが過去の傷に囚われず、現実世界で新しい友情や人生を築けるように、自らアキラの記憶から消えることを選んでいたのだ。アキラの負担にならないように、彼が現実を生きられるように、毎年、自分の存在を薄れさせていた。
「嘘だ……」
アキラは床に座り込み、両手で頭を抱えた。これまで「友情」だと思っていたものが、実は自分自身の作り出した「幻影」だった。それだけでも衝撃なのに、その幻影が、自分自身の幸せのために、自らを犠牲にしていたという事実。彼の価値観は、根底から揺らぎ、崩壊した。これまでユイに会える日を心待ちにしていた純粋な喜びは、途方もない罪悪感と悲しみに変わった。彼は、何て残酷なことをしてしまっていたのだろう。ユイは、最初からずっと、アキラの幸せを願う「彼自身の心」そのものだったのだ。
第四章 最後の夏至の約束
来年の夏至が来た。しかし、アキラはもう、桜の木の下でユイを待つことはしなかった。彼は、この一年間、ずっとユイの真実と向き合い、自分自身と向き合ってきた。幼い頃の心の傷が、どれほど彼を蝕み、そしてユイという存在を通して、どれほど深く彼を支えてくれていたか。
アキラは、ユイが教えてくれたあの不思議な歌を口ずさみながら、彼女がいつも座っていた桜の木の根元に、手作りの小さな花冠を置いた。それは、ユイが毎年、出会いの日に作ってくれた、あの花冠を模したものだった。
日が傾き、薄紫色の空が広がる頃、アキラは微かな気配を感じた。視線を上げると、桜の木の下に、ほとんど透明になったユイが立っていた。彼女の白いワンピースは、風もないのに揺れていた。
「アキラ……」
彼女の声は、か細く、今にも消え入りそうだった。
アキラはゆっくりと立ち上がり、ユイの前に歩み寄った。もう、触れることはできない。彼には分かっていた。
「ユイ……ごめん」
アキラの目から、大粒の涙が溢れ落ちた。
「僕、ずっと君の本当の気持ちに気づいていなかった。君が、僕のために、毎年どれだけ心を痛めていたか……」
ユイは、悲しげに、そして優しく微笑んだ。
「ううん、アキラ。気づかなくて、よかったんだよ。それが、私の願いだったから」
彼女の翠色の瞳が、月明かりに照らされて、かすかに輝いた。
「アキラが、もう私に頼らなくても、自分の足で歩けるようになった。それが、私にとって最高の幸せ」
ユイの言葉は、アキラの心の奥深くに響いた。彼女は、アキラが忘れていた過去の苦しみを共に背負い、彼が癒えるまで、ずっと傍にいてくれた。そして、彼が自立する時が来たなら、迷わず消えることを選んだのだ。
アキラは、涙を拭い、まっすぐにユイを見つめた。
「ありがとう、ユイ。君が教えてくれたこと、僕は決して忘れない。君がくれた友情も、僕のためにしてくれたことも。君は、僕の心の中に、ずっと生き続ける」
ユイは、満足そうに、そして少しだけ寂しそうに目を閉じた。
「アキラ。あの歌、覚えてる?」
アキラは頷き、ユイが教えてくれた、あの不思議な子守唄を、震える声で歌い始めた。それは、ユイが語った「お腹の中にいた頃から知っている歌」であり、紛れもなく、幼いアキラが心の奥底で紡ぎ出した、希望の歌だった。
アキラの歌声が夜空に響き渡る中、ユイの姿はゆっくりと、しかし確実に薄れていった。光の粒子のようになり、そして、夜風に溶けるように、完全に消え去った。
アキラは、もう桜の木の下でユイを待つことはないだろう。彼の心には、決して埋まることのない深い喪失感と、感謝の念、そしてユイが残してくれた、温かい友情の記憶が深く刻まれていた。ユイは消えたが、彼女がアキラの心に残したものは、決して消えない。それは、彼が現実世界で新しい友情を築き、人生を歩んでいくための、揺るぎない礎となるだろう。友情とは、形あるものではなく、心に宿る光だ。アキラは、その光を胸に、静かに夜空を見上げた。月が、花冠を優しく照らしていた。