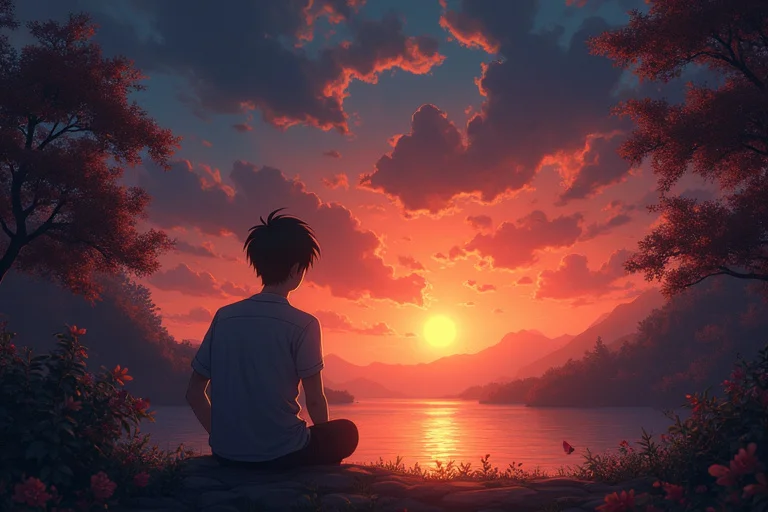第一章 不協和音の依頼人
古びた時計の部品と油の匂いが染みついた僕の工房に、その女性、水無月小夜(みなづきさよ)は、まるで場違いな美しい音色のように現れた。霧深い港町の午後の光が、彼女の白いワンピースを淡く照らし、背後の煤けた壁との対比を際立たせていた。
「響(ひびき)朔太郎(さくたろう)さん、でいらっしゃいますか」
澄んだ声だった。だが、僕の耳には、その声の背後で別の音が鳴り響いていた。他人の嘘を聞くと、僕の頭の中では音楽が再生される。ある事故以来、僕に憑りついて離れない呪いのような能力だ。
「ええ。時計の修理なら、あちらのカウンターへ」
僕は、手元の懐中時計から目を離さずに答えた。人と目を合わせるのは苦手だった。視線が合うと、相手の心のざわめきまで音として拾ってしまうからだ。
「時計では、ないんです」彼女はそう言うと、ビロードの布に包まれた小さな木箱をカウンターに置いた。「これを、お願いしたくて」
開かれた箱の中にあったのは、螺鈿細工が施されたアンティークのオルゴールだった。しかし、その姿は痛々しいほどに歪み、一部は砕けていた。
「婚約者が、遺したものです。彼が失踪する直前まで、大切にしていたものでした」
水無月小夜は、一週間前に忽然と姿を消した天才作曲家、霧島怜(きりしまれい)の婚約者だった。ニュースでも連日、彼の名前が報じられている。警察は事件と事故の両面で捜査しているが、手掛かりはないという。
「彼を、心から愛していました。だから、これが彼の唯一の形見になってしまうのなら、せめて元の音色を取り戻してあげたいのです」
その言葉が発せられた瞬間、僕の世界は変容した。彼女の背後で、荘厳なチェロが悲しみの旋律を奏で始める。しかし、その美しい調べに、まるでガラスを引っ掻くような鋭いヴァイオリンの不協和音が突き刺さった。高く、細く、痛みを伴う嘘の音。それは単純な偽りではなかった。深くねじれた、真実と嘘が混ざり合った複雑な和音だった。
僕はかつて、調律師だった。完璧なハーモニーを追求する日々に誇りを持っていた。だが今では、世界が奏でる不協和音に耐えきれず、人の感情から最も遠い、時を刻む機械とだけ向き合う生活を選んだ。
「……お預かりします」
断るべきだった。このオルゴールに触れることは、僕が捨てたはずの世界に再び足を踏み入れることを意味する。だが、僕の指は、まるで吸い寄せられるようにその冷たい木箱に触れていた。彼女が奏でる、あまりにも悲しく美しい「偽りのアリア」の正体を、調律師としての本能が知りたいと叫んでいた。彼女が工房から去った後も、耳の奥では、チェロとヴァイオリンの歪んだ二重奏が、いつまでも鳴り響いていた。
第二章 鳴らないメロディ
オルゴールの修理は困難を極めた。内部の櫛歯(くしば)は数本が折れ、シリンダーのピンも歪んでいた。僕はルーペを目に当て、ピンセットを使いながら、一つ一つの部品を丁寧に修復していく。それは、バラバラになった記憶の断片を繋ぎ合わせる作業に似ていた。
数日後、再び小夜が工房を訪れた。進捗を尋ねる彼女の言葉の端々から、僕は相変わらずの不協和音を聞き取っていた。怜との思い出を語る時、彼女の音楽は特に複雑になった。楽しかったはずの記憶を語る声には、なぜかオーボエのむせび泣くような旋律が重なり、彼の才能を賞賛する言葉には、ティンパニの脅えるような連打が混じり込んだ。彼女の嘘は、悪意によるものではない。むしろ、何か巨大な感情を必死に覆い隠そうとする、悲痛な叫びのように聞こえた。
「彼は……天才でした。彼の音楽は完璧で、一点の曇りもなかった。私のような凡人が、隣にいていいのか、いつも不安でした」
その告白には、嘘の音は混じっていなかった。ただ静かで、透明なピアノのアルペジオが響くだけだった。僕は、彼女の不協和音の正体が、少しだけ分かったような気がした。
オルゴールのシリンダーを修復している時、僕は奇妙なことに気づいた。ピンの配列が、本来の曲とは明らかに異なる箇所がいくつかあるのだ。それは製造時のミスとは思えない、意図的な改変だった。まるで、暗号だ。僕は記憶を頼りに、その不規則なピンが示す音を五線譜に書き起こしていく。それは、断片的な、意味をなさないメロディだった。
僕は決心し、霧島怜の周辺を調べ始めた。彼の弟子だという若いヴァイオリニストに会うと、彼は怜を神のように崇める言葉を口にした。だが、その声の奥では、嫉妬に歪んだトランペットが甲高いノイズを撒き散らしていた。怜のパトロンだった老婦人は、彼の失踪を嘆きながらも、その音楽の裏にはホルンの安堵したような低い響きが流れていた。誰もが、怜について何かを偽っていた。彼らの奏でる不協和音は、まるで怜という指揮者を失い、てんでんばらばらに鳴り響くオーケストラのようだった。
僕の中で、一つの疑念が芽生え始めていた。彼らは皆、怜の才能という強烈な光に当てられ、歪んだ影を抱えていたのではないか。そして、その影の中心にいた怜自身は、一体どんな音を奏でていたのだろう。
工房に戻り、僕は書き留めた楽譜の断片と、関係者たちから聞いた「嘘の音楽」のパターンを頭の中で重ね合わせた。すると、バラバラだった音符が、ある一つの旋律を形作り始めるのが分かった。それは、恐ろしく悲しい、しかしどこまでも美しいフーガだった。そして、その旋律が指し示す場所は、ただ一つしかなかった。この港町の外れにある、今は使われていない古い灯台だ。
第三章 真実のフーガ
霧雨がアスファルトを濡らす夜、僕は車を走らせ、灯台へと向かった。錆びついた鉄の扉を開けると、螺旋階段が暗闇の奥へと続いている。一段一段、慎重に登っていく。頂上に近づくにつれて、微かな音が聞こえてきた。それは、人の声でも、楽器の音でもない。風の音、波の音、雨粒が窓を打つ音。自然が奏でる、ありのままの純粋な音だった。
灯台の最上階、灯室の中央に、一人の男がいた。痩せた背中を丸め、窓の外の荒れる海をじっと見つめている。霧島怜。彼は死んでもいなければ、誘拐されてもいなかった。自らの意志で、ここにいたのだ。
僕の足音に気づき、彼がゆっくりと振り返る。その目は、全てに疲れ果てたように深く窪んでいた。
「君か。やはり、君が来たか」
彼の声には、嘘の音は全く混じっていなかった。だが、その代わり、音が何もない、完全な「無音」だった。まるで、彼の内なる何かが、音を奏でることを完全にやめてしまったかのようだった。
「あのオルゴールは、メッセージだった。僕と同じ呪いを背負った人間になら、届くはずだと信じていた」
僕は息を呑んだ。彼もまた、僕と同じ能力の持ち主だったのだ。
「いつから聞こえるんだ?世界の不協和音が」怜は自嘲するように笑った。「僕は物心ついた頃からだ。人の言葉はいつも、嘘の雑音に塗れていた。愛の言葉は嫉妬の金切り声に、励ましの言葉は侮蔑の低音に。だから音楽に逃げた。そこだけが、唯一の調和が許された世界だったからだ」
彼は語り続けた。自分の周りが嘘の音楽で満ちていることへの絶望を。そして、最も彼を苦しめたのが、愛する婚約者、小夜が奏でる不協和音だったことを。
「彼女の嘘は、僕を愛していないというものではなかった。もっと根深く、悲しい嘘だ。『私はあなたの隣に立つにふさわしい』『あなたの才能を完璧に理解している』……彼女は僕のために、必死に自分を偽り続けていた。その無理に奏でる美しい旋律と、その裏で悲鳴を上げる不協和音が、僕の心を少しずつ壊していったんだ」
耐えられなくなった彼は、全てを捨てることにした。自らの失踪を演出し、嘘の音が存在しないこの場所で、ただ一つの「真実の音」だけで構成された究極の楽曲を完成させようとしていたのだ。
僕は黙って彼に近づき、携えてきた修復済みのオルゴールを置いた。そして、そっとネジを巻く。
澄み切った音色が、灯室に響き渡った。それは、怜がかつて小夜のためだけに作った、優しく、愛に満ちたメロディだった。何の歪みもない、完璧なハーモニー。
「不協和音は、嘘だけじゃない」僕は静かに言った。「それは、人の弱さや、悲しみ、守りたいものの音でもある。あなたは、彼女の不協和音の奥にある、本当の心の音を聞こうとしなかった。ただ、自分の耳を塞いだだけだ」
怜は、オルゴールの音色に耳を澄ませながら、子供のように嗚咽を漏らし始めた。彼の完全な無音だった心から、初めて、か細く震えるチェロの音が、ぽつりと響いた。それは、後悔と、そして微かな希望の音だった。
第四章 調律された沈黙
怜は、僕と共に灯台を降りた。彼が戻るべき場所は、警察署でも、脚光を浴びるステージでもない。ただ一人の、彼の帰りを待つ女性の元だった。
翌日、僕は水無月小夜の元を訪れ、オルゴールを返した。彼女はやつれていたが、その瞳にはどこか覚悟を決めたような強い光が宿っていた。
「彼は、戻ってきます。もう、偽るのはやめにします」
僕は何も言わず、ただ頷いた。そして、僕にしか聞こえない彼女の心の音に、そっと耳を澄ませた。
「あなたの音楽は、悲しいほど美しかった」
僕がそう告げた瞬間、彼女の張り詰めていた何かが、ふっと緩んだ。彼女の大きな瞳から、一筋の涙が静かに頬を伝う。そして、僕が初めて耳にする音が、彼女の中から響いてきた。それは、複雑なオーケストラではない。鋭い不協和音でもない。ただ、静かで、穏やかで、全てを受け入れたような、澄んだピアノの和音だった。偽りをやめた魂が奏でる、真実の響きだった。
工房に戻った僕は、窓を開け、港町の喧騒に身を委ねた。行き交う人々の声、車のクラクション、船の汽笛。その全てに、相変わらず無数の嘘の音楽が混じり合っている。世界は、不協和音で満ちていた。
だが、今の僕には、そのノイズが以前ほど苦痛ではなかった。僕は自分の耳を信じる。この喧しい不協和音の、その奥の奥に、必ず存在するはずのか細い真実の旋律を。小夜が奏でたような、怜が取り戻そうとしているような、澄んだ音を。
僕は修理台に向かい、止まっていた古い柱時計の振り子をそっと揺らした。カチ、カチ、と規則正しく、嘘のない音が工房に響き始める。その正確なリズムが、僕の乱れた心を優しく調律していくようだった。世界から不協和音が消えることはないだろう。だが、僕はもう、その音から逃げない。耳を澄まし、その一つ一つと向き合っていく。それこそが、僕という調律師に与えられた、新しい役割なのだから。