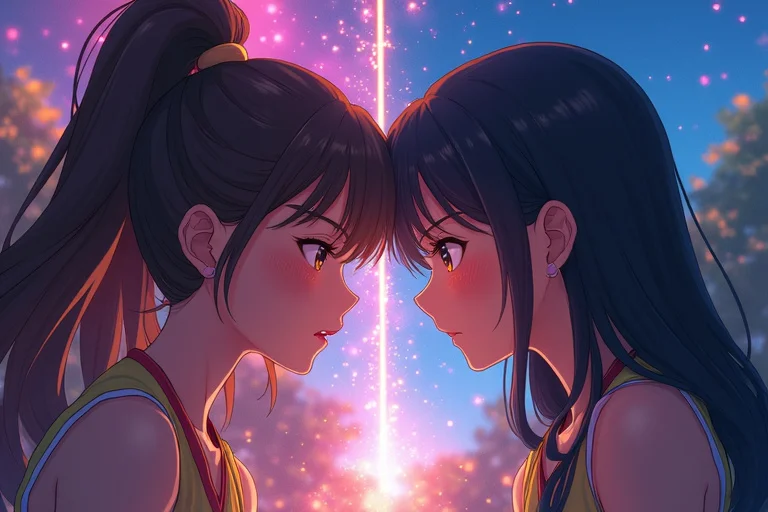第一章 口の中のビターチョコレート
それは、退屈な現代思想史の講義の最中、不意に訪れた。
僕、神崎湊(かんざきみなと)の舌の上に、何の脈絡もなく、濃厚なビターチョコレートの味が広がったのだ。カカオの含有率が高い、本格的なそれだ。苦味の奥に潜む、ほのかな酸味とフルーティーな香り。僕は何も口に含んでいない。前の席の学生がガムを噛んでいるわけでもない。講義室に漂うのは、埃と古い紙、そして微かな消毒液の匂いだけだ。
混乱する僕の意識に、さらなる異変が割り込んでくる。左の鼓膜が、サリサリという乾いた鉛筆の音を拾い始めた。右耳は変わらず、老教授の抑揚のない声を捉えているというのに。そして、瞼を閉じているわけでもないのに、視界の右半分に、窓から差し込む午後の陽光が、白い画用紙の上で柔らかな陰影を作る光景が、フィルムのように重なった。
「……神崎くん、大丈夫かね」
教授の声に我に返る。いつの間にか講義は止まり、全ての視線が僕に突き刺さっていた。僕は慌てて背筋を伸ばし、「すみません」と小さな声で謝った。
これが、僕と相葉陽(あいばはる)の間で起こるようになった奇妙な現象、『共感覚シンクロ』だった。
陽とは、大学に入ってからできた、唯一の友人だった。人との間に見えない壁を作り、自分の殻に閉じこもりがちな僕に、陽は太陽のように屈託なく話しかけてきた。僕が一人で古いモノクロ映画を観ていると言えば、「面白そうじゃん、今度付き合わせろよ」と笑い、僕が黙り込んでも、彼は気にせず隣で空のスケッチを始めるような男だった。
最初は心地よかった。僕の静寂を、彼は土足で踏み荒らすことなく、ただ隣で温めてくれる。その距離感が絶妙だった。しかし、このシンクロが始まってから、全てが変わった。
陽が感じているはずの感覚が、僕の世界に容赦なく侵食してくる。それは、彼のプライベートな領域に強制的に引きずり込まれるような、気味の悪い感覚だった。友情が深まるほど、シンクロの頻度と強度は増していく。まるで、僕らの境界線が溶けて、曖昧になっていくみたいに。
僕は怖くなった。自分の世界が、自分だけの静かな聖域が、他人の感覚によって汚されていくことが。だから、僕は陽を避けるようになった。彼の誘いを断り、彼がいる場所をわざと迂回した。友情という名の侵略から、自分を守るために。
第二章 共有された痛みと色彩
陽を避けるようになって一週間が経った。シンクロはぴたりと止み、僕の日常にはかつての平穏が戻ってきた。講義に集中でき、一人で観る映画の世界に心ゆくまで没入できる。これでいいんだ、と自分に言い聞かせた。孤独だが、安全な僕だけの世界。
だが、その平穏はどこか色褪せていた。まるで、モノクロ映画のフィルムから、さらに光と影の階調を奪い取ったかのように、世界はのっぺりと平板に見えた。
ある日の昼休み、僕は図書館の片隅で分厚い専門書を広げていた。静寂が心地いい。そう思った瞬間、左腕にガラスが突き刺さるような、鋭い痛みが走った。思わず「うっ」と呻き声を漏らし、腕を押さえる。だが、僕の腕には何の傷もない。ワイシャツの袖は白く、血の一滴も滲んでいなかった。
これは、陽の痛みだ。直感的にそう悟った。彼は今、どこかで怪我をしたのだ。僕が感じたのは、物理的な痛みだけではなかった。痛みの奥にある、彼の「しまった」という焦りや、じわりと広がる熱のような感覚まで、生々しく伝わってきた。
数分後、痛みが嘘のように引いていくと同時に、僕の心には形容しがたい感情が渦巻いた。安堵と、そして言いようのない罪悪感。彼が危険な目に遭っているかもしれないのに、僕は何もできない。いや、何もしようとしない自分を選んだのだ。
その日の夕方、僕は陽にばったりと会ってしまった。彼の左腕には、痛々しい包帯が巻かれていた。
「よう、湊」
陽はいつもと変わらない笑顔で手を振る。
「その腕、どうしたんだ」
僕は努めて冷静に尋ねた。
「ああ、これ?美術室の準備中に、ガラスケースを倒しちゃってさ。大したことないよ」
「……そうか」
それ以上、言葉が続かなかった。何か言わなければ。心配していると、伝えるべきだ。だが、喉に何かがつかえて声が出ない。今、ここで彼に優しさを見せれば、またあの侵食が始まってしまう。
「湊、最近、俺のこと避けてるだろ」
陽の声のトーンが少しだけ低くなる。僕は視線を落とした。
「別に……」
「嘘つくなよ。なんか、俺、お前に悪いことしたか?」
真剣な眼差しが僕を射抜く。僕は耐えきれず、最も残酷な言葉を選んでしまった。
「君といると、疲れるんだ」
陽の顔から、すっと表情が消えた。彼の瞳が、見たことのない色に揺らぐのを僕は見た。それは、僕が彼に与えた痛みだった。共有されることのない、一方的な痛み。彼は何も言わず、僕の横を通り過ぎていった。
その夜、僕は自分の部屋で一人、膝を抱えていた。陽との繋がりを断ち切ったはずなのに、胸に空いた穴は広がるばかりだった。彼が見せてくれた鮮やかな世界、彼が感じていた純粋な喜びや驚きが、僕の灰色の日常をどれほど彩ってくれていたか。失って初めて、その大切さに気づくなんて、あまりにも愚かだった。
第三章 暗闇の中のスケッチブック
陽と会わなくなって、一ヶ月が経った。シンクロは完全に消え、僕の日常は完璧な静寂を取り戻した。だが、その静寂は墓場のように冷たく、僕の心を蝕んでいった。
ある金曜日の深夜、ベッドで本を読んでいた僕の視界が、前触れもなくブラックアウトした。停電ではない。瞼を閉じているのとも違う。それは、光が一切存在しない、絶対的な無。冷たい空気が肌を撫で、息が詰まるような圧迫感が全身を襲う。遠くで、ぽつり、ぽつりと、規則的な水滴の音が響いていた。
恐怖で心臓が凍りついた。これは僕自身の感覚ではない。陽だ。陽に、何かとんでもないことが起きている。
僕はパニック状態でベッドから飛び起き、スマートフォンの明かりを頼りに陽に電話をかけた。コール音は虚しく響くだけで、誰も出ない。何度も、何度もかけ続けたが、結果は同じだった。
暗闇のビジョンは数分で消え、自分の部屋の慣れた光景が戻ってきた。しかし、僕の中に刻まれた恐怖と焦燥は消えなかった。いてもたってもいられず、共通の友人に片っ端から連絡を取った。そこで、陽が古い廃墟を探検するのが趣味で、特に海沿いの古い療養所跡によく行っていたという話を聞き出した。
僕はコートを羽織ると、アパートを飛び出した。終電はもうない。タクシーを拾い、震える声で行き先を告げる。運転手は訝しげな顔をしたが、何も言わずに車を発進させた。
一時間後、月明かりに照らされた不気味なシルエットが姿を現した。療養所跡だ。僕はスマートフォンのライトを頼りに、崩れかけた建物の中へと足を踏み入れた。カビと潮の匂いが混じった空気が、肺を満たす。
「陽!いるのか、陽!」
叫びながら、瓦礫の散らばる廊下を進む。返事はない。僕の心臓は破れそうなほど高鳴っていた。あの暗闇と水滴の音。地下だ。きっと地下にいる。
崩れた床の一部に、地下へと続く階段を見つけた。慎重に降りていくと、そこは水が溜まった空間になっていた。そして、その水たまりの中に、うつ伏せで倒れている人影があった。
「陽!」
僕は駆け寄り、彼の体を抱き起こした。額から血を流し、意識がない。どうやら階段から足を踏み外して転落したらしい。僕は震える手で救急車を呼んだ。
病院の白い廊下で、僕は陽の意識が戻るのを待ち続けた。彼の荷物の中から、一冊のスケッチブックが滑り落ちた。何気なく拾い上げ、ページをめくった僕は、息を呑んだ。
そこに描かれていたのは、僕が見ていた世界だった。僕が一人で観ていたモノクロ映画のワンシーン。僕が読んでいた本の、活字が並ぶページ。僕の部屋の窓から見える、電線に縁取られた夕焼け。そして、講義中に僕が見ていた、退屈な教授の後ろ姿まで。
最後のページには、鉛筆でこう書かれていた。
『湊の世界は、静かで、少し寂しい。でも、とても優しい色をしている。俺は、その色が好きだ』
涙が、スケッチブックの上に落ちて染みを作った。僕は、陽からの侵食を恐れていた。だが、陽は、僕から流れ込んでくる世界を、こんなにも愛おしく思い、受け止めてくれていたのだ。彼もまた、僕の世界を感じていた。僕が彼を拒絶した時、彼はどんなに傷ついただろう。暗闇に落ちた時、どんなに心細かっただろう。僕が感じたのは、彼の絶望の、ほんのひとかけらに過ぎなかったのだ。
第四章 二人の地平線
陽の意識が戻ったのは、翌日の昼過ぎだった。僕はずっと、彼の手を握っていた。
「……みな、と?」
掠れた声で僕の名を呼んだ陽に、僕は堰を切ったように泣きじゃくった。
「ごめん、陽、ごめん……!」
謝罪と後悔の言葉が、支離滅裂に口から溢れ出る。陽は驚いたように目を瞬かせた後、ゆっくりと微笑んだ。
「お前が助けてくれたんだろ。……暗闇の中でさ、ずっとお前のこと考えてた。そしたら、お前の部屋の夕焼けが見えたんだ。不思議だよな」
彼の言葉に、僕はさらに涙を流した。僕らが感じていたのは、一方的な侵食ではなかった。それは、言葉に頼らない、魂の対話だったのだ。
「お前の見てる世界、結構好きだったんだぜ」
陽は、包帯の巻かれていない方の手で、僕の頭を優しく撫でた。
退院後、僕らの関係は以前よりもずっと深く、確かなものになった。シンクロは、今も時々起こる。でも、もはやそれは恐怖や煩わしさの対象ではなかった。
ある晴れた午後、僕らは海辺の丘に座っていた。陽はスケッチブックを広げ、僕は文庫本を開いている。不意に、僕の視界に、陽が見ているカモメの群れが飛び込んできた。空の青と、鳥たちの白い翼が鮮やかなコントラストを描く。それは僕の視界と混じり合い、まるで本の活字の上をカモメが飛んでいるかのような、不思議な光景を生み出した。
「すごいな、今」
僕が言うと、陽がにやりと笑った。
「お前こそ。今、この潮風が、お前が読んでる本のインクの匂いがする」
僕らは顔を見合わせて、声を出して笑った。
僕らの世界は、これからも時々、混じり合うだろう。共有される感覚は、時に不便で、時に痛みを伴うかもしれない。でも、それは孤独だった二つの魂が、互いの存在を確かめ合うための、かけがえのない奇跡なのだ。
友情とは、相手の世界を自分のものとして感じることなのかもしれない。たとえそれが、自分の世界の一部を、その境界線を、少しだけ明け渡すことになったとしても。その不確かで不自由な繋がりこそが、人を孤独という名の暗闇から救い出してくれる、唯一の光なのかもしれない。
僕の視界に広がる地平線は、陽が見つめる地平線と、今、確かに一つに重なっていた。