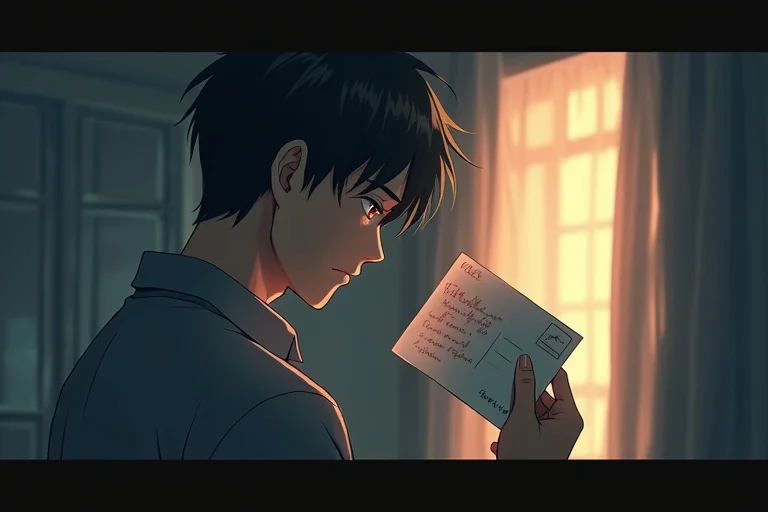第一章 沈黙の香り
柏木湊(かしわぎ みなと)の世界は、香りで満ちていた。ただし、それは花や香水といった物理的な匂いではない。彼が嗅ぎ取っているのは、人が物に遺した「感情の残り香」だった。古書店『往来堂』の店主である彼にとって、その能力は呪いであり、同時に天職でもあった。古い本には、持ち主の様々な感情が染みついている。ページをめくるたびに、インクと古紙の匂いに混じって、静かな喜びや、インクの染みのような悲しみ、あるいは紙魚(しみ)のように潜んだ嫉妬の香りが、彼の鼻腔をくすぐるのだ。
だから湊は、人と深く関わることを避けてきた。人の感情はあまりに強く、生々しく、彼の心を乱す。静かな書架に囲まれ、過去の持ち主たちの遠い感情の残滓に触れている方が、ずっと穏やかでいられた。
その日も、湊はカウンターの奥で、値付けの終わった文庫本の背を布で拭いていた。ちりん、とドアベルが鳴り、一人の女性が入ってくる。年の頃は湊と同じくらいだろうか。少し緊張した面持ちで、大きな段ボール箱を二つ、床に置いた。
「すみません、古本の買い取りをお願いしたいのですが」
「はい、どうぞ」
湊は立ち上がり、箱に近づいた。彼女、早川栞(はやかわ しおり)が言うには、先日亡くなった祖父の蔵書だという。湊が箱の蓋を開けた瞬間、ふわりと舞い上がった埃と共に、彼の意識を強く揺さぶる香りがした。
それは、今まで嗅いだことのない、あまりに複雑で、深く、そして美しい香りだった。
雨上がりの森の、湿った土と若葉が放つような清冽な安堵。その奥に、錆びた鉄の匂いを思わせる、鋭い後悔の念。そしてそれら全てを包み込むように、冬の陽だまりのような、穏やかで温かい愛情の香りが、確かに存在していた。これほどまでに相反する感情が、完璧な調和を保って一つの香りを成していることに、湊は眩暈さえ覚えた。
「あ、の……何か?」
栞が不安そうに湊の顔を覗き込む。我に返った湊は、慌てて咳払いをした。
「いえ、失礼。素晴らしい蔵書ですね。大切にされていたのが、伝わってきます」
それは嘘ではなかった。だが、湊が本当に伝えたかったのは、この本の持ち主が抱えていた、言葉にならないほどの想いの深さだった。
「祖父は……無口な人でした。本が好きで、いつも書斎に籠ってばかり。正直、どんな人だったのか、よく分からないんです」
栞は寂しそうに微笑んだ。その言葉と、本から立ち上る香りとの間にある、あまりに大きな隔たり。湊は、この香りの正体を知りたいと、強く思った。人との関わりを避けてきたはずの心が、静かに警鐘を鳴らすのを無視して、彼は口を開いていた。
「もしよろしければ、少しお時間をいただいて、一冊ずつ拝見してもよろしいですか。急な話でなければ、ですが」
その申し出は、古書店の店主として不自然なものではない。しかし湊の胸には、単なる好奇心とは違う、熱い何かが込み上げていた。この沈黙の香りが語る物語を、どうしても聞きたかったのだ。
第二章 頁の記憶
それから数日、栞は時間を見つけては店を訪れ、湊と共に祖父の蔵書を整理することになった。湊の「一冊ずつ丁寧に価値を判断したい」という言葉を、彼女は真摯に受け止めてくれた。
作業は、まるで記憶の地層を掘り起こしていくようだった。湊は一冊の本を手に取るたび、栞の祖父が生きた時間の断片を追体験していた。
海辺の町を舞台にした恋愛小説からは、潮風と混じり合った、初恋の甘酸っぱい高揚の香りがした。
「この本を読んでいた時、お祖父様はきっと、誰かに恋をしていたんでしょうね。とても幸せそうです」
湊がそう言うと、栞は驚いて目を丸くした。
「祖母との馴れ初めです。祖父は港町で、船乗りの祖母に一目惚れしたと、一度だけ聞いたことがあります」
経済学の難解な専門書には、事業に失敗したのだろうか、ひどく焦げ付いたような絶望と、それでも諦めきれない執念の匂いが染みついていた。湊がその気配を告げると、栞は頷いた。
「若い頃、一度だけ事業を起こして、大失敗したそうです。その時の借金を返すために、祖父は随分苦労したと……」
そして、一冊の使い古された絵本。そのページからは、焼きたてのパンのようにふっくらと温かく、一点の曇りもない純粋な歓喜の香りがした。湊がそれを手に取っただけで、胸が温かくなるような香りだった。
「これは……栞さんがお生まれになった頃に、読んでいた本ではないでしょうか。言葉にできないほどの、喜びの香りがします」
栞は、その絵本のタイトルを見て、はっと息を呑んだ。
「……どうして、分かるんですか? これは、私が小さい頃、祖父が毎晩読んでくれた本です。私が一番好きだった……」
彼女の声は震えていた。湊は、自分の能力のことは伏せたまま、「本の佇まいや、ページのめくられ方から、そう感じるんです。行間から、持ち主の想いが滲み出ているような気がして」と、曖昧に微笑んだ。
栞は、湊の言葉を魔法のように感じていた。彼女が知らなかった祖父の姿が、湊というフィルターを通して、次々と鮮やかに蘇ってくる。無口で、何を考えているか分からなかった祖父。その内面には、こんなにも豊かな感情の海が広がっていたのだ。
湊にとっても、この日々は大きな変化をもたらしていた。これまで彼を苛んできた他人の感情が、栞という存在を介することで、苦痛ではなく、温かい物語として心に届く。人の感情と向き合うことが、初めて怖くないと思えた。栞の、驚き、喜び、そして涙ぐむ表情を見るたびに、彼の閉ざされた世界にも、少しずつ光が差し込んでくるようだった。二人の間には、古書と香りを介した、静かで穏やかな信頼関係が築かれていった。
第三章 無臭の辞書
蔵書の整理が終わりに近づいた頃、段ボールの底から、一冊の分厚い辞書が出てきた。革の表紙は擦り切れ、角は丸くなっている。栞の祖父が、生涯使い込んできたものだろう。湊は、いつものようにその辞書を手に取り、そっと香りを嗅いだ。
そして、凍りついた。
何の香りもしなかったのだ。
無臭。それは、新品の本とも違う。新品の本には、紙とインクの、まだ誰の色にも染まっていない未来の香りがする。だが、この辞書は違った。そこにあるのは、完全な「無」だった。まるでブラックホールのように、あらゆる感情を吸い尽くしてしまったかのような、底知れない空虚さ。長年使い込まれた本に、感情の残り香が一切ないなど、あり得ないことだった。湊の能力が、初めて機能しない。いや、機能しないのではなく、「無」という状態を正確に捉えているのだ。
「どうかしましたか?」
湊の異変に気づいた栞が尋ねる。
「いえ……この辞書だけ、何も感じないんです。不思議なほどに」
栞もその辞書を受け取り、パラパラとページをめくった。彼女にとっても、それはただの古い辞書にしか見えなかった。だが、その時だった。あるページに、栞の指がふと止まった。小さな紙片が挟まっている。栞がそれを慎重に取り出すと、そこには祖父の震えるような筆跡で、短い言葉が記されていた。
『この感情だけは、誰にも渡したくない。私だけの宝物だ』
湊は息を呑んだ。そのメモが挟まっていたページの見出し語に、二人の視線が吸い寄せられる。そこに印刷されていたのは、たった一つの単語だった。
―――赦し(ゆるし)。
その瞬間、栞の指先から離れたメモが、ひらりと湊の手に触れた。
途端に、湊の全身を、今まで経験したことのない衝撃が駆け巡った。それは香りではなかった。感覚の嵐。全ての音が消え、視界の色が抜け落ち、時間が停止するような、絶対的な虚無。祖父がこの辞書に込めたであろう、感情の残滓ではなく、感情そのものを消し去った「行為」の痕跡。脳が理解を拒むほどの、強烈な意志の力。
湊は、雷に打たれたように悟った。
栞の祖父も、自分と同じだったのだ。彼もまた、感情の香りを嗅ぎ取る能力を持っていた。そして彼は、人生の最後に訪れたであろう、あまりに強大で、あまりに個人的な「赦し」という感情を、誰にも嗅ぎ取らせないために、誰にも影響を与えないために、その能力の全てを使って、この辞書に封印したのだ。これは「無臭」なのではない。感情の存在そのものを「無化」した痕跡なのだ。愛する孫娘にさえ、遺すことをためらうほどの、あまりに聖域な感情。それは、一体誰に対する「赦し」だったのだろうか。
第四章 解かれた言葉
店の窓から差し込む西日が、埃を金色に照らしていた。沈黙を破ったのは、湊だった。彼は、震える声で、栞に全てを打ち明けた。自分が「感情の残り香」を嗅ぎ取れること。その能力のせいで、ずっと孤独だったこと。そして、彼女の祖父もまた、同じ力を持っていたに違いないということ。
栞は驚きで言葉を失っていたが、彼の目をじっと見つめていた。そこには疑いの色はない。これまでの数日間、湊が語ってきた祖父の姿が、何よりの証拠だった。彼女の瞳から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「祖父も……独りだったのでしょうか。ずっと、たくさんの感情に耐えて」
「分かりません。でも、彼は最後に、その力を使って何かを守ろうとした。この『赦し』という感情を」
二人は、その辞書を前に、静かに祖父の人生に想いを馳せた。栞がぽつりと言った。
「母……私の母は、祖父が事業に失敗したことを、ずっと許していませんでした。母が苦労したのを見て育ったから。祖父が亡くなる直前まで、二人はどこかぎこちなくて……」
その言葉に、パズルの最後のピースがはまった気がした。祖父の「赦し」は、きっと、自分を許してくれなかった娘へ向けられたものであり、同時に、娘に苦労をかけた自分自身へ向けられたものでもあったのだろう。あまりに深く、複雑で、不器用な愛情の最終形態。だからこそ彼は、その聖なる感情を、誰にも汚されぬよう、そっと「無」へと還したのだ。
「僕はずっと、この力を呪わしいものだと思っていました」
湊は、自分の手のひらを見つめながら言った。
「人の感情は重くて、苦しい。だから、関わらないように生きてきた。でも、お祖父さんは違ったのかもしれない。彼は最後まで感情と向き合い、そして、それを守り抜いた。この力は、呪いじゃないのかもしれない。人と深く繋がるための、特別な贈り物なのかもしれない」
湊の目にも、熱いものがこみ上げていた。祖父の孤独な戦いは、時を超え、湊に一つの答えを教えてくれた。逃げるのではなく、受け入れ、そして、誰かのために使う。それが、この力と共に生きるということなのだ。
数日後、栞は晴れやかな顔で店を訪れた。祖父の蔵書は、湊がすべて引き取ることになった。
「この辞書は、ここに置いてください」と栞は言った。「ここが、この本の、祖父の想いが、一番安らげる場所だと思うから」
湊は、その辞書をカウンターの後ろ、一番日当たりの良い棚に置いた。栞が帰った後、湊はもう一度、そっとその辞書に手を伸ばした。
すると、どうだろう。あの絶対的な「無」は消え、代わりに、春の雪解け水のように、どこまでも透明で、穏やかな安らぎの香りが、微かに立ち上っているのを感じた。封印が解かれたわけではない。だが、孫娘に想いが届いたことで、頑なだった祖父の心が、ようやく安らぎを得たのかもしれない。
湊は、店の窓から外の往来を眺めた。行き交う人々から流れてくる、様々な感情の香り。それはもう、彼を苛むノイズではなかった。一つ一つが、誰かの人生の一部を成す、愛おしい物語の断片に感じられた。
彼は、書架に残された香りと、これから出会うであろう人々の香りに、静かに耳を澄ませる。彼の新しい人生が、今、静かに始まった。