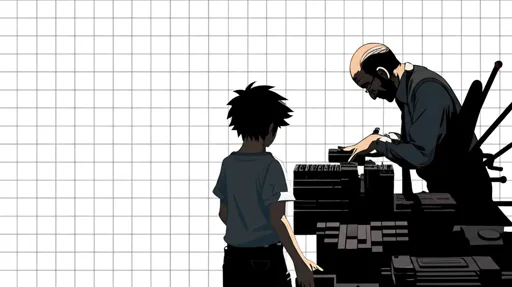第一章 過ぎ去りし音色
僕、リヒトの耳は、呪いのように祝福されていた。他人の人生における「最も輝かしい瞬間」、その人の魂が最も高らかに歌い上げたハイライトを、微細な「音楽」として聴き取ることができたのだ。
雑踏に紛れれば、そこは無数のオーケストラが同時に鳴り響くコンサートホールと化す。老紳士からは、戦後の焼け野原で妻と交わした誓いの旋律が、荘厳なパイプオルガンの音色で。向かいの席の少女からは、初めてコンクールで入賞したピアノソナタの喜びが、弾けるようなスタッカートで。
僕はその音楽を聴くたび、胸に提げたガラスの『共鳴する空の小瓶』を覗き込む。すると、聴こえてきた音色がそのまま光の粒子となり、小瓶の中で数秒間だけ、星屑のようにきらめいて舞い上がるのだ。しかし、その輝きはすぐに空気に溶けて消え、小瓶はまた虚しい「空」に戻る。過去の輝きは、決して留めてはおけない。
この世界では、人々は時折、自らの思い出を「記憶のしずく」として分かち合う。親しい者同士が思い出を語ると、手のひらに朝露のような宝石が生まれ、それを交換する。だが、その行為には代償が伴った。共有された記憶は、語り手の内側から少しずつ輪郭を失い、曖昧になっていくのだ。だからこそ、誰もが本当に大切な、魂の核となるようなハイライトの記憶は、胸の奥に固く仕舞い込んでいた。
僕は他人の過去の栄光を聴き、小瓶に一瞬の幻を映すだけ。僕自身の人生の音楽は、まだ一度も鳴ったことがない。空っぽの小瓶は、まるで僕の心のようだった。
第二章 静寂の古書店
その日、僕は雨宿りのために、路地裏にひっそりと佇む古書店に足を踏み入れた。黴とインクの混じった、どこか懐かしい匂いが肺を満たす。ぎしりと軋む床を踏みしめ、書架の迷宮を彷徨っていると、カウンターの奥で一人の女性が静かに本を読んでいた。
カノン、と名札にはあった。
彼女が顔を上げた瞬間、僕は息を呑んだ。そして、耳を澄ます。だが――何も聴こえない。完全な「無音」。僕の能力が、彼女の前でだけ沈黙している。そんなことは初めてだった。
混乱しながらも、僕は一冊の本を手に取り、会計のためにカウンターへ向かった。彼女が僕と視線を合わせ、かすかに微笑む。その時も、他の客が入店してきた時も、彼女からは何の音楽も聴こえなかった。彼女が常連客と短い言葉を交わしても、テーブルの上には「記憶のしずく」一つ生まれなかった。
この人は、人生のハイライトを持たないのだろうか? あるいは、この世界の記憶の法則から、完全に逸脱した存在なのだろうか?
静寂が、僕の心を強く掴んで離さなかった。雨の匂いが濃くなっていく中で、僕はただ、彼女という名の深淵な謎の前に立ち尽くしていた。
第三章 不協和音の正体
僕は吸い寄せられるように、カノンの古書店に通い始めた。彼女は多くを語らない。だが、その静かな佇まいには不思議な引力があった。僕たちは、本の背表紙を眺めながら、ぽつり、ぽつりとどうでもいい話をした。
ある午後、西日が差し込む店内で、僕は再び彼女の音楽を聴こうと意識を集中させた。すると、完全な無音だと思っていた彼女の内側から、ごく微かな音が聴こえてきたのだ。
それは音楽と呼べるものではなかった。オーケストラが開演前に、思い思いの楽器を鳴らし、音程を確かめているような、混沌とした「不協和音」。美しくもなければ、心地よくもない。だが、無数の可能性を秘めた、始まりの前の音。
僕はたまらず口を開いた。
「あなたの人生には……輝かしい瞬間は、なかったのですか?」
失礼な問いだと分かっていた。だが、聞かずにはいられなかった。
カノンは、指先で古い本のページをそっとなぞりながら、顔を上げた。
「輝きとは、何でしょうね」
彼女は静かに問い返した。
「過去の一点を磨き上げることでしょうか。それとも――」
言葉はそこで途切れた。だが、その問いは僕の心に深く突き刺さった。僕が今まで聴いてきた数多のハイライトは、全て過去のもの。過ぎ去った一点の輝き。それを聴くことに、一体何の意味があるのだろう。僕の信じてきた世界の輪郭が、彼女の言葉で静かに揺らぎ始めていた。
第四章 零れ落ちた記憶
街角で、けたたましいブレーキ音と人々の悲鳴が上がった。僕の顔見知りの花屋の老婆、エマさんが事故に遭い、道に倒れていた。
駆け寄ると、彼女のハイライトが聴こえた。それは初孫が生まれた日の、温かく優しい子守唄のメロディ。だが、その音色は今にも消え入りそうに弱々しく、途切れ途切れだった。
病院の白いベッドの上で、エマさんは意識が戻らなかった。医者は記憶の混濁を口にした。集まった家族たちは、涙ながらに彼女との思い出を語り合った。彼らの手のひらから、いくつもの「記憶のしずく」が生まれ、枕元にそっと置かれる。どうか、この記憶が届いてほしい、と。
しかし、その願いは残酷な法則に阻まれる。共有すればするほど、彼らの記憶は曖昧になり、エマさんの心にも届かない。誰もが、最も大切で、最も鮮やかな記憶を分かち合うことを、無意識にためらっていた。失うことが、怖かったのだ。
その時、病室の扉が静かに開き、カノンが入ってきた。彼女は何も言わず、ただエマさんの冷たくなった手を、両手でそっと包み込んだ。
第五章 創造されるハイライト
カノンがエマさんの手を握った瞬間、僕の耳の中で信じられないことが起きた。
彼女から聴こえていた混沌とした不協和音が、急速に一つの方向へと収束を始めたのだ。それはまるで、天才的な指揮者がオーケストラを掌握するかのようだった。
家族たちが共有した「記憶のしずく」の淡い光。エマさん自身の消えかけた子守唄の旋律。道端で交わした何気ない会話の断片。それら全てが音の素材となり、カノンの内側で紡がれ、編み上げられていく。不協和音は調和を取り戻し、全く新しい、壮麗で、どこまでも優しい交響曲へと昇華されていった。
これは、過去の再現ではない。「創造」だ。
カノンは、他者の思い出や関係性を素材に、その人の人生の新たなハイライトを編み上げる「調律師」だったのだ。彼女自身に過去のハイライトの音楽がなかったのは、彼女の存在そのものが、常に誰かの未来の輝きを創造するための「過程」であり「序曲」だったから。
僕が聴いていたのは、完成された曲ではなかった。今まさに、この瞬間に、誰かのために音楽が生まれる、その奇跡の現場だったのだ。
第六章 私のための序曲
奇跡は起きた。エマさんはゆっくりと目を開け、「……綺麗な夢を、見たわ」と微笑んだ。彼女の魂に、カノンが創造した新しいハイライトが、確かな記憶として刻まれたのだ。
病室を出ると、カノンは僕に向き直った。
「あなたにも聴こえましたか。これが、私のしていることです」
夜風が僕たちの間を通り抜ける。
「あなたが私と出会い、この真実を知った。そして、これからあなた自身の人生の選択をしようとしている」
彼女は僕の胸の小瓶を一瞥した。
「その瞬間を、私はずっと調律していました。だから、私の音楽はあなたには聴こえなかったのです。……あなたのハイライトを、創っていたのですから」
その言葉は、雷のように僕の心を貫いた。僕と彼女の出会い、僕の抱えていた葛藤、そして今この瞬間の気づき。それら全てが、僕自身の人生のハイライトを構成する音符だった。
僕は空の小瓶を握りしめる。もはや、そこに虚しさはなかった。僕もまた、誰かの音楽をただ聴くだけの傍観者でいることを、やめる時が来たのだ。
第七章 共鳴する未来
翌日、僕は馴染みのカフェで友人と会った。そして、カノンとの出会いから昨夜の出来事まで、全てを語り始めた。僕が言葉を紡ぐにつれて、手のひらに温かい光が集まっていくのを感じた。
やがて、僕のてのひらに、生まれて初めての「記憶のしずく」が生まれた。透き通るような輝きを放つ、僕自身の記憶。
「これを、君に」
友人にしずくを渡した瞬間、僕の頭からカノンの面影や言葉の輪郭が、ほんの少しだけ霞んだ。だが、不思議と寂しさはなかった。むしろ、喪失感を埋めるように、友人との間に確かな繋がりが生まれた温もりが、胸いっぱいに広がった。
その時だ。
僕の耳に、新しい音楽が聴こえてきた。誰かの過去のハイライトではない。僕自身の内側から、静かに、だが力強く鳴り響いてくる、未来への希望に満ちた「序曲」だった。
僕はテーブルの上に、『共鳴する空の小瓶』を置いた。それは相変わらず空っぽだったが、もう気にならなかった。人生のハイライトとは、過去の輝かしい一点を小瓶に閉じ込めて懐かしむことではない。自らの記憶を誰かと分かち合い、曖昧になる痛みすら受け入れ、その関係性の中から新しい物語を共に奏でていく、そのプロセスそのものなのだ。
窓の外でざわめく街の音が、まるで僕の序曲を祝福する壮大なオーケストラのように聴こえる。僕は、静かに微笑んだ。僕の人生の演奏は、まだ始まったばかりだ。