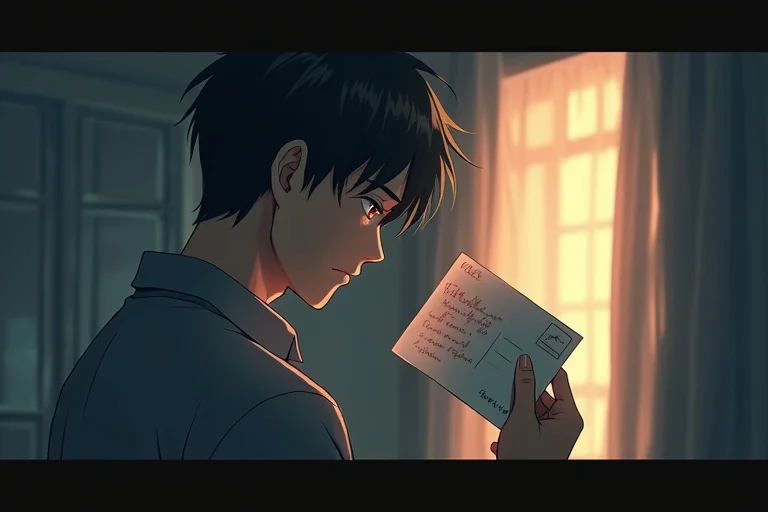第一章 鉛の雨
千景(ちかげ)にとって、雨はただの水滴ではなかった。空から降り注ぐ無数の小さな鉛だった。アスファルトを叩く雨音に混じり、すれ違う人々の肩から滴り落ちる「悲しみ」が、彼の全身に纏わりつく。濡れた外套のようにずしりと重く、一歩進むごとに足がコンクリートに沈み込むような錯覚に陥る。
「また、重そうな顔をしているな」
路地裏で古道具屋を営む老店主、時枝(ときえだ)が、店の軒先から煙管(きせる)の煙をくゆらせながら言った。店先に並ぶ埃をかぶった品々は、どれもこれも持ち主の「未練」という重さを帯びて、静かに沈黙している。ここだけは、千景にとって重さに満ちていながらも、奇妙に落ち着ける場所だった。
「雨の日は、どうもね。街全体がため息をついているみたいだ」
千景は息を吐き、肩をすくめた。喜びは風船のように心を軽くし、時には足が地に着かなくなるほど浮遊させてくれる。だが、この街に漂う感情のほとんどは、底なしの沼のように重く、暗い。特に死者が遺した「後悔」が凝固した遺恨石(いこんせき)は、触れずともその存在だけで空気を澱ませる。千景は、その重さを生まれつき感じ取ってしまう。誰にも理解されない、孤独な能力だった。
第二章 透明な壁
最近、奇妙な感覚に悩まされていた。駅前の広場。いつも多くの人々が行き交うその場所だけ、空気が歪んでいる。まるで巨大なレンズ越しに世界を見ているような、言いようのない違和感。そして、そこに足を踏み入れると、見えない壁に全身を押し付けられるような、途方もない圧力がかかるのだ。
それは、特定の誰かから発せられる感情の重さとは異質だった。方向がなく、源がわからない。ただ、そこにある。巨大な質量が空間そのものを捻じ曲げているかのような、絶対的な重力。
奇妙なことに、他の誰もその異常に気づいていない。しかし人々は、まるで川の流れが岩を避けるように、無意識のうちに広場の中心を避けて歩いている。その不自然な人の流れが、そこに「何か」があることを雄弁に物語っていた。
千景は眉をひそめ、広場を睨んだ。遺恨石だ。だが、これほど巨大で、しかも誰の目にも見えない石など、聞いたことがない。煤けたガラスのような塊でも、鈍色の琥珀のような結晶でもない。それは完全に「透明」で、ただ圧倒的な「重さ」だけをそこに顕現させていた。
第三章 遺恨石の囁き
正体を突き止めなければならない。そんな強迫観念に駆られ、千景は覚悟を決めた。息を止め、透明な重力の中心へと、一歩、また一歩と足を進める。近づくにつれて、呼吸が苦しくなり、心臓が内側から万力で締め付けられるような痛みを覚えた。まるで深海に沈んでいくようだ。
指先が、その「何か」に触れた。
瞬間、世界が反転した。
無数の声が脳内に直接流れ込んでくる。嘆き、叫び、懇願する声。
『もう感じたくない』
『この重さから解放してくれ』
『忘れさせてくれ、何もかも』
それは特定の誰かの後悔ではなかった。幾千、幾万という人々の、一つの願い。何かを「捨てた」ことへの、巨大な安堵。そして、その安堵の裏側にこびりつく、深淵のような虚無感。ビジョンはあまりに断片的で、千景は激しい頭痛と共に後ずさった。全身から汗が噴き出し、立っていることすらままならない。一体、人々は何を捨てたというのか。そして、なぜそれを後悔しているのか。
謎は深まるばかりだった。
第四章 真理の天秤
満月の夜、透明な遺恨石の重力はピークに達した。千景は自室のベッドの上で身を捩っていた。見えない巨人に体を踏みつけられているかのようだ。骨がきしみ、呼吸は途切れ途切れになる。このままでは圧し潰される。意識が遠のきかけた、その時だった。
彼の胸元で、古びたネックレスが灼けつくような熱を放った。
「ぐっ……!」
燐光が部屋を照らし、光の粒子が千景の目の前で渦を巻いて、一つの形を成していく。それは、繊細な細工が施された、美しい天秤だった。星屑を溶かして作ったかのような、幻想的な天秤。片方の皿には、千景自身の苦しみが青白い炎となって乗り、もう一方の皿には、窓の外に存在する「透明な遺恨石」の重さが、暗く濃密な影となって沈み込んだ。
ギリ、ギリリ、と天秤が悲鳴を上げる。
影の乗った皿が、ゆっくりと、しかし圧倒的な質量で沈んでいく。千景の苦しみなど、比較にすらならないほどの重さ。
「これが……真理の天秤……」
時枝から譲り受けた、ただの形見だと思っていたネックレス。天秤が均衡を失った瞬間、千景の意識は再び、あの巨大な記憶の奔流へと引きずり込まれた。今度は、もっと鮮明に。もっと深く。
第五章 失われた感覚
そこは、今とは違う世界だった。誰もが、他人の感情の重さを感じていた。愛する者の喜びは自らの体を浮かせ、隣人の悲しみは自らの肩にのしかかった。人々は痛みを分かち合い、喜びを共有し、深く繋がり合っていた。
だが、世界は苦痛に満ちていた。戦争、飢餓、疫病。他人の絶望が、自分の絶望として伝染していく。愛する者を失った悲しみは、鉛の鎖となって生きる者の足枷となった。人々は、あまりの苦痛に耐えきれなくなった。
そして、彼らは願ったのだ。集団で、一つの巨大な儀式をもって。
この「共感」という名の呪いを、世界から消し去ることを。
その願いは成就した。人々は感情の重さから解放された。しかし、同時に大切なものも失った。他人の痛みに鈍感になり、喜びを真に分かち合う術を忘れた。世界から色が抜け落ち、人々は孤独な個として分断された。
巨大な透明な遺恨石の正体。それは、人類全体が「感情の重さを感じる能力」を捨て去った、その行為そのものへの集合的な後悔だった。
千景の能力は、その消え去ったはずの能力の「再発」。彼がずっと抱えてきた孤独と苦痛は、全人類がかつて味わい、そして忘れ去ろうとした痛みそのものだったのだ。
第六章 選択
真理の天秤は、静かに千景に語りかけていた。選択をしろ、と。
目の前には二つの道がある。
一つは、この天秤の力を使って、巨大な遺恨石を完全に消し去る道。そうすれば、世界は二度と感情の重さを取り戻すことはない。千景自身も、この忌まわしい能力から解放され、普通の人間として生きていける。孤独な苦しみは、それで終わる。
もう一つは、この遺恨石を受け入れ、その重さを世界に「還す」道。それは、全人類が再び感情の重さを感じる世界に戻ることを意味する。世界は再び、他人の痛みで満ち溢れるだろう。しかし、失われた繋がりを取り戻すことができるかもしれない。
千景は唇を噛んだ。自分の苦しみは、自分だけのものではなかった。それは人類が捨てた、痛みの記憶だった。この重さを消し去ることは、その歴史から目を背け、忘却に加担することに他ならない。
孤独だった。ずっと、世界で一人だけ、この重荷を背負っているのだと思っていた。だが、違ったのだ。自分は、忘れられた全ての人々の心と、繋がっていたのだ。
第七章 重力と共に生きる
「……俺は」
千景の声は、静かな決意に満ちていた。
「この重さを、忘れない」
彼がそう告げた瞬間、真理の天秤はひときわ強く輝いた。そして、千景の目の前にあった透明な壁――巨大な遺恨石は、音もなく崩れ、無数の光の粒子となって夜空に舞い上がった。粒子は雪のように、静かに街へと降り注いでいく。
世界はすぐには変わらない。人々は眠り続け、明日もまた同じ日常が始まるだろう。だが、何かが決定的に変わった。千景の肩にかかる重さは、もう彼一人のものではなかった。それは世界全体で分かち合うべき、温かな重さに変わっていた。
夜が明け、街に朝の光が差し込む。千景は窓を開け、湿った空気を深く吸い込んだ。遠くで赤ん坊の泣き声が聞こえる。その声に宿る小さな悲しみが、鉛ではなく、柔らかな羽のように彼の胸に触れた。
人々はまだ気づかない。自分たちの心に、失われたはずの微かな「重さ」が戻り始めていることに。千景は、静かに微笑んだ。これから始まる世界は、きっと苦痛に満ちている。でも、きっとそれだけじゃない。彼は、その重力と共に生きていく。忘れ去られた痛みを、そして温もりを、その両肩で受け止めながら。