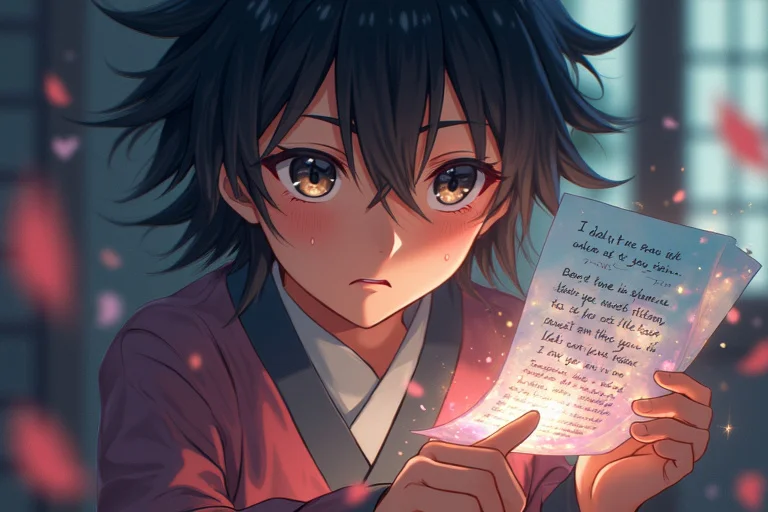第一章 色褪せる世界
空は、いつからこんなにも灰色だっただろうか。
俺、水無月(みなつき) 湊(みなと)の世界から色彩が失われ始めたのは、もうずいぶん前のことになる。最初に消えたのは、庭先に咲く紫陽花の、あの雨に濡れた青色だった。次に、夕暮れの茜色。そして、ついには、燦々と降り注ぐ陽光さえもが、色褪せたセピアの画のようにしか見えなくなった。
視界だけではない。風の囁きは遠のき、鳥の歌声はくぐもった響きとなって鼓膜を揺らすだけ。好きだった珈琲の香りも、焼きたてのパンの匂いも、今はもう判別がつかない。世界は音と匂いを奪い、ただ静かに、無味乾燥に広がっている。
医者は首を傾げるばかりだった。原因不明の、進行性の五感喪失。だが、俺だけは知っている。これは病などではない。呪いだ。世界から失われたたった一人の存在を、俺だけが「覚えている」ことへの代償。
妹の、海(うみ)の名を呼ぶたびに。
屈託なく笑う顔を思い浮かべるたびに。
交わした約束を反芻するたびに、俺の世界は少しずつ崩壊していく。
『どんな困難があろうとも、決して離れない』
幼い日、高熱に浮かされる俺の手を握りしめ、海はそう誓った。小さな指を絡ませて交わした、子供の戯言のような約束。だが、それが俺たちの世界のすべてだった。両親を早くに亡くし、二人きりで生きてきた俺たちにとって、それは魂を結びつける楔そのものだった。
だというのに、海は消えた。
ある朝、忽然と。まるで初めから存在しなかったかのように、彼女の部屋は空っぽになり、アルバムから写真は消え、近所の人々も、学校の友人も、誰も彼もが海のことを忘れていた。この世界で、水無月 海という少女の存在を記憶しているのは、兄である俺、ただ一人になってしまった。
ポケットの中で、冷たくなった指先がごつごつとした感触に触れる。妹がいつも首から下げていた、小さな木彫りの兎の根付。俺が病に倒れた時、海が自らの黒髪を一本、その兎の首に結びつけ、「お兄ちゃんが元気になるまで、肌身離さず持ってるね」と誓った、思い出の品。
世界が海を忘れても、この根付だけは俺の手の中に残った。
強く握りしめると、幻のように、微かな温もりが指先に蘇る。そして、心の奥底で、か細い声が響くのだ。
『約束だよ、お兄ちゃん』
その残響だけが、俺がまだ正気であることを証明してくれる、唯一の光だった。
視界の端がまた少し、闇に侵食される。わかっている。このまま海を想い続ければ、やがて俺は光も音も、何もかもを失い、完全な無の世界に閉ざされるだろう。
それでも、忘れることなどできるはずがなかった。
海を忘れることは、俺の魂を殺すことと同義だったからだ。
第二章 残響の羅針盤
旅に出たのは、根付が発する「残響」が、微かに北を指し示したからだ。
それは物理的な振動ではない。心の羅針盤とでも言うべきか。海を強く想い、根付を握りしめると、魂の引力のようなものが、俺を特定の方向へといざなうのだ。
失われゆく五感を頼りに、俺はあてのない旅を続けた。霞む目で地図を読み、遠のく聴力で汽笛の音を拾う。すれ違う人々に海のことを尋ねても、返ってくるのは決まって、訝しげな顔か、憐れむような視線だけだった。
「妹さん? さあ、存じませんね」
「お気の毒に。記憶が混乱されているのでは?」
違う。混乱しているのは、お前たちのほうだ。世界こそが、狂っている。
苛立ちと孤独が、心を削っていく。
ある寂れた宿場町で、奇妙な老婆に出会った。軒先で干し柿を作っていた老婆は、俺が根付を握りしめているのを見て、皺だらけの顔を上げた。
「あんた、何か大事な『約束』を失くしたのかい」
ぎくりとして顔を上げると、老婆は虚空を見つめるように続けた。
「この世の約束は、魂に刻まれる。重い約束ほど、深く、強く。それが破られた時、軽いほうの魂は風に吹かれて消えてしまうのさ。忘れられるのが、一番の薬なんじゃがね…」
老婆の言葉は、世界の法則の断片を垣間見せた。海は、誰かとの約束に破られたのだろうか? だから、その存在が消されてしまった? 俺との約束ではない。俺は、あの日交わした約束を、一瞬たりとも忘れたことはないのだから。
だとしたら、一体誰と? なぜ?
答えを探すほどに、呪いは加速度的に俺の身体を蝕んでいく。
ある夜、宿の一室で、俺はついに海の笑い声を思い出せなくなった。どんなに耳を澄ませても、記憶の底から響いてくるのは、ただのノイズだけ。
「ああ…あ…」
声にならない嗚咽が漏れる。胸を掻きむしり、壁に頭を打ち付けた。痛みすら、今は鈍い。
ふと、絶望の中で、恐ろしい考えが頭をよぎった。
もし、海を救う唯一の方法が、俺が彼女を忘れ去ることだとしたら?
俺が「覚えている」こと自体が、海の魂をこの世に不完全に留め、苦しめているのだとしたら?
俺の記憶こそが、呪いの源泉だとしたら?
その考えは、甘い毒のように心を侵食し始める。忘れてしまえば、この五感を失う苦しみから解放される。楽になれる。
「違う…!」
俺は兎の根付を強く、強く握りしめた。爪が食い込み、掌から血が滲む。
その瞬間、今までで最も鮮明な残響が、脳内に直接響き渡った。それは言葉ではなかった。桜の花びらが舞い散る、古い寺の光景。そして、深い、深い慈愛の感情。
ここだ。この場所に行かなければ。
俺はふらつく足で立ち上がり、夜の闇へと再び歩き出した。残された時間は、もう僅かしかない。
第三章 交換の真実
根付が示した場所は、山深い森の奥深くに佇む、荒れ果てた古寺だった。打ち捨てられてから幾星霜が過ぎたのか、苔むした屋根は崩れ落ち、境内には桜の古木が、季節外れの亡霊のように静かに立っていた。
導かれるように本堂の奥へ進むと、床の一部が不自然に新しいことに気づく。力を込めてそれをずらすと、地下へと続く冷たい石の階段が現れた。
黴と土の匂いが立ち込める暗闇の中を、壁を手探りで進む。もうほとんど見えない目で、松明の微かな光を頼りにした。
その最奥に、それはあった。
静かに佇む、一枚の石碑。
そして、その表面に刻まれた、見慣れた、愛おしい筆跡。
海の字だ。
震える指で、石碑の表面をなぞる。そこに刻まれていたのは、俺の知らない、海の悲痛な祈りだった。
『――この身、この魂、この世に在ったすべての記憶と引き換えに、どうか兄、水無月湊の命をお救いください。私がこの世から消え去ろうとも、兄が健やかに生きられるのなら、何も厭いませぬ。ここに、我が存在を賭して、神仏と『交換の約束』を交わします――』
息が、止まった。
全身の血が逆流するような衝撃。記憶の扉が、激しい音を立てて開かれる。
そうだ。俺は忘れていた。海が消える少し前、俺は不治の病に侵され、死の淵を彷徨っていたのだ。医者も見放し、明日をも知れぬ命だった。その時、海は…この場所で、たった一人で、こんな途方もない約束を…。
俺との「離れない」という約束を、俺の命を救うため、自らの手で破ったのだ。
神仏という、抗いようのない相手との、もっと大きな約束のために。
約束が破られたことで、海の存在は世界から希薄化し、消滅した。俺だけが覚えているのは、恐らく、この「交換の約束」の対象が俺自身だったから。俺の命が、彼女の存在の対価だったからだ。
「ああ…あああああああああっ!」
絶叫が、地下の空間に木霊した。
なんで、なんでだよ、海! 俺は、お前がいなければ、生きていたって意味がないんだ! お前を守るために、俺は…!
涙が、枯れ果てたはずの瞳から溢れ出す。石碑にすがりつき、俺は子供のように泣きじゃくった。怒りと、悲しみと、そして、身を裂くほどの愛情が、壊れかけた心の中で荒れ狂う。
その時、石碑の下のほうに、さらに小さな文字が刻まれていることに気づいた。最後の力を振り絞り、顔を近づける。
『お兄ちゃんへ。
もし、これを読んでいるのなら、あなたは私を覚えていてくれたんだね。ありがとう。
兄さんが私を覚えていてくれる間は、私の魂は兄さんの心の中で生き続ける。それが私の幸せ。
でも、もし苦しいなら、どうか忘れて。
私が、お兄ちゃんを許すから。
約束を破って、ごめんなさい。でも、愛しています』
――私が、お兄ちゃんを許すから。
その一文を読み終えた瞬間。
世界が、砕け散った。
妹からの、魂からの「許し」が、時を超えて成就したのだ。俺を縛り付けていた「覚えている」ことへの呪いが、その絶対的な力によって、解かれ始めた。
ゴッ、と喉から嫌な音がした。
視界が急速に暗転していく。耳鳴りが全てを掻き消す。
そして、脳を直接掴まれるような激痛と共に、大切な何かが、砂の城のように崩れ落ちていくのがわかった。
黒髪の、少女の顔が、霞んでいく。
鈴の鳴るような、笑い声が、遠ざかっていく。
俺の手を握った、小さな温もりが、消えていく。
「待ってくれ…」
声にならない声で、懇願する。
「行くな…思い出せなくなる…お前の名前は…」
水無月、――。
「誰だ…? 俺は、誰を探していた…?」
最後に残った右手の掌で、必死に兎の根付を握りしめる。だが、その温もりも、意味も、もう何も感じなかった。
意識が途切れる寸前、俺は確かに聞いた。
風のように優しい声で、さよなら、と。
第四章 忘れ桜の下で
柔らかな陽光が瞼を撫で、俺はゆっくりと目を開けた。
見上げると、満開の桜が空を覆い尽くし、風が吹くたびに薄紅色の花びらが雪のように舞い散っている。
ここは、どこだろう。
なぜ、自分はこんな場所にいるのだろう。
ゆっくりと身を起こす。身体のどこにも、痛みや不調は感じられない。それどころか、驚くほどに世界は鮮やかで、鳥のさえずりや川のせせらぎが、心地よく耳に届いた。まるで、長い間閉ざされていた扉が開かれたような、不思議な解放感があった。
だが、胸の奥には、ぽっかりと大きな穴が空いていた。
何か、命よりも大切なものを失くしてしまったような、途方もない喪失感。頬を伝う、生乾きの涙の跡に指で触れる。なぜ泣いていたのか、全く思い出せない。
ふと、右手に何かを握りしめていることに気づいた。
掌を開くと、そこには古びた木彫りの兎の根付があった。兎の首には、なぜか一本の長い髪の毛が結びつけられている。
これを、なぜ持っているのだろう。
わからない。けれど、どうしようもなく懐かしく、温かい気持ちになった。決して手放してはならない、魂の片割れのようなものだと、直感的に理解した。
俺は立ち上がり、桜並木をあてもなく歩き始める。
人々が楽しげに行き交う中、俺だけが、何かを探しているような、誰かを待っているような、奇妙な感覚に囚われていた。
舞い散る花びらの一枚が、ふわりと俺の掌に落ちる。
それを見つめていると、不意に、胸の奥がちくりと痛んだ。
温かいような、寂しいような、名前のつけられない感情が込み上げてくる。
空を見上げる。
果てしなく広がる青空と、舞い続ける桜吹雪。
美しい世界だ。本当に。
なのに、なぜだろう。
この美しい世界には、たった一つだけ、何かが足りない気がしてならなかった。
俺は、きっと、ずっと、ここで誰かを待ち続けるのだろう。
その誰かの名前も、顔も、声も、永遠に思い出すことはないまま。
ただ、この胸に残る温もりだけを抱きしめて。
風が吹き抜け、桜の花びらが一斉に舞い上がった。
それはまるで、遠い空の誰かが、優しく微笑んでいるかのようだった。