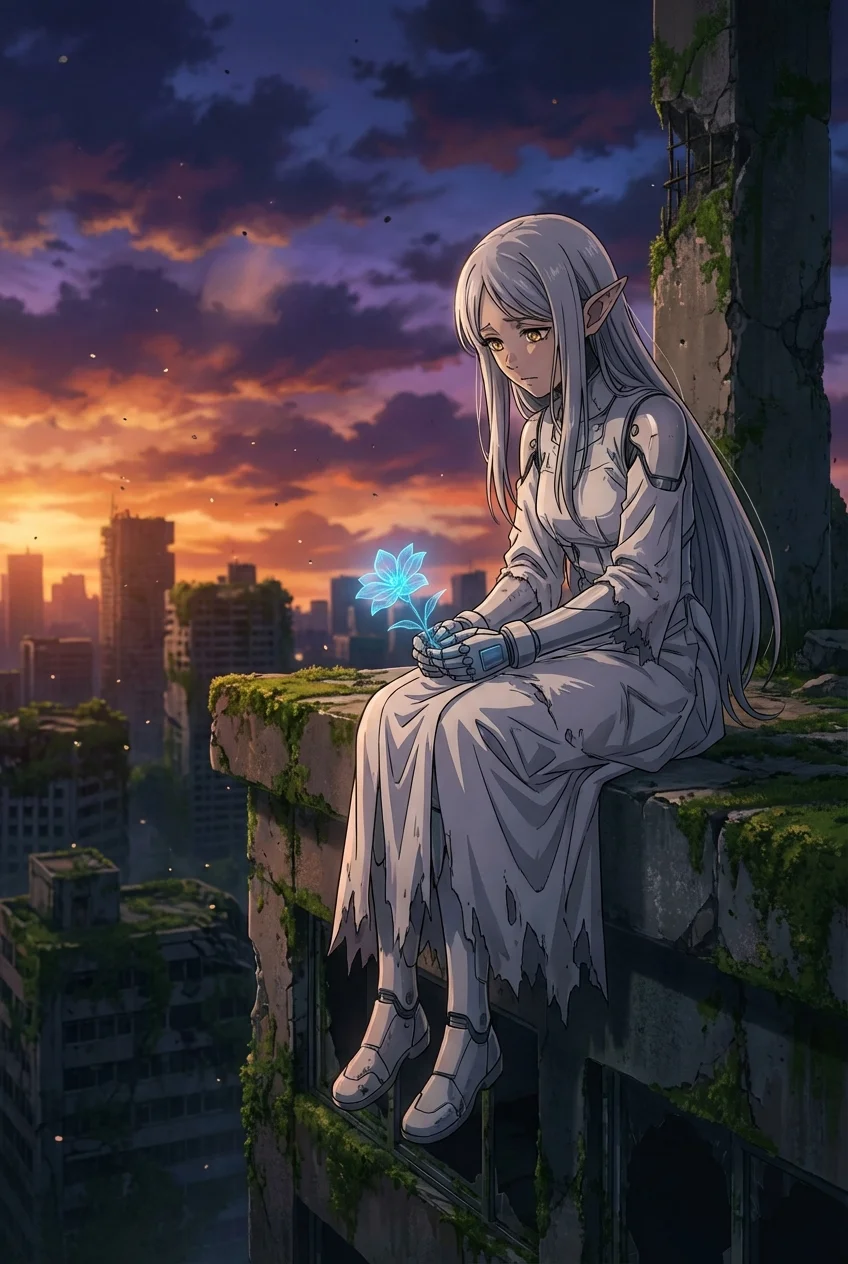第一章 インクの染みと白い栞
俺の人生は、どうやら物語らしい。朝、目が覚めると新しい「章」が始まる感覚。出会う人々は、まるで与えられた役割を忠実に演じる役者のようだ。俺、カイという主人公の隣人、友人、そして時には敵対者として。
胸ポケットに忍ばせた一枚の「白い栞」。それが、この虚構めいた世界で唯一、俺が「現実」を測るための指標だった。栞の表面には、今日の日付と共に、インクが滲むように一文が浮かび上がっている。
『雨上がりの街で、リナと再会した。』
その記述通り、石畳の濡れた匂いが立ち込める広場で、俺はリナを見つけた。彼女は、街の一角で陽炎のように揺らめく「記憶の断片」に駆け寄ろうとする子供の手を、静かに引いていた。
「だめよ。あれは、誰かの嘘の記憶だから」
リナの声は澄んでいたが、その瞳の奥には、まるで舞台の背景を見透かすような、奇妙な諦念が宿っていた。彼女もまた、この世界の法則に気づいているのだろうか。彼女という「役割」もまた、この物語に書かれた登場人物の一人に過ぎないということに。
その夜、俺はいつもの夢を見た。無限に広がる白紙の空間に、一冊の巨大な本が開かれている。その中央には、ぽっかりと空白のページがあった。人型の染みが描かれたそこからは、声にならない、インクの渇いた悲鳴が聞こえてくる。俺は、あの空白こそが自分の本当の姿ではないかと、ずっと感じていた。
第二章 褪せる文字、揺らぐ現実
あの悲鳴の正体を知りたい。俺は禁じられている「幻影の街」の深部へと足を踏み入れた。そこは、強く願われた過去が、何度も繰り返し再生される場所。ある恋人たちの幸福な記憶、ある家族の崩壊の記憶。しかし、よく見ると奇妙だった。同じ情景のはずが、役者の立ち位置や台詞が、再生されるたびに僅かに異なっているのだ。まるで、作者が何度も推敲を重ねているかのように。
その時、胸ポケットの栞が熱を持った。取り出して見ると、俺が疑いようもなく信じていたはずの一文が、ゆっくりと薄れ始めていた。
『リナは、俺のたった一人の幼馴染だ。』
文字が、まるで乾いたインクのように掠れていく。足元の地面が崩れ落ちるような感覚。俺たちの関係性すら、確定された「設定」ではなかったというのか。絶望の中で顔を上げると、幻影の街の向こうに、誰も足を踏み入れない古びた図書館の尖塔が、まるで俺を呼ぶように聳え立っていた。夢の中の空白の影が、そこを指し示している気がした。
第三章 作者の絶望
図書館の最奥。そこには、夢で見た光景が広がっていた。埃の匂いとカビ臭さが混じり合う中、巨大な「空白のページ」が鎮座していた。インクの染みで描かれた人型の影が、俺の接近に気づき、激しく身じろぎする。
「お前は、誰だ」
俺が問いかけると、影から直接、思考が流れ込んできた。それは言葉ではなく、純粋な感情の濁流。後悔、焦燥、そして、物語を完成させられなかった者の、底なしの絶望だった。
――これは、未完の物語。
――お前たちは、私の失敗作だ。
――この世界は、私が書き捨てた下書きに過ぎない。
真実が、脳を焼き切る。俺も、リナも、街の人々も、全ては作者のペン先から生まれ、そして見捨てられた存在だった。空白の登場人物の正体は、この物語を完結させることを諦めた「作者」の絶望そのものだったのだ。
胸の栞を見ると、全ての文字が跡形もなく消え、完全な白紙に戻っていた。俺の「現実」は、完全に崩壊した。
「ふざけるな!」
俺は叫んだ。それは、この物語の中で、初めて心の底から絞り出した、俺自身の言葉だった。
「俺たちの人生は、お前の諦めの産物だったというのか! なら、結末は俺が決める!」
第四章 最後の一文とプロローグ
選択肢は二つ。この未完の物語を、作者の絶望と共に永遠にループさせるか。あるいは、「主人公」という物語の楔である俺自身を消し去り、彼らを虚構の鎖から解放するか。
答えは、決まっていた。
「俺が、この物語の最後の一文になる」
俺は真っ白になった栞を、巨大な「空白のページ」へと、静かに差し込んだ。瞬間、俺の身体が足元から光の粒子となって崩れ始める。リナの記憶から、街の風景から、カイという存在が消しゴムで消されるように、静かに、確実に消えていく。悲しみはなかった。これで、彼らは「登場人物」ではなく、ただの「人」になれるのだから。
意識が完全に途切れる寸前、俺の目に、最後の光景が映った。
俺の手の中にあったはずの白い栞。それが、空白のページの上で、新たなインクを吸い込むように、最後の一文を静かに綴っていた。
『――そして、彼らは初めて、自分の意志で朝を迎えた。』
それは、誰かのための物語の終わり。
そして、彼ら自身の、物語の始まりだった。