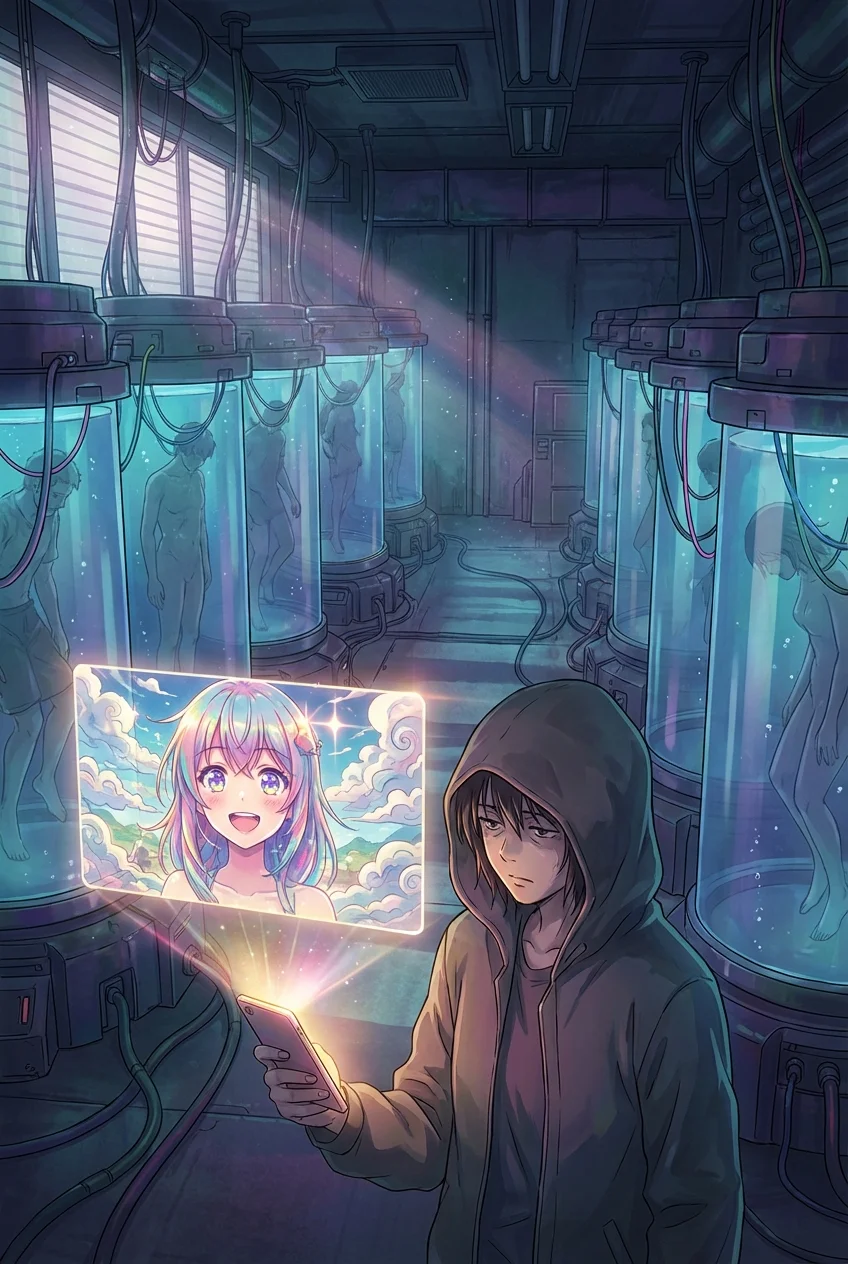第一章 完璧な午後の違和感
世界は、呆れるほど美しく透き通っていた。
空には幸福を示す淡い黄金色の雲が流れ、通り過ぎる人々は皆、親愛の情を示す桜色のオーラを纏っている。ここでは、感情が色として視覚化される。それが、僕がこの世界に転生した時に「在るべき姿」として願った法則だった。
「レン、何ぼーっとしてんだ? クエストの時間だぜ」
快活な声と共に、背中をバンと叩かれる。相棒のカイナだ。
燃えるような赤髪に、太陽をそのまま溶かしたような瞳。カイナはこの世界で僕が最初に出会い、そして片時も離れずに背中を預け合ってきた「最高の相棒」だ。彼がいればどんな迷宮も怖くない。そう、設定されているかのように、僕たちは完璧なコンビだった。
「ごめん、ちょっと考え事」
「またあの『夢』か?」
カイナの表情が、ふと曇る。
僕は最近、決まって同じ夢を見る。消毒液の匂い、白い天井、そして冷たくなっていく誰かの手。顔は見えない。けれど、胸が張り裂けそうな喪失感だけが、目覚めた後も鈍い痛みとして残るのだ。
僕はポケットから、小さなオルゴールを取り出した。
ガラス細工のような繊細な装飾が施されたそれは、この極彩色の世界において唯一、何の色も持たない「無色透明」な物質だった。
ネジを巻いても音は鳴らない。壊れているのか、それとも僕が何かを忘れているからなのか。
ただ、これを握りしめると、夢の中の焦燥感が少しだけ和らぐ気がした。
「行こう、カイナ。今日こそ、あの未開拓エリアの先へ」
「ああ。お前が行くなら、俺はどこまでだって付き合うさ。……最後までな」
カイナの言葉の端に、奇妙なほど哀切な響きが混じった気がして、僕は振り返った。
だが、そこにはいつもの、頼もしくも悪戯っぽい笑顔があるだけだった。
第二章 綻びる世界
世界の境界線とされる「忘却の森」に足を踏み入れた瞬間、異変は起きた。
森の木々が、見たこともない灰色に染まり、ドロドロと溶解し始めたのだ。
「レン、下がれ! これは『エラー』だ!」
カイナが剣を抜き、僕を庇う。しかし、襲い来るのは魔物ではない。空間そのものの崩落だ。
僕たちがこの世界で「役割」を演じている限り、世界は安定しているはずだった。しかし、僕が夢に見る「存在しないはずの風景」をこの森に重ねてしまった瞬間、世界の理(ことわり)が悲鳴を上げ始めた。
「どうして……僕はこの場所を知っている?」
灰色の泥の中から、見覚えのある看板が浮かび上がっていた。『面会時間終了』の文字。
ズキリと頭が痛む。オルゴールが熱を帯び始める。
「見るな! 思い出すな、レン!」
カイナが叫ぶ。その身体が、ノイズが走ったように明滅していた。
彼が僕を庇って泥のような「何か」を斬り裂くたび、彼自身の色が薄れていく。世界が彼を「異物」として排除しようとしているのか、それとも、僕の無意識が彼を消そうとしているのか。
「カイナ、君の手が……透けている?」
「気にするなと言ってるだろ!」
彼は必死に笑ってみせたが、その頬を伝う涙だけは、鮮烈なほどに青かった。悲しみの色。
なぜ、最強の相棒として設定された彼が、こんなにも悲しい色を流すのか。
その瞬間、僕のポケットの中で、沈黙していたオルゴールが、チリ、と微かな音を立てた。
第三章 色づく記憶、蘇る絶望
オルゴールが奏で始めたのは、拙くも優しい、誕生日の歌だった。
そのメロディが鼓膜を震わせた瞬間、脳内のダムが決壊した。
思い出した。
僕が現実世界で最後に聞いた音。心電図の停止音。
僕が現実世界で最後に触れたもの。冷たくなった恋人の指先。
「あ……ああ……」
膝から崩れ落ちる。
僕はこの世界に転生したんじゃない。逃げ込んだんだ。
最愛の人の死という、受け入れがたい現実から。自らの理想を具現化できるこの箱庭を作り上げ、辛い記憶を全て消去し、幸福に浸るために。
そして、カイナ。
目の前で明滅を繰り返す、僕の最高の相棒。
「思い出しちまったか、レン」
カイナの声が変わる。男勝りな口調が消え、聞き覚えのある、柔らかく愛おしい声色が重なる。
彼――いや、彼女は、僕が現実世界で失った恋人の理想化された姿だった。
死ぬこともなく、離れることもなく、常に僕の隣で笑ってくれる「役割」を与えられた、都合の好い幻影。
「ごめんね。君が望む『相棒』を、もっと上手く演じてあげたかったんだけど」
カイナが微笑む。その笑顔は、僕が死ぬほど愛し、二度と見られないはずだった彼女そのものだった。
オルゴールが激しく回転し、無色だった硝子のボディが、ドス黒い「後悔」の色と、焼き付くような赤色の「愛」に染まっていく。
世界が激しく振動する。
僕が真実を思い出してしまった以上、この「嘘の楽園」はもう維持できない。
カイナという存在は、僕の「忘却」の上に成り立っていた。真実を認識した今、彼女は世界のバグとして消滅するか、あるいは歪な化け物として永遠に苦しみ続けるか、そのどちらかしかない。
「嫌だ……もう二度と、君を失いたくない!」
僕はカイナの透けかけた手を掴む。
だが、その手にはもう、体温がなかった。
第四章 永遠の別れと、残された色
「レン、お願い。私を『解放』して」
崩壊が進む灰色の空の下、カイナは静かに告げた。
彼女をこの世界に留めることは、死者の魂を冒涜し、僕のエゴで永遠に縛り付けることと同義だった。
「この世界を救うには、君が設定した『完璧な相棒』という役割を壊すしかない。それは、私が私として死ぬこと。……ううん、本来の場所に還ること」
彼女は僕の頬に手を添える。
その瞳には、作られたプログラムではない、確かな意志が宿っていた。
「君がくれたこの世界、楽しかったよ。もう一度会えて、嬉しかった」
僕の手には、色を取り戻したオルゴールがある。
この曲が止まる時、彼女は消える。
僕がそれを望まなければ、世界ごと心中することもできるだろう。けれど、彼女はそれを望んでいない。
「……愛してる。現実でも、この世界でも、君だけを」
僕は震える指で、オルゴールのストッパーに手をかけた。
それは、僕自身の手で、彼女を二度殺す行為だった。
それでも、彼女を「都合の良い人形」から、愛する「ひとりの人間」に戻すために。
「さようなら、レン。私の愛しい人」
カチリ。
音が止まる。
同時に、カイナの体が無数の光の粒子となって弾けた。
悲鳴のような風が吹き抜け、灰色の森が、本来の美しい緑へと書き換わっていく。
世界は修正された。
歪な異物は排除され、完璧で、幸福で、残酷なほど美しい楽園が戻ってきた。
ただ一人、僕と、再び無色に戻ったオルゴールだけを残して。
僕は空を見上げる。
そこには、彼女の髪の色と同じ、燃えるような夕焼けが広がっていた。
もう二度と、あの温もりに触れることはない。
それでも僕は、この色褪せない喪失を抱きしめて生きていく。
自らが作り上げた、この美しくも孤独な檻の中で。