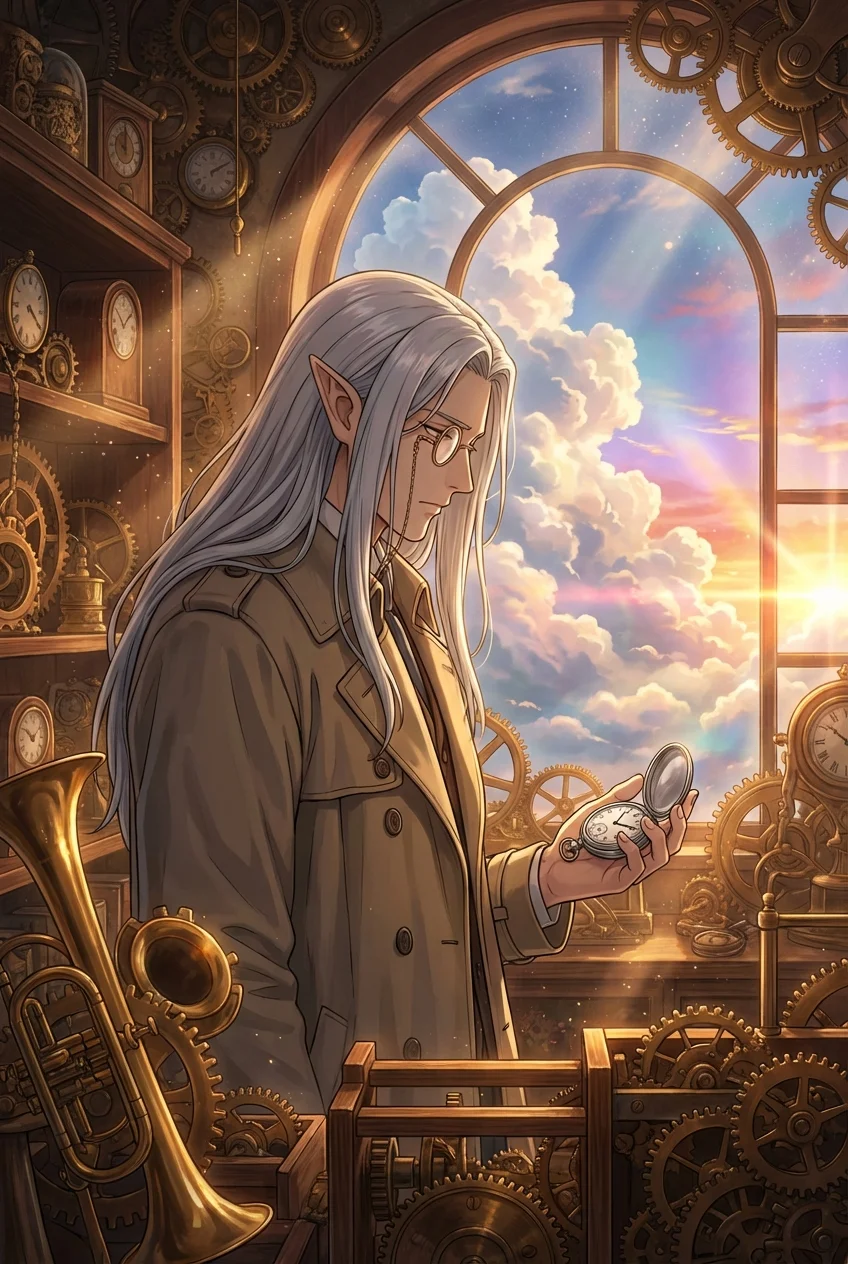第一章 残高ゼロの絶対王者
玉座の間の冷気が、骨の髄まで染み込んでくる。
かつて人間界を恐怖で塗り潰したビロードのマントは、今や虫食いだらけの古布だ。
床を指でなぞる。
埃ひとつない。
金目のものはシャンデリアの破片に至るまで売り払い、もはや塵すら残っていないからだ。
「……腹が、減ったな」
魔王ヴァルゼイドの呟きは、誰に届くこともなく虚空へ消えた。
魔力の源泉である「畏怖」が底をついて久しい。
平和ボケした人間たちは、もはや闇夜も雷鳴も恐れない。
このまま餓死するか、あるいは存在が希釈されて消滅するか。
二つに一つの未来しか見えなかった。
「魔王様、今月の収支です」
側近のゴブリンが、ひび割れたタブレットを差し出す。
赤い折れ線グラフが、断崖絶壁のように垂直落下していた。
「『恐怖ポイント』の未回収分が累積し、生命維持ラインを割り込みました。これ以上は……」
ヴァルゼイドは乾いた唇を舐め、懐から黒曜石を取り出した。
『魔王石』。
かつては絶望を集める器だったが、今はただの黒い石塊だ。
「恐怖という感情は、鮮度が落ちるのが早い」
ヴァルゼイドは石を握りしめる。
指の関節が白く浮き出るほどに。
「だが、人間にはもっと根深く、持続性のある欲望があるはずだ」
端末の画面をタップする。
煌びやかなSNSのタイムライン。
そこには、承認を求め、何かに縋りつこうとする無数の魂が蠢いていた。
「『信仰』だ」
ヴァルゼイドの瞳に、久しく忘れていた捕食者の光が宿る。
「私の魔力(存在)を切り売りして、奴らに分け与えてやる。心地よい微熱のような『加護』をな。奴らを依存させろ。恐怖ではなく、狂信的な『推し』の感情を搾り取る」
「は……? 推し、でございますか?」
「そうだ。魔王軍公式サブスクリプション『魔王LIFE』。これより、魂の徴収を開始する」
第二章 バズりと勇者の相関関係
『***初配信***魔王だけど質問ある?』
『四天王のモーニングルーティン(炎上覚悟)』
『聖女をナンパしてみた結果www』
配信開始から三ヶ月。
世界は紫色の熱狂に包まれていた。
端末越しに魔王と目が合うたび、視聴者の脳髄には甘美な魔力が注入される。
それは麻薬的な多幸感となり、彼らを画面の前から離れられなくした。
「ああ、魔王様……今日も尊い……」
「スパチャ(寿命)投げます!」
「もっと私を見て! 加護をください!」
サーバー室と化した地下牢獄で、無数の魔王石が脈打つように明滅している。
膨れ上がる「依存」のエネルギー。
ヴァルゼイドの枯れ木のような肌には潤いが戻り、漆黒の角は宝石のような艶を帯びていた。
「素晴らしい。恐怖よりも濃密で、粘着質な魂の味だ」
ヴァルゼイドが愉悦に浸りながらコメント欄を眺めていた、その時。
轟音と共に、城壁が粉々に吹き飛んだ。
ズガァァァァァン!!
粉塵を切り裂き、銀色の影が走る。
速い。
「魔王ヴァルゼイド! 世界の調和を乱す悪よ、滅びろ!」
またか。
今月ですでに七人目だ。
「しつこいぞ! 私は街一つ焼いていない! むしろ昨日は迷子の仔猫を助ける配信をしたばかりだぞ!?」
ヴァルゼイドは舌打ちし、黒炎の剣を生成する。
しかし、違和感があった。
サブスク会員が増え、世界が魔王に好意的になればなるほど、襲来する勇者のレベルが跳ね上がっている。
眼前の勇者は、片手でやすやすと魔王の黒炎を弾いた。
強すぎる。
過去のどの勇者よりも。
「くっ、配信を切れ! 戦闘シーンは規約違反でBANされる!」
「間に合いません! 同接数が急増しています!」
ヴァルゼイドはマントを翻し、勇者の剣撃を紙一重でかわす。
(おかしい……)
剣を交えるたび、勇者の動きから「人間らしさ」が感じられない。
まるで、プログラムされた殺戮機械だ。
この世界で、一体何が起きている?
第三章 エンドロールは流れない
城の最上階。
瓦礫の山となった玉座の前で、ヴァルゼイドは膝をついた。
切っ先が、喉元に突きつけられる。
皮膚が裂け、一筋の血が流れた。
「終わりだ、魔王」
勇者が剣を振り上げる。
その時、ヴァルゼイドは見た。
勇者の瞳を。
そこには憎しみも、正義感すらもなかった。
あるのは、空虚な「穴」だ。
焦点の合わない瞳から、生理現象のように涙だけが流れている。
剣を握る手は、意思に反して痙攣していた。
(こいつは……被害者か)
ヴァルゼイドの脳裏で、すべてが繋がる。
魔王石に流れ込む莫大なエネルギー。
その裏に含まれる、視聴者たちの無意識の渇望。
『平和な配信なんて飽きた』
『もっと過激な展開が見たい』
『感動の最終回(フィナーレ)を』
その集合的無意識が、システムとしてこの「舞台装置(勇者)」を生成し、無理やり魔王を殺させようとしているのだ。
世界という巨大なコンテンツが、演者の死を求めている。
(ふざけるな。私は消費材ではない)
死の直前、ヴァルゼイドは嗤った。
プロデューサーとしての、冷徹な計算が脳内を駆け巡る。
「……なぁ、勇者よ」
切っ先が止まる。
システムが一瞬、バグったような挙動を見せた。
「私を殺してハッピーエンド。それで、視聴者が満足すると思うか?」
「……なに、を」
「お前が剣を振り下ろした瞬間、この物語(コンテンツ)は終わる。画面は暗転し、視聴者は次の娯楽へ去るだろう。お前は用済みとなり、誰の記憶にも残らず消滅する」
ヴァルゼイドはゆっくりと、喉元の剣を指先で押しのけた。
極限の賭けだ。
「殺し合い(ドラマ)が見たいなら、見せてやればいい。だが、終わらせる必要はない」
「……」
「私と組め。最高の『敵役』として、お前を輝かせてやる。永遠に続く、終わらない闘争という名のエンターテインメントをな」
勇者の瞳の奥で、システムのエラー音が聞こえた気がした。
やがて、剣がゆっくりと降ろされる。
「……そのプラン、詳しく聞かせろ」
ヴァルゼイドは口角を吊り上げた。
それはかつての支配者の顔ではなく、悪徳実業家の顔だった。
*
「はい、カーット! 勇者ちゃん、今の必殺技エフェクト最高だったよ!」
「ありがとうございます! 魔王P!」
スタジオへと改装された大広間。
カメラの赤いランプが消えると、勇者は泥のようにソファへ倒れ込んだ。
連日の撮影とライブ配信。
休みはない。
モニターには、過去最高益を叩き出した『勇者vs魔王:涙の休戦スペシャル』のアーカイブが流れている。
魔王石は爆発しそうなほどのエネルギーを吸い上げ、ヴァルゼイドの身体を満たしていた。
彼は、マグカップのコーヒーを煽った。
苦い。
舌が痺れるほどに。
画面の向こうには、笑顔のヴァルゼイドと勇者が映っている。
コメント欄は称賛の嵐だ。
だが、ヴァルゼイドは知っている。
この笑顔を一度でも崩せば。
あるいは、視聴者を「退屈」させたその瞬間に。
世界は再び、彼らを処刑しようとするだろう。
「次は『四天王アイドル化計画』だ。脚本(シナリオ)を修正するぞ」
ヴァルゼイドは、充血した目で台本に向かう。
震える手でペンを走らせるその背中からは、もはや魔王の威厳は消え失せていた。
そこには、終わることのない狂騒に囚われた、哀れな奴隷の姿だけがあった。