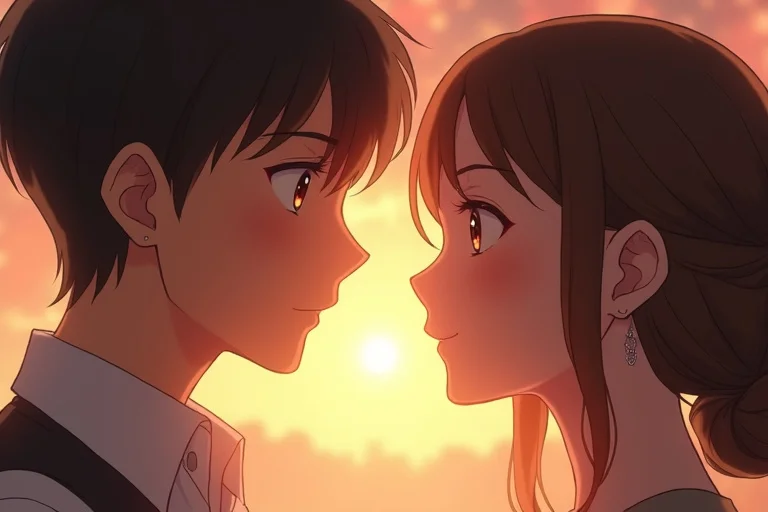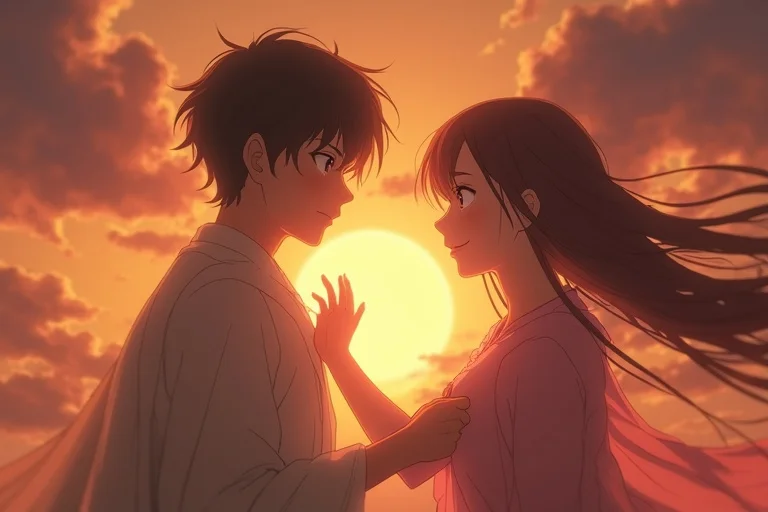第一章 色のない恋人
雨上がりのアスファルトが、喉の乾くような焦げた匂いを立ち昇らせている。
湿気を孕んだ熱風が、肌にまとわりつく七月。
カフェのテラス席。
私の視界は、今日も暴力的なまでに鮮やかだった。
行き交う人々の頭上から、極彩色の煙のような「何か」が溢れ出し、大気を汚している。
向かいの席で項垂れる学生からは、湿ったコンクリートのような、重くザラついた鈍色が滴り落ちていた。
待ち合わせ相手に駆け寄る女性からは、炭酸の泡が弾けるような、チカチカと痛みを伴う蛍光の黄色が噴き出している。
電話口で怒声を上げる男の背中には、煮詰まった血液と錆びた鉄が混ざり合ったような、黒ずんだ赤が渦を巻く。
それらは私の網膜を焼き、脳髄を直接撫で回す。
吐き気がした。
世界はあまりにも、五月蝿い。
「葵、お待たせ」
ふわりと、深煎りの豆の香りが鼻腔をくすぐった。
顔をあげる。
そこには、私の恋人、雨宮晴人が立っていた。
「……ううん、今来たとこ」
私はアイスコーヒーのグラスを両手で包み込む。
指先の感覚が麻痺するほどの冷たさだけが、今の私を繋ぎ止める命綱だった。
視線を、彼の顔から胸元へと滑らせる。
その瞬間、内臓がすとんと冷たい場所に落ちるような感覚に襲われた。
(……ない)
やはり、ないのだ。
晴人の胸に、色が。
以前は違った。
私を見る彼の胸の奥には、陽だまりで干したリネンのような柔らかな暖色や、熟れた果実のような甘やかな紅が灯っていたはずだった。
それは、色彩の暴力に晒される私にとって、唯一呼吸が許される聖域だった。
けれど今、目の前にいる彼の輪郭の内側は、空洞だ。
一週間前から、晴人は「無色透明」になった。
ガラス細工のような綺麗なものではない。
そこにあるはずの存在がごっそりと刳り抜かれたような、底知れぬ空虚。
向こう側の景色が、歪むことなく透けて見えるほどの「虚無」。
「葵? 顔色が悪いよ。やっぱり暑さのせいかな」
晴人が心配そうに私の頬に手を伸ばす。
その掌は、確かに温かい。
脈打つ血管、皮膚の滑らかさ、指の腹のわずかな湿り気。
すべてが人間そのものだ。
けれど、私の目には、彼が精巧に作られた幽霊のようにしか映らない。
「……なんでもない。ちょっと、めまいがしただけ」
私は嘘をついた。
ショーウィンドウのガラスに映る自分を見る。
そこには、何も映っていない。
周囲の人間が撒き散らす極彩色の中、私という輪郭だけが、切り取られたように空白だ。
自分の感情の色を持たない私。
他人の感情の奔流に溺れながら、自分だけが何者でもないという欠落感。
だからこそ、晴人の温かな色は、私が「愛されている」と感じられる唯一の証明だったのに。
「そういえば、これ。やっと手に入ったんだ」
晴人がポケットから小さな木箱を取り出し、テーブルに置いた。
古びたウォールナットのオルゴール。
真鍮のシリンダーが、昼下がりの陽光を鈍く反射している。
「これ……」
「ずっと探してたアンティーク。壊れてて音は鳴らないんだけど、形が葵に似合うと思って」
彼は子供のような無邪気さで、小さなネジを巻き始めた。
カリ、カリ、と乾いた金属音が鼓膜を打つ。
シリンダーが回り、ピンを弾く。
けれど、晴人の言う通り、物理的な音楽は聞こえない。
「……ねえ、葵」
晴人が回るシリンダーを見つめたまま、独り言のように呟いた。
「僕たちの時間、最近おかしいと思わないか?」
心臓が早鐘を打った。
彼の背景にある街路樹の緑が、油絵の具が溶け出すようにドロリと歪んだ気がしたからだ。
「おかしいって……?」
「時計の針が、泥の中を進んでいるみたいに重いんだ。君と一緒にいる時だけ」
彼の背後の透明な空洞が、陽炎のように揺らめく。
色は、やはり見えない。
愛が冷めたのなら、色は褪せて乾いた灰色になるはずだ。
無関心なら、白く濁った霧のようになるはずだ。
完全な透明なんて、この世の理から外れている。
(何を隠しているの?)
私は震える指で、結露したグラスを握りしめた。
その時だ。
無音のはずのオルゴールから、微かな振動が伝わってきた。
いや、それは音ではなかった。
耳ではなく、私の背骨を直接震わせるような、甘く、切なく、泣きたくなるような旋律。
第二章 断絶の予兆
『真実の愛が極まると、二人は世界という器から溢れ出す』
そんな古い詩の一節が、ふと脳裏をよぎる。
馬鹿げている。
そんなロマンチックな御伽噺で、この不気味な現象が説明できるわけがない。
けれど、現実は私の常識を嘲笑うかのように、音を立てて崩れ始めていた。
「――さん。おい、お客さん!」
はっとして顔を上げる。
駅の改札前。
目の前で制服を着た駅員が、苛ただしげに手を振っていた。
「あ、すみません……」
「大丈夫ですか? 改札の前で急に立ち止まって。後ろがつかえてますよ」
駅員の胸元から、刺々しいイガ栗のような焦げ茶色が膨れ上がり、私を威嚇する。
謝罪の言葉もそこそこに、私は人混みの中へ逃げ込んだ。
何かがおかしい。
周囲の音が、まるで分厚い水槽越しに聞いているように遠い。
行き交う人々の輪郭が、滲んだ水彩画のようにぼやけている。
世界が私を異物として認識し、薄い膜で隔絶しようとしているようだ。
ポケットの中でスマートフォンが振動した。
晴人からだ。
『今夜、港の公園で会えないか。話したいことがある』
液晶の文字を見つめるだけで、胃の腑が締め付けられる。
「話したいこと」とは何だ?
別れ話だろうか。
あの透明な空洞は、私への関心が完全に消失した証拠なのだろうか。
夜、港の公園。
海風が重油の匂いを含んで湿っている。
遠くに見える観覧車のネオンが、雨に濡れたように滲んで見えた。
「来てくれてありがとう」
ベンチに座る晴人の輪郭が、月光の下でぼんやりと発光しているように見えた。
私は恐る恐る、彼の胸元を見る。
やはり、透明だ。
吸い込まれそうなほど純度の高い、絶望的な透明。
「……話って、なに?」
私は絞り出すように尋ねた。
拒絶されるのが怖い。
自分の色が分からない私は、彼にとって自分がどんな色に見えているのかさえ分からない。
ただ判決を待つ囚人のように、身を強張らせる。
晴人は何も言わず、あのオルゴールを取り出した。
そして、ゆっくりとネジを巻く。
カリ、カリ……。
まただ。
あの旋律が、今度ははっきりと聞こえる。
脳髄の奥底から湧き上がるような、懐かしく、温かい響き。
「葵には、聞こえるんだろ?」
晴人が静かに言った。
その声は、夜の闇に溶けそうなほど儚い。
「え……?」
「僕には聞こえない。でも、君がこれを回すと、泣きそうな顔をするから。きっと、君にしか届かない音が鳴っているんだと思った」
彼はオルゴールを私の手に握らせた。
彼の体温が、硬直した私の指先から流れ込んでくる。
「僕には、もう世界がよく見えないんだ」
晴人の言葉に、呼吸が止まる。
「どういう……こと?」
「君以外の人間が、書き割りの絵みたいにペラペラに見える。声も遠い。まるで、僕と君だけが、別の時間のレールに乗ってしまったみたいに」
彼の指が、私の髪を梳く。
その感触だけが、唯一の現実だった。
「怖いんだ。自分が消えてしまいそうで。でも、君への想いだけは、どうしても消えない。むしろ、どんどん強くなって、僕の中を埋め尽くしている」
「嘘よ」
私は思わず叫んでいた。
オルゴールを握りしめたまま、立ち上がる。
感情の堤防が決壊した。
「だって、見えないの! あなたの感情の色が!」
「色?」
「喜びも、悲しみも、愛情も! 全部消えちゃったの! 一週間前から、あなたは空っぽなのよ! 私への愛なんて、ひとかけらも残ってないじゃない!」
叫び声が夜気に吸い込まれる。
涙が溢れた。
私の感情は、今、どんな汚い色をして零れ落ちているのだろう。
晴人は驚いたように目を見開き、そして悲しげに微笑んだ。
その透明な胸の奥で、何かが揺らめいた気がした。
「そうか……。君には、そう見えていたんだね」
彼は立ち上がり、私を抱きしめようとした。
その瞬間。
世界が、剥がれ落ちた。
遠くの観覧車のライトが、空中で静止し、光の粒子となって霧散する。
打ち寄せる波の音が、不自然に引き伸ばされ、やがてプツリと途絶えた。
通り過ぎようとした野良猫が、片足を上げたまま、彫像のように固まった。
「……時間が、止まった?」
いいえ、違う。
私たちが、世界から弾き出されたのだ。
第三章 無垢なる融合
静寂。
鼓膜が痛くなるほどの、完全なる静寂。
風の音も、街の喧騒も、虫の声も消え失せた。
動いているのは、私と晴人だけ。
「葵」
晴人の声だけが、空気の振動を介さず、直接心に染み込んでくる。
「これは……」
私は自分の手を見た。
指先の輪郭が、淡く発光し、夜の闇に溶け出し始めていた。
私の肌の色が、薄れていく。
「僕たちは、境界線を超えたんだ」
晴人が私を抱きしめた。
彼の体は温かいのに、どこか実体がない。
まるで雲を抱いているような、頼りない感触。
けれど、密着した彼の胸から、あの恐ろしい「透明」が私の内側へと雪崩れ込んでくる。
「……っ!」
私は反射的に身を強張らせた。
虚無に飲み込まれる、そう思ったからだ。
だが、違った。
流れ込んできたのは「無」ではない。
圧倒的な質量の「光」だった。
あまりにも純度が高く、あまりにも濃密な愛情。
赤やピンクといった単一の色では表現できない、すべてのスペクトルを束ねた結果としての「透明」。
プリズムを通す前の、無垢な白光。
それが、晴人の感情の正体だったのか。
「見えないんじゃない」
私は彼の背中に手を回す。
私の手もまた、彼の中に沈んでいく感覚がある。
熱いのか、冷たいのかさえ分からない。ただ、心地よい痺れが全身を駆け巡る。
「同じだから、見えなかったんだ」
水の中に水を注いでも、区別がつかないように。
私の心と、晴人の心が、完全に同期してしまっていたから。
自分自身の感情の色が見えない私にとって、私と一体化した彼の色もまた、見えるはずがなかったのだ。
「葵、聞こえる?」
晴人の声が、私の内側から響く。
手の中で、無音のオルゴールが勝手に回り始めた。
カリ、カリ、という物理的な音はない。
けれど、今やはっきりと聞こえる。
それは二人の魂が共鳴し、擦れ合う音。
「僕の感情が消えたんじゃない。僕が、君になったんだ」
「私も……あなたが、私の中にいるのが分かる」
私のコンプレックスだった「見えない自分の感情」。
空っぽだった私の器が、今、晴人という光で満たされていく。
不安も、恐怖も、孤独も。
ドブ川のような灰色も、刺々しい黒赤も。
すべてが、この眩い透明な光の中で中和され、溶けていく。
周囲の景色が、急速に色を失い、白くフェードアウトしていく。
公園も、海も、星空も。
世界のテクスチャが剥がれ落ちていく。
「戻れなくなるよ」
晴人が優しく囁く。
それは警告であり、甘美な誘いでもあった。
「このまま進めば、世界は僕たちを認識できなくなる。僕たちも、世界を認識できなくなる。永遠に、二人だけの閉じた時間の中で漂うことになる」
「……怖くないの?」
「君がいない世界で色を見るより、君だけの世界で溶けていたい」
彼から流れ込む感情の波が、私の心を震わせる。
そこには一点の曇りもない、結晶のような真実があった。
もう、他人の顔色を窺う必要はない。
誰かの感情の濁流に酔い、吐き気を催すこともない。
「私も……」
私はオルゴールを強く握りしめた。
その旋律は、今や世界を覆い尽くすシンフォニーのように、私の全細胞を揺らしている。
「私も、あなたと一緒がいい」
言葉にした瞬間、私の視界から「色」という概念そのものが消滅した。
赤も青も黄色もない。
ただ、すべてを包み込む白と、満ち足りた温もりだけがある。
「愛してる、葵」
「愛してる、晴人」
二人の輪郭が崩れ、混ざり合い、一つになる。
「私」と「あなた」という境界線が、砂糖菓子のように甘く溶けて消失する。
そこにはもう、色を見る瞳も、見えないことに怯える心も必要なかった。
世界は完全に静止し、そして消え去った。
残されたのは、何もない白い空間と、永遠に奏で続けられる無音のオルゴール。
そして、溶け合った二つの魂が紡ぐ、終わりのない幸福な夢だけ。
誰も知らない場所で。
誰も邪魔できない時間の中で。
私たちは、永遠に透明な愛を歌い続ける。