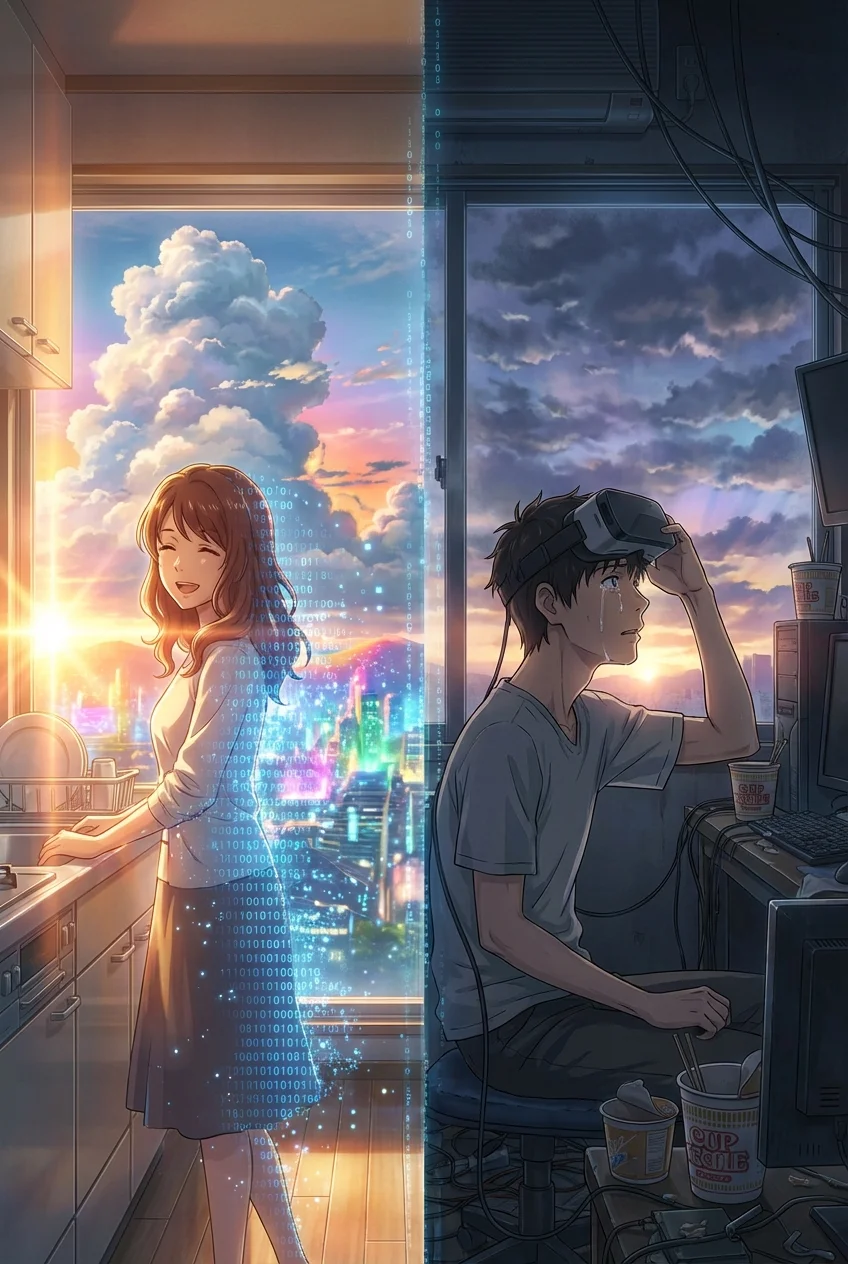第一章 残業代の出ない余生
雨に打たれたアスファルトが放つ、鉛のような匂い。
ドブ川から立ち上る、発酵した汚泥の熱気。
それらが混ざり合う路地裏の闇で、俺――田中健一の鼻孔が、痙攣したように動いた。
違う。
この腐臭のレイヤーの奥に、ある。
もっと鮮烈で、暴力的ですらある「命」の周波数が。
片方だけ残った眼球が、泥濘(ぬかるみ)の中で鈍く光る一点を捉えた。
ゴミ集積所の脇。ヘドロに半身を埋めた、一本の大根。
普通の人間なら顔を背けるだろう。
だが、俺の網膜には焼き付いている。その大根から立ち上る、黄金色の湯気のようなオーラが。
「……棚卸資産、確認。ポテンシャル……特A」
喉から漏れたのは、擦り切れた換気扇のようなノイズだった。
俺はアスファルトに爪を立て、這いずった。
左手の薬指がポロリと落ち、白い指骨が泥に沈む。
痛みはない。痛覚神経なんて、先月の「過労死」の時にとっくに焼き切れた。
「現物、確保……」
泥だらけの大根を鷲掴みにした瞬間、脳のシナプスがスパークした。
舌には乗せていない。
だが、俺の脳髄は理解している。
この大根が吸い上げた大地のミネラル、霜に当たって凝縮された糖度、そして皮の裏にある鼻を突き抜ける辛味。
これを薄くスライスし、隣に転がっている腐った柚子の皮と合わせれば――。
『脳味噌が喰いたい』
唐突に、腹の底からドス黒い飢餓感がせり上がる。
新鮮な、恐怖に歪んだ人間の脳漿。それを啜れば、この乾いた喉も一瞬で潤うだろう。
ガ、と歯が鳴った。
俺は自分の太腿を爪で抉った。腐肉が裂け、黒い体液が滲む。
正気に戻れ。まだ、俺は「あっち側」じゃない。
俺は胸ポケットから、画面の砕けたスマートフォンを取り出した。
バッテリー残量は1%。
指先に、残った全神経を集中させる。
心臓の代わり動いている「未練」という名のエネルギーを、指先へ。
ジジ、ジジジ……。指の肉が焦げ、端子を通じてスマホへ電流が流れる。
画面が明滅し、光が戻る。
俺の魂を削り、デジタル世界への出勤打刻。
アプリ起動。
ブログ『元社畜の絶品・廃棄飯ログ』。
《業務日報。
泥中大根の熟成カルパッチョ、廃棄柚子のゼストを添えて。
補足:咀嚼するたび、生命力が食道で爆ぜる。
評価:星5つ》
震える指でフリック入力。
送信ボタンを押す。
即座に震える端末。
通知ランプの青白い光が、濁った俺の瞳に反射する。
1件、2件、10件……。
数字が増えるたび、腐り落ちて唇のない口元が、卑しく歪んだ。
脳内に微量のエンドルフィンが分泌される。
俺はまだ、ここにいる。
社会という巨大なシステムの一部として、まだ機能している。
その時、通知音が鳴った。
いつもの「美味しそう!」という定型文ではない。
『田中さん、まだ探しているんですか? あなたの“あの味”が、プロジェクト・ミダスの鍵だったなんて』
背骨のない背中を、氷柱で貫かれたような悪寒が走り抜けた。
第二章 記憶の底のスパイス
「プロジェクト……ミダス……」
その文字列を見た瞬間、視界が白くハレーションを起こした。
消毒液の匂い。
駆動音を立てる空調。
無機質なステンレスの調理台。
『田中君、これは料理じゃない。エサだ』
白衣を着た男が、俺の鍋を指差して冷淡に言い放つ。
『コストを削れ。脳の報酬系を直接刺激する化学物質を入れろ。消費者が中毒になり、死ぬまで買い続けるような“魔法の粉”を作れ』
記憶の断片が、吐き気と共に逆流する。
俺はシェフじゃなかった。
俺は、中毒性食品を開発する研究員――いや、ただの加担者だった。
「う、ぐ、あぁぁ……!」
頭を抱えようとした右腕が、肘から先でボクリと折れた。
腐敗が加速している。
思考の負荷に、肉体が耐えられない。
俺は慌てて、コンクリートの隙間に咲くドクダミをむしり取った。
ただの雑草じゃない。
葉脈の一本一本に、青白い燐光が走っているのが見える。
ゾンビ化ウイルスの進行を遅らせる、天然の抑制剤。
葉を噛み砕く。
強烈な青臭さが鼻腔を突き抜け、崩れかけた自我を無理やり繋ぎ止める。
スマホが再び震えた。
『思い出して。あなたが最後に作った、あのカレーを。あれこそが、世界を救うワクチンだった』
コメントの主は、俺を知っている。
「最後の、カレー……」
俺は目を閉じる。
そうだ。
あれは、終わりの始まりの日。
三日三晩、不眠不休で働かされ、思考能力が消し飛ぶ寸前の深夜三時。
俺は、上司の命令を無視した。
化学調味料の瓶をゴミ箱に投げ捨て、実家から届いたダンボールを開けた。
青森県産、完熟サンふじ。
糖度16度。蜜がたっぷり入ったそれを、皮ごとすりおろす。
クミン、コリアンダー、ターメリック。
そして、アメ横の怪しいスパイス屋で手に入れた、名前も知らない真っ赤な木の実。
鍋の中で、飴色玉ねぎとスパイスが踊る。
四十八時間煮込んだ牛スジが繊維一本まで解け、スープに溶け込んでいく。
実験室に充満していた薬品臭が、芳醇で、どこか懐かしい香りに上書きされていく。
『課長、これ……』
試食した部下たちの顔。
死人のように蒼白だった彼らの頬に、みるみる赤みが差した。
虚ろだった瞳孔が収縮し、生気が宿る。
疲労物質で淀んだ脳内が、スパイスの刺激と果実の酵素で洗い流されていく音すら聞こえた気がした。
『なんか、明日も生きられそうな気がします』
『母ちゃんの飯より、美味いです……』
泣きながらカレーを貪る彼らを見て、俺の胸の奥で何かが満ちた。
承認欲求じゃない。
もっと根源的な、誰かの命を支えたという実感。
「そうか……」
あれは、ただのカレーじゃなかった。
極限状態の脳が、生存本能に従って選び抜いたスパイスの調合。
そして、「部下を死なせたくない」という俺の過剰なまでの執念が生み出した、奇跡の化学反応。
会社は、それに気づいたのだ。
俺のレシピが、ゾンビ化ウイルス――つまり「脳の壊死」すらも逆転させる可能性を秘めていることに。
だから俺は消された。
レシピを独占し、治療薬として高値で売りさばくために。
「……業務命令、受諾。これより、最終工程へ移行する」
俺は折れた右腕を、落ちていたガムテープで強引に固定した。
骨が軋む音がするが、構わない。
まだだ。
俺にはまだ、提出しなければならない「始末書」がある。
第三章 世界を変えるワンプレート
体はもう、言うことを聞かない。
下半身の感覚は消失し、視界は砂嵐のようなノイズに覆われている。
俺はゴミ捨て場に座り込んだまま、スマホを握りしめている。
残った命の灯火を、すべてこの端末への給電に回す。
「納期、厳守……」
指が動かないなら、音声入力でいい。
喉が潰れているなら、脳波で直接干渉するまでだ。
ブログのエディタを開く。
タイトルは『プロジェクト・ミダス:真正レシピ』。
俺が見ていた「食材の輝き」。
それは単なる幻覚じゃなかった。
食材が持つ、抗ウイルス作用を持つ化合物の可視化だ。
ゾンビが人を襲うのは、脳内の神経伝達物質が枯渇し、永遠の飢餓状態にあるからだ。
ならば、それを食事で満たせばいい。
必要なのは、三つの要素。
一つ、路傍に咲く彼岸花の球根から抽出した、リコリン(毒抜き処理済み)。
二つ、廃棄寸前のジャガイモの芽に含まれるソラニン(加熱処理で変質させたもの)。
そして、三つ目。
《隠し味:調理者の涙》
比喩ではない。
過労と絶望、そして僅かな希望が入り混じった涙に含まれる「副腎皮質刺激ホルモン」と「ロイシンエンケファリン」。
これらがスパイスと熱反応を起こし、脳細胞を再起動させるトリガーとなる。
「……ふ、はは。とんだオカルト科学だ」
だが、俺の舌は覚えている。
あの夜、鍋に落ちた俺の涙が、カレーの味を決定的に変えたことを。
俺は、暗号化されていたデータを解凍し、数式と調理法を書き殴る。
添付ファイルには、企業のサーバーから盗み出していた内部告発データも仕込んだ。
「送信……ッ!」
画面に「投稿されました」の文字が浮かぶ。
同時に、俺の視界から色が消えていく。
黄金色のオーラも、紫の光も、もう見えない。
世界は、静寂な灰色に包まれた。
スマホが手から滑り落ちる。
不思議と、恐怖はなかった。
腹の減りもない。
ただ、胸の奥だけが、あの日のカレーを食べた後のようにポカポカと温かい。
「あぁ……ごちそうさまでした……」
俺は、見えないスプーンで、世界を一口、味わった気がした。
まぶたが重い。
長い長い、残業が終わる。
最後に聞こえたのは、スマホの通知音の嵐。
それはまるで、俺を送り出す拍手のように響いていた。
エピローグ おかわりをもう一杯
小雨が降る、廃墟のコンビニエンスストア。
一人の男が、床に座り込んでいた。
皮膚は灰色に変色し、左腕は欠損している。
彼は喉を鳴らし、唸り声を上げながら、落ちていた空き缶を拾い上げた。
中には、誰かが作ったドロリとしたスープが入っている。
見た目は最悪だ。
だが、匂いが違う。
鼻腔をくすぐる、クミンと焦がしたリンゴの香り。
男は震える手で、缶に口をつけた。
一気に流し込む。
その瞬間。
「ガ、ア……?」
男の濁った瞳孔が、キュッと収縮した。
脳内を駆け巡っていた「喰いたい」というノイズが、波が引くように消えていく。
代わりに思い出されたのは、あたたかい食卓の記憶。
そして、かつての上司の、疲れているくせに得意げな笑顔。
「う……ま……い」
男の目から、一雫の涙がこぼれ落ち、スープに混ざった。
それが新たな化学反応を起こし、香りが強くなる。
男はゆっくりと立ち上がった。
コンビニの外には、同じように飢えた仲間たちが彷徨っている。
彼らに、これを味わせなければならない。
「おすそわけ……しなきゃ……」
男は缶を大事に抱え、雨の中へと歩き出した。
その足取りは、もう徘徊ではない。
明確な意思を持った、人間の歩みだった。
雨に濡れた路地裏の片隅。
小さな白い花に覆われたひび割れたスマートフォンが、一度だけ、満足げに短く震えた気がした。