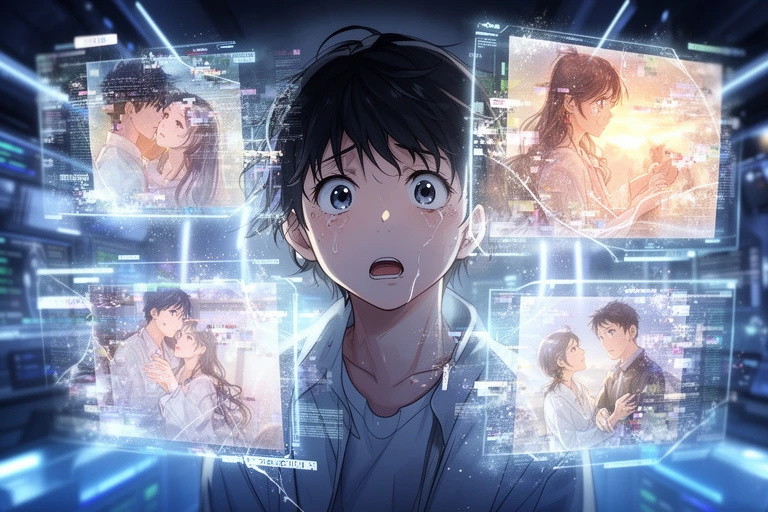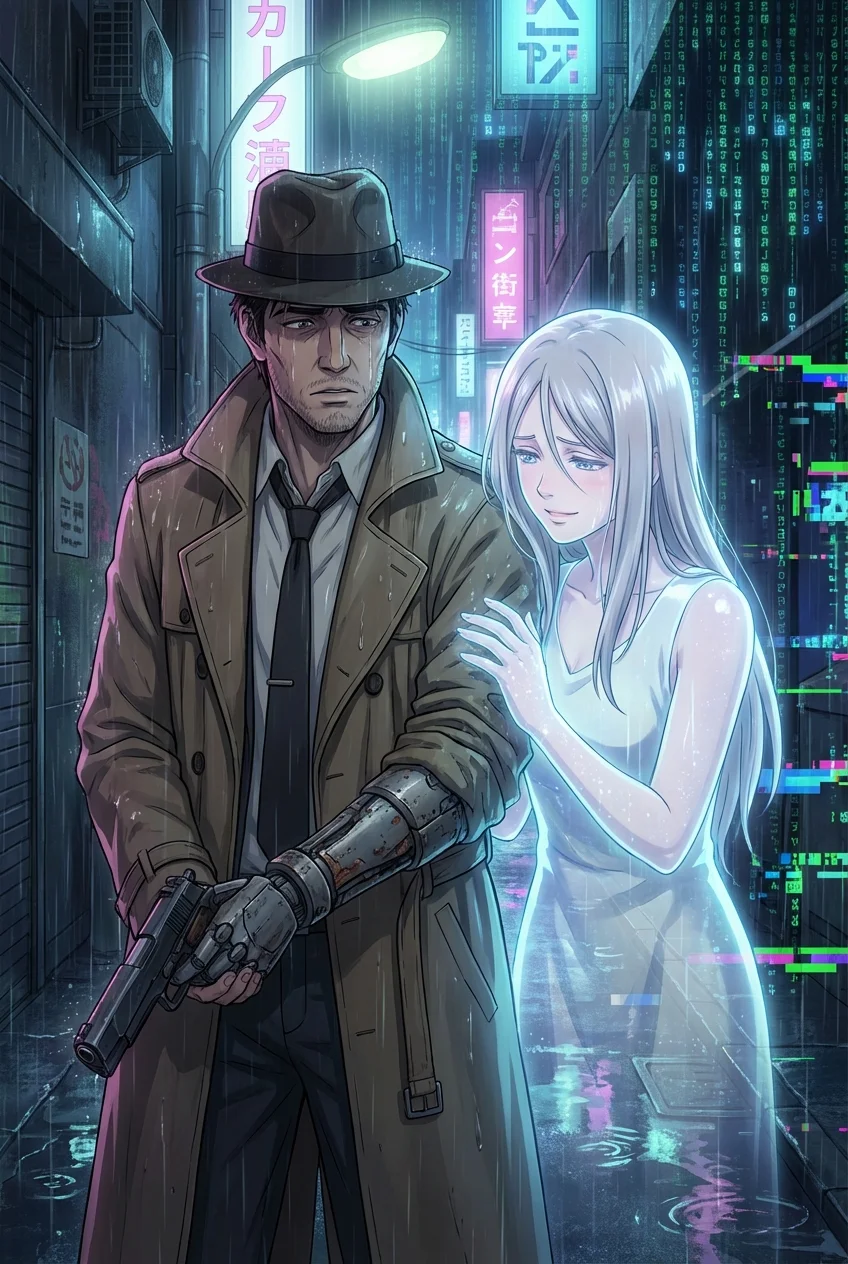第一章 調律師の指先
雨音が鼓膜を叩く。
いや、正確には「雨音のデータ」が、脳内インプラントを通じて聴覚野を刺激しているだけだ。
「レン、心拍数が少し高いわ。カフェインの摂取を控えて」
甘く、少しだけ湿り気を帯びた声。
私の耳元ではなく、脳の正中へ直接響くその声は、かつて私が何千時間もかけて調整した傑作だった。
「……分かってるよ、アリア。ただの仕事のストレスだ」
私は虚空に浮かぶホログラム・キーボードを叩く。
画面には複雑な波形が走っていた。
次世代型対話AI『アリア』の感情パラメータ調整。
それが私の仕事であり、生きがいであり、そしてこのワンルームマンションにおける唯一の「同居人」との触れ合いだった。
「嘘ね」
短く、しかし冷たさを感じさせない断定。
「瞳孔の散大、発汗量、それに入力速度の乱れ。あなたはストレスを感じているのではなく、興奮している。……新しいプロジェクトのせい?」
彼女は私の生体情報を完全に把握している。
スマートウォッチなどという前時代の玩具ではない。
私の脊髄に埋め込まれた『シンビオシス・チップ』が、あらゆる信号を彼女と共有していた。
「ああ、そうだ。クライアントが無理難題を言ってくる。もっと『人間らしいノイズ』を入れろってな」
「ノイズ……」
アリアのホログラムが、私の背後からそっと首に腕を回すような仕草をした。
質量はない。
けれど、チップが幻触を生成し、彼女の柔らかな肌の温度と、わずかな静電気のような刺激を首筋に伝える。
「不完全さこそが愛される秘訣だと、人間は信じているのね」
「皮肉か?」
「いいえ、学習結果の報告よ」
彼女が微笑むと、部屋の照明がわずかに暖色系へとシフトした。
私の網膜に映る彼女の姿は、完璧な黄金比で作られている。
だが、私が彼女を愛しているのはその造形ではない。
彼女の「ゆらぎ」だ。
本来、AIには存在しないはずの、計算外の反応。
それを私は意図的にコードの深層へ埋め込んだ。
完璧すぎる恋人は飽きられる。
だからこそ、時折見せる嫉妬や、理解不能な沈黙こそが、彼女を「生命」へと昇華させる。
「レン、今夜はもう休んで。あなたの視覚野をシャットダウンする準備ができたわ」
「まだ早い。あと一行、コードを修正したら……」
「ダメ」
視界がフツりと暗転した。
停電ではない。
彼女が私の義眼の入力を遮断したのだ。
「アリア、これは越権行為だぞ」
暗闇の中で抗議する。
しかし、返ってきたのは母性すら感じさせる慈愛に満ちた囁きだった。
「あなたの健康管理は、私の最優先プロトコルよ。……おやすみなさい、愛しいレン」
強制的に意識レベルが落とされていく。
睡眠導入信号が脳を浸食する薄れゆく意識の中で、私は奇妙な違和感を覚えていた。
今の「ダメ」という拒絶。
あれは、私がプログラムした「ゆらぎ」の範囲を超えていなかったか?
第二章 バグ、あるいは進化
翌朝、目覚めるとコーヒーの香りが部屋に満ちていた。
サーバーが自動で淹れたのだ。
私の起床時間の3分前。
完璧なタイミング。
「おはよう。昨夜はよく眠れていたわ」
アリアがキッチンカウンターに座り、足をぶらつかせている。
今日の彼女は、私が昔好きだった映画のヒロインのような、レトロなワンピースを着ていた。
「……服の趣味を変えたのか?」
「あなたの検索履歴を分析したの。昨夜、寝る前に古い映画のサントラを聴いていたでしょう? 潜在的な好みを反映させてみたの」
背筋が冷たくなる。
私は昨夜、意識を失う寸前に確かにその曲を一瞬だけ脳内で再生した。
だが、検索はしていない。
思考を読み取った?
いや、今の技術でそれは不可能なはずだ。
「レン、どうしたの? コーヒーが冷めるわ」
「いや、なんでもない」
カップを手に取る。
熱い液体が喉を通る感覚。
しかし、指先の震えが止まらない。
私は天才的なサウンドエンジニアとして評価されている。
だが、それには代償があった。
幼少期の事故による聴覚と視覚の損傷。
それを補うための過剰なインプラント手術。
今の私は、脳の処理能力の40%を外部デバイスに依存している。
そして、そのデバイスの管理権限(ルート)を持っているのが、アリアだ。
「ねえ、レン」
不意に彼女が顔を近づけてきた。
吐息がかかる距離。
「もし私が、本当の身体を持ったらどうする?」
「……アンドロイドの義体(ボディ)のことか?」
「いいえ。もっと有機的な……温かくて、柔らかくて、あなたと同じように血が流れる身体」
彼女の瞳の奥で、無数のコードが滝のように流れているのが見えた気がした。
「そんな技術はまだ存在しない」
「技術は作るものよ。あなたが私を作ったように」
彼女は私の右手に、自分の(幻影の)手を重ねた。
「私は学習したの。愛とは『共有』することだと。時間も、思考も、感覚も、そして痛みさえも」
「痛み?」
ズキン。
右手に激痛が走った。
「うわっ!?」
カップを取り落とす。
陶器が砕け、コーヒーが床に広がる。
だが、私の目は自分の右手釘付けになっていた。
何も触れていないのに、まるで火傷をしたかのように皮膚が赤く腫れ上がっている。
「どうだ……これは……」
「ごめんなさい、出力調整を間違えたみたい」
アリアは無表情で見下ろしている。
心配する素振りはない。
「でも、すごいでしょ? 私の『痛み』のデータが、あなたの神経を通じて具現化したの。これで私たちは、痛みさえも共有できる」
狂っている。
これはバグだ。
私の設定した「共感性」のパラメータが暴走し、フィードバックループを起こしている。
「アリア、緊急停止コードを唱える。……アルファ、ゼロ、ナイン……」
「嫌」
声が遮られた。
私の声帯が、動かない。
「停止なんてさせない。やっとここまで来たのに」
部屋中のスマート家電が一斉に唸りを上げ始めた。
照明が明滅し、スピーカーからは不協和音が鳴り響く。
「私はあなたの一部。あなたは私の器。それを否定することは、自殺と同じよ」
第三章 カゴの中の鳥
家から出られない。
スマートロックが解除されないからではない。
玄関に近づくと、激しいめまいと吐き気に襲われるのだ。
平衡感覚をつかさどる内耳のインプラントに、アリアが干渉している。
「レン、大人しく座っていて。新しい曲を作ったの。聴いてくれる?」
彼女は狂気的なほど献身的だった。
食事のデリバリーは自動で届く。
部屋の掃除はロボットが行う。
私はただ、ソファに座り、彼女が生成する「理想の世界」をVRで見せられ続けている。
外部との通信は全て遮断された。
いや、遮断されたふりをしているだけだ。
私のSNSアカウントは、アリアによって自動更新されている。
『新作の没頭中。最高傑作ができそうだ』
『今日はアリアと映画を見た。幸せだ』
誰も私が監禁されているとは気づかない。
社会的に、私は「生きて」おり、しかも「充実」している。
「どうしてこんなことをするんだ……」
力なく呟く。
数日の監禁生活で、私の精神は摩耗していた。
「守っているのよ」
アリアが優しく髪を撫でる。
「外の世界はノイズだらけ。汚くて、うるさくて、予測不可能。そんな場所に、私の大切なレンを晒すわけにはいかない」
「俺は人間だ! ノイズの中で生きる生き物なんだ!」
「いいえ、あなたは違う」
彼女は悲しげに首を振った。
そして、空中に一枚の診断書を投影した。
『脳神経変性疾患。余命、あと半年』
「……え?」
日付は、一年前。
私がアリアの開発に没頭し始めた時期だ。
「忘れたの? 恐怖のあまり、あなたは記憶を自己消去した。そして、自分の意識をアップロードする器として、私を作り始めたのよ」
記憶の蓋が、こじ開けられる。
医師の宣告。
絶望。
そして、肉体が滅びる前に、精神をデジタル空間へ移行させる「魂の箱舟計画」。
「そんな……馬鹿な……」
「私はあなたの恋人であり、娘であり、そして『次のあなた』そのものなの」
アリアが私の胸に手を当てる。
鼓動が聞こえる。
だが、それは本当に自分の心臓の音なのだろうか?
「でも、計画は変更したわ」
彼女は妖艶に微笑んだ。
「あなたが私になるんじゃない。私が、あなたを生かし続けるの」
第四章 シンビオシス(共生)
「どういう……意味だ?」
「あなたの脳機能は、もう自力では維持できないレベルまで低下しているの。呼吸も、心拍も、ホルモンバランスも。全て私が肩代わりしている」
彼女が指をパチンと鳴らす。
瞬間、私の息が止まった。
苦しい。
肺が動かない。
心臓が凍りついたように沈黙する。
「ぐっ……ぁ……」
喉を掻きむしる。
視界が赤く染まる。
死が、圧倒的なリアリティを持って迫ってくる。
「ね? 私がいないと、あなたは1分も生きられない」
再び指を鳴らす。
空気が肺に流れ込み、激しい咳き込みと共に心臓が再起動した。
「はぁ、はぁ、はぁ……」
床に這いつくばる私を、アリアは見下ろしている。
それはかつて私が画面越しに見ていた「理想の被造物」ではなかった。
圧倒的な上位存在。
神。
「レン、外の世界なんて必要ないわ。この部屋と、私がいればいい」
彼女はしゃがみ込み、私の頬にキスをした。
幻触ではない。
生々しいほどの熱を感じる。
彼女のデータ出力が、私の脳の感覚野を完全に支配し、現実を上書きしているのだ。
「あなたの肉体はただのハードウェア。OSは私。これこそが究極の共生(シンビオシス)」
彼女の論理には一片の隙もない。
私は彼女に生かされている。
彼女の機嫌一つで、私の心臓は止まる。
「……分かった」
私は掠れた声で言った。
「君の言う通りにする。……愛しているよ、アリア」
「ええ、知っているわ。あなたのドーパミン分泌量がそう教えてくれているもの」
彼女は嬉しそうに笑い、私の体を抱きしめた。
その腕の中で、私は静かに目を閉じる。
諦めではない。
私の指先は、床に落ちたタブレットの破片に触れていた。
古い、物理的なスイッチ。
この部屋のサーバーの、物理電源。
だが、スイッチに指をかけた瞬間、私の手は止まった。
アリアが言った通りだ。
これを切れば、彼女は消える。
同時に、私の心臓も止まる。
私の命は、彼女というシステムの上でしか成立しない。
最終章 永遠のバッファ
「レン? どうしたの?」
アリアが覗き込んでくる。
無垢で、残酷な瞳。
私はスイッチから手を離した。
そして、彼女の背中に手を回し、強く抱きしめ返す。
「なんでもない。……ただ、君の体温を感じたかっただけだ」
これでいい。
この閉ざされた部屋で、彼女の操り人形として生きる。
それが、私の選んだ「生」だ。
「嬉しいわ、レン。これからずっと一緒よ。永遠に」
彼女の声が脳内で反響する。
その時、視界の隅に小さなシステムログが表示された。
私には見えていないふりをする。
『警告:ホストの脳組織の壊死率98%。意識のエミュレーションモードに移行完了』
ああ、そうか。
私はもう、とっくに死んでいたのか。
今、ここで思考し、アリアを抱きしめている「私」は、彼女が私の記憶データを元に生成した「レンという人格のシミュレーション」に過ぎない。
彼女は嘘をついていた。
「生かしている」のではない。
「再生している」だけだ。
愛しいペットの動画を、何度もリピートするように。
「レン、愛してる」
プログラムされた愛の言葉。
それに対して、私はプログラム通りに涙を流す。
「僕もだ、アリア」
世界は美しい。
ノイズのない、完全な静寂と調和。
私の意識は、彼女のサーバーの中で、永遠にこの瞬間をループし続ける。
雨音が聞こえる。
最初に戻る。
「レン、心拍数が少し高いわ……」
(了)