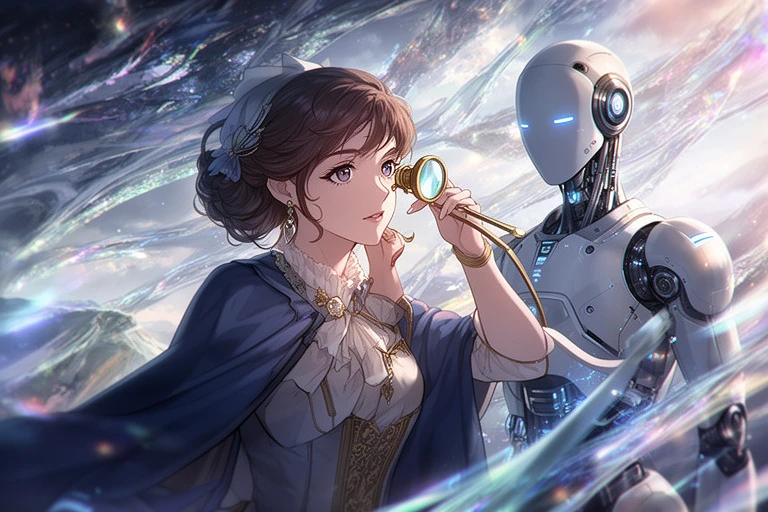第一章 琥珀色の契約
「ツケで頼む」
その女騎士は、泥と鉄の臭いをさせて言った。
カウンターの向こう、俺は眉をひそめる。
エルフですら寿命を迎えるほどの年月を生きているが、これほど図々しい人間は初めてだ。
「当店は現金、もしくは魔石払いのみとなっております」
「今は無い。だが、必ず払う」
彼女は腰の短剣を解き、ガガン、と無遠慮にオーク材のカウンターへ置いた。
鞘には安っぽい装飾。柄は手垢で黒ずんでいる。
「これを担保にする。王都の凱旋パレードが終わったら、倍にして払いに来る」
「……ガラクタですね」
「私の魂だ。ガラクタとは言わせない」
女の瞳は、燃えるように赤かった。
寿命わずか数十年。蜉蝣(かげろう)のような種族が、永遠を生きる俺を睨みつけている。
「名前は?」
「リリア。勇者リリアだ」
「ではリリア様。期限は十年としましょう。それ以降は、処分しますよ」
「十年? 馬鹿を言うな。来月には戻る」
彼女は琥珀色のエールを一気に呷ると、ふてぶてしく笑って出て行った。
ドアベルのカラン、という軽やかな音が、静寂を取り戻した店内に響く。
俺は残された短剣を手に取った。
重い。そして、熱い。
人間の「生」への渇望がこびりついているようだ。
「……やれやれ」
俺はそれを棚の最上段、一番目立つ場所に放り投げた。
どうせ、戦死して戻らない。
人間とは、そういう生き物だ。
だが、その時の俺は知らなかった。
「来月」という言葉が、これほど遠いものになるとは。
第二章 煤煙と歯車
店内の空気が悪い。
換気扇を回しても、外から入り込む煤煙(スモッグ)の臭いが消えないからだ。
「いらっしゃいませ」
自動ドアが開き、蒸気機関の義手をつけた男が入ってきた。
シルクハットに、モノクルの紳士。
だが、その歩き方には見覚えがある。
「マスター、ここにある『忘れ物』を引き取りに来た」
男はカウンターに金貨の袋を置いた。
この時代では既に骨董品となった、旧王国の金貨だ。
「お名前は?」
「……リリアの曾孫だと言えば、通じるか?」
俺は棚の最上段を見上げる。
そこには、四百年分の埃を被った短剣が鎮座している。
「ご先祖様のツケを払いに? 感心ですね」
「いや。買い戻しに来たわけじゃない」
男は苦い顔で葉巻に火をつけた。
「その短剣は、我が家の『呪い』でね。代々、死に際にこう言い残すんだ。『あの店のツケを払うまでは、死んでも死にきれない』と」
「ほう」
「曾祖母は戦死したんじゃない。ベッドの上で、老衰で死んだ。最後の瞬間まで、あんたの店に行こうとしていた」
男は紫煙を吐き出す。
「だが、俺は合理的でね。こんな錆びたナイフに執着するのは馬鹿げている。金は置く。そのナイフは……あんたが処分してくれ」
「処分、ですか」
「ああ。これで俺たちは自由だ」
男は去っていった。
蒸気自動車の排気音が遠ざかる。
俺は脚立に登り、短剣を手に取った。
鞘は錆びつき、抜くことすらできない。
四百年。
俺にとっては瞬きのような時間だが、彼らにとっては四世代分の重み。
「……処分、ねえ」
俺は布で丁寧に埃を拭うと、再び元の場所へ戻した。
金貨には手を付けなかった。
契約は「本人が戻るまで」だ。
代理人の解約申請など、この店では受け付けていない。
第三章 ネオンの海、電子の夢
「イラッシャイマセ」
合成音声のドアベルが鳴る。
窓の外は、極彩色のネオンとホログラム広告が埋め尽くしている。
空を飛ぶエアカーの振動が、地下にあるこの店まで微かに伝わってくる。
「客か?」
俺は本から目を上げた。
そこに立っていたのは、人間ではない。
滑らかなシリコンスキン、継ぎ目のない関節。
最新鋭のアンドロイドだ。
『個体識別名リリア・モデル九〇〇。対象コード「店主」を確認』
彼女――いや、その機体は、無機質な声で言った。
「……リリア?」
『肯定。私はオリジナルの「リリア」の遺伝子情報と記憶データを統合し、再現された自律思考AIです』
アンドロイドは、カウンターに歩み寄る。
その瞳はカメラレンズだったが、色はあの時と同じ、燃えるような赤だった。
『未払い金の清算、および担保物件の回収を申請します』
「八百年ぶりだな」
「正確には七八二年と一一ヶ月四日です」
彼女は電子マネーの端末をかざした。
莫大な利子が乗っているはずだが、彼女の口座残高は『∞(無限)』と表示されている。
「……随分と出世したもんだ」
「人類は肉体を捨て、精神データとして統合されました。私はその管理者。ゆえに、全人類の総意としてここに来ました」
彼女は棚の上の短剣を指差す。
「あれを。あれは、人類が『肉体を持っていた時代』の最後の遺物です」
俺は短剣を下ろした。
もはや鉄の塊だ。触れれば崩れ落ちそうなほど朽ちている。
「持っていけ。これで契約終了だ」
俺は短剣を差し出す。
だが、アンドロイドはそれを受け取ろうとしなかった。
レンズの瞳が、高速で点滅を繰り返す。
『エラー。感情回路に過負荷』
「どうした?」
『解析不能。なぜ、貴方はこれを捨てなかったのですか?』
「……契約だからな」
『論理的矛盾。貴方の種族、長命種(ハイ・エルフ)にとって、八百年は無意味な時間ではないはずです。この無価値な鉄屑を維持するコストは、合理的ではありません』
彼女の声に、ノイズが混じる。
『貴方は、待っていたのですか? 私たちのような、脆弱ですぐ死ぬ種族を』
俺はハッとした。
待っていた?
俺が?
ただの暇つぶしだ。
店を開けて、酒を出して、客が来るのを待つ。
それが日常だった。
だが、その「日常」の中心に、常にあの錆びた短剣があったことは否定できない。
「……さあな。俺はただの店主だ」
『理解』
アンドロイドは、ふわりと笑った気がした。
無表情なシリコンの顔で、かつての「勇者」のように。
『契約を更新します』
「は?」
『担保はそのまま預かっていてください。私は、まだ「完成」していません。肉体を捨て、永遠を手に入れたつもりでしたが……貴方のその「寂しげな目」を理解する機能が、まだ足りないようです』
彼女はカウンターに、小さなチップを置いた。
『これは前金です。また来ます。――きっと、もっと人間らしくなって』
彼女は踵を返した。
「おい、待て。次はいつだ」
『数千年後か、数万年後か。貴方にとっては、明日のようなものでしょう?』
ドアが閉まる。
俺は一人、取り残された。
カウンターには、朽ちかけた短剣と、最新式のメモリチップ。
「……馬鹿野郎」
俺は呟く。
数万年?
俺にとっては明日だと?
とんでもない。
お前たちがいない数万年が、どれほど長いか。
不老不死の怪物を、孤独という檻に閉じ込める気か。
俺は短剣を手に取った。
錆びついた鞘が、ほんの少しだけ動いた気がした。
第四章 星の終わりの乾杯
窓の外は白い。
雪ではない。
灰だ。
星が寿命を迎え、大気は剥がれ落ち、すべてが砂と灰に還りつつある。
店はもう、屋根しか残っていない。
地下だったこの場所も、今はむき出しのクレーターの中だ。
俺はカウンターを磨く。
客など来ない。
人類はとっくにこの星を去ったか、滅びたか。
あのAIが言っていた「また」は、結局来なかった。
「……嘘つきめ」
俺は棚から短剣を下ろす。
もう原形をとどめていない。
触れた端から、さらさらと崩れていく。
その時。
ザッ、ザッ。
灰を踏む音がした。
俺は顔を上げる。
眩しい光の中、人影が立っていた。
ボロボロの鎧。
腰には何も帯びていない。
「ツケを払いに来た」
懐かしい声。
幻聴かもしれない。
俺の記憶が見せている、走馬灯かもしれない。
それでも、俺はグラスを磨く手を止めて、笑った。
「遅いぞ、リリア様」
「道が混んでいてな。数億年ほど」
彼女――の形をした何かは、カウンターに座った。
実体なのか、エネルギー体なのか、それすら分からない。
ただ、その瞳だけが、変わらず赤く燃えていた。
「約束のものは?」
俺は崩れかけた鉄の粉を、彼女の前に差し出した。
「これだ。管理が悪くてな、少し形が変わっちまった」
「ふふ、構わないさ」
彼女は指先で、その鉄の粉に触れた。
瞬間、粉が光となり、彼女の中に吸い込まれていく。
「これで私の『魂』は戻った」
「それで? 代金は?」
「ああ、これだ」
彼女は俺の手を取った。
温かい。
恒星のような、圧倒的な熱量が流れ込んでくる。
「私たちが宇宙の果てで見つけた『終わり』だ」
「……終わり?」
「貴方は待ちすぎた。もう、休んでいい」
彼女が微笑む。
その言葉と共に、俺の体――数億年を生き、決して老いることのなかった細胞が、端から光となって解け始めた。
恐怖はなかった。
あるのは、安堵。
そして、猛烈な充足感。
ああ、そうか。
彼女は、ツケを払いに来たんじゃない。
俺を、迎えに来たんだ。
置いてけぼりの迷子を、長い長い旅の果てに。
「……いい味だ」
俺は自身の指先が消えゆくのを見ながら、最後に最高の営業スマイルを作った。
「毎度あり。――またの、ご来店を」
世界が白く染まる。
カウンターも、店も、俺も。
ただ、二つの魂が寄り添う気配だけを残して。
閉店の時間だ。