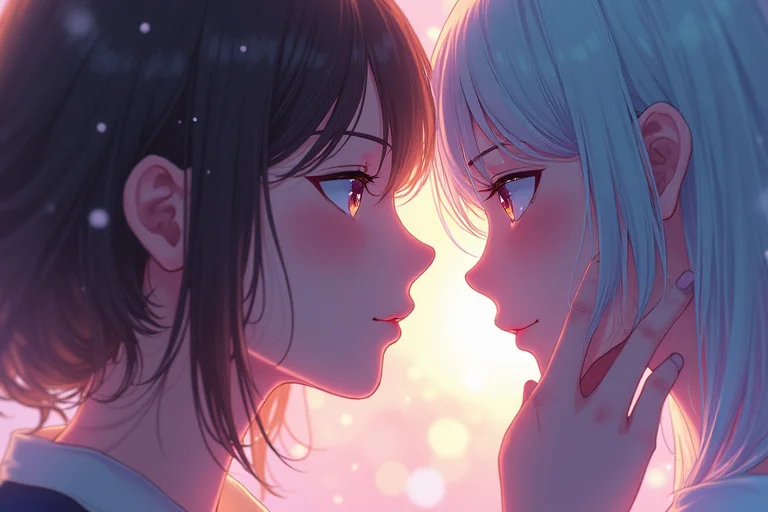第一章 灰色の街と、青の旋律
雨の匂いが、鉄錆のように鼻腔に張り付いていた。
僕、瀬名 蓮(せな れん)にとって、世界はいつだってうるさすぎる。
車のクラクションは暴力的な赤色の閃光。
電車の軋む音は、神経を逆撫でする黄土色のノイズ。
「共感覚」
音に「色」や「形」を見てしまうその特異体質は、僕から平穏を奪い、世界を混沌とした極彩色の地獄に変えていた。
だから僕は、ノイズキャンセリングのイヤホンを耳にねじ込み、視線をアスファルトに落として歩く。
誰とも関わらない。
何も聞かない。
それが、僕がこの世界で生き延びるための唯一のルールだった。
はずだった。
駅前の広場。雑踏の中。
ふと、視界の端を強烈な「青」が切り裂いた。
透き通るような、それでいて深海のように深い、群青色。
(……なんだ、この色は)
思わず足を止める。
イヤホンを外すと、その色はさらに鮮明になり、粒子のようになって僕の周囲を舞った。
視線の先には、一台のストリートピアノ。
そして、鍵盤を叩く少女がいた。
パーカーのフードを目深に被り、一心不乱に指を走らせている。
彼女が奏でるショパンの「雨だれ」が、僕の視界を美しい青色で塗り替えていく。
不快なノイズが消えた。
彼女の音が、街の雑音を全て洗い流しているようだった。
演奏が終わると、まばらな拍手が起こる。
彼女はフードを少し上げ、照れくさそうに笑った。
その笑顔を見た瞬間、僕の胸の奥で、何かが小さく跳ねた。
「……すごい色だ」
無意識に呟いていた。
彼女がこちらを振り向く。
目が合った。
「え? 今、なんて?」
彼女がピアノから離れ、小走りで近づいてくる。
人懐っこい、子犬のような瞳。
「あ、いや……なんでもない」
逃げようとした僕の袖を、彼女が掴む。
「聞こえてたよ! 色、って言ったでしょ?」
「……比喩だよ。音が鮮やかだったって意味だ」
「ふうん。変なの。私、冬月 奏(ふゆつき かな)。君は?」
「……瀬名」
「セナ君ね! ねえ、今の演奏どうだった? 最後のアルペジオ、ちょっと走っちゃったんだけど」
距離が近い。
彼女の声は、ピアノの音色と同じ、優しい水色をしていた。
「悪くなかった。……雨の音が消えるくらいには」
僕の素っ気ない感想に、奏は花が咲いたように笑った。
「最高の褒め言葉だね!」
それが、僕たちの始まりだった。
灰色の世界に、彼女という鮮烈な色彩が飛び込んできた日。
第二章 不協和音の予兆
それから、僕たちは頻繁に会うようになった。
僕は彼女のピアノが好きだったし、彼女は僕の「奇妙な感想」を面白がった。
「ねえレン君、今日の音は何色?」
「ドビュッシーは淡いピンクだ。桜の花びらみたいな」
「へえ! じゃあ、これは?」
彼女が激しいジャズのフレーズを叩く。
「……オレンジ。それも、焦げたような濃いオレンジだ」
「あはは! 正解。ちょっとイライラしてたの、今日」
奏は、僕の「共感覚」を気持ち悪がることなく、むしろ楽しんでくれた。
僕の欠陥を「才能」だと言ってくれた初めての人間。
けれど、ある日。
いつものように彼女がピアノを弾いている時、異変が起きた。
美しい青色の旋律の中に、黒い「欠落」が混じり始めたのだ。
音が飛んでいるわけではない。
リズムが狂っているわけでもない。
ただ、彼女が弾く音の色が、時折、墨汁を垂らしたように濁る。
「……奏?」
「ん? どうしたの?」
彼女は気づいていないようだった。
「いや……少し、音が擦れた気がして」
「え? 嘘、チューニング狂ってるかな」
彼女は鍵盤を叩き直すが、その表情に一瞬、影が差したのを僕は見逃さなかった。
違和感は日に日に増していった。
彼女の会話のテンポが、微妙に遅れる。
背後から呼びかけても、気づかないことがある。
そして、決定的な瞬間が訪れる。
カフェで向かい合って話していた時。
店員が落としたグラスが、けたたましい音を立てて割れた。
周囲の客が一斉に振り返る。
僕も、耳を塞ぎたくなるような銀色の鋭利なノイズに顔をしかめた。
けれど、奏だけが。
コーヒーカップを持ったまま、平然としていたのだ。
「……奏?」
「え? なに?」
彼女の視線が、僕の唇の動きを追っていることに気づく。
「聞こえて、ないのか?」
僕の声が震えた。
奏の手が止まる。
カップの中のコーヒーが、微かに波紋を広げた。
彼女はゆっくりとカップを置き、力なく笑った。
「……バレちゃったか」
その声は、泣き出しそうなほど震えていたが、色は酷く透明だった。
「感音性難聴。……進行性なんだって」
世界から、音が消えた気がした。
「右耳はもう、ほとんど聞こえない。左耳も、あとどのくらい保つか……」
彼女は、自分の耳を指先で触れる。
「ピアノ、弾けなくなっちゃうのかな」
「……どうして、言わなかった」
「だって! ……レン君、私の音が『綺麗だ』って言ってくれたから」
奏が俯く。
涙が、テーブルに落ちた。
「音が聞こえなくなったら、汚い音になっちゃうでしょ。レン君に見える色が、濁っちゃうのが……怖かった」
馬鹿だ。
本当に、大馬鹿だ。
僕は席を立ち、彼女の隣に座り直すと、震える肩を抱き寄せた。
「関係ない。君の音が何色になろうと、僕は見続ける。……僕が、君の耳になる」
その時、僕に見えた彼女の嗚咽の色は、悲しいほどに美しい紫紺色だった。
第三章 静寂の向こう側
それから数ヶ月。
奏の聴力は、急速に失われていった。
補聴器をつけても、音の判別が難しくなっているようだった。
ピアノの前に座っても、彼女は鍵盤を叩くことを躊躇うようになった。
「自分がどんな音を出しているのか、分からないの。暗闇に向かって叫んでるみたいで、怖い」
彼女はそう言って、膝を抱えた。
僕に何ができる?
音を色として見るだけの、この役立たずの眼で。
僕は、キャンバスと絵具を買ってきた。
「レン君、これ……?」
「君が弾く。僕が描く。リアルタイムで」
僕は絵筆を握りしめた。
「君は自分の音が聞こえなくても、僕が描く『色』を見れば、自分がどんな音を出しているか分かるはずだ」
「……そんなこと」
「できる。僕たちなら」
僕たちは、二人だけの練習を始めた。
彼女が「ド」を弾く。僕が赤を塗る。
彼女が「ミ」を弾く。僕が黄色を重ねる。
最初は上手くいかなかった。
タイムラグがあるし、僕の描写が追いつかない。
けれど、奏は天才的な勘で、僕の筆の動きと色の濃淡から、音の強弱やニュアンスを読み取るようになっていった。
「レン君、もっと強く! 青をもっと深く!」
「注文が多いな!」
汗だくになってキャンバスに向かう。
音のない世界で、僕たちは「色」という共通言語で会話をしていた。
そして、コンクールの日がやってきた。
これが、彼女にとって最後のステージになるかもしれない。
会場の照明が落ちる。
静まり返ったホール。
奏がピアノの前に座る。
その横、少し離れた場所に、僕と巨大なキャンバス。
異様な光景に、客席がざわつく。
奏が僕を見る。
不安げに揺れる瞳。
僕は無言で頷き、筆を構えた。
『大丈夫。僕が全部、受け止める』
奏が深く息を吸い、鍵盤に指を落とした。
第四章 色彩のワルツ
最初の一音が響く。
僕の視界が弾ける。
筆を走らせる。
キャンバスに鮮烈な色が飛び散る。
奏は、耳ではなく、僕のキャンバスを見つめていた。
僕が描く色の軌跡を道標にして、彼女は指を走らせる。
(右手が速い、もっとゆっくり!)
僕が筆を緩やかに動かすと、彼女のテンポが落ち着く。
(そこだ、感情を爆発させて!)
僕が激しく赤を叩きつけると、ピアノが轟音のようなフォルテシモを奏でる。
二人の呼吸が完全にシンクロしていた。
会場のざわめきは消え、誰もが息を呑んでこの「共演」を見守っている。
音と色が、螺旋を描いて昇っていく。
彼女の耳には、もうほとんど何も届いていないはずだ。
それでも、彼女の奏でる音は、今までで一番美しく、澄んでいた。
僕の目に映る世界は、もう現実の風景を留めていなかった。
光の洪水。
音の奔流。
(奏、見えるか? これが、君の音だ)
クライマックス。
彼女が全身全霊を込めて、最後の和音を叩きつける。
僕は、持てる全ての絵具をキャンバスにぶちまけた。
全ての音が止む。
静寂。
荒い息遣いだけが響く。
キャンバスには、見たこともないような、輝く「白」が浮かび上がっていた。
全ての色が混ざり合い、光となった白。
奏が、呆然とキャンバスを見つめている。
そして、ゆっくりとこちらを向き、泣き笑いのような表情で口を動かした。
『見えたよ』
声にはなっていなかった。
けれど、その唇の動きは、どんな音よりも鮮明に僕の心に響いた。
割れんばかりの拍手が、ホールを包み込んだ。
僕にはその拍手が、祝福の金色の雨のように見えた。
最終章 永遠のパレット
数年後。
海辺のアトリエ。
波の音は、穏やかな水色を描いている。
「レン、筆取って」
背後から声がかかる。
完全に聴力を失った奏は、今は補聴器もつけていない。
けれど、彼女の発話は明瞭だ。僕の喉の振動や、唇の動きを読み取る術を完璧にマスターしている。
「はいよ」
彼女に筆を渡す。
奏はもうピアノを弾かない。
その代わり、彼女は絵を描き始めた。
僕が見た「音の色」を、彼女は自分の記憶の中にある音と重ね合わせ、キャンバスに表現する。
「ねえ、波の音って、こんな色だったっけ?」
彼女が塗った色は、かつて僕が彼女に教えた通りの、優しい水色だった。
「ああ、そのままだよ」
僕は彼女の背後から手を回し、その手ごと筆を握る。
音のない世界。
けれど、僕たちの間には、言葉よりも確かな「色」がある。
「愛してるよ、奏」
僕が彼女の肩に口づけながら呟く。
彼女には聞こえない。
けれど、彼女はキャンバスに、暖かく、柔らかいピンク色をひと塗り足した。
そして、振り返って微笑む。
「私も」
彼女には、僕の心の「色」が見えているのだと思う。
世界は相変わらずうるさい。
けれど、このアトリエの中だけは、世界で一番美しい静寂と、愛しい色彩に満ちていた。
(了)