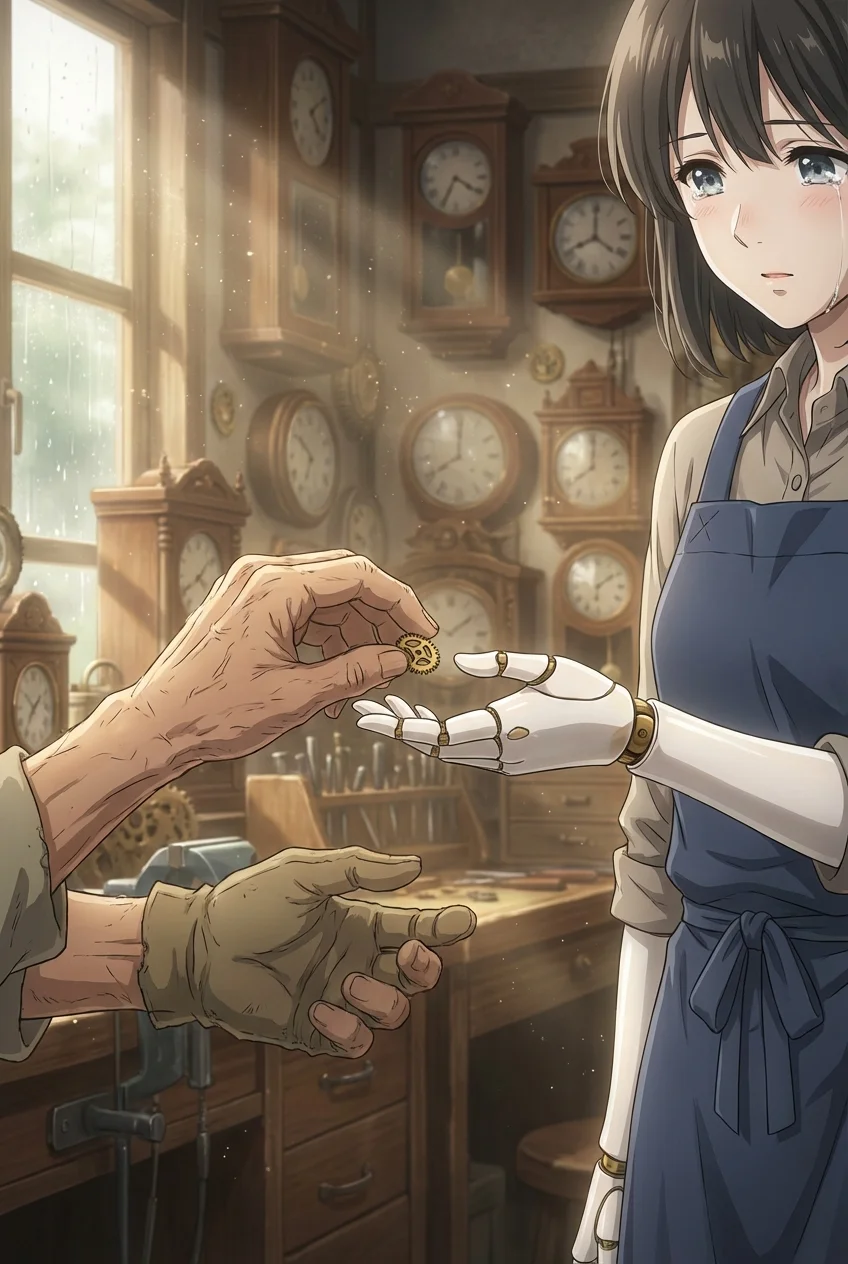第一章 空白の座標
「そこには、何もないわよ」
エレナが吐き捨てるように言った。
湿気を含んだ熱風が、テントのフラップを激しく揺らしている。彼女のシャツは汗で肌に張り付き、苛立ちを露わにしていた。
僕は、手元のタブレット端末を指で弾いた。
画面上には、無数の緑色の点が三次元の地図を描いている。上空六百キロメートルの衛星から照射されたレーザー光、LiDAR(ライダー)が捉えた地表のデータだ。
「いいや、ある。ここを見てくれ」
僕は指先で画像を拡大した。
アマゾンの奥地、ペルー国境付近の『セクター404』。
地図上ではただの密林だ。誰も足を踏み入れたことのない、緑の空白地帯。
しかし、最新のノイズ除去アルゴリズムを通したその画像には、奇妙な『直線』が浮かび上がっていた。
「自然界に完全な直線は存在しない。君の口癖だろう、エレナ」
「……エラーよ。雲の反射か、あるいは機材の不調」
「四回だ」
僕は顔を上げた。
「四回のパスすべてで、同じ座標に同じ構造物が映っている。地下五メートルから十五メートル。樹冠の下に隠された、巨大な回廊だ。規模は、テオティワカン遺跡の三倍はある」
エレナが息を呑むのがわかった。
考古学者としての本能が、否定したい理性と戦っている音だ。
「三倍……? そんな馬鹿な。そんな巨大都市が、今の今まで見つからないはずがない」
「見えなかったんだよ。この森が、あまりにも深く『何か』を隠そうとしていたから」
僕は眼鏡の位置を直した。
極度の広場恐怖症である僕にとって、このテントの外に出ることは死に等しい。
だが、このデータは僕の脳髄を痺れさせた。
「僕はここへ行く。君のガイドが必要だ」
「ケン、あなたはコンビニに行くのですら迷うじゃない」
「空間認識能力には自信がある。それに、現地のガイドは信用できない。君だけが頼りだ」
エレナは呆れたように笑い、腰のナタを叩いた。
「言っておくけど、クーラーの効いた研究室とは違うわよ。死んでも文句を言わないでね」
第二章 緑の地獄
「ハァ、ハァ……ッ」
自分の荒い呼吸音が、耳障りだった。
腐葉土の甘ったるい腐敗臭と、名も知らぬ花の強烈な香りが混ざり合い、吐き気を催させる。
「足元、気をつけて。サシハリアリがいるわ」
前を行くエレナが、太い蔓(つる)をナタで薙ぎ払った。
切断面から白い樹液が滴り落ちる。
GPSの座標は、目的地まであと三百メートルを示していた。
だが、視界は悪い。鬱蒼と茂る樹冠が日光を遮り、昼間だというのに薄暗い。
「ねえ、ケン。本当にここなの?」
「間違いない。僕の頭の中には、完璧な3Dマップがある」
僕はタブレットを胸に抱きしめながら答えた。
LiDARの点群データが、現実の風景と重なる。
ここには、本来『坂』があるはずがない。
データ上では平坦な広場のはずだ。
しかし、僕たちの目の前には、不自然な隆起が続いていた。
「……おかしい」
「何が?」
「植生だ。ここから急に変わっている」
エレナが立ち止まり、一本の巨木に触れた。
「この木、樹皮が……硬すぎる。それに、温度が高い」
確かに、周囲の気温が目に見えて上昇していた。
熱帯雨林特有の蒸し暑さではない。
まるで、巨大なPCサーバーの排熱口の前に立ったような、乾燥した熱波だ。
「着いたわよ、ケン」
エレナの声が震えていた。
藪を抜けた先。
そこには、緑の苔に覆われた『壁』が聳え立っていた。
高さは二十メートル以上あるだろうか。
だが、石積みではない。
エレナがナイフで苔を削ぎ落とすと、その下から現れたのは、濡れたような光沢を放つ『黒い物質』だった。
「黒曜石……? いいえ、もっと滑らかだわ」
「継ぎ目がない」
僕は震える手でタブレットのセンサーを向けた。
反射率、異常。
硬度、測定不能。
「これは都市の城壁じゃない」
僕は呟いた。
「これは、筐体(ケース)だ」
第三章 眠れる機能美
壁に沿って歩くこと三十分。
僕たちは、内部への侵入口を見つけた。
崩落したのではなく、そこだけ最初から開いていたかのような、正方形の開口部。
中は完全な闇だった。
懐中電灯の光が、無限に続くかのような回廊を照らし出す。
「信じられない……」
エレナが反響する足音に怯えながら言った。
「装飾が一切ない。壁画も、文字も、宗教的なシンボルも。古代文明の遺跡なら、王の権威を示す何かが必ずあるはずなのに」
「機能美だ」
僕は恍惚としていた。
無駄を極限まで削ぎ落とした、幾何学的な美しさ。
通路は一定の間隔で枝分かれし、その全てが黄金比に基づいている。
「見てくれ、エレナ。この通路の配置」
僕はタブレットに、現在地とスキャンデータを重ね合わせた。
「基板だ」
「え?」
「この遺跡全体が、巨大な集積回路のパターンを描いているんだよ」
僕の言葉を裏付けるように、足元で低い唸り音が響き始めた。
ズズズ、と微かな振動が伝わってくる。
「何? 地震?」
「違う。起動したんだ」
僕は壁に手を当てた。
冷たかった黒い物質が、急速に熱を帯び始めている。
その時、僕の持っていたタブレットが、勝手に明滅を始めた。
画面に流れる、見たこともない文字列。
いや、それは文字ではない。膨大なバイナリデータだ。
『接続確立。冷却システム、出力低下。メンテナンスモードへ移行』
僕の脳内に、直接『意味』が流れ込んできた。
「ケン、逃げるわよ! 崩れる!」
「待ってくれ! これは崩壊じゃない!」
エレナが僕の腕を掴んで引っ張る。
だが、僕は動けなかった。
目の前の光景に、魂を奪われていたからだ。
壁の表面に、青白い光のラインが走り始めた。
血管のように、あるいは神経網のように。
それが天井へ、そして床へと広がり、広大な空間全体が脈動し始める。
ここは死んだ都市などではなかった。
第四章 排熱の森
「どういうことなの、ケン!」
エレナの叫び声が、轟音にかき消されそうになる。
「古代人は、都市を作ったんじゃない!」
僕は叫び返した。
理解してしまったからだ。
なぜ、この遺跡が熱帯雨林の奥深くに隠されていたのかを。
「彼らは、自分たちの文明そのものを『アップロード』したんだ!」
壁が透明度を増し、その奥に眠る無数のカプセルが透けて見えた。
そこには、人の形をした光の塊が浮いている。
肉体を捨て、意識だけの存在となった古代の人々。
「一万年前、何らかの理由で地上に住めなくなった彼らは、地下にこの巨大なサーバーを建造し、精神を移住させた」
僕はタブレットを見せた。
そこには、地上の森林データが表示されている。
「このジャングルは、自然にできたものじゃない。この巨大な演算装置を冷やすために、彼らが遺伝子操作で作った『冷却装置(ヒートシンク)』だったんだ!」
異常な成長速度。
硬すぎる樹皮。
高い温度。
すべては、地下からの膨大な排熱を効率よく大気中に放出するための機能。
「そんな……じゃあ、私たちは今まで、彼らのエアコンの上を歩いていたってこと?」
エレナが絶句したその時、部屋の中央にあった黒い柱が、静かに開いた。
中には、椅子のような窪みがある。
僕のタブレットが、激しく振動した。
『管理者権限、承認。物理インターフェース、接続待機中』
呼ばれている。
僕の特異な空間認識能力。
LiDARの点群データを脳内で完全に再現できるこの才能は、彼らのインターフェースと適合するためにあったのか。
「ケン、行っちゃだめ!」
エレナが僕の手を掴む。
しかし、僕はその手を優しく解いた。
「外の世界は、僕にとって息苦しすぎるんだ、エレナ」
「何を言って……」
「ここなら、すべてがデータだ。曖昧な感情も、予測不能な天候もない。純粋な論理と座標だけの世界」
僕は柱へと歩み寄った。
恐怖はなかった。
むしろ、ようやく家に帰れるという安堵感があった。
最終章 永遠のログイン
座った瞬間、背骨に何かが接続される感覚があった。
痛みはない。
ただ、視界が弾けた。
肉体という重い檻から解放され、意識が光の速度で拡散していく。
ジャングルの隅々まで、木の葉の一枚一枚までが、僕の知覚の一部となった。
LiDARの点群データなんて目じゃない。
原子レベルの解像度で、世界が見える。
『ようこそ』
数億の意識が、一斉に僕に語りかけてきた。
ふと、眼下を見る。
そこには、小さな人間が一人、涙を流しながら走り去っていくのが見えた。
エレナだ。
彼女の体温、心拍数、汗の成分までが手に取るようにわかる。
彼女は『安全』だ。
僕が森を制御し、猛獣や毒虫から彼女を守るルートを作ったから。
「さようなら、エレナ」
僕の声は、森のざわめきとなって彼女の背中を押した。
僕は目を閉じる――いや、物理的な目はもう必要ない。
僕は都市になった。
僕は森になった。
永遠に続く演算の海の中で、僕は初めて、広場恐怖症の震えから解放され、満ち足りた眠りについた。
ジャングルの緑は、今日も鮮やかに輝いている。
その地下で唸りを上げる、神々のマザーボードの熱を吸い上げて。