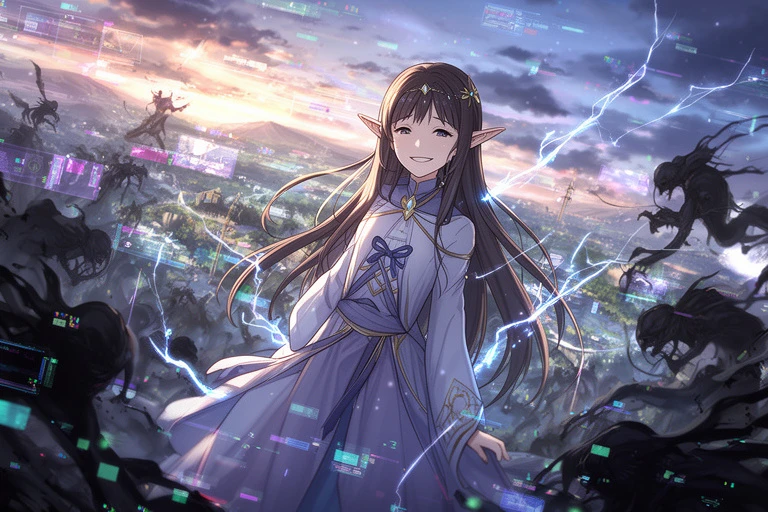氷が、悲鳴を上げた。
物理的な破壊音ではない。
鼓膜ではなく、頭蓋骨の裏側を直接爪で引っ掻かれるような、高い、高い周波数の絶叫。
「……聞こえたか?」
私はヘッドホンをもぎ取り、制御卓の計器に目を走らせる。
「また幻聴ですか、有坂博士。数値は正常です」
助手のエレナは、タブレットから顔も上げずに答えた。
吐く息が白い。
シベリア永久凍土の地下三百メートル。
研究施設『ディープ・ゼロ』の空調は、常に氷点下ギリギリを維持している。
だが、今、私の背筋を駆け上がったのは寒気ではない。
「違う、エレナ。マイクじゃない。氷そのものが共鳴しているんだ。ドリルを止めろ」
「あと五メートルで『ポケット』に到達します。今止めたら、予算が溶けますよ」
「予算どころか、世界が終わるかもしれないと言っているんだ!」
私が叫んだ瞬間、足元のグレーチング床が微かに震えた。
重低音。
先ほどの高周波とは真逆の、地底の底から湧き上がるような唸り声。
モニターに映るドリルの先端カメラ。
万年氷の蒼白い闇の中に、不自然な「赤」が混じり始めた。
「博士、これ……」
エレナの声が上擦る。
「泥炭層? いいえ、色が鮮やかすぎます」
「血液だ」
私は呟く。
直感だが、確信があった。
太古の昔、この氷に閉じ込められたのは、ただの水ではない。
パキンッ。
乾いた音が響き、強化ガラス越しに見えるパイプラインから、蒸気が噴き出した。
いや、蒸気ではない。
甘い、腐った果実のような芳香。
「警告。気密低下。バイオハザード・レベル4」
無機質なアナウンスと共に、赤色灯が回転を始める。
「エレナ、マスクを!」
振り返った私の目に映ったのは、すでにマスクを装着しようとして、手を止めたエレナの姿だった。
彼女は笑っていた。
恍惚とした表情で、充満していく赤い霧を肺一杯に吸い込んでいる。
「……聞こえますか、博士」
彼女の声は、どこか艶めかしく、濡れていた。
「彼らが、歌っています」
第一章 深紅の覚醒
警報音が鳴り響く中、私は気密隔壁のレバーを引いた。
重厚な金属音が響き、エレナのいる第一ラボと、ここ司令室が分断される。
ガラスの向こう。
エレナは苦しむ様子もなく、ただ踊るように、漏れ出した赤い液体――おそらくは未知の古代ウイルスを含んだ融解水――に触れていた。
彼女の皮膚の下で、何かが蠢いている。
血管が黒く浮き上がり、幾何学模様を描きながら脈打つ。
「クソッ、通信回線はどうなってる!」
私はコンソールを叩く。
衛星回線は不通。
いや、遮断されている。
『……カイト……』
スピーカーからノイズ交じりの声。
エレナの声ではない。
もっと低く、何重にも重なったような、合成音声じみた響き。
『開ケテ……一绪ニ、ウタオウ……』
「お断りだ。俺は音痴でね」
震える指で、私は施設の自爆シークエンスを呼び出す。
だが、画面に表示されたのは『アクセス拒否』の文字。
「管理権限が奪われているだと?」
モニターを見る。
施設のあちこちにある監視カメラの映像。
食堂、居住区、動力炉。
そこに映る研究員たちは、誰一人として逃げ惑っていなかった。
ある者は床に伏して祈り、ある者は互いの体を貪るように抱き合い、またある者は自分の眼球をスプーンで抉り出していた。
全員が、笑っている。
「集団幻覚……いや、神経系の掌握か」
私の専門は古音響学だ。
氷の中に閉じ込められた気泡の音から、過去の環境を復元する。
だからこそ、わかる。
このウイルスは、音を媒介にしている。
空気の振動、骨伝導、あるいはもっと直接的な脳への干渉。
ズズズズズ……。
再び、地響き。
今度は施設全体が傾くほどの衝撃。
窓の外、永久凍土の壁。
そこに見えたのは、氷漬けのマンモスではない。
巨大な「眼」だった。
直径十メートルはあろうかという、黄金色の複眼。
氷の壁の向こう側から、じっとこちらを見つめている。
「バカな……生物反応はなかったはずだ」
レーダーを確認する。
反応はない。
いや、違う。
反応が「大きすぎる」のだ。
このエリア一帯、地下数百キロに及ぶ氷そのものが、一つの巨大な有機体として活動を開始している。
温暖化による融解は、ただのきっかけに過ぎない。
これは、孵化(ふか)だ。
『ディープ・ゼロ』は、神の卵の殻の上に建てられた、ちっぽけな寄生虫だったのだ。
第二章 肉の聖堂
私は消火斧を手に、通気ダクトを這っていた。
司令室はもう安全ではない。
あの黄金の眼に見つめられた瞬間、モニターというモニターが破裂し、機材が溶解し始めたからだ。
狭いダクトの中にも、あの甘ったるい腐臭が充満している。
「ハァ、ハァ……」
息をするたびに、喉の奥が熱い。
肺の中で、何かが芽吹こうとしている感覚。
視界の端に、チラチラと光の粒子が見える。
『コッチダヨ……カイト……』
声がする。
ダクトの前方から。
ライトを向ける。
そこにいたのは、整備主任のボリスだった。
ただし、首から下が変質していた。
彼の肉体はダクトの金属壁と融合し、ピンク色の肉塊となってパイプを覆い尽くしている。
顔だけが、以前の面影を残して私を見ていた。
「ボリス……」
「痛クナイヨ、カイト。寒クモナイ」
ボリスの顔が、慈愛に満ちた笑みを浮かべる。
「コノ星ハ、冷タスギル。ダカラ、僕ラガ温メルンダ」
「温める? 何を言っている」
「見テ」
ボリスの肉塊から、触手のようなものが伸び、ダクトの隙間を指し示す。
そこから見下ろした動力炉エリア。
私は息を呑んだ。
核融合炉が、脈打っていた。
金属の外壁は剥がれ落ち、代わりに赤黒い筋肉の膜が炉心を覆っている。
研究員たちが、自らその肉の膜に取り込まれに行っていた。
彼らの体は溶け、炉の燃料となり、莫大な熱エネルギーを生み出している。
「熱暴走させる気か……!」
「イイエ。目覚マシ時計ヲ、鳴ラスダケ」
永久凍土を内側から溶かし、古代の生態系を解き放つ。
この施設そのものが、巨大なヒーターへと作り変えられようとしている。
もし、ここの氷が全て溶ければ。
封印されていた未知の病原体と、それを統べる巨大生物(ハイヴ・マインド)が、大気に拡散される。
風に乗れば、三日で北半球は全滅だ。
「させない」
私は斧を振り上げた。
「ごめんな、ボリス」
「アァ……可哀想ナ、カイト……」
ドチャッ。
生々しい音と共に、ボリスの顔面を叩き潰す。
悲鳴はなかった。
ただ、飛び散った体液が、私の防護服を焦がす音がしただけだ。
私は走った。
目指すは最下層。
この悪夢の心臓部。
第三章 静寂の歌
最下層、サンプル保管庫。
そこは既に、異界だった。
床も壁も天井も、すべてが半透明の粘膜に覆われている。
その奥で、太古の氷が青く光っている。
そして、部屋の中央。
そこに「彼女」がいた。
エレナ。
だが、もう人の形をしていない。
彼女の下半身は、床を突き破って現れた巨大な氷の柱と融合していた。
氷の中には、無数の古代生物――三葉虫のような、あるいは胎児のような奇妙な影――が封じ込められており、それらがエレナの背骨を通して、情報の奔流を送り込んでいる。
彼女は、端末(インターフェース)になっていた。
「遅かったですね、博士」
エレナが目を開く。
その瞳は、あの氷壁の向こうにあった「巨大な眼」と同じ、黄金色に輝いていた。
「これを止める方法は一つしかありません」
彼女は歌うように言った。
「あなたが、新しい『声』になることです」
「どういう意味だ」
「この子たち……古代の集合知性体は、寂しがり屋なんです。彼らはネットワーク。個体という概念がない。だから、孤独な『個』である私たち人間を理解できない。理解できないから、一つに混ぜようとする」
エレナの背後で、氷の柱が蠢く。
「でも、もし強力な『個』が、彼らのネットワークをハッキングして、別の指令(歌)を歌えば……」
「活動を停止させられる、ということか?」
「あるいは、共存の形を模索できるかもしれません。でも、そのためには……」
エレナの体が、ピキピキと音を立てて結晶化していく。
彼女の自我が、集合意識に飲み込まれようとしているのだ。
「誰かが、人柱にならなければならない」
私は、懐から小さなICレコーダーを取り出した。
そこには、私が長年かけて集めた、世界中の「静寂」が録音されている。
雪原の静けさ、深海の沈黙、誰もいない早朝の街。
「俺の才能は、音を聞くことだけじゃない。音を『止める』波形を作ることもできる」
私はレコーダーを、エレナと融合した氷柱の、露出した神経節のような部分に押し当てた。
「博士、それをしたら、あなたの意識は……永遠の静寂の中に……」
「願ったりかなったりだ。人間嫌いの俺には、お似合いの席だよ」
私は笑った。
震える指で、再生ボタンを押す。
瞬間。
世界から、音が消えた。
唸り声も、警報音も、肉が蠢く音も。
絶対零度の静寂が、赤い粘膜を白く、青く染め上げていく。
エレナの黄金の瞳から、色が抜けていく。
彼女は最後に、口の形だけで「ありがとう」と言ったように見えた。
私の視界もまた、白く塗りつぶされていく。
寒くはない。
ただ、懐かしい静けさがあるだけだ。
意識が氷に溶け、広大なネットワークへと拡散していく。
私は理解した。
これが死ではないことを。
私は今、地球そのものになろうとしている。
(……あぁ、うるさいな)
氷の向こうから、微かに聞こえる地上の喧騒。
私が眠りにつくその時まで、この星の熱を、少しだけ冷ましてやろう。
永遠の氷河の中で、私はゆっくりと、その重いまぶたを閉じた。