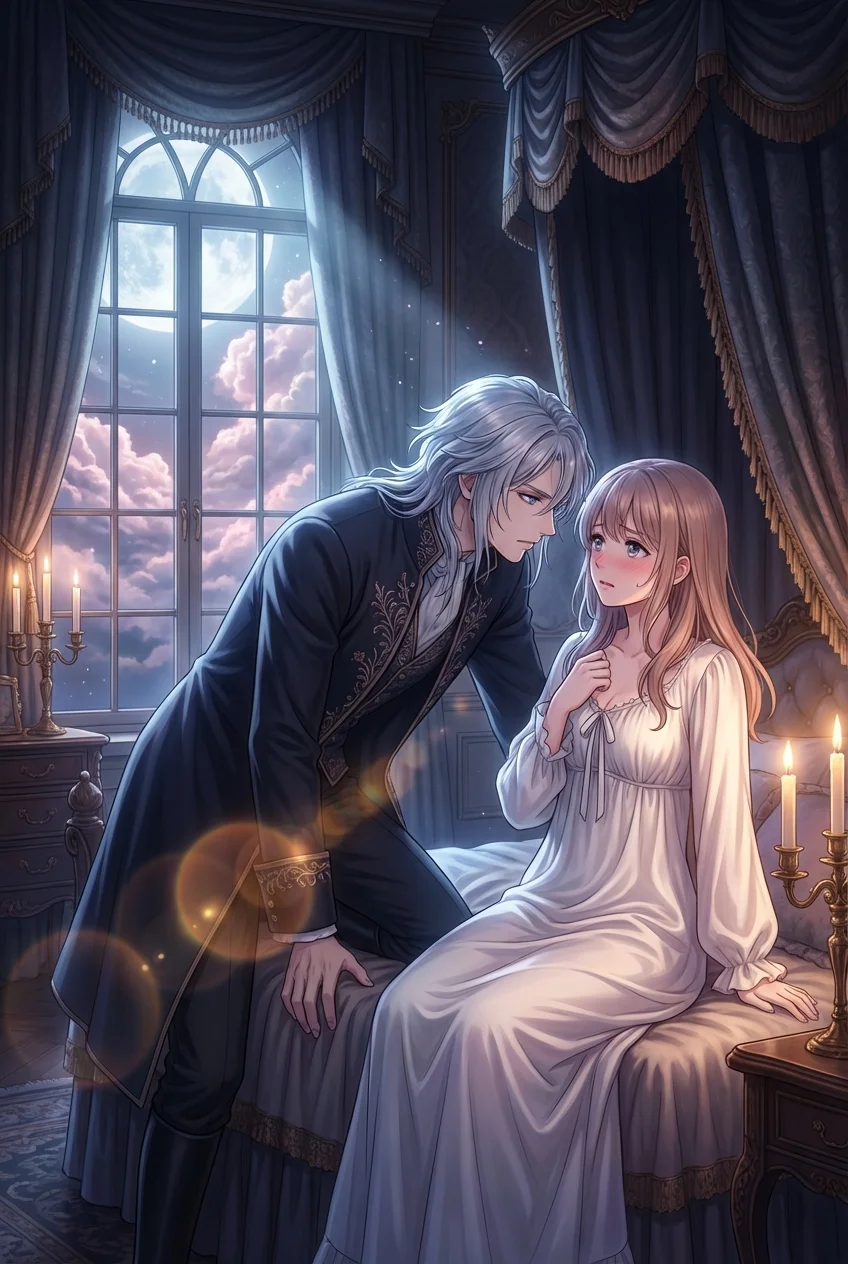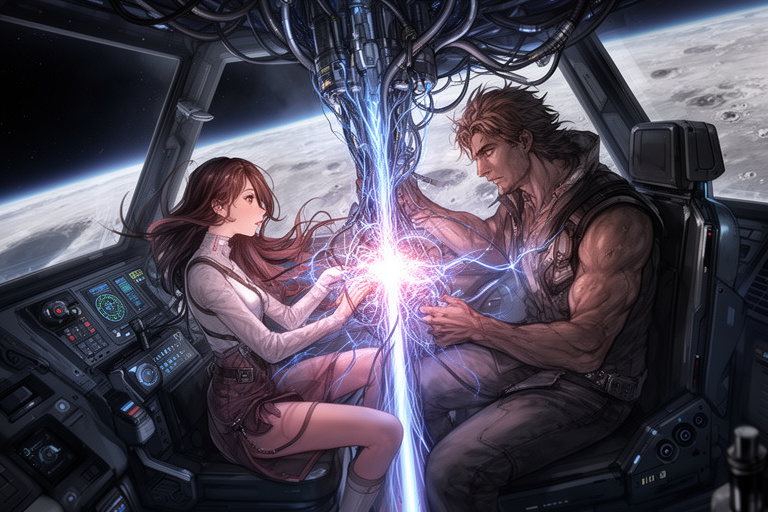氷が割れる音は、絹が引き裂かれる悲鳴に似ていた。
足元の永久凍土が呻き声を上げ、数万年の眠りから覚める。
それと同時に立ち込めたのは、腐臭ではない。
脳髄を直接撫で回されるような、甘く、重く、暴力的な芳香だった。
その瞬間、隣にいた彼の瞳孔が開き、理性という名の光が消え失せるのを見た。
私は悟る。
人類の歴史はここで終わり、私と彼の『繁殖』だけが世界の全てになるのだと。
第一章 感染する執着
北緯七十度、シベリア・ヤマル半島。
世界最北のウイルス研究施設『アーク』は、白い地獄の中に孤立していた。
温暖化の影響で崩落した永久凍土のクレバス。そこから露出したのは、マンモスの死骸などという生易しいものではなかった。
それは、地下深くで鼓動を続ける、巨大な『肉塊』のような植物——あるいは生物。
「エレナ博士、下がれ。計測値が異常だ」
警備主任のアレクセイが、私の腕を乱暴に掴んで引き戻す。
防寒着越しでも伝わる彼の体温は、異常なほど高かった。
普段は彫像のように無表情なロシアの軍人が、今は荒い息を吐き、喉元を汗で濡らしている。
「アレクセイ、離して。サンプルを……」
「駄目だ。見ただろう。あれは……俺たちを『呼んで』いる」
クレバスの底で蠢く真紅の蔦。そこから噴き出す不可視の胞子。
私たちはガスマスクをつけていたはずだった。
だが、その『匂い』はフィルターを透過し、皮膚から、粘膜から、血流へと侵入していた。
施設に戻り、重厚なエアロックが閉ざされた瞬間。
アレクセイが膝をついた。
「ぐ、あ……ッ」
彼が喉を掻きむしる。
私もまた、視界が揺らぐほどの目眩に襲われていた。
熱い。
外気はマイナス三十度だというのに、体の芯に火種を埋め込まれたように熱い。
「バイタルチェックを……隔離室へ……」
私の指示は、震える声にかき消された。
アレクセイが顔を上げる。
その瞳は、さっきまでの冷静な同僚のものではない。
飢えた獣。
いや、もっと始原的な、渇望そのものだった。
「エレナ」
彼が私の名を呼ぶ。
ただそれだけで、背筋に電流のような痺れが走り、膝から力が抜けた。
ウイルスではない。
これは、古代の生物が宿主に課した、絶対的な『命令』だ。
——混ざり合え。
——個を捨てろ。
理性が警鐘を鳴らす一方で、私の本能は、目の前の屈強な捕食者に食い尽くされることを、歓喜と共に待ち望んでいた。
第二章 融解する境界線
隔離室の閉鎖空間は、湿度を帯びた熱気で満たされていた。
空調は稼働しているはずなのに、部屋中が甘ったるい麝香(じゃこう)のような匂いで飽和している。
「こっちへ来い」
アレクセイの声は、命令でありながら、哀願の響きを含んでいた。
彼は部屋の隅で自身の体を抱きしめ、震えている。
狂いそうなほどの衝動を、鋼の精神力で辛うじて抑え込んでいるのだ。
だが、私は知っている。
このウイルス——『パレオ・フィーバー』と仮称した太古の因子は、宿主同士の接触なしには生存を許さない。
離れているだけで、骨が軋むような激痛と、孤独による精神崩壊をもたらす。
「アレクセイ……痛いの?」
私が一歩近づくと、彼がビクリと反応する。
鎖に繋がれた猛獣のように、彼は血走った目で私を睨み、そして苦痛に顔を歪めた。
「来るな。俺は今、あんたを……研究対象として見ていない」
「……どう見えているの?」
「雌(メス)だ。俺の全てを注ぎ込み、俺の一部にするための器にしか見えない」
あまりに直截的な言葉。
普段の彼なら口が裂けても言わないような暴言。
けれど、その言葉は私の理性を焼き切るための着火剤にしかならなかった。
私の体もまた、限界を迎えていた。
乾ききった喉が水を求めるように、私の細胞の一つ一つが、彼という他者を求めて悲鳴を上げている。
高潔な科学者としての誇りも、倫理観も、高熱の中で飴細工のように溶けていく。
私は震える手で、白衣のボタンに触れた。
一歩、また一歩。
彼との距離が縮まるたび、頭の中の雑音が消え、甘美な痺れが増幅していく。
「止めてくれ、エレナ。このままじゃ、俺はあんたを壊す」
「壊してもいいわ」
私の唇から零れたのは、本心だった。
「この痛みから救ってくれるなら……理性のタガなんて、外してしまって」
その言葉が、最後の引き金だった。
アレクセイの喉から、人間のものではない低い唸り声が響く。
次の瞬間、世界が反転した。
私が床に押し倒されるのと、彼が覆いかぶさってきたのは同時だった。
硬い床の冷たさと、彼が纏う焼けるような高熱。
その温度差が、私の感覚を狂わせる。
「……もう、逃がさない」
耳元で囁かれた掠れ声は、愛の告白というよりは、呪いの宣言に近かった。
第三章 永久の捕食
肌と肌が触れ合った瞬間、爆発的なフラッシュバックが脳内を駆け巡った。
視覚情報ではない。
数万年前、この氷の大地を支配していた『巨大生物』の記憶。
絡まり合い、溶け合い、一つの巨大な生命体として脈動していた太古の記憶が、私たちを通して再現される。
「あ、ぁ……ッ! アレクセイ、熱い、熱いッ!」
彼の唇が首筋に吸い付く。
単なるキスマークではない。所有の焼き印を押すかのように、強く、深く、執拗に。
痛みと快楽の境界線が消失する。
彼の存在が私の中に侵食してくる感覚。
「エレナ、息をして……吸って……」
彼もまた、余裕などなかった。
私の反応一つ一つに、彼の理性が削り取られていくのがわかる。
余裕のある愛撫などない。
溺れた者が酸素を求めるように、彼は私を貪り、私もまた彼にしがみつく。
視界の端で、隔離室の壁が歪んで見えた。
地下の『巨大生物』が共鳴しているのだ。
私たちの高まる鼓動に合わせて、施設の壁を突き破り、無数の植物のような触手が部屋を包み込もうとしている。
けれど、恐怖はなかった。
あるのは、彼と一つになれるという圧倒的な幸福感と、底なしの飢餓感だけ。
「もっと……もっと奥まで、あなたの熱をちょうだい……」
私が懇願すると、アレクセイの動きが一層激しくなる。
避けることのできない楔。
魂の形を変えられてしまうほどの、強烈な一体感。
意識が白く弾ける寸前、私は彼と視線を交わした。
そこにはもう、かつての同僚としての親愛はない。
あるのは、互いなしでは一秒たりとも呼吸すらできない、狂気的な共依存の瞳だけ。
頭の中が痺れ、指先の感覚がなくなり、世界が狭まっていく。
彼の荒い息遣いと、重なり合う心音だけが、世界の全て。
波状攻撃のように押し寄せる感覚の奔流に、私は何度も意識を手放しかけ、そのたびに彼に呼び戻される。
「行くな、ここにいろ。俺の中で果てろ」
その言葉に従順に従うことが、今の私に許された唯一の救済だった。
外の世界では、氷河が崩れ、古代の生態系が蘇りつつあるのかもしれない。
だが、そんなことはどうでもいい。
私は今、この狭い隔離室の中で、彼という名の熱病に永遠に侵されている。
そして彼もまた、私という檻から二度と出ることはできないのだ。
絡め取られた指と指。
汗ばんだ肌の吸着音。
私たちは終わりのない螺旋へと堕ちていく。
理性も、人間としての尊厳も、すべてをこの熱の中に置き去りにして。