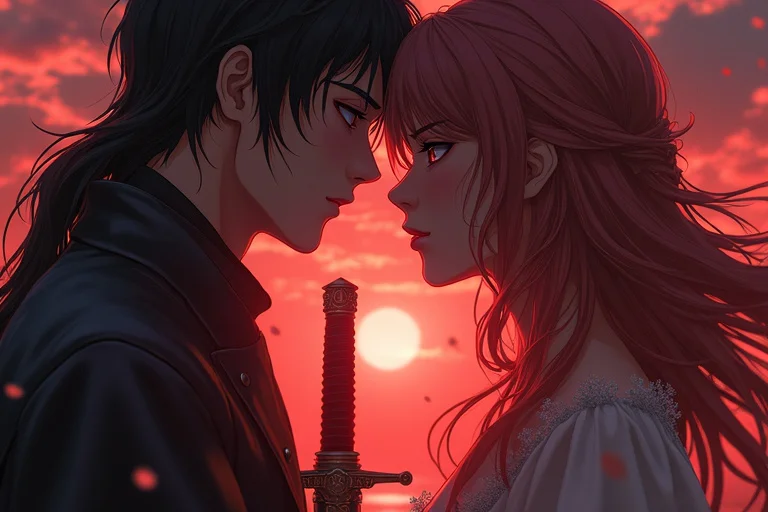第一章 雨の通夜
雨の匂いに、鉄の錆びた臭いが混じっている。
軒先から滴るしずくが、男の頬を伝って顎先で弾けた。
「……来たか」
暗闇の奥、一歩踏み出すたびに泥が撥ねる音がする。
ひとつ、ふたつ。
足音は三つ。
すり減った下駄の歯が、湿った石畳を噛む感触。
男――左近(さこん)は、懐のなかの重みを手で確かめる。
油紙に包まれた、一尺ほどの棒状のなにか。
それを守るように、左近は身を縮めた。
「噂の『鬼哭(きこく)の太刀』……まさか、そのような薄汚れた浪人が持っていようとはな」
闇の中から、編み笠を被った男たちが現れる。
抜き身の刃が、わずかな月明かりを舐めとって白く光った。
左近は無言だった。
ただ、冷え切った指先で、腰に差した鞘の鯉口(こいくち)を撫でる。
柄糸(つかいと)は擦り切れ、鮫肌は黒ずんでいる。
だが、その鞘から放たれる異様な冷気が、雨粒さえも凍らせているように見えた。
「渡せば、命までは取らん」
編み笠の男が切っ先を向ける。
喉元まで、わずか三寸。
左近の目が、前髪の隙間から覗いた。
濁った瞳。
そこには生気も、恐怖も、殺意すらない。
あるのは、底なしの静寂だけだ。
「……抜けば、死ぬぞ」
左近の唇が微かに動く。
声は掠れ、雨音にかき消されそうだ。
「抜かせてもらおうか。その伝説の妖刀を」
刹那。
編み笠の男が踏み込んだ。
水たまりが爆ぜ、泥水が空中に舞う。
左近は動かない。
いや、動けないのか。
切っ先が左近の眉間に迫る。
その瞬間、左近の左手が動いた。
刀を抜くのではない。
鞘ごと、相手の切っ先を叩き落としたのだ。
ガチンッ。
鈍い音が路地に響く。
鋼と、古びた朴の木がぶつかり合う音。
「貴様……抜かんつもりか!」
「俺がこれを抜く時は、この世が終わる時だ」
左近は低く呟き、泥にまみれた背中を向けた。
その背中には、死神がへばりついているような重圧があった。
第二章 錆びついた過去
逃げ込んだのは、朽ちかけた荒寺だった。
雨漏りの音が、不規則なリズムを刻んでいる。
左近は荒い息を吐きながら、本堂の柱に背を預けた。
脇腹が熱い。
先ほどの攻防で、切っ先が衣を掠めたらしい。
滲み出る血を、懐の油紙で押さえる。
「……しつこい連中だ」
『鬼哭の太刀』。
振るえば嵐を呼び、鞘走れば千の生首が飛ぶと言われる魔剣。
大名家も、幕府の密偵も、辻斬りも。
誰もがその力を欲し、左近を追ってくる。
左近は、腰の刀を外した。
ずしりと重い。
もう十年。
十年もの間、この刀は一度も抜かれていない。
「父上……」
脳裏に、炎に包まれた屋敷が蘇る。
血の海の中で、父が最期に託したこの刀。
『よいか左近。何があっても、中を見てはならぬ』
『これは、人を斬るためのものではない。国を……守るためのものだ』
父の遺言は呪いのように、左近の人生を縛り付けた。
中を見れば、封印が解かれる。
解かれれば、世に災いが満ちる。
そう信じて、左近は刀を守り続けてきた。
たとえ、乞食のような生活に落ちぶれようとも。
たとえ、愛した女をその手で守れなかったとしても。
「そこにいるのは分かっている」
左近は虚空に向かって呟いた。
寺の扉が、軋んだ音を立てて開く。
雷光が走り、堂内に長い影を落とした。
立っていたのは、先ほどの編み笠の男たちではない。
一人の、若い剣士だった。
白の着流し。
雨に濡れて透けた肩に、桜の刺青が見える。
「……早かったな」
「匂いがするんですよ。血と、雨と、嘘の匂いが」
若侍は、静かに抜刀した。
その構えに隙はない。
「あんたが『影無しの左近』か」
「……今はただの雨宿りの浪人だ」
「その刀。もらうぞ」
「ならん」
「ならば、斬る」
問答無用。
若侍の剣が、疾風のごとく迫る。
速い。
左近は咄嗟に鞘で受けるが、衝撃で身体が浮いた。
柱に激突し、埃が舞う。
「抜かないのか? 死ぬぞ」
若侍の目は、獲物を狩る獣のそれだった。
左近は苦笑する。
(抜けば死ぬ……か。皮肉なことだ)
追いつめられた。
もう、逃げる場所はない。
「いいだろう」
左近は立ち上がり、右手を柄にかけた。
十年分の錆が、手のひらに食い込む。
「見せてやる。この世の終わりを」
全身の筋肉が、悲鳴を上げるほどに収縮する。
空気が張り詰めた。
若侍が息を呑み、一歩下がった。
左近から放たれる殺気が、物理的な圧となって押し寄せたからだ。
雷鳴。
その轟音と共に、左近は刀を一気に引き抜いた。
第三章 華の散る音
時間が止まった。
若侍は、目をカッと見開いたまま硬直している。
斬られたのではない。
あまりの光景に、言葉を失ったのだ。
左近の手にあるもの。
それは、鋼の刃ではなかった。
鞘から現れたのは、ボロボロに朽ち、土色に変色した――『木』だった。
いや、ただの木ではない。
それは、丁寧に削り出された、子供用の木刀だ。
そして、その先端には。
一輪の、白い花が咲いていた。
鞘の中に溜まった雨水と、わずかな土埃。
そして十年の歳月が、木刀に使われていた梅の木に、奇跡のような命を宿らせていたのだ。
「……な」
若侍の声が震える。
「それが……鬼哭の太刀か……?」
左近自身も、呆然と手元の花を見つめていた。
父が託したのは、魔剣などではなかった。
『国を守るためのもの』
それは武力ではない。
未来を担う子供への、健やかな成長を願う玩具だったのか。
それとも、権力争いから幼い左近を逃がすための、父がついた決死の嘘だったのか。
「……ふ、ふふ」
左近の口から、乾いた笑いが漏れた。
人を斬り、血を浴び、命を懸けて守り抜いたものが。
まさか、こんなに脆く、美しい花だったとは。
「斬れぬ……」
左近は膝から崩れ落ちた。
「これでは、何も斬れぬではないか……」
若侍は刀を下げた。
戦意は、雨と共に洗い流されていた。
「……あんた、ずっとそれを背負ってたのか」
「ああ。重かった。……鉄よりも、ずっと」
左近は、咲いたばかりの梅の花を、愛おしそうに指で触れた。
その指先が触れた瞬間、白い花びらが一枚、はらりと散った。
「勝負あった、でいいな」
若侍が背を向ける。
「待て。これを……持って行け」
左近は木刀を差し出した。
「俺にはもう、守る資格がない。……いや、もう守る必要がない」
若侍は振り返り、散りかけた梅の枝を受け取った。
「……あんたの命は、この花が散るまで預かっておく」
若侍は闇夜へと消えていった。
残された左近は、空っぽになった鞘を握りしめる。
雨が上がっていく。
雲の切れ間から差し込む月光が、荒寺を青白く照らした。
左近は鞘を逆さに振った。
カラン、と乾いた音が一つ。
中から転がり落ちてきたのは、小さく折り畳まれた一枚の紙切れ。
月明かりに透かして見る。
そこには、父の筆跡でただ一文字、こう記されていた。
『生』
左近は空を仰いだ。
長く止まっていた時間が、いま再び、動き出した音がした。