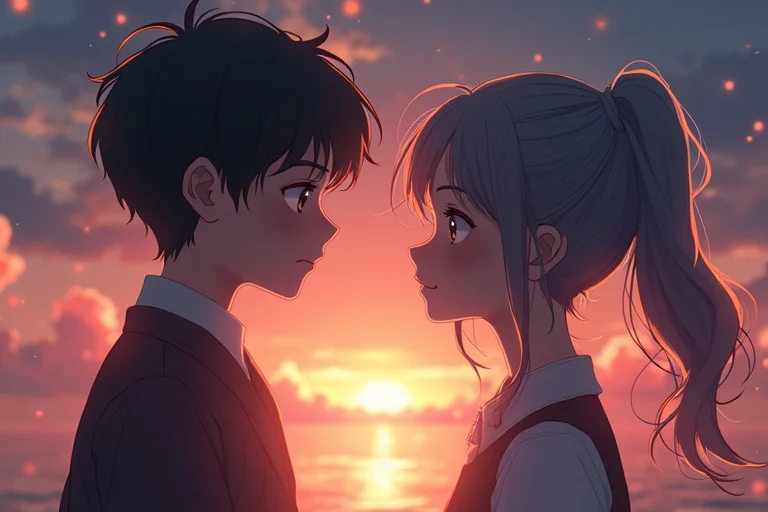嘘の音は、意外と甲高い。
ガラス瓶に閉じ込められた蚊の羽音に似ている。
俺には、それが聞こえるのだ。
放課後の放送室。
埃と古い機材の焼ける匂いが充満する密室で、俺はマイクに向かって息を潜めていた。
手元のレコーダーの赤いランプが点滅している。
「……これで、最後だ」
俺は小さく呟き、スイッチを切った。
窓の外では、グラウンドから野球部の掛け声と、金属バットがボールを弾く乾いた音が響いている。
だが、俺が録音したのはそんな青春の喧騒じゃない。
もっと静かで、残酷な嘘だ。
第一章 透明なリクエスト
「ねえカイト、『星が死ぬ音』って録れる?」
三ヶ月前の屋上。
フェンス越しに街を見下ろしながら、舞(まい)はそう言った。
風が彼女の短い髪を揺らし、洗剤と陽だまりの混ざった匂いが俺の鼻をくすぐる。
「無理に決まってんだろ」
「えー、カイトならできるよ。絶対音感あるし、機械オタクだし」
舞は悪戯っぽく笑い、耳元の補聴器に触れた。
進行性の難聴。
彼女の世界からは、少しずつ、確実に音が消えている。
「私の耳が完全にダメになる前にさ、この世の素敵な音、全部集めておきたいんだよね」
彼女の願いは切実さを隠した、軽いジョークのようだった。
深海魚のあくび。
虹が出る瞬間の音。
そして、星が死ぬ音。
俺は「善処する」とだけ答えた。
本当は「全部お前のために録ってやる」と言いたかった。
だが、俺の喉からはいつものように、素っ気ない言葉しか出てこない。
それが俺の欠陥だ。
大事なことほど、言葉にできない。
だから俺は、音を捏造する。
第二章 偽りのコンポーザー
俺の特技は、あらゆる音をサンプリングして、別の音を作り出すことだ。
パソコンの波形編集ソフトを開く。
『深海魚のあくび』は、理科室の水槽のポンプ音のピッチを極限まで下げ、俺が布団の中で漏らした溜息をミックスして作った。
『虹が出る音』は、炭酸水が弾ける音と、風鈴の余韻を重ねた。
舞はそれを聴くたびに、目を輝かせた。
「すごい! 本当にこんな音がするんだ!」
彼女はヘッドホンを強く押し当て、消えゆく聴覚のすべてを使って、俺の嘘を聴いた。
「カイトは魔法使いだね」
違う。
俺はただの詐欺師だ。
お前が聴いているのは、世界の神秘なんかじゃない。
俺の部屋の生活音と、深夜の孤独な作業音だけだ。
罪悪感が胸の奥で重低音のように響く。
だが、彼女の笑顔を見ると、どうしても真実が言えなかった。
そして今日。
最後のリクエスト、『星が死ぬ音』。
俺は放送室の古いピアノの、一番低い『ラ』の弦を指で弾いた。
ボーン、と鈍い音が響く。
そこに、黒板消しを叩いた時の『パン』という破裂音を逆再生して重ねる。
さらに、俺自身の心臓の鼓動を、微かに混ぜた。
完成した音は、どこか寂しく、けれど温かい。
まるで、胎内にいるような響きだった。
第三章 沈黙の講評会
病院のベッドの上で、舞は痩せ細った腕を伸ばし、レコーダーを受け取った。
窓からは夕焼けが差し込み、白いシーツをオレンジ色に染めている。
消毒液の鋭い匂いが、鼻の奥をツンと刺した。
もう、彼女の耳はほとんど聞こえていないはずだ。
それでも彼女は、儀式のようにヘッドホンを装着する。
「聴くね」
彼女の唇が動く。
俺は膝の上で拳を握りしめた。
再生ボタンが押される。
数十秒の静寂。
いや、彼女の中では、俺が作った『星が死ぬ音』が流れているはずだ。
どんな顔をするだろう。
また「すごい」と笑うだろうか。
それとも、もう音が聞こえなくて、泣き出すだろうか。
不意に、舞がヘッドホンを外し、俺の方を見た。
その瞳は、驚くほど澄んでいた。
「……カイト」
「なんだよ」
「これ、嘘だよね」
心臓が止まるかと思った。
バレていた。
最初から?
俺は口を開こうとしたが、声が出ない。
言い訳も、謝罪も、喉で詰まって塊になる。
舞は静かに微笑んだ。
「だって、聞こえたもん」
彼女はレコーダーを胸に抱きしめた。
「カイトの匂いがした。……夜中に起きて、キーボード叩いて、コーヒー飲んで。私のために悩んでくれてる、カイトの生活の音がしたよ」
俺は呆然とした。
彼女が聴いていたのは、俺が作った『魔法の音』じゃなかった。
その背景にある、ノイズ。
俺の息遣い。
指がキーを叩く摩擦音。
「星が死ぬ音なんて、誰も知らないもんね」
舞は悪戯っぽく笑うと、涙を一筋だけ流した。
「でも、これが一番、私の好きな音だった」
最終章 嘘つきたちの周波数
「……バーカ」
ようやく出た俺の声は、震えていた。
舞にはもう、その言葉の音自体は届いていないかもしれない。
でも、彼女は俺の口の動きを見て、満足そうに頷いた。
「私もね、嘘ついてたの」
彼女は枕の下から、古ぼけたカセットテープを取り出した。
「これ、あげる」
タイトルには『私の心臓の音』と書かれている。
舞が眠りについたあと、俺は病院の屋上でそのテープを再生した。
そこには、何も録音されていなかった。
ただ、ザーッというホワイトノイズが続くだけ。
いや、違う。
ボリュームを最大にする。
風の音。
遠くのチャイム。
そして、微かに聞こえる声。
『……好きだよ、カイト』
それは、音の波形に埋もれるほど小さな、けれど確かに存在する周波数。
俺は空を見上げた。
星は見えない。
街の明かりが眩しすぎるからだ。
涙が溢れて、景色が滲む。
俺たちは互いに嘘をつき、互いの嘘を愛した。
レコーダーの中の『星が死ぬ音』を消去する。
そして代わりに、俺は今の、この鼻をすする無様な音を録音した。
いつか彼女の耳が奇跡的に治った時、一番に聴かせるために。
「……生きてる音だ、文句あるか」
夜風が、俺の嘘を遠くへ運んでいった。