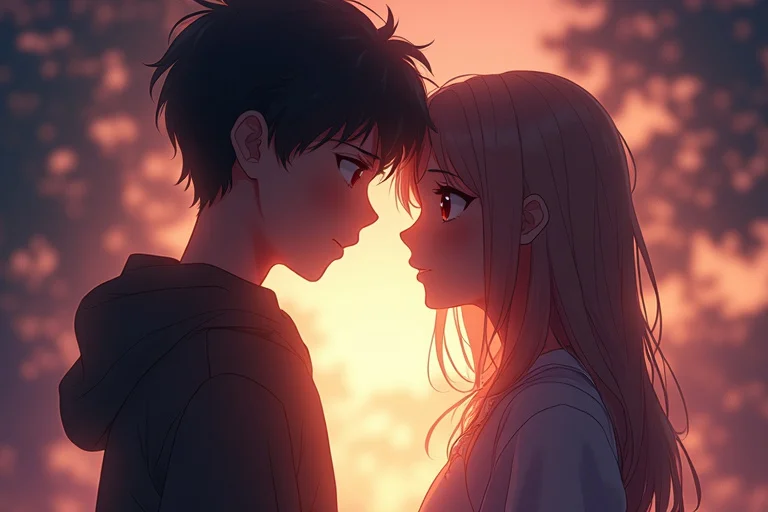第一章 世界のノイズと炭酸の泡
プシュ、と小気味よい音が鼓膜を叩く。
続けて、シュワシュワと弾ける微細な破裂音。
俺は、愛用しているソニーのPCMレコーダーのマイクを、開けたばかりのサイダーの缶に極限まで近づけた。
液晶画面のレベルメーターが、小刻みに跳ねる。
ヘッドホン越しに聴くその音は、まるで真夏の夜に打ち上がる線香花火のようだった。
世界は、ノイズで満ちている。
教室のざわめき、廊下を走る上履きの摩擦音、遠くから聞こえる吹奏楽部の不揃いなチューニング。
それらは俺にとって、処理しきれない情報の洪水だ。
だから俺は、こうしてヘッドホンで耳を塞ぎ、自分の好きな音だけを切り取って収集する。
「……ねえ」
不意に、ノイズキャンセリングの壁を突き破るような、透明な声が降ってきた。
心臓が嫌な音を立てて跳ねる。
レコーダーを取り落としそうになりながら、俺は顔を上げた。
そこにいたのは、雨宮(あまみや)六花(りっか)だった。
長い黒髪が、屋上の風に煽られて踊っている。
彼女は、まるでこの世の光をすべて集めたような、眩しい存在だ。
クラスの中心にいる彼女が、なぜ、こんな校舎の吹き溜まりのような場所にいる俺に声をかけてくるのか。
「な、な、なに……かな」
俺の喉からは、いつものように、壊れたラジオみたいな声が出た。
吃音。
俺が他人との会話を避ける、最大の理由。
けれど、雨宮は俺の滑稽な喋り方を笑わなかった。
それどころか、彼女は俺が持っているレコーダーを興味深そうに覗き込んでくる。
制汗剤と、甘い日向の匂いがした。
「それ、何してるの?」
「お、音を……あ、集めて……」
「音?」
「こ、この……炭酸の、音とか」
俺は逃げるように視線を逸らした。
気持ち悪いと思われるに決まっている。
しかし、彼女の反応は予想外だった。
「へえ。聞かせて」
彼女は俺の頭からヘッドホンを外すと、躊躇なく自分の耳に当てた。
俺の体温が残っているはずのイヤーパッドを、彼女は気にしないのだろうか。
数秒の沈黙。
風が、彼女のスカートを揺らす音だけが聞こえる。
「……すごい」
雨宮が、ほう、と息を吐いた。
「ただのサイダーなのに、海に潜ってるみたい」
彼女はヘッドホンを首にかけたまま、真っ直ぐに俺を見た。
その瞳は、夏の空よりも深く、吸い込まれそうなほど澄んでいた。
「ねえ、湊(みなと)くん。お願いがあるの」
俺の名前を知っていたことにも驚いたが、その真剣な表情に圧倒されて、俺は小さく頷くことしかできなかった。
「私に、『青』の音を作ってくれない?」
「……あ、青?」
「そう。空の青じゃない。海の青でもない。もっと、胸が苦しくなるような……『本当の青』の音」
意味がわからなかった。
けれど、彼女の瞳の奥に、言葉では説明できない切迫した何かが揺らめいているのを見て、俺は断ることができなかった。
それが、俺たちの短くも濃密な、音探しの夏の始まりだった。
第二章 硝子の破片と蝉時雨
その日から、俺たちの奇妙な放課後が始まった。
「青」を探すために、俺たちは街中のあらゆる場所へ足を運んだ。
河川敷の鉄橋の下。
電車が通過する時の、轟音と振動。
雨宮は目を閉じて、その音を全身で浴びていた。
「これじゃない」
彼女は首を振る。
次は、早朝の神社。
竹箒が砂利を掃く、ザッ、ザッ、という乾燥した音。
「もっと、湿度が欲しいの」
彼女の注文は抽象的で、難解だった。
けれど、俺はその過程を不思議と楽しんでいた。
パソコンの波形編集ソフトに向かい、録音した音を加工する。
高音を削り、リバーブをかけ、時間を引き伸ばす。
俺の特技であるサウンドデザインが、彼女のために役立っているという事実が、俺の自尊心をくすぐった。
「そ、その……あ、雨宮さん」
「六花でいいよ」
彼女はアイスキャンディーをかじりながら言った。
古いバス停のベンチ。
遠くで入道雲が湧き上がっている。
「り、六花ちゃんは……どうして、そんな音が……ほ、欲しいの?」
彼女はアイスの棒を口から離し、空を見上げた。
「忘れたくないからかな」
「わ、忘れる?」
「うん。私ね、もうすぐヴァイオリンが弾けなくなるんだ」
彼女がヴァイオリンのコンクールで何度も優勝している有名な奏者であることは、俺でも知っていた。
「ど、どうして……」
「……音がね、遠いの」
彼女は微笑んでいたが、その笑顔は今にも崩れ落ちそうな硝子細工のようだった。
「右耳はもう、ほとんど聞こえない。左耳も、時間の問題なんだって」
蝉時雨が、急にうるさく感じられた。
世界中のノイズが、俺たちを責め立てているように錯覚する。
彼女は、音を失う恐怖の中にいる。
音楽家にとって、それは死刑宣告に等しいはずだ。
「だから、最後に聴きたいの。私がイメージする、一番綺麗な音を。それを記憶に焼き付けておきたい」
彼女は俺の手を握った。
熱くて、少し湿った手のひら。
「湊くんの作る音は、立体的だもん。湊くんなら、きっと作れる」
俺は、自分の無力さを呪った。
俺が集めていたのは、ただの現実の断片だ。
彼女が求めているのは、現実を超えた「心象風景」としての音。
そんなものが、俺に作れるのだろうか。
その夜、俺は部屋に籠もり、数百のトラックを重ねた。
風鈴の音。
自転車のチェーンが回る音。
雨がアスファルトを叩く音。
夜のプールの水面が揺れる音。
それらを混ぜ合わせ、ピッチを操作し、イコライザーで周波数をいじる。
違う。
これでもない。
俺が求めているのは、技術的な完成度じゃない。
彼女の孤独に寄り添える、魂の震えるような音だ。
徹夜明けの白んだ空を見ながら、俺はふと、あることに気がついた。
彼女は「青」と言った。
でも、彼女が本当に欲しているのは、色としての青じゃない。
それは、静寂の向こう側にある、安らぎの色なのではないか。
第三章 指先で触れる世界
約束の期限である、夏祭りの日が来た。
俺たちは、人混みを避けて、学校の旧校舎にある天文ドームに忍び込んだ。
埃とカビの匂いがする狭い空間。
スリットから差し込む月明かりが、彼女の横顔を蒼白く照らしている。
浴衣姿の彼女は、どこかこの世のものとは思えない儚さを纏っていた。
「できた?」
彼女の声が、以前よりも少し大きく、平坦になっていることに気づいた。
聴力が、落ちているのだ。
「う、うん」
俺はノートパソコンを開き、外付けの大型スピーカーに接続した。
「お、大きな音で……なが、流すから」
「え?」
彼女は聞き取れなかったようで、耳を俺の方に向けた。
俺は首を振り、無言で彼女の手を取り、スピーカーのコーン紙(振動板)の上に置かせた。
「……?」
再生ボタンを押す。
空間が震えた。
俺が作ったのは、可聴域ギリギリの重低音をベースにした、振動する「青」だった。
深海の底で響くようなベース音。
その上に、クリスタルボウルを砕いたような高周波音が、キラキラと降り注ぐ。
耳で聴くのではない。
皮膚で、骨で、魂で聴く音。
スピーカーの振動が、彼女の指先から腕へ、そして心臓へと伝わっていく。
ドクン、ドクン、と波打つようなリズム。
それは、母親の胎内にいる時に聞く心音にも似ていた。
「あ……」
六花の目から、大粒の涙がこぼれ落ちた。
「聞こえる……ううん、感じる」
彼女はスピーカーを抱きしめるようにして、その振動に身を委ねた。
「これが、青……。冷たくて、でも、すごく暖かい」
俺は、ボリュームフェーダーをゆっくりと上げていく。
彼女の世界から音が消えていくのなら、俺は世界そのものを振動させて、彼女に届ける。
言葉なんていらない。
吃音も関係ない。
ただ、この振動だけが、俺と彼女を繋ぐ唯一の言語だった。
フィナーレに向けて、音圧が上がっていく。
花火が上がる音さえもかき消すような、圧倒的な音の奔流。
彼女は泣きじゃくりながら、笑っていた。
「ありがとう、湊くん。私、怖くないよ」
彼女の声は、音楽の中に溶けていった。
第四章 無音の奏で
二学期が始まると、雨宮六花は学校に来なくなった。
手術のために入院したと聞いた。
そしてそのまま、遠くの療養所がある街へ転校していった。
俺たちは、あれ以来一度も会っていない。
メールも、電話もしていない。
ただ、俺の手元には、あの夏に作った「青い音」のデータだけが残っている。
俺は今でも、レコーダーを持って街を歩く。
でも、集める音は少し変わった。
以前のような、自分だけの世界に閉じこもるための音じゃない。
誰かに届けるための、誰かの心を震わせるための音だ。
放課後の音楽室。
誰もいないはずのそこから、微かにヴァイオリンの音が聞こえた気がした。
空耳だ。
わかっている。
でも、俺は足を止めて、耳を澄ます。
窓の外には、突き抜けるような秋の空。
俺は空に向かって、小さく口を開いた。
「げ、元気で……やってる、かな」
言葉は風に乗って消えた。
でも、きっと届いている。
あの日の振動が、彼女の記憶の中で鳴り響いている限り。
俺はレコーダーの録音ボタンを押した。
この静寂こそが、今の俺にとって一番愛おしい「音」だったから。