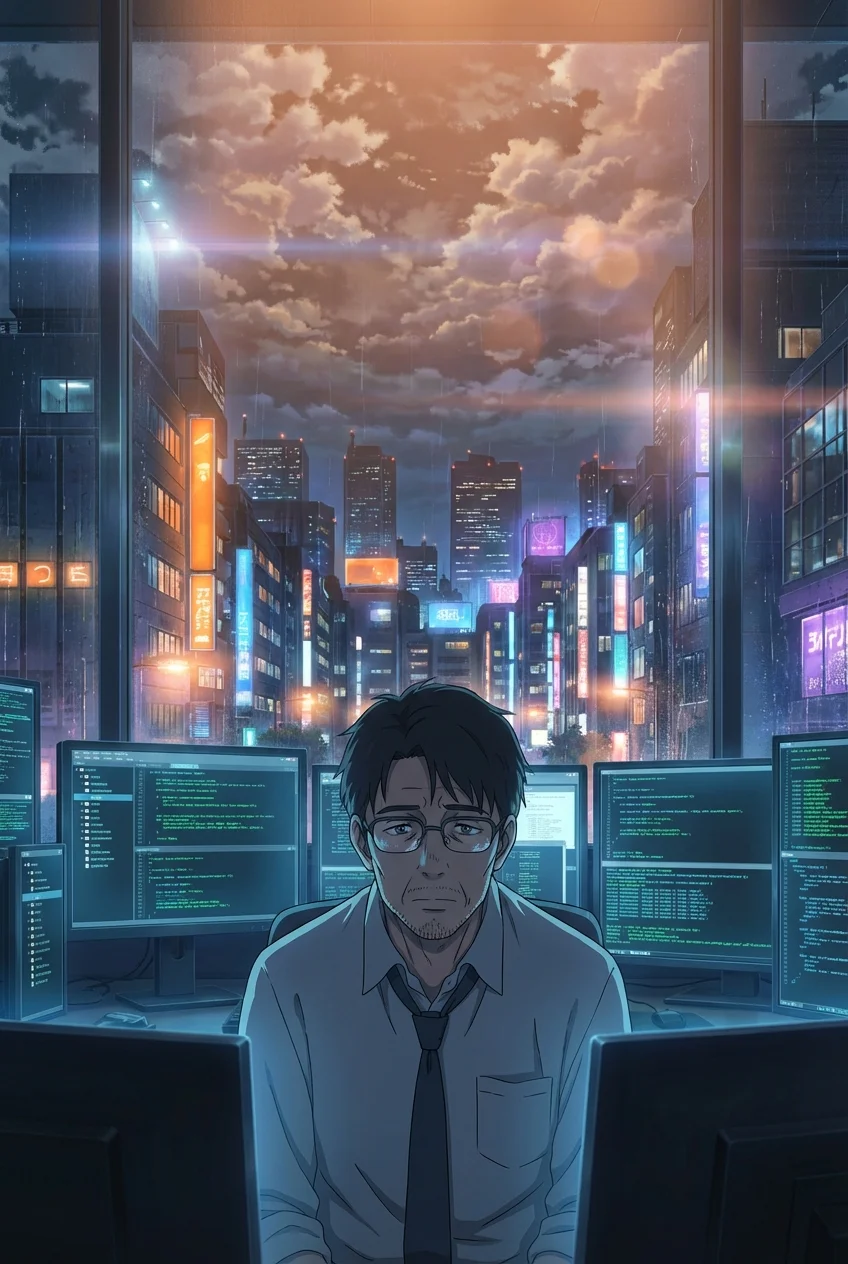第一章 レンタルされた他人の体温
湿気た畳の匂いに、安っぽいシトラスの香水が混ざった。
「で、どこに座ればいいの? おじいちゃん」
玄関の三和土(たたき)に立ったまま、濡れた傘の先から雫を垂らしている少女は、不機嫌を隠そうともしなかった。
金髪のインナーカラー。耳には安物のピアス。
年齢は資料通りなら十九歳。
俺、大迫賢次郎(おおさこ けんじろう)は、作業机のルーペを目に押し当てたまま、振り返りもせずに言った。
「そこにあるタオルで足を拭け。畳が腐る」
「うわ、厳し。マジで昭和」
悪態をつく音が聞こえる。
ガサゴソとバッグを漁る音。ペタリ、ペタリと湿った足音が近づいてくる。
これが、一時間三千円の「孫」だ。
「代行ファミリー社」のパンフレットには、もっと愛想の良い黒髪の女子学生が載っていたはずだ。
だが、派遣されてきたのは、どう見ても補導歴がありそうなこの小娘だった。
「……お茶」
「は?」
「客が来たらお茶を出す。それが『孫』の役目だろうが」
俺がピンセットで極小の歯車をつまみながら言うと、背後で大きな溜息が聞こえた。
「あのさ、契約書読んだ? オプション追加してないでしょ。基本プランは『話し相手』だけ。家事代行は別料金」
少女――マヤは、ドカッと座布団に胡座をかいた。
「それに私、こういうの向いてないんだよね。更生プログラムの一環だからやってるだけで」
「更生プログラム?」
指が止まる。
ルーペを外し、俺は初めてまじまじと彼女を見た。
切れ長の目。意志の強そうな眉。
どこか、見覚えがあるような気がした。
だが、七十二年の人生ですれ違った何千人の顔の中に、こんな生意気な小娘がいたはずもない。
「児童養護施設を出た後の、自立支援みたいなもんよ。ジジババの相手をして、社会性を身につけろってやつ」
マヤはポケットからスマートフォンを取り出し、画面をタップし始めた。
「だから、適当に時間が過ぎるのを待ってよ。私も適当にやるから」
俺は鼻で笑った。
「帰れ」
「は?」
「社会性もクソもない人間に、払う金はない。ハンコは押してやるから、とっとと失せろ」
俺は作業机の引き出しから認印を取り出し、机の上に放り投げた。
朱肉の蓋も開けずに。
マヤの目が、スッと細められた。
スマホを置く。
「……あんたさ、何様?」
「時計屋だ」
俺は再びルーペを目に当て、0.5ミリのネジを回し始めた。
「壊れた時間を直すのが仕事だ。お前のような、ネジの巻き方を忘れたガキの相手をしている暇はない」
部屋に、古時計のチクタクという音だけが響く。
秒針の音が、心臓の鼓動のように重たい。
マヤは立ち上がらなかった。
むしろ、身体を前のめりにして、俺の手元を覗き込んできた。
「それ、直るの?」
「直す」
「もう捨てた方が早くない? 錆びてるじゃん」
「捨てれば終わりだ。人間と同じでな」
皮肉を込めて言うと、マヤはふっと笑った。
その笑い方が、妙に癇に障る。
そして同時に、胸の奥の古傷が疼くような感覚を覚えた。
「ふーん。人間は直せないくせに」
彼女はボソリと呟いた。
「なんだと?」
「なんでもない。……ねえ、お茶淹れてあげるよ。別料金なしでいいから」
マヤは立ち上がり、勝手知ったる他人の家のように台所へ向かった。
急須にお湯が注がれる音。
その音が、独り身の静寂に慣れきった部屋には、やけに生々しく響いた。
第二章 錆びついた歯車
それから毎週水曜日、マヤはやってくるようになった。
雨の日も、風の日も。
この街特有の、湿った海風が吹く日も。
「はい、どら焼き。コンビニの廃棄寸前のやつもらった」
「賞味期限切れを持ってくるな」
「切れてないって。あと三時間は大丈夫」
作業机の端に置かれたどら焼き。
俺は手を止めず、分解された懐中時計のゼンマイを洗浄液に浸していた。
最初の険悪な雰囲気は、奇妙な共存関係に変わっていた。
マヤは俺の仕事を見るのが好きだった。
息を止めてピンセットを動かす俺の横顔を、じっと見つめている。
「ねえ、なんで時計屋になったの?」
ある日、マヤが唐突に聞いてきた。
窓の外は夕立。激しい雨音が、部屋の中の静けさを際立たせている。
「……裏切らないからだ」
「時計が?」
「機械は正直だ。手入れをすれば動く。サボれば止まる。人間のように、突然嘘をついたり、黙って消えたりしない」
俺の言葉に、マヤは視線を落とし、自分の指先のささくれをいじった。
「……奥さんは?」
「死んだ。十年前に」
「子供は?」
俺の手が一瞬、ブレた。
極小のバネがピンセットから弾け飛び、床のどこかへ消えた。
「……いない」
嘘をついた。
機械は嘘をつかないが、人間はつく。
「ふーん。じゃあ、ずっと一人なんだ」
「一人が一番いい。誰にも期待しなくて済む」
俺は這いつくばってバネを探そうとした。
老眼には厳しい作業だ。
「あ、あった」
マヤが素早く床に手を伸ばし、米粒よりも小さな部品をつまみ上げた。
その若く、しなやかな指先。
「ありがとよ」
バネを受け取ろうとした時、俺の指とマヤの指が触れた。
冷たかった。
外は蒸し暑いのに、彼女の指先は氷のように冷えている。
「……あんた、飯食ってるのか?」
「食べてるよ。カップ麺とか」
「そんなもんは飯じゃねえ」
俺は立ち上がり、冷蔵庫を開けた。
作り置きの煮物と、昨日の残りの冷やご飯。
「食ってけ」
「え、いいよ。オプション料金払えないでしょ」
「試作品の毒見だ。金はいらん」
マヤは少し驚いた顔をして、それから「いただきまーす」と小さく手を合わせた。
彼女が煮物を口に運ぶ。
その横顔。
咀嚼する口元。
箸の持ち方の悪さ。
なぜだろう。
二十年前に勘当して家を追い出した、あの一人娘の面影が重なる。
「……美味いか?」
「うん。しょっぱいけど」
マヤは目元を拭う仕草をした。
「しょっぱいのがいいんだよ。汗かいた後はな」
俺たちは、雨音を聞きながら並んで座った。
俺は時計を直し、彼女は俺の作った飯を食う。
ただそれだけのことが、どうしようもなく「生活」だった。
止まっていた俺の時間のネジが、ギギギと音を立てて巻かれていくような気がした。
だが、そんな時間は長くは続かない。
すべての契約には、終わりがある。
第三章 刻まれたイニシャル
三ヶ月後。契約最後の日。
マヤは手ぶらでやってきた。
いつもより少しだけ、化粧が薄い気がした。
「今日で終わりだね、おじいちゃん」
「ああ。せいせいする」
俺はいつものように憎まれ口を叩きながら、一つの包みを差し出した。
「やるよ」
「なにこれ?」
「退職金代わりだ。持っていけ」
マヤが包みを開ける。
中に入っていたのは、綺麗に磨き上げられたアンティークの腕時計だった。
ベルトは新しい革に替え、ガラスも研磨してある。
「これ……動くの?」
「当たり前だ。俺が直したんだぞ」
マヤは時計を耳に当てた。
チク、チク、チク。
正確なリズム。
「……ねえ、これ見て」
マヤは自分のバッグから、古ぼけた懐中時計を取り出した。
蓋が歪み、ガラスが割れ、錆びついた鉄の塊。
「これ、私の母親の形見なんだけど」
俺はその時計を見て、息を呑んだ。
心臓が、早鐘を打つ。
見間違えるはずがない。
文字盤の裏に刻まれた、微細な傷のような彫刻。
『K to Y』。
Kenjiro to Yoko。
二十五年前、娘の二十歳の誕生日に、俺が手作りして贈った時計だ。
娘が男と駆け落ちして家を出て行った時、これだけは持って行った。
「……なんで、お前がこれを持っている」
声が震えた。
マヤは静かに俺を見つめ返した。
その目は、もう反抗的な少女のそれではない。
「母さん、死ぬまで大事にしてたよ。動かなくなっても、ずっと」
「お前……まさか」
「マヤって名前、本当は漢字なの。『真夜』。真夜中の静けさが好きだったおじいちゃんが、もし孫ができたらつけたかった名前だって、母さんが言ってた」
膝から力が抜けた。
その場に座り込む。
更生プログラム。
社会性。
そんなものは建前だったのか。
あるいは、彼女なりの、不器用な「検索」だったのか。
「母さん、最期に言ってた。『お父さんの時計は、世界一正確だけど、時々進みすぎる』って」
マヤは涙を流しながら、笑った。
「だから、私が合わせに来たんだよ。遅れた分を」
俺は震える手で、その錆びついた懐中時計を受け取った。
重い。
二十年分の沈黙と、後悔と、そして繋がっていた血の重さ。
「……直せるか? それ」
マヤが聞いた。
俺は涙で霞む視界を袖で乱暴に拭い、ルーペを目に押し当てた。
「馬鹿野郎」
声が詰まる。
「俺を誰だと思っている」
俺は裏蓋をこじ開けた。
中は酷い錆だ。歯車は癒着し、油は乾ききっている。
だが、心臓部は生きている。
「時間がかかるぞ」
「いいよ。私、暇だから」
「オプション料金は高いぞ」
「出世払いで頼むわ」
「……承知した」
俺は工具を握った。
指先の震えは、もう止まっていた。
窓の外、雨が上がっていた。
雲の切れ間から差し込んだ夕陽が、机の上の無数の歯車を、黄金色に輝かせていた。
止まっていた時間が、今、再び動き出す。
チク、チク、チク。
それは時計の音か、それとも、二人の鼓動か。
部屋には、確かな「家族」の音が響いていた。