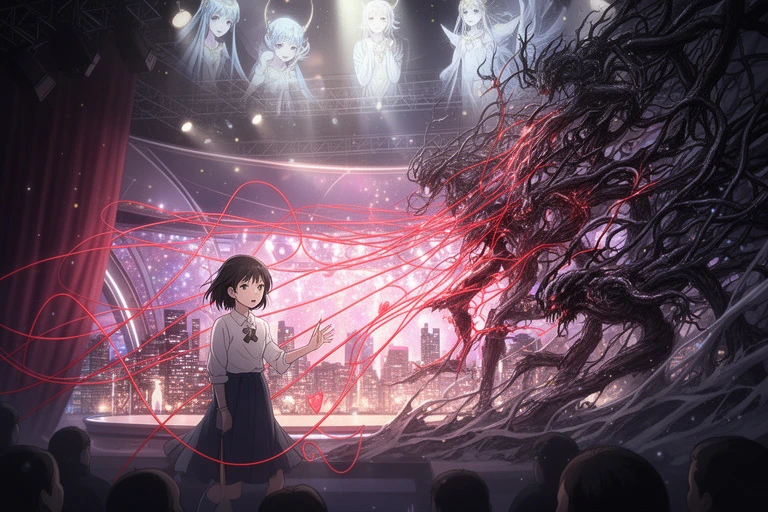第一章 廃棄された雑巾
泥水に沈んだ銅貨が、鈍い光を放っていた。
「拾えよ、アレン。それがお前の退職金だ」
頭上から降り注ぐ嘲笑。雨音よりも冷たく、重い。
視線を上げると、かつての仲間たちが立っていた。
黄金の鎧を纏う勇者レオ。
聖女マリア。
賢者ギル。
彼らの瞳に映っているのは、仲間ではない。
道端に落ちた、汚らわしいゴミを見る目だ。
「お前のスキル『整頓』はさ、もう限界なんだよ」
レオが濡れた髪をかき上げながら、ため息交じりに吐き捨てる。
「野営の片付けや装備の手入れは便利だったけどさ。これからの魔王城攻略じゃ、火力不足もいいとこだろ? 荷物持ちとしても、もう邪魔なんだ」
「……邪魔」
喉の奥が張り付き、掠れた声しか出ない。
「そう、邪魔。お前がいると、パーティーの格が下がるんだよ。不遇職の『清掃員』なんて連れて歩いてたら、俺たちが笑われる」
マリアがくすくすと笑い、ギルが憐れむように肩をすくめた。
僕の胸元には、パーティーの紋章が刻まれたバッジがある。
震える指でそれを外し、彼らの足元へ置いた。
「……今まで、ありがとうございました」
「おー、殊勝な心がけだ。じゃあな、アレン。せいぜいどっかの宿屋で便所掃除でもしてろよ!」
彼らは背を向け、雨のカーテンの向こうへと消えていった。
残されたのは、泥だらけの銅貨と、僕だけ。
冷たい雨が、頬を伝う。
悔しさなのか、絶望なのか、自分でもわからない。
ただ、一つだけ確かなことがあった。
僕のスキル『整頓』。
彼らはそれを、「物を片付けるだけの生活魔法」だと思っていた。
僕自身も、そう信じていた。
でも、違ったんだ。
足元の泥を見つめる。
靴にこびりついた、粘り気のある土。
(汚い……)
無意識に、スキルを発動した。
「『整頓』」
瞬間。
僕の靴から泥が消えたわけではない。
僕の足元の半径1メートル。
その空間から、「泥」という概念そのものが消失した。
地面が、まるで切り取られたように陥没している。
そこには水も、土も、石もない。
完全な「無」が、口を開けていた。
「……え?」
心臓が早鐘を打つ。
僕が今まで「片付けて」いたのは、物理的なゴミだけじゃなかったのか?
『整頓』の本質。
それは対象を移動させることではない。
世界というキャンバスから、不要なノイズを「削除(デリート)」すること。
僕は震える手を見つめた。
彼らは僕を捨てた。
僕を、パーティーにとっての「不要なゴミ」として扱った。
なら、僕にとっての彼らは?
雨が止まない。
けれど、僕の周りだけは、雨粒さえも存在を許されず、乾いた空間が広がっていた。
第二章 汚れの定義
追放されてから、三日が過ぎた。
僕は魔境の森を彷徨っていた。
食料はない。武器もない。
あるのは、研ぎ澄まされた『整頓』のスキルだけ。
「グルルルゥ……」
茂みから、涎を垂らしたオークが現れる。
身長3メートルを超える巨体。錆びついた大剣を引きずっている。
以前の僕なら、悲鳴を上げて逃げ出していただろう。
でも今は、不思議と恐怖がない。
オークの体からは、鼻をつく悪臭が漂っていた。
腐った肉と、古い血の臭い。
生理的な嫌悪感が、背筋を駆け上がる。
(臭い。汚い。……目障りだ)
僕の視界が、無機質に変わる。
世界が情報の羅列に見えてくる。
木々の緑、空の青、そして目の前の、赤黒いノイズ。
オークが大剣を振り上げた。
「『整頓』対象:敵意を持つ有機物」
呟きは、誰に聞かせるものでもない。
ただの作業確認だ。
右手を軽く振る。
埃を払うような、何気ない動作。
ヒュン。
風を切る音さえしなかった。
オークの上半身が、忽然と消えていた。
血飛沫さえ上がらない。
断面は鏡のように滑らかで、そこには血管も骨も見えない。
ただ、存在が「そこになかった」かのように、空間が閉じている。
ドサリ。
下半身だけが、重力に従って倒れた。
「……片付いた」
僕は、オークが持っていた大剣に目を向ける。
赤錆が浮き、刃こぼれしている。
「『整頓』対象:酸化と劣化」
指先で触れる。
一瞬で錆が剥がれ落ち――いや、錆という事象が「なかったこと」になり、大剣は打ちたてのような銀色の輝きを取り戻した。
これが、僕の力。
僕は今まで、食器の汚れを落としたり、散らかった本を並べ替えたりすることにしか使っていなかった。
けれど、概念のレベルで捉え直せば、これは最強の干渉力になる。
「汚れ」とは何か?
それは「あるべき場所にないもの」のことだ。
部屋にある泥は汚れだが、庭にある泥は土だ。
つまり、僕が「ここに在ってはならない」と定義した瞬間、それは「汚れ」となり、消去対象になる。
森の奥から、さらに気配がする。
どうやら、この森は「散らかって」いるらしい。
僕は深く息を吸い込んだ。
大掃除の時間だ。
第三章 勇者という名のシミ
一ヶ月後。
僕は王都に近い平原に立っていた。
風に乗って、焦げ臭い匂いと、悲鳴が聞こえてくる。
「嘘だろ……! なんで攻撃が通じないんだ!?」
聞き覚えのある声。
勇者レオだ。
丘の上から見下ろすと、そこには絶望的な光景が広がっていた。
漆黒のヘドロのような不定形の怪物。
「ヴォイド・イーター」。
あらゆる魔法を吸収し、物理攻撃を無効化する、厄災級の魔物だ。
レオの聖剣が弾かれる。
マリアの聖なる光が、ヘドロに飲み込まれて消える。
ギルの炎魔法が、逆に怪物を巨大化させている。
「ひ、ひぃ……! いやだ、死にたくない!」
マリアが尻餅をつき、後ずさる。
華麗だった彼らの装備は泥と煤にまみれ、見る影もない。
(ああ、やっぱり)
僕は静かに丘を降りていく。
(彼らは、片付けが下手だ)
戦場に足を踏み入れると、最初に気づいたのはギルだった。
「ア、アレン……? お前、生きて……」
「下がってください。邪魔です」
僕は彼らの横を通り過ぎる。
「は? 何言ってんだ、お前! 逃げろ、こいつはレベルが違う!」
レオが叫ぶ。
ヴォイド・イーターが、僕に気づいた。
数千の目玉がギョロリと開き、僕を「餌」として認識する。
襲いかかる漆黒の触手。
山をも砕くその一撃が、僕の鼻先で止まった。
「汚いなあ」
僕は眉をひそめる。
「食事の前に、手を洗うって教わらなかった?」
「『整頓』」
パチン、と指を鳴らす。
触手が消滅した。
「……は?」
レオたちが口を開けて固まる。
ヴォイド・イーターが困惑したように身を捩る。
再生しようとするが、できない。
僕が消したのは細胞ではない。「再生能力」という概念そのものだ。
「次は、その不快な粘液」
一歩進む。
怪物の体の表面から、粘り気が消え、乾燥した灰のような砂に変わっていく。
「そして、その悪意」
もう一歩進む。
怪物の動きが止まる。
殺意という動力を失い、ただの巨大な砂山へと成り果てる。
「仕上げだ」
僕は怪物の核――コアを見据える。
「『全廃棄』」
音もなく。
本当に、何の予兆もなく。
巨大な怪物は、春の雪解けのように、世界から滲んで消えた。
後に残ったのは、綺麗に整地された平原と、澄み渡った青空だけ。
静寂。
誰かが唾を飲む音が聞こえた。
「ア、アレン……お前、その力……」
レオが震える声で話しかけてくる。
その顔には、先刻までの絶望は消え、卑しい希望の色が浮かんでいた。
「すごい! すごいぞアレン! やっぱりお前は俺たちの仲間だ!」
レオが駆け寄ろうとする。
「なぁ、水臭いこと言うなよ。あの時はちょっと魔が差しただけなんだ。戻ってきてくれよ。お前がいれば、俺たちは世界最強だ!」
マリアも、ギルも、媚びへつらうような笑顔を浮かべて頷く。
彼らの鎧は汚れている。
でも、それ以上に汚れているのは。
僕は、レオに向けられた手をゆっくりと降ろした。
「仲間?」
「そ、そうだ! 俺たちは運命共同体だろ?」
レオが僕の肩に手を置こうとする。
その瞬間。
僕の視界の中で、レオという存在に赤いタグが付与された。
【分類:不要物】
「触るな」
冷たい声が出た。
「え?」
「僕の新しい服に、菌がつく」
「き、菌って……お前、俺に向かって……」
レオの顔が怒りで赤くなる。
その感情の起伏さえ、今の僕にはノイズにしか見えない。
「『整頓』対象:僕の視界における不快な過去」
僕はレオを見つめたまま、スキルを発動した。
殺しはしない。
ただ、「勇者」という肩書きと、彼らが積み上げてきた「名声」という汚れを、綺麗さっぱり洗い流すだけだ。
「う、うわあああああ!?」
レオが悲鳴を上げる。
彼の身に纏っていた黄金の鎧が、ボロボロの布切れに変わっていく。
聖剣が、ただの鉄屑へと劣化する。
「な、なんだこれ!? 俺の装備が! 俺の力が!?」
「マリアの聖女の衣も、ギルの杖も、全部『掃除』しておいたよ。君たちには分不相応だったから」
僕は踵を返す。
「待て! 待ってくれアレン! 俺たちはこれからどうすればいいんだ!」
背後から縋るような声が響く。
僕は振り返らずに答えた。
「一からやり直せばいい。……ああ、でも」
僕は一度だけ立ち止まり、肩越しに彼らを見た。
「次はもっと綺麗に生きたほうがいい。そうしないと、また僕に『掃除』されるから」
青空の下、僕は歩き出す。
世界はこんなにも美しい。
ただ、少しだけ掃除が必要な場所が残っているだけだ。
さて、次はどこを綺麗にしようか。
僕の仕事は、まだ始まったばかりだ。