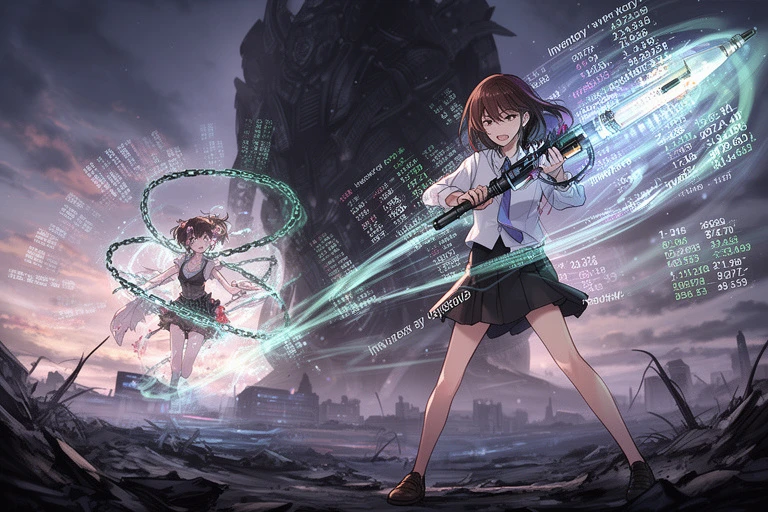第一章 借り物の鼓動
俺の心臓は、俺のものではない。
冷たい手術台の上で生命を取り留めたあの日から、この胸で脈打つ鼓動は、見知らぬ誰かの物語を奏で続けている。夜ごと見る夢がその証拠だった。俺、高槻蓮(たかつき れん)の記憶にはないはずの、セピア色の風景。潮風に錆びた手すり、指に絡まる柔らかな髪の感触、そして、俺ではない誰かが「ユウナ」と愛おしげに囁く声。
それは、この心臓の元の持ち主――アキトという男の記憶の断片らしい。医師はそれを、細胞が記憶する「セルラー・メモリー」という曖昧な言葉で片付けた。だが、夢は日を追うごとに鮮明さを増し、俺の現実を侵食し始めた。朝、鏡に映る自分の顔に、アキトの苦悩に満ちた表情が重なる。コーヒーを飲めば、彼の記憶にある海の匂いが鼻をつき、俺自身の好物だったはずの味が分からなくなる。
「俺は、誰だ?」
その問いは、空虚な部屋に吸い込まれて消えた。唯一の手がかりは、彼の遺品として俺の元へ送られてきた、一台の古びた蓄音機だけだった。黒光りする木製の箱に、鈍色のラッパ。針を落としても、回転するレコードは沈黙を続けるだけ。それでも、アキトはこのガラクタを宝物のように抱きしめていたのだと、夢が告げていた。
ある雨の日の午後、俺はアキトの記憶に導かれるように、古い図書館の裏手にあるベンチに辿り着いた。そこには、陽炎のように揺らめく人影があった。人々は気にも留めず通り過ぎていくが、俺には分かった。あれが『影』だ。死者が、生前の最も強い感情と共に留まり続けるという、魂の残滓。
ふと、胸の奥が疼いた。アキトの心臓が、あの影に共鳴している。衝動的に、持っていた蓄音機の蓋にそっと触れた。
その瞬間だった。
――ジジッ、と耳障りなノイズが頭蓋に直接響き渡った。音など出るはずのない蓄音機から、歪んだ旋律が溢れ出す。それは、後悔の音色だった。伝えられなかった言葉の悲鳴、届かなかった想いの慟哭。影が、忘れ去られることへの恐怖に叫んでいた。俺はたまらず耳を塞いだが、音は内側から鳴り響き、止むことはなかった。
第二章 沈黙の旋律
影との接触以来、侵食は加速した。俺の日常は急速に色褪せ、アキトの過去が鮮やかな現実として立ち上がってくる。俺はアキトの足跡を辿るように街を彷徨い、壊れた蓄音機を携えて影を探した。蓄音機は、影が放つ感情の音色を拾うチューナーのようなものらしかった。愛の影は甘美な和音を、憎しみの影は不協和音を奏でたが、そのどれもが、忘れられたくないという切ない願いの残響を伴っていた。
夢の中で、アキトが蓄音機に触れながら、愛する女性――ユウナに語りかける場面を何度も見た。
「この沈黙こそが、君を永遠にするための音楽だ」
意味の分からない言葉だった。だが、その声には狂気にも似た愛情が満ちていた。彼は、ユウナを深く愛していた。そして、何かから必死で守ろうとしていた。
俺は、ユウナの『影』を探さねばならないと確信していた。アキトの未練の根源。この侵食を止めるか、あるいは完全に飲み込まれるかの答えが、そこにあるはずだった。
記憶の断片を繋ぎ合わせ、俺はある場所に行き着いた。海を見下ろす岬に立つ、古びた白い灯台。二人が何度も訪れたという、約束の場所。
石の階段を上りきると、そこに彼女はいた。
夕陽を背に、海を見つめるユウナの影。他の影よりもずっと儚く、輪郭が薄れかけている。俺の胸の心臓が、歓喜と絶望の入り混じった叫びを上げた。アキトの感情が、俺自身のものとして溢れ出す。
「ユウナ…」
俺の口から、俺のものではない声が漏れた。
影がゆっくりと振り返る。その顔は、夢で見たどの彼女よりも鮮明で、美しかった。生きている人間が強い感情を抱けば、影は一瞬だけ生前の姿を取り戻す。だが、それは同時に、その存在を削り取る諸刃の剣。
「アキト…?」
ユウナの影が、愛おしげに俺の名を呼んだ。いや、アキトの名を。
第三章 永遠という名の実験
その声を聞いた瞬間、俺の中の何かが壊れた。俺は蓮だ。アキトじゃない。だが、この胸の痛みも、愛しさも、紛れもなく本物だった。
俺は震える手で、足元の蓄音機に触れた。
アキトの本当の目的を知るために。
――閃光。
奔流のような情報が、俺の意識を洗い流していく。アキトの絶望、彼の見つけた世界の真実、そして、その狂おしい計画の全てが、悲鳴となって脳内に流れ込んできた。
この世界の法則の残酷さ。影は、生きる者に忘れられた時、完全に消滅する。そして、その影が生きていたという記憶すら、世界から綺麗に消え去るのだ。アキトは、いずれユウナの影が誰かと語らい、摩耗し、世界から忘れ去られる未来に耐えられなかった。
だから彼は、世界の法則を書き換えようとした。
影を、その記憶を、永遠に保存する器を作り出そうとした。
壊れた蓄音機は、影の存在情報を吸い上げるアンテナ。そして、その情報を定着させる記録媒体こそが――特殊な適合性を持つ、生きた人間の心臓。
『セカンドライフの侵食』。
それは、愛する者の記憶を、他者の人生そのものに上書きし、永遠に語り継がせるための、究極にして残忍な実験だった。
「この沈黙こそが、君を永遠にするための音楽だ」
蓄音機が奏でるのは、音ではない。存在そのものだ。
俺の心臓は、ユウナという音楽を永遠に奏でるために選ばれた、生きたレコード盤だったのだ。胸の傷跡が、レコードの盤面に刻まれた最初の溝のように、熱く、深く疼いた。
「ああ……ああああああああッ!」
俺は絶叫した。それは蓮の悲鳴であり、アキトの慟哭でもあった。
「俺はッ! お前の愛のエゴのための、生贄だったというのか!」
目の前のユウナの影が、悲しげに揺らめく。彼女は何も知らない。ただ、愛する男が自分を忘れずに会いに来てくれたと、その一瞬の奇跡に微笑んでいる。その笑顔が、俺の心を粉々に砕いた。
第四章 影喰らいのレクイエム
俺は、もう俺ではいられなかった。アキトの愛と狂気は、俺という器を満たし、境界線を溶かしてしまった。俺は蓮であり、アキトでもあった。
俺はゆっくりと立ち上がり、ユウナの影へと歩み寄る。
「アキト」として、彼女に最後の言葉を告げなければならない。
「待たせて、ごめん」
その一言に、全ての愛と、別れを込めた。ユウナの影は、世界で最も幸せな微笑みを浮かべると、光の粒子となって夕暮れの空気に溶けていった。満足し、安らかに。
彼女の影が消える。だが、アキトの計画通り、ユウナの存在は、記憶は、愛は、俺の心臓に、魂に、完全に刻み込まれた。世界が彼女を忘れても、俺が覚えている。
そして、役目を終えたアキト自身の『影』もまた、この世界から静かに消滅していった。彼が生きた証も、その狂おしい愛の物語も、世界からは失われた。ただ一人、俺を除いて。
俺は岬に一人、佇んでいた。
胸に抱いた壊れた蓄音機は、もう何の音も奏でない。ただ、冷たい。
俺は高槻蓮を失った。だが、新たな役割を得た。
アキトはユウナの記憶を永遠にするために俺を選んだ。ならば俺は、アキトのその願いごと、引き受けよう。世界から忘れ去られていく、全ての哀しい影たちのために。
街の灯りが灯り始める頃、俺は岬を降りた。路地裏で、誰にも気づかれずに消えかけている老婆の影を見つける。俺はそっとその隣に腰を下ろし、蓄音機に手を置いた。
俺は、忘れられた者たちの記憶を喰らう。
俺のセカンドライフは、彼らを忘れさせないための、静かな「侵食」を続けること。
何が救いで、何が悲劇だったのか。
答えを探すには、この借り物の心臓が刻む時間は、あまりにも長すぎた。