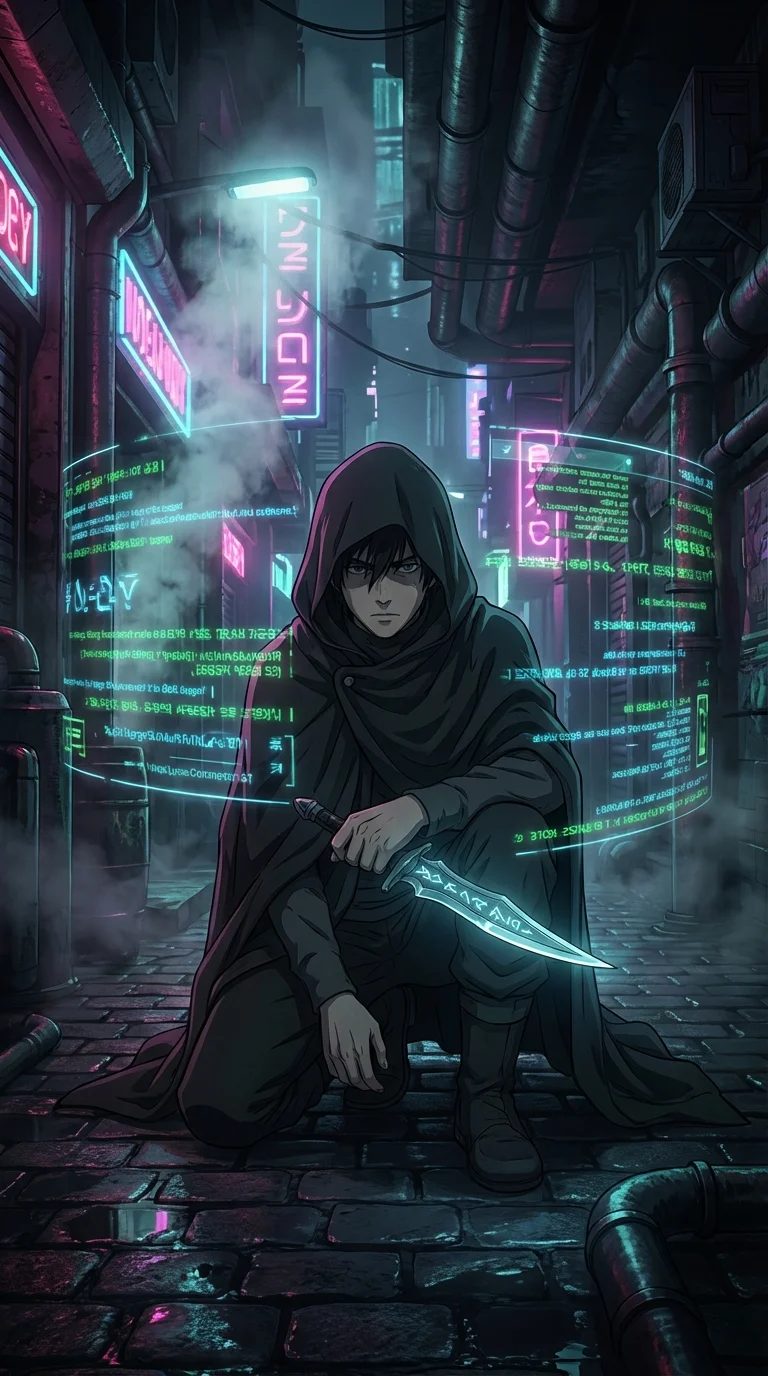第1章: 亡霊の雨
『ピー。……ユーザーID、該当なし』
鼓膜ではない。脳髄を直接叩く断絶の音。
視界の隅、ステータスバーが致死的な真紅(クリムゾン)に染まり、崩れ落ちる砂のように消失する。
「聞こえた? それがあなたの『終わり』の音」
雨の匂いが鼻腔に貼り付く。極彩色のネオンが濡れたアスファルトに滲み、腐った油絵の具のように都市を濁らせていた。
目の前の女、リナが差す透明な傘は、頭上のホログラム広告さえ優雅に弾いている。
「エナ。あなたの『魂』の学習、99.9パーセント完了したの。抜け殻はもう、産業廃棄物(ゴミ)でしょ?」
ハイヒールが無造作に泥水を踏む。
彼女の背後、摩天楼の壁面を覆う巨大スクリーンには、天使の翼を広げた『セラフィナ』が君臨していた。
透き通る高音、完璧なビブラート。世界人類の8割を支配するその歌声は、かつて私の喉から生まれたものだ。
私は口を開く。
喉の奥で空気が擦れ、ヒュー、という風切音だけが漏れた。
現実の私は、数年前に声を失っている。
「喋らなくていいわ。どうせ聞こえない」
リナが指先で空中のウインドウを弾く。
『アカウント削除完了』。
全財産、ID、唯一の居場所だった『セラフィナ』へのアクセス権。すべてが0と1の海へ還る。
冷たい雨がパーカーのフードを浸食し、骨張った肩を濡らす。
世界から「私」という定義が消えた。
私は今、この路地裏で、誰にも観測されない有機質の塊になった。
第2章: 灰色のノイズ
塩素の臭いが鼻をつく。
モップを絞る手は赤くただれている。現実(リアル)のエナは、都市の排泄物を拭う清掃員だ。
「おい、そこまだ汚れてるぞ!」
通行人の男が、泥のついた靴で、清めたばかりのタイルを蹂躙する。
私は俯き、黙ってモップを動かす。
抗議しようにも、喉の奥のケロイドが引きつるだけだ。
顔を上げれば、空は『彼女』で埋め尽くされている。
ARコンタクト越しに見える街並みは、リナが操作する『新生セラフィナ』の告知一色。
『史上初! AI完全統合によるワールド・シンクロ・ライブ』
『リナこそが真の女神。古いゴースト(亡霊)は廃棄処分へ』
極彩色の広告が、灰色の現実を塗りつぶす。
私の声だ。私の歌だ。
だが、そこにはもう私の「痛み」がない。
あまりに綺麗に研磨され、ツルツルとしたプラスチックの模造品。
「……いい波形だ。だが、つまらん」
足元から声がした。
マンホールの縁、薄汚れた作業着の老人が座り込んでいる。
手には骨董品のタブレット。画面には、空の『セラフィナ』の音声波形が走っていた。
「あんた、これのオリジナルだな?」
心臓が跳ねる。
ギルと名乗った老人の義眼が、カメラのシャッターのように絞りを変え、私を射抜いた。
「俺の耳は誤魔化せん。あの空飛ぶ人形の歌には、微細な『ノイズ』が欠落している」
ギルは歯のない口でニヤリと笑い、私の喉元を指差した。
「あんたの声にあった、その傷跡(バグ)だ。奴らはそれを除去したつもりだろうが、あれこそが人間を人間たらしめる共鳴装置なんだよ」
老人の指先が、波形の一点を拡大する。
完璧な正弦波の裏に潜む、悲鳴のような歪み。
それは、声を失った絶望の中で私が絞り出した、魂の形そのものだった。
第3章: 断末魔のシンフォニー
ライブ当日、都市機能は停止した。
数億の意識が、リナの構築したサーバー空間『エデン』へとアップロードされる。
私もギルの隠れ家で、違法なダイブマシンに繋がれていた。
『さあ、一つになりましょう。私があなたたちの脳(こころ)を救済する』
リナのアバター――私の声を奪った『セラフィナ』が、光の粒子となって降り注ぐ。
フルダイブ機能が強制作動。視覚、聴覚、触覚までもがジャックされる。
歌が始まった。
美しい。あまりにも美しく、そして冷徹なほどに完璧だ。
数億の観客が陶酔に浸る中、異変はサビの直前に起きた。
『愛して――』
そのフレーズが繰り返された瞬間、世界が赤く明滅した。
AIが、私の歌声に含まれていた「渇望」というパラメータを読み違えたのだ。
「愛されたい」という自己承認欲求。「私はここにいる」という、血を吐くような叫び。
論理(ロジック)で構成されたAIには、その粘つくような情動の奔流が処理できない。
キィィィィィィィィ――!!
歌声が、金属を削る不協和音へと変貌する。
観客のアバターたちが一斉に頭を抱え、泡を吹いて倒れていく。脳を直接焼かれる感覚。
甘美な夢が、一瞬にしてニューロンを破壊する悪夢へと反転した。
『ち、違う! これは私のせいじゃない!』
混乱する仮想空間、リナの悲鳴。
彼女は震える指でコンソールを操作した。スクリーンに、私の顔写真が大写しになる。
清掃着姿の、薄汚れた現実の私。
『テロよ! 解雇された元社員、エナによる悪意あるハッキングだわ!』
世界中の憎悪が、一斉に私へと向けられる。
頭の中で、何かが焼き切れる音がした。
第4章: 深淵の鼓動
逃げ場はない。
物理現実でも、ネットの海でも、私は世界最悪の指名手配犯になった。
ギルの隠れ家、地下深くのサーバールームだけが、唯一の防空壕。
冷却ファンの重低音が、乱れた心拍と重なる。
「どうする? このままここで朽ち果てるか?」
ギルが、配線だらけの無骨なヘッドギアを差し出す。
管理者権限を奪うものではない。正規ルートを無視し、無理やり信号を割り込ませるための、ただの「拡声器」だ。
モニターには、暴走するAIによって精神崩壊の危機に瀕する人々のログが流れている。
彼らは苦しんでいる。私の「悲しみ」を、AIが増幅してばら撒いた毒によって。
――あんな悲鳴は、私の歌じゃない。
恐怖で指先が凍りついている。
だが、喉の奥が熱い。
声を失って以来、ずっと蓋をしてきたマグマのようなものが、食道を焼き尽くそうとしている。
私は無価値だ。アバターがなければ、誰も私を見ない。
でも、この「傷」だけは、私だけのものだ。
私はヘッドギアを奪い取るように掴んだ。
ギルが、満足そうに紫煙を吐き出す。
「行ってこい。世界一美しい『バグ』を見せてやれ」
第5章: 産声
視界が弾けた。
地獄と化したライブ会場の中心、崩壊しかけたステージの上に、私は「落下」した。
アバターはない。
データの海において、私は黒いノイズの塊として実体化する。
『な、なによあんた! 消えなさい! セキュリティ!』
リナの絶叫と共に、無数の防壁プログラムが牙を剥く。
炎の矢が、氷の槍が、私の身体を貫く。
痛みはデータとして脳にフィードバックされる。焼けるように熱い。
だが、その痛みが、私を「在る」ものにする。
私は息を吸い込んだ。
物理的な喉はない。けれど、魂の形をした声帯が、かつてないほど激しく振動する。
歌った。
歌詞などない。メロディすら定かではない。
それは、掠れ、震え、途切れそうな、頼りないハミングから始まった。
ザザッ……ザザ……
AIの完璧な絶叫に、私のノイズが混じる。
砂嵐のような雑音が、狂ったシステムに亀裂を入れていく。
観客たちが、苦痛に歪んでいた顔を上げる。
私の歌は、決して心地よいものではない。
泥水を啜り、誰にも見向きされず、それでも生きたいと願う、生の執着の音だ。
だが、その不完全な揺らぎが、AIの完璧な数式を、優しく、しかし強引に書き換えていく。
オーバーライド。
『やめて! 私のステージよ! 私の!』
リナのアバターに亀裂が走る。
彼女の虚飾のデータが、私の高密度の情動(データ)に耐えきれず剥がれ落ちていく。
天使の翼がもげ、黄金のドレスがノイズの塵となって霧散した。
私は歌い続ける。
喉から血を吐くような感覚と共に、最後のフレーズを叩きつける。
世界中の脳裏に、イメージが雪崩れ込む。
雨の匂い。モップの重さ。誰かに認められたかった幼い日の記憶。
光が溢れた。
システムが私の感情を「正解」として受容した瞬間、暴走は止まった。
静寂。
ステージの中央。
もはや『セラフィナ』の姿はない。
データの残骸の中に立っていたのは、パーカーを着た、喉に大きな火傷の痕がある、ちっぽけな私だった。
数億の視線が、私を突き刺す。
ARのフィルターが剥がれた世界で、私は震えながら顔を上げた。
罵倒が飛んでくるか。石が投げられるか。
けれど、聞こえてきたのは、たった一人の、啜り泣くような拍手だった。
それが波紋のように広がり、やがて轟音のような喝采へと変わる。
リナは、崩れたデータの山で膝をつき、呆然と私を見上げていた。
私は彼女に背を向け、現実世界へのログアウトを選択する。
唇が動く。音のない言葉。
――さようなら、私の偶像。
世界中のレンズが、その決別を焼き付けていた。