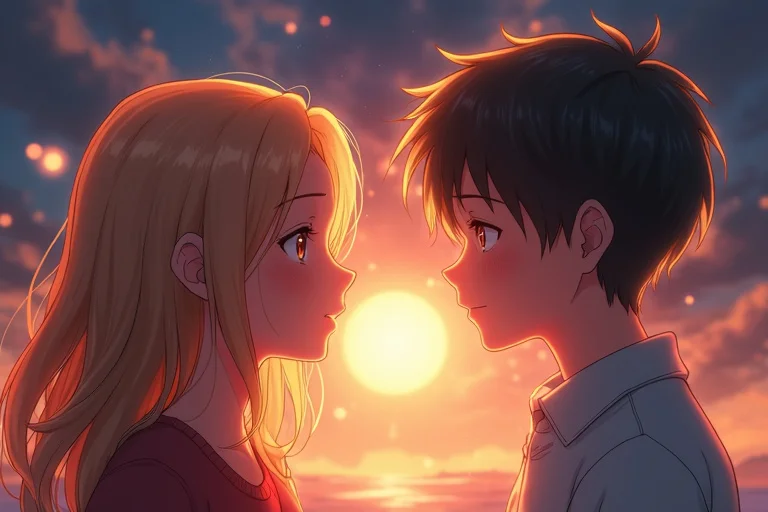君に『愛』を譲渡した刹那、僕の世界から君を恋う機能は死滅した。
それは等価交換ですらない。僕という個体の崩壊と引き換えに行われた、もっとも残酷な救済だった。
第1章: 灰色の屋上と色彩の取引
錆びついたフェンスに触れると、指先に鉄の味が伝染する。
五月の風は生温かく、アスファルトの照り返しが視界を揺らしていた。僕の網膜には、世界が極彩色の油絵具をぶちまけたように映る。すれ違う生徒の肩から立ち昇る苛立ちは濁った紫、早弁する男子の胃袋から漏れ出す満足感は安っぽい蛍光イエロー。
過剰な色彩が、三半規管を常に酔わせていた。
だが、フェンスの向こう側に立つ水無月冬花だけは違った。
彼女の背中に色はなく、黒ですらない。そこにあるはずの空間がスプーンでえぐり取られたような、完全な「無」。
冬花が踵を浮かせ、重力がその華奢な足首を地上へと誘う。僕は駆け出すよりも速く、声を投げた。
「そこから落ちても、君の空洞は埋まらない」
冬花が振り向く。その瞳は底の抜けた井戸だ。絶望も恐怖もなく、ただ存在への違和感だけが張り付いている。
「……透くん」
乾いた紙が擦れるような声だった。
「邪魔しないで。私、自分が何なのか分からない。嬉しいも、悲しいも、痛いも、全部すり抜けていく。不良品は廃棄されるべきよ」
彼女が重心を空へ預けようとした瞬間、僕はフェンス越しにその腕を強引に引いた。陶器の人形のように冷たい。
「なら、僕が直す」
「直す……?」
「僕には感情が余りすぎている。色がうるさくて眠れない夜があるほどだ。だから、君にあげる」
「あげる?」
「移植だ。僕の心を切り取って君の穴を埋める。その代わり、君は生きる理由を探せ」
僕は彼女の手首を握り締め、瞼を閉じた。胸の奥で渦巻く淡いピンク色の光――『安らぎ』を、血管を通じて流し込む。
ドクン、と脈が跳ねた。
指先から光が抜け、冬花の肌へと吸い込まれていく。彼女が小さく息を呑み、胸元を抑えた。
「……あたたかい」
冬花の頬に、極めて薄い朱色が差す。それは僕が失った色だった。
胸の中にあった温かな塊が一つ消え、代わりに冷ややかな風が吹き抜ける。
その喪失感に、背筋が粟立つほどの快感を覚えた。
ああ、やっと軽くなれる。僕はこの重たい色彩を誰かに押し付けることでしか、輪郭を保てないのだから。
第2章: 鮮やかな痛み
放課後の美術室。テレピン油と古びたキャンバスの匂いが充満し、舞い上がる埃が西日を受けて金粉のように煌めく。
「透くん、見て」
冬花がパレットナイフを踊らせた。キャンバスには、弾けるようなオレンジと鮮烈な青が衝突している。先日譲渡した『楽しみ』と『好奇心』の色だ。
「綺麗な色だ」
嘘ではない。だが、僕の目にはその彩度が以前より数段落ちて見えていた。世界は徐々に、しかし確実に脱色されている。
冬花が笑った。
口角が上がり、目尻が下がる。不器用だが、紛れもなく人間の表情。
「今日ね、購買のパンが売り切れる前に買えたの。すごくドキドキした。心臓が早鐘を打って、手汗が出て……これが『焦燥』と『達成感』なのね」
彼女は僕の手をとり、自身の胸に当てた。
トクトクと脈打つ鼓動のリズムは、かつて僕のものだった。
「ありがとう、透くん。私、生きてるって感じがする」
万華鏡のように輝く彼女の瞳とは対照的に、僕の瞳からは光が失われていく。かつてノイズのように押し寄せていた色彩は、視界の端からグレーに侵食されていた。
「よかったね」
微笑むために、どの顔面筋肉を動かせばいいのか一瞬思考する。『喜び』を渡した代償に、笑い方のマニュアルを失いつつある。
それでも満足だった。中身が空っぽになるほど、僕という存在が「誰かの役に立った」という事実だけが墓標のように残る。
「もっと、教えて。もっと色が欲しい」
冬花の渇望に頷き、自分の胸に手を突き入れる感覚で、次の感情を引き抜く。
痛みはない。あるのは、麻酔が効いていくような甘美な麻痺だけ。
第3章: 愛のパラドックス
文化祭前日、教室は喧騒の坩堝だった。
その中心で、冬花は立ち尽くし、一点を見つめている。僕だ。
僕は黙々と段ボールをカッターで切り裂いていた。手元が狂い、指先から赤い液体が滲むのを他人事のように眺める。痛覚すら鈍っている。
「透くん」
冬花が近づいてきた。頬は上気し、瞳は潤んでいる。彼女の胸元から、激しい真紅のオーラが噴出しているのが視えた。
「私、変なの。透くんを見ると、ここが苦しくて、締め付けられて……息ができない」
彼女は自身の胸を握りしめる。
「これって、『恋』なんでしょう?」
教室のざわめきが遠のく。カッターの刃を引っ込めた。
彼女が感じているその激しい情動。それは数週間前、僕が彼女に譲渡した『他者を愛おしむ心』そのもの。
皮肉な話だ。彼女が僕に向け始めたその恋心は、元を正せば、僕が彼女に対して抱いていたものなのだから。
かつてなら、彼女の潤んだ瞳を見ただけで世界がバラ色に染まっていただろう。けれど今、僕の胸にあるのは凍てついた湖面のような静寂だけ。
「……そうだよ。それが恋だ」
温度のない声で告げる。
「よかったね、冬花。君はもう、立派な人間だ」
冬花が凍りついた。
僕の瞳に、自分への好意が欠片も残っていないことに気づいたのだ。
「待って……。どうして、そんな顔をするの? 私がこんなに透くんを想っているのに、どうして透くんからは……何も感じないの?」
感情を得たことで、彼女の勘は鋭くなっていた。
「まさか……透くん。私にくれた『これ』は……あなたが私に向けていた気持ちだったの?」
沈黙が肯定となる。冬花の顔から血の気が引いた。
「私がこの幸せを感じれば感じるほど、あなたは私を好きじゃなくなっていくの……?」
その問いに答えるための『罪悪感』すら、僕はもう持っていなかった。
第4章: 抜け殻の少年と溢れる少女
屋上の風は、春よりも冷たくなっていた。
鉛色の空。視界にはもう色彩は残っていない。世界は白と黒と、無限の灰色で構成されていた。
「返して」
冬花が叫ぶ。その涙は、僕にはただの透明な水に見えた。かつては宝石のような青だったはずなのに。
「いらない。こんなもの、いらない! 透くんが空っぽになるなら、私、また人形に戻る!」
彼女が僕の胸を叩く。拳から伝わる衝撃だけが、僕の存在証明だった。
「無理だよ。一度定着した感情は戻せない。君の心臓に根付いてしまった」
「そんな……ひどいよ。これじゃあ、私は透くんの命を食べて生きながらえる怪物じゃない!」
冬花が崩れ落ちる。僕から流れ込んだ大量の感情――怒り、悲しみ、後悔、愛着――が濁流となって未熟な精神を蝕んでいるのだ。
僕はそれを見下ろしている。
抱きしめてやるべきだという知識はある。背中をさするべきだという論理も分かる。
だが、身体が動かない。『憐れみ』も『焦り』も『慈しみ』もない。僕はただの高性能な録画機器のように、彼女の崩壊を記録していた。
「君が幸せなら、それでいい」
僕の口癖が呪いのように響く。
「ふざけないで!」
冬花が僕を睨みつけた。その目は血走っている。
「あなたが感情を捨てたのは、私の為じゃない。傷つくのが怖かったからでしょう! 自分を犠牲にしている自分が好きだっただけでしょう!」
図星だった。
だが、それを指摘されても『羞恥』すら湧いてこない。
「そうかもしれないね」
僕の平坦な肯定が、冬花をさらに絶望させた。
彼女は悲鳴を上げ、両手で耳を塞ぐ。愛する人が目の前にいるのに、その人はもう、自分を愛する機能を物理的に失っている。
その断絶が、彼女の心を粉々に砕こうとしていた。
第5章: ゼロからの筆致
放課後の美術室に、僕たちはまた戻ってきた。
冬花がそう望んだからだ。
彼女はキャンバスの前に立ち、筆を握っている。
鬼気迫る背中から、オーラのような色彩が陽炎のように立ち上っている――らしい。僕にはもう見えない。ただのモノクロ映画のワンシーンだ。
「透くん、見ていて」
叫ぶように言い、彼女は筆を叩きつけた。
静寂な部屋に、筆がキャンバスを擦る音だけが響く。激しく、荒々しく、時に優しく。
彼女は泣きながら描いていた。僕が与えた『喜び』を、『悲しみ』を、『怒り』を、そして『愛』を。
全てを絵の具に混ぜ合わせ、叩きつけていく。
「これが、あなたが捨てた色よ!」
冬花が筆を走らせるたびに、絵の具が飛び散り、制服を汚す。
彼女は「返却」しようとしているのではなかった。言葉の通じない異国人が身振り手振りで意志を伝えるように、魂のすべてを使って、僕という空虚な器を震わせようとしていた。
一時間後。彼女は筆を落とし、肩で息をしていた。
そこには一枚の絵があった。
僕は、その絵の前に立つ。
白黒の視界。だが――。
ドクン。
心臓が、痛いほど大きく跳ねた。
それは、かつて持っていた感情のどれとも違った。『喜び』のような甘さはない。『悲しみ』のような湿り気もない。
ただ、烈しい『衝撃』。
視神経が焼き切れるかと思うほどの、鮮烈な一撃。モノクロの世界に一滴のインクが垂らされたように、その絵の中心から色が滲み出してくる。
僕が彼女にあげた色ではない。
彼女が僕の中で混ぜ合わせ、熟成させ、彼女自身の魂で濾過した、全く新しい「色」だった。
名前のつけようのない感情が、空っぽの器に注ぎ込まれる。熱い。熱くて、火傷しそうだ。
「……あ」
視界が歪む。頬を何かが伝った。
指で触れると濡れている。舐めると、しょっぱい味がした。
「泣いてるの……? 透くん」
冬花が恐る恐る手を伸ばし、僕の頬に触れる。その手のひらの温もりが、凍りついていた芯を溶かしていく。
失った感情は戻らない。僕が彼女を愛していた記憶も、感覚も、二度と蘇らない。
けれど今、僕の胸には、この絵を描いた彼女に対する強烈な畏敬と、どうしようもない渇望が生まれていた。
それはゼロから始まった、新しい感情の芽吹き。
「……すごい絵だ」
喉が震えた。自分の声が、久しぶりに湿り気を帯びている。
「君の涙の色は……こんなに、熱かったんだね」
僕は震える手で、彼女の手を握り返す。強く。痛いくらいに強く。
灰色の世界が、彼女を中心にゆっくりと色づき始めていた。
かつての世界よりもずっと鮮明で、痛々しく、そして美しい色で。
冬花が泣き笑いのような顔で、僕の胸に崩れ落ちてくる。
その重みを、僕は今度こそ、逃げずに受け止めた。