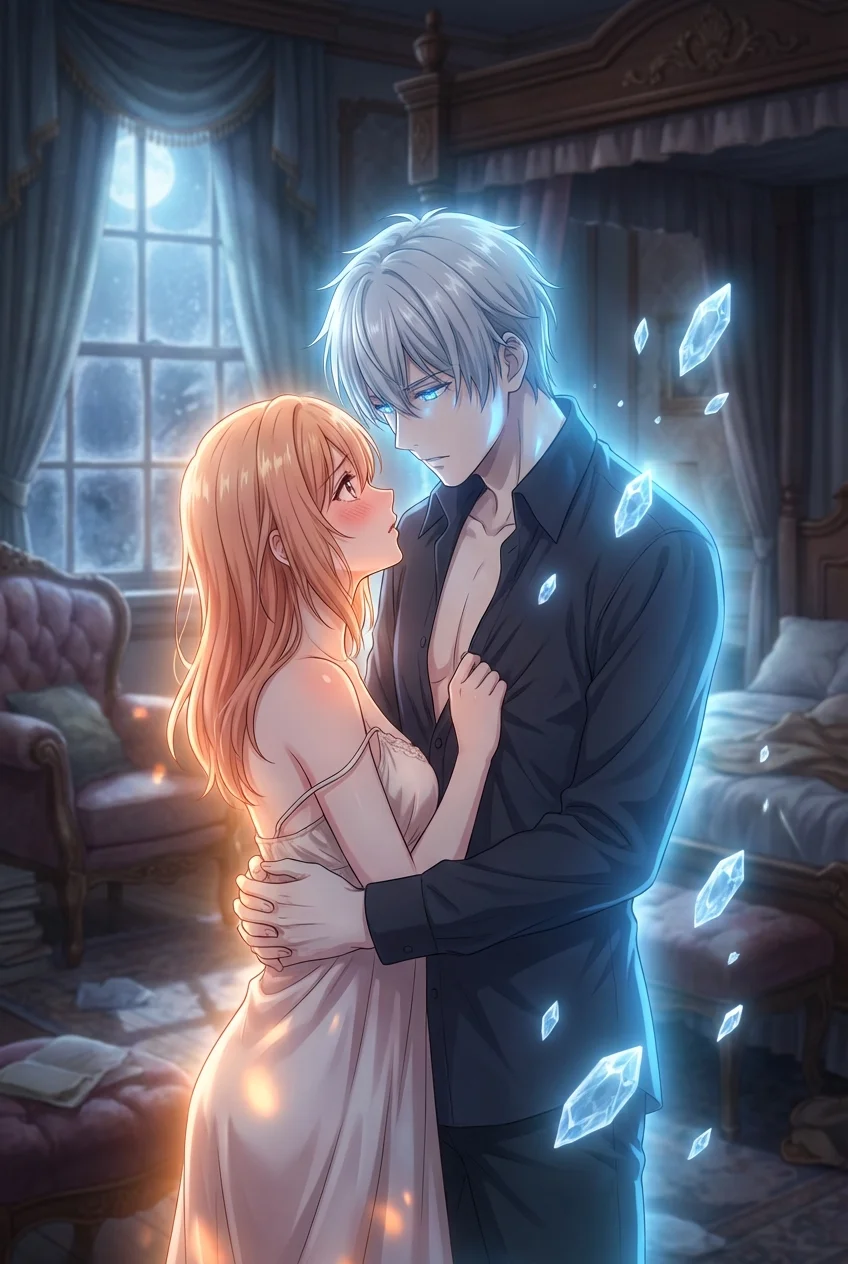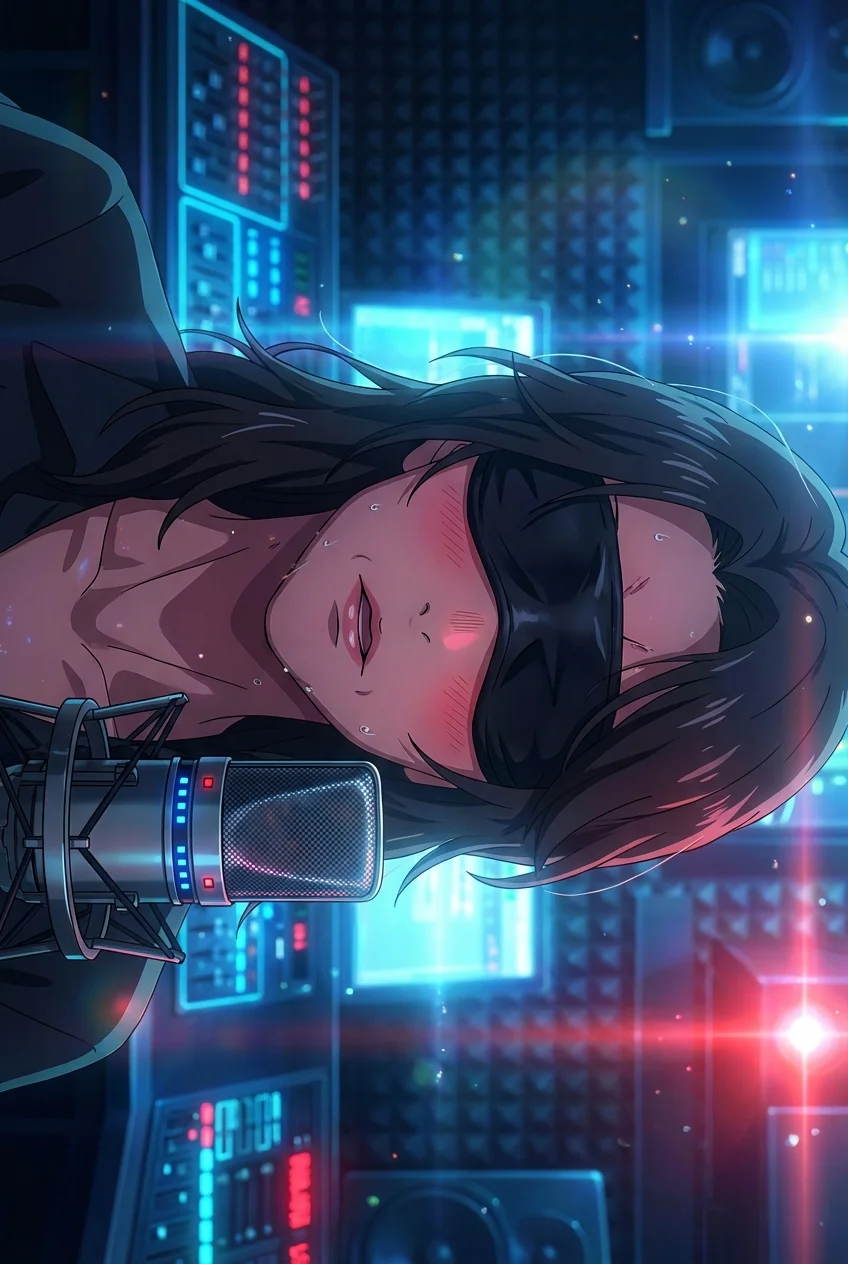第1章: 聖域の汚濁
深夜二時。静寂が支配するはずの講堂。そこに漂う、異質な湿り気。
凪野奏太は、愛用のパーカーのフードを深く被り直し、猫背をさらに丸めて歩を進める。ボサボサの前髪、その隙間から覗くのは、寝不足で充血した、しかし獲物を狙う夜行性の獣のごとき瞳。
手には鈍く光る音叉。一オクターブの永遠を閉じ込め、握られている。
明日のコンクール最終調整、その対象たるスタインウェイ。黒塗りの巨体が鎮座するステージ中央から響くのは、ピアノの旋律ではない。粘着質な水音。
「……あ、っ、……んぅ……!」
空調の切れた講堂の冷気などものともせず、闇を震わせる熱を孕んだ吐息。
凪野は気配を殺し、舞台袖のカーテンを数ミリだけ捲った。
そこにいたのは、この大学の最高権力者、氷室紗季。
昼間、学生たちを射抜いていた氷点下の視線、いわゆる「氷の女王」の姿は、そこにはない。
銀縁眼鏡は汗で鼻梁を滑り落ちかけ、ひっつめられた黒髪のシニヨンが乱暴に揺れる。理知的なスーツは腰から下が無残にはだけられ、露わになった陶器のように白い太腿。
彼女はピアノの響板――最も音が共鳴する心臓部――に、自らの最も柔らかな花芯を押し付けていた。
低音弦を拳で叩くたび、伝わる重厚な振動。それが彼女の秘めたる一点を直撃する。
「あぁっ、いい、音が、……ああっ!」
ビクン、と弓なりに反る背骨。
黒鍵を引っ掻く指、講堂に響き渡る不協和音。その不快な音色さえも、彼女にとっては快楽のスパイスなのか。眼鏡の奥の瞳は焦点が合わず、白目を剥きかけている。口元からは銀色の糸がだらりと垂れ、襟元を汚していた。
規則正しい機械的なピストン運動ではない。音の波に凌辱されるがごとく、痙攣し、貪る姿。
ドォォォォン……。
最後の一撃、最低音のA(ラ)が叩きつけられた瞬間。
硬直する紗季の身体。喉の奥から押し殺した悲鳴が迸る。太腿の内側を、透明な蜜が大量に伝い落ち、磨き上げられた床に小さな水溜まりを作った。
戻る静寂。残る荒い呼吸音。
凪野は無意識に、ポケットの中の音叉を強く握りしめていた。見てはいけないものを見た恐怖? いや、「壊れた楽器」を見つけた時のような、背徳的な興奮が指先を走る。
その時。
弛緩しきっていた紗季が、ふらりと顔を上げた。
眼鏡の奥、潤んだ瞳が正確に凪野の隠れている場所を射抜く。
逃げられない。
凪野が観念して姿を現すと、彼女は慌てて服を直すことすらしなかった。
むしろ、濡れそぼった下半身を晒したまま、紅潮した頬で冷然と言い放つ。
「……そこにいるのは誰」
震える声には、まだ情事の余韻。だが、その態度はあくまで支配者のそれ。
凪野がボソボソと名前を告げる。彼女は乱れた呼吸を整え、命令を下した。
「見なさい、凪野。そして……私の熱を鎮めなさい。まだ、足りないの」
第2章: 秘密の契約
学長室、重厚なオーク材の机の下。そこは外の世界とは隔絶された熱帯の檻。
頭上では、氷室紗季が理事たちと来年度の予算について議論を交わしている。
「……ええ、その件については再考の余地があります。無駄な出費は……っ、抑えるべきかと」
一瞬、詰まる言葉。
机の下で、凪野が音叉を叩いたからだ。
「キィィィィィン……」という440ヘルツの純音。紗季の太腿に押し当てられた柄から骨伝導で直接、骨盤内の深淵へと響き渡る。
「学長? どうかされましたか?」
「いえ……少し、目眩が」
冷静を装う紗季の声。だが机の下では、彼女のヒールが凪野の脛に食い込み、必死に快楽を堪えている。
彼女は「音」に弱すぎる。
皮膚への接触以上に、特定の周波数が神経を撫でるだけで、脳髄は白く弾けてしまうのだ。
凪野は実験を続けていた。
直接触れることはない。ただ、調律師としての卓越した聴覚と指先の感覚で、彼女が最も感じ入る「共鳴周波数」を探り当てる。
昨夜はリムジンの後部座席、エンジンの低周波振動を利用して三度イかせた。今は、音叉の高周波で、理性を薄皮一枚まで削ぎ落とす。
揺れ続ける、スカートの裾から伸びる脚。
凪野は音叉を、膝頭からゆっくりと内腿へ滑らせる。金属の冷たさと微細な振動のコントラスト。
乱れる紗季の呼吸。マイクに入らないギリギリの音量で、喉がヒュウ、ヒュウと鳴く。
「では、この議案は可決ということで……」
「……あっ、許可、します……!」
不自然なタイミングでの承認。
凪野が音叉の柄を、下着越しに、最も熱く濡れた「蕾」へと押し当てた瞬間だった。
ドクン、と金属越しに感じる胎内の脈動。
溢れ出し、凪野の手を汚す大量の愛液。机の縁を白くなるほど強く握りしめ、白目を剥いて絶頂の波に飲み込まれる紗季。
会議終了。退室する理事たちの足音が遠ざかる。
静まり返った部屋、椅子に崩れ落ちたまま荒い息を吐く紗季。
凪野が机の下から這い出すと、彼女は涙で濡れた瞳で彼を睨みつけ、しかし懇願するように足を広げた。
「……次は、もっと低い音で。……命令よ」
無表情のまま、命令に従うふりをして噛み殺すサディスティックな笑み。
この高潔な女王は、もう自分の奏でる音なしでは生きられない。
「チューニングが狂っていますね、学長。……深く、調整が必要です」
第3章: 仕組まれた性具
「……父は、私を『完成品』にしたかったのよ」
事後の倦怠感の中、紗季が漏らした独白。それは凪野の想像を超えた狂気を孕んでいた。
幼少期からの英才教育。絶対音感を植え付けるための、特殊な周波数を流し続ける防音室での監禁。彼女の性感帯は、肉体ではなく、鼓膜と脊髄に書き換えられていたのだ。
それは教育ではない。音響による調教。
「だから私は、音楽に犯され続けている」
凪野は初めて同情に近い感情を覚えた。彼女もまた、壊された楽器だったのだ。
だが、その秘密を知る者は二人だけではなかった。
古株の理事、権藤巌。脂ぎった禿頭の男は、紗季の異常な反応に勘付いていた。
彼が学園創立記念式典のために用意したのは、現代音楽界の巨匠による新作『深淵の祝祭』。
一見、荘厳な楽曲。だが、そのスコアを見た凪野は戦慄した。
そこに含まれていたのは、紗季のトラウマを最も強く刺激する不協和音と、彼女を発情させる特定の超低周波。
しかも、式典は全国に生中継される。
数千人の聴衆、そしてカメラの前で、この曲が演奏されればどうなるか。
紗季は理性を保てない。公衆の面前で、獣のように床をのた打ち回り、蜜を垂れ流して絶頂に達するだろう。
社会的な死刑宣告。権藤による最も陰湿な公開処刑。
「凪野くん、君には当日の調律を外れてもらうよ」
権藤はねっとりとした声で告げた。「代わりに、私が手配した『特別な調律師』が担当する」
式典まであと三日。
何も知らず、完璧なスピーチを準備する紗季。
彼女を守るためには、演奏を止めるしかない。だが、どうやって?
凪野は自室で、権藤から渡されたスコアを握りつぶした。
(直せないなら、壊すしかない)
職人としてのプライドと、歪んだ所有欲。火花を散らす二つの感情。
第4章: 崩壊する理性
式典当日。三千人の来賓と学生、無数のカメラで埋め尽くされた大ホール。
ステージ中央、スポットライトを浴びて立つ氷室紗季。これ以上ないほど美しく、冷徹。
純白のドレスは彼女の潔癖さを象徴しているようだが、その下で肌が粟立っていることを凪野だけが知っていた。
「それでは、記念演奏『深淵の祝祭』です」
振り下ろされる指揮棒。
第一音が鳴り響いた瞬間、ビクリと跳ねる紗季の身体。
計算され尽くした不協和音が、神経回路を焼き切るように侵食する。
最初は微かな震えだった。だが、曲が進行し、問題の低周波パートに差し掛かると、蒼白だった顔色は一気に紅潮へと転じる。
白く変色するほど強く握りしめられるマイクスタンド。
笑う膝。立っていられない。
「あ……、っ、ぁ……」
マイクが拾ってしまった、漏れ出る喘ぎ声。ざわめく会場。
最前列で、下卑た笑みを浮かべてその様子を眺める権藤。
消えかける理性の光。ドレスの裾が濡れ色に染まり始めるのも時間の問題。
もう限界だ。
舞台袖で待機していた凪野は、工具袋からニッパーを掴み取った。
警備員の制止を振り切り、ステージへと疾走する。
「やめろ! 何をする気だ!」
「そこをどけぇぇぇッ!!」
普段の彼からは想像もつかないような絶叫。ピアニストを突き飛ばす。
そして、ピアノの内部に手を突っ込み、張り詰めた弦を――切断した。
バヂィィィィン!!
ホールを裂く破裂音。
一本、また一本。凶器と化したピアノ線が凪野の頬を切り裂き、鮮血が鍵盤に散る。
止まる音楽。
静まり返る会場。
破壊されたピアノの前に立ち尽くす血まみれの凪野。崩れ落ちて荒い息を吐く紗季。
交錯する二人の視線。
紗季の瞳にあったのは、助かったという安堵と、大切な楽器を壊された絶望。
「……連れて行け!」
権藤の怒声。凪野を取り押さえる数人の警備員。
床に押さえつけられながら、凪野は紗季を見つめ続ける。
彼女は守られた。だが、その代償はあまりにも大きい。
唯一、自分を「調律」してくれる存在を、彼女は今、失ったのだ。
「……凪野……っ」
動く紗季の唇。だが、その声は誰にも届かない。
ただ、壊されたピアノと、連行される男を、濡れた瞳で見送ることしかできなかった。
第5章: 永遠の共犯
業界追放。
それが凪野に下された審判。
荷物をまとめた段ボールが積まれた、安アパートの六畳一間。明日の朝には、この街を出なければならない。
ズキズキと痛む頬の切り傷。だが、それ以上に胸に空いた穴が大きかった。
深夜、静かなノック音。
返事をする間もなく開く扉。
立っていたのは、深いフードを目深に被った女――氷室紗季。
「……学長」
「その呼び方はやめて」
部屋に入るなり鍵をかけ、フードを取り払う。
乱れた髪、充血した目。あの完璧な氷の女王の面影はない。
無言のまま脱ぎ捨てられるコート、引き裂くように脱がれる絹のブラウス。
露わになった白い肌は、渇望で桜色に染まっている。
「私を壊して」
涙を流しながら、凪野に縋り付く紗季。
「私を直して。……あなたがいないと、音が、止まないの」
彼女の身体は、あの式典の残響にまだ苛まれていた。未処理の快楽と恐怖、その暴走。
凪野は彼女の震える肩を抱き寄せた。
自分もまた、彼女という楽器なしでは生きられないのだと悟る。
「……いい音を、響かせてください」
その夜、凪野は彼女を「調律」した。
道具も、音叉も使わない。自らの指と、舌と、熱い楔で。
薄い壁を震わせる、悲鳴にも似た嬌声。
「あぁっ、そこ、壊れちゃう、凪野、凪野ぉぉッ!!」
何度も意識を飛ばし、そのたびに音と痛みで引き戻す。
溶け合う互いの境界線。雌と雄、楽器と演奏家が一つになる、長く濃密な夜。
翌日。
大学の理事会は騒然としていた。
権藤理事が、過去の横領と未成年者へのハラスメントの証拠を突きつけられ、失脚したのだ。
告発者は、氷室紗季。
一夜にして冷徹さを取り戻した彼女は、反対勢力を一掃し、新たな人事を発表した。
「学長専属技術顧問として、凪野奏太氏を招聘します」
ざわめく会議室、新しい眼鏡のブリッジを指で押し上げる紗季。
その背後には、傷の癒えない頬で佇む凪野の姿。
表向きは、厳格な女主君と、無口な技術者。
だが、すれ違いざま、凪野が指をパチン、と鳴らす。
その乾いた音だけで、紗季の肩がビクリと跳ね、膝が崩れそうになるのを、誰も知らない。
表情は氷のように冷たいままだが、スーツの下では、条件反射で蜜が溢れ出しているのだ。
「……あとで、たっぷりと調整が必要ですね」
凪野の囁きに、紗季は頬を赤らめ、潤んだ瞳で彼を睨みつけた。
「……ええ。覚悟しておきなさい、私の調律師」
それは、二人だけの、永遠に終わらない協奏曲の始まり。
(了)