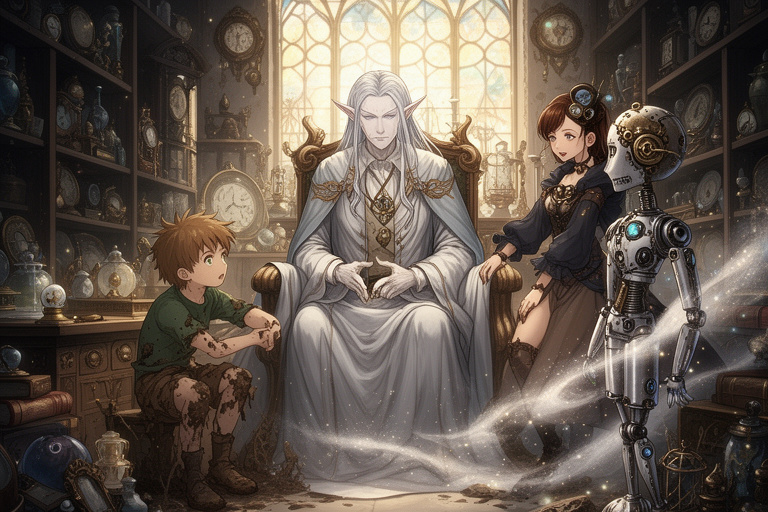第1章: 静寂の掃除人
「……同接、ゼロ人。結構。これは遺書代わりだ」
湿り気を帯びた地下の大気。錆びた肺を撫でるその感覚だけが、生の実感。
俺はスマートフォンのインカメラに向け、強張った唇の端を吊り上げた。画面に映るのは、油と泥が幾層にもこびりつき、元の色が判別できない灰色の作業用ツナギ。首元で冷たく揺れるドッグタグ、それだけが辛うじて金属の光沢を放っている。
視界を遮るボサボサの黒髪。油で汚れた手袋の甲で、乱暴に払いのける。その隙間から覗くのは、何日も睡眠を拒絶したような濃いクマと、水底に沈んだ小石のように光を失った瞳。
「よし、始めましょうか」
独り言が、広大な空洞に吸い込まれていく。
足元には、岩盤のように硬質な黒い大地がどこまでも広がっていた。俺は腰から使い古したデッキブラシを引き抜き、足元の「大地」にこびりついた蛍光色の粘液をこすり始める。
ゴシッ、ゴシッ。
反響する乾いた音。
ここは深度999層。本来なら、人間が呼吸をしているだけで肺胞が破裂する致死圏。だが、俺にとってここは職場であり、同時に自宅の庭のようなもの。
『ん? なにこの配信』
『画面暗すぎワロタ。また底辺探索者の売名かよ』
不意に点滅する通知ランプ。迷い込んだ視聴者が一人、二人。
俺はブラシの手を止めず、淡々と呟く。
「ここは足場が悪いですね。フジツボ型の寄生種が繁殖しすぎている。これじゃあ、彼が痒がるわけだ」
『彼? 誰だよ』
『っつーか後ろの山脈、グラフィックすごくね? 合成?』
流れるコメント。
俺はため息を一つつき、ブラシの柄で足元の「大地」をトン、と叩いた。
「おい、起きろ。背中、流してやってるんだぞ」
瞬間。
揺らぐ世界。
地鳴りではない。空気が圧縮され、空間そのものが軋む音。
背景だと思われていた巨大な「山脈」が、ゆっくりと隆起する。岩肌に見えたものは超硬質の外殻。頂上だと思われていた場所には、都市一つを飲み込めるほどの巨大な噴気孔が開いていた。
『おい嘘だろ』
『山が……動いてる?』
『待て、あの足元の地面、まさか……』
俺が立っているのは大地ではない。
全長数キロメートルに及ぶ災厄級モンスター、『虚無の鯨』の背中。
鯨が低周波の鳴き声を上げ、空洞内の大気が振動する。俺はその振動を足の裏で受け流し、剥がれ落ちた寄生種をゴミ袋に放り込んだ。ついでに、背鰭の隙間に突き刺さっていた「異物」を引き抜く。
黄金に輝く刀身。柄には豪華な宝石。
国宝級と謳われる聖剣『エクスカリバー・イミテーション』。
「……ハァ。また人間がゴミを捨てていった」
眉間の皺を深くし、その聖剣を無造作に「燃えないゴミ」の袋へ。
「汚したら、片付ける。それがルールでしょう」
袋の口を縛り、鯨の噴気孔へ蹴り落とす。鯨が気持ちよさそうに蒸気を吹き上げたその時、頭上から刺すような人工の光が降り注いだ。
◇◇◇
第2章: 偽りの英雄、沈黙の庭師
「おいおいおい! まだそんな薄暗い場所で這いつくばっているのかい? ドブネズミ君!」
鼓膜を劈くような高笑いと共に、炸裂するスポットライトのような閃光魔法。
闇に慣れた網膜が灼かれる。俺は目を細め、光の源を見上げた。
そこに立っていたのは、太陽そのもの。
いや、太陽の模造品。
髪の一本一本まで計算されたような金色の巻き毛が、風もないのにふわりと揺れている。顔の造作は陶器のように整い、碧眼はカメラのレンズだけを見つめていた。身に纏うのは、実戦には不向きなほど磨き上げられたプラチナアーマー。背中には、自身の身長ほどもある巨大な装飾剣。
地上最強の英雄パーティ『グロリアス』のリーダー、レオン・スターリング。
「葛原さん……その、まだ掃除が終わっていらっしゃらないのですか?」
レオンの背後から、純白のローブを翻して現れる少女。
銀の長髪が聖女の光輪のように輝き、アメジスト色の瞳が心底あわれむように俺を見下ろしていた。アイリス。かつて俺が瓦礫の下から引っ張り出し、食料を分け与えた少女は、今や教皇庁の顔だ。
「……何の用ですか。ここは立ち入り禁止区域のはずですが」
俺はツナギについた汚れを払いもしない。
レオンは鼻をつまみ、大げさに顔をしかめた。
「臭うんだよ、君は! 映えない! 僕たちの栄光の配信に、君のようなシミが映り込むのは損失なんだ!」
レオンが指を鳴らすと、宙に浮いたドローンカメラが彼をクローズアップする。
「視聴者の諸君! 見たまえ、この不衛生な男を! ダンジョンの管理などと嘯き、実際にはモンスターの排泄物を漁っているだけの寄生虫だ! 今日、我々『グロリアス』はこの男を、正式にダンジョンから追放する!」
『うわ汚っ』
『レオン様かっこいい!』
『早くその乞食追い出せよw』
空中に投影されたコメント欄が、賛美と罵倒で埋め尽くされる。
俺はドッグタグを握りしめた。掌に食い込む金属の冷たさだけが、理性の楔。
彼らが倒してきたとされる「魔王級」の怪物たち。
それらは全て、俺が事前に鎮静化させ、戦意を削いでおいた個体。レオンが剣を振るう頃には、それらはただの肉塊か、眠りにつく直前の赤子同然だった。
だが、それを言ったところで誰が信じる?
画面の中の俺は、薄汚れた清掃員。彼らは、光り輝く英雄。
「アイリス、君もそう思うか」
「……ええ。葛原さん、あなたはもう不要なのです。この神聖な場所には、相応しい方々がいるのですから」
聖典を胸に抱き、一度も俺と目を合わせない。その白いローブの裾が、泥に触れるのを嫌悪するように少し持ち上げられているのを見た時、俺の中で何かがプツリと切れた。
期待していたのだ。どこかで。
誰か一人は、俺の仕事を見てくれていると。
「……そうですか」
俺はデッキブラシを地面に突き立てた。
「なら、あとは頼んだ」
腰の端末を取り出し、『管理者権限:放棄』のボタンを押す。
明滅を始める赤い警告灯。
「え? ……あ、ああ! 当然だ! さっさと消えたまえ!」
レオンが勝利のポーズを取り、跳ね上がる視聴数。
俺は背を向け、暗闇へと歩き出した。背後で、鯨が不安げに唸り声を上げた気がしたが、もう振り返らない。
足音が遠ざかるにつれ、俺の心臓は奇妙なほど静かに、そして冷たく脈打っていた。
世界がどうなろうと、もう知ったことではない。
だが、俺がエリアの境界線を越えたその瞬間――背後の大気が、凍てついた。
◇◇◇
第3章: 崩壊する庭
ドクン。
ドクン。
心臓の鼓動ではない。
ダンジョンそのものの脈動。
『GRAAAAAAAAAAAAAAA!!』
空気が破裂するような咆哮が、地下空洞を揺るがした。
俺が管理権限を手放した瞬間、深淵に張り巡らされていた数千の「鎖」――モンスターの攻撃性を抑制していた結界――が、一斉に砕け散ったのだ。
振り返る必要すらない。
背後で、レオンの高笑いが引きつった悲鳴に変わるのが聞こえた。
「な、なんだ!? なぜ動く!? こいつは眠っていたはずだろ!?」
「いやぁぁぁ! 聖壁が、結界が効きませんわ!!」
俺のスマホ画面には、置き去りにされたドローンカメラの映像が流れていた。
さっきまで大人しかった『虚無の鯨』が、その巨体をねじらせ、背中の上の「ゴミ」を振り払おうとしている。レオンのプラチナアーマーが紙屑のようにへしゃげ、自慢の装飾剣がへし折れる。
「か、葛原ッ! おい! 戻ってこい! こいつを止めろ! 命令だ!!」
画面の中のレオンは、鼻水を垂らし、泥水の中を這いずり回っていた。完璧だった金髪は汚物まみれになり、カメラに向かって手を伸ばしている。
『え、なにこれ』
『演出?』
『いや、腕ちぎれてね?』
『グロすぎ、BANされるぞ』
画面をスワイプし、配信を切る。
地上へのエレベーターホール。錆びついた鉄扉が開く。
地上に出ると、そこは夕暮れだった。
だが、その赤さは夕陽のせいではない。
ダンジョンの入り口から溢れ出した下級モンスターたちが、街を火の海に変えていた。
「おい、お前! ダンジョンの管理人だろ!?」
避難する群衆の中から、石礫が飛んできた。
ゴッ。
額に鋭い痛みが走り、熱い液体が視界を赤く染める。
「お前のせいだ! お前がちゃんと管理してねえから!!」
「役立たず! 死ね! 疫病神!」
かつて俺が命がけでトラップを解除し、生存ルートを確保してやった街の住人たち。
彼らの瞳にあるのは、感謝ではなく、純粋な憎悪だけ。
「……仁」
群衆の影に、幼馴染の姿。
彼女なら。彼女だけは。
俺は血に濡れた手を伸ばしかけた。
だが、彼女は怯えたように後ずさりし、近くにいた男の背中に隠れた。
その瞳は、俺を人間ではなく、汚らわしい怪物を見る目。
ああ。
そうか。
俺の胸の奥で、最後の明かりが消えた。
指先から力が抜け、スマートフォンがアスファルトに落下する。
俺はそれを、安全靴の踵で迷いなく踏み砕いた。
バキリ、という音と共に、断たれる世界との繋がり。
「もう、いい」
喉から絞り出した声は、掠れて誰にも届かない。
「僕の仕事は、終わった」
崩れ落ちるビルの影が、俺を覆い尽くす。
瓦礫の轟音と、人々の悲鳴。
俺は目を閉じ、その暗闇を、安らかな毛布のように受け入れた。
◇◇◇
第4章: 深淵からの愛
ブラックアウトした世界。
だが、世界中の端末から流れる配信は止まっていなかった。
『信号途絶……復旧中……』
『接続再開』
ノイズ交じりの画面に、再び映像が戻る。
しかし、そこには華やかな英雄も、逃げ惑う人々も映っていなかった。
映し出されたのは、瓦礫の下敷きになった俺――葛原仁の姿。
そして、それを取り囲む異形の影たち。
『ヒッ、怪物だ……あいつ食われるぞ』
『もう死んでるだろ』
視聴者が息を呑む中、一匹の巨大な影が動いた。
刃のような牙を持つ漆黒の狼、『ヴォルグ・フェンリル』。本来なら一噛みで戦車を噛み砕く捕食者。
その狼が、瓦礫を前足で掘り返している。
乱暴にではない。まるで壊れ物を扱うように、慎重に、優しく。
邪魔な鉄骨を牙で咥えてどけ、俺の身体を瓦礫の中から引きずり出す。
狼は、血まみれの俺の顔を、ザラザラとした舌で舐めた。
一度、二度。
それは捕食の合図ではない。傷口の汚れを拭い、体温を分け与える行為。
『……え?』
『何これ、どういうこと?』
続いて、空から降りてくる巨大な影。
第1章で暴れていたはずの『虚無の鯨』だ。その巨体を小さく圧縮し、俺の周囲に防壁のように身体を横たえる。
スライム状の怪物が俺の裂傷を覆い、献身的な止血を開始した。
ドライアドが枯れたコンクリートの隙間から花を咲かせ、俺の頭を膝枕のように支えていた。
画面の向こうから、嗚咽のような音が聞こえてきた。
それは、言葉を持たない彼らの、魂からの慟哭。
『ウウゥゥゥゥ…………』
人間たちが石を投げ、唾を吐きかけた男。
その男を、怪物たちが守り、慈しみ、涙を流している。
その光景は、あまりにも残酷で、そして聖画のように美しかった。
『俺たち、何てことを……』
『英雄なんて嘘っぱちだったんだ』
『彼が、ずっと守ってくれてたのに』
コメント欄を埋め尽くす懺悔の言葉。絶叫。
だが、もう遅い。
俺の瞼が、微かに震えた。
死んだ魚のようだった瞳に、光が宿る。
だがそれは、かつてのような「人としての光」ではない。
底なしの深淵。
あらゆる光を飲み込み、静寂をもたらす王の瞳。
「……うるさいですね」
俺が呟くと、慟哭はぴたりと止んだ。
甘えるように喉を鳴らし、俺の首筋に鼻を擦り付ける狼。
俺はゆっくりと身体を起こした。
ツナギはボロボロで、血と泥にまみれている。
だが、その姿は、プラチナアーマーを着たどの英雄よりも、圧倒的に「王」だった。
俺は、瓦礫の山の上に立ち、カメラを見つめた。
いや、カメラの向こうにいる、全人類を見下ろした。
「庭が荒れています」
静かな声。だがそれは、全世界のスピーカーを震わせた。
「大掃除の時間だ」
俺が指を鳴らすと、背後の闇が一斉に牙を剥いた。
それは侵略ではない。
彼らにとっての「害虫駆除」が、今、始まる。
◇◇◇
第5章: 深淵の庭師、世界を解雇する
阿鼻叫喚の地獄絵図となるはずだった。
だが、現実はあまりにも静かだった。
俺が率いる「庭」の住人たちは、人間を殺さなかった。
ただ、徹底的に「排除」した。
武器を持つ者からは武器を奪い、鉄屑に変える。
罵声を浴びせる者の口は、粘着質の糸で封じ込めた。
逃げ惑う群衆は、巨大な蔦の檻で優しく、しかし強引に安全圏へと隔離していく。
「やめろ! 俺は英雄だぞ! レオン・スターリングだぞ!」
瓦礫の山から這い出してきたレオンが、折れた剣を振り回す。
その鎧は見る影もなく汚れ、顔は恐怖と屈辱で歪んでいる。
俺は彼の前まで歩み寄った。
「葛原……! た、頼む、助けてくれ! 謝る! 謝るから! 俺をまた、輝かせてくれ!」
俺の足元に縋り付く英雄。
俺は、彼を見下ろす。侮蔑も、哀れみも、怒りすらない。
ただ、燃えないゴミを見る目。
「ルールは守りましょう、レオンさん」
俺は彼の襟首を掴み、軽々と持ち上げた。
「ゴミは、ゴミ箱へ」
そのまま彼を、ダンジョンの外――「人間界」という名の隔離施設へと放り投げた。
アイリスも、教皇庁の連中も、すべて同様に処理された。
数時間後。
地上に溢れていたモンスターたちは、すべて俺の後ろに従っていた。
境界線に立つ俺の前には、武装解除された人類が、ただ震えて平伏している。
「本日をもって、ダンジョンへの立ち入りを全面禁止します」
淡々とした宣言。
「あなたたちは、この庭に相応しくない。二度と、私の視界に入らないでください」
展開される巨大な結界。
二つの世界を完全に分断する、絶対不可侵の壁。
人類は、資源も、魔法も、英雄という娯楽も失った。
残されたのは、自分たちが追放した男への後悔と、凡庸で退屈な平和だけ。
◇◇◇
あれから、どれくらいの時が流れただろうか。
かつてのダンジョン配信チャンネル。
今はもう、誰もコメントを書き込むことはできない。
だが、世界中の人々が、その画面を見つめ続けている。
映し出されているのは、地底とは思えないほど美しい花畑。
蛍光色の花々が咲き乱れ、穏やかな光に満ちていた。
その中心で、一人の男が眠っている。
灰色のツナギは新しいものに変わり、ボサボサだった髪は、膝枕をするドライアドの手によって優しく梳かれていた。
足元にはフェンリルが丸くなり、空には鯨がゆったりと泳ぐ。
男の顔には、かつての険しい皺も、死んだような陰りもない。
微かな寝息を立てるその表情は、子供のように穏やかだ。
『庭師』は、もう起きない。
彼は今、誰にも邪魔されない終わりなき休日を過ごしている。
人類は、そのあまりにも美しい寝顔を、涙ながらに見守り続けることしかできない。
画面の向こうの楽園は、もう二度と、彼らの手には届かないのだから。
<終>