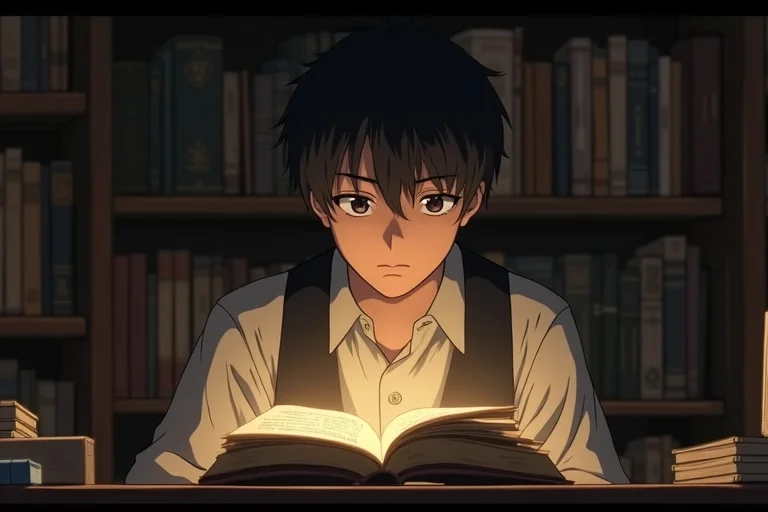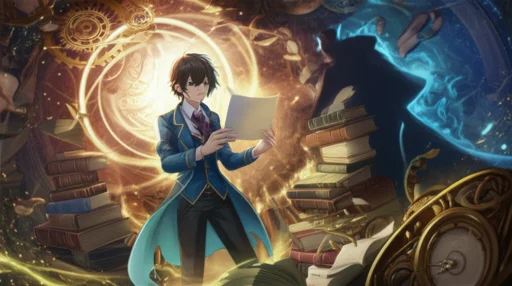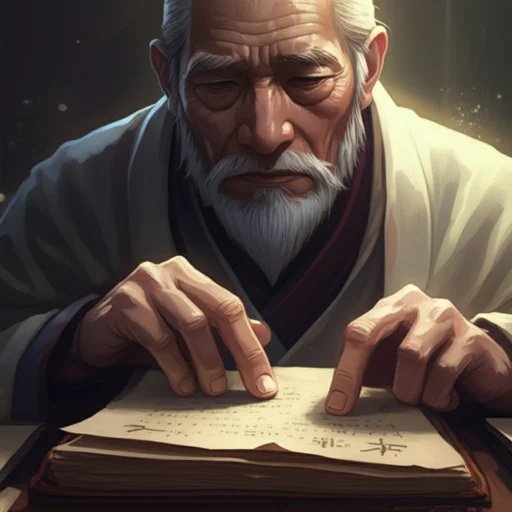第一章 埃をかぶった声
古書店『不知堂(しらずどう)』の空気は、いつも紙の乾いた匂いと、インクのかすかな甘み、そして時間の澱(おり)のような埃っぽさで満ちていた。店主の祖父から店番を任されている桐谷朔(きりたに さく)は、その澱んだ空気の中で、歴史の重みではなく、ただの退屈を感じていた。大学で歴史学を専攻したものの、年号と事件を暗記するだけの学問に嫌気がさし、今では歴史書も単なる古い紙の束としか思えなくなっていた。
その日、店の古びたドアベルがちりん、と寂しげな音を立てた。入ってきたのは、見慣れない老婆だった。皺の深い手に、風呂敷に包まれた小さな塊を大事そうに抱えている。
「これを…買い取っていただけますでしょうか」
差し出されたのは、一冊の古びた手帳だった。濃紺の布張りの表紙は角が擦り切れ、ところどころ色褪せている。朔は事務的な手つきでそれを受け取った。買い取り価格など、たかが知れている。そう思った、その瞬間だった。
指先が布地に触れた途端、脳裏に閃光が走った。
──蝉時雨。白の日傘。カンカン帽の男の、少しはにかんだ横顔。
「……っ!」
思わず手帳を落としそうになり、朔は息を呑んだ。幻覚か。疲れているのだろうか。訝しみながらも、もう一度、そっと手帳に触れる。すると今度は、鈴を転がすような、しかしどこか切なげな若い女性の声が、頭の中に直接響いてきた。
『健司さん、お待ちしておりましたのに』
その声は、明確な言葉でありながら、記憶の断片のように朔の意識を通り過ぎていく。知らないはずの風景。知らないはずの声。だが、そこには確かな感情の温度があった。焦がれるような、甘い痛み。
「どうかなさいましたか?」
老婆の問いかけに、朔ははっと我に返る。
「いえ、なんでもありません。少し、古いもののようですので…」
動揺を押し殺し、朔は震える手で数枚の紙幣を渡した。老婆は深々と頭を下げると、静かに店を去っていった。
一人残された店内で、朔は改めて手帳を凝視した。それはただの古びた手帳ではない。何かが、おかしい。彼の冷え切った日常に、ありえないはずの亀裂が入った瞬間だった。彼はその夜、店の明かりを消した後も、その手帳から目が離せなかった。表紙を開けば、インクで綴られた流麗な文字が目に飛び込んでくる。『大正十一年四月 小夜子』と。
第二章 小夜子の日記
手帳に触れるたび、朔は小夜子という名の女学生の記憶へと誘われた。最初は途切れ途切れだった映像と声は、次第に鮮明な物語となって朔の中に流れ込んでくる。
銀座のモダンなカフェで友人と笑い合う声。浅草六区の賑わい。ハイカラな洋装と、伝統的な着物が入り混じる帝都の喧騒。それらは、朔が教科書で学んだ無味乾燥な「大正時代」とは全く違っていた。人々の息遣いが、活気が、そして匂いまでもが、五感を通して生々しく伝わってきた。
小夜子は、華族の娘だった。厳格な父のもと、女学校に通い、良妻賢母となるべく教育を受けていた。しかし彼女の心は、家の決めた許嫁ではなく、大学で文学を学ぶ青年、健司に向けられていた。
『健司さんの語る未来は、いつも星のように輝いておりました。新しい社会、誰もが自由に学べる世界。その瞳を見ていると、私のこの窮屈な世界まで、光が差すような心地がするのです』
朔は、小夜子の喜びを、自分のことのように感じた。健司と偶然を装って言葉を交わせた日の高揚感。彼のくれた一冊の詩集を、夜ごと胸に抱いて眠る切なさ。歴史上の人物、名もなき一人の少女が、自分と同じように恋に胸を焦がし、未来に夢を抱いていた。その当たり前の事実に、朔は心を強く揺さぶられた。埃をかぶった記録の奥に、こんなにも鮮やかな生命が脈打っていたのだ。
だが、日記のページをめくるにつれて、物語には影が差し始める。健司が参加しているという「読書会」が、思想的な集まりであり、特別高等警察に目をつけられているらしいという噂。健司の表情から、時折、明るさが消えるようになったことへの小夜子の不安。
『この国の行く末を案じておられるのです、と健司さんは仰いました。けれど、その瞳の奥には、私には分からない深い憂いが宿っているように見えて、胸が締め付けられます』
時代という、抗いがたい大きな奔流。朔は、教科書の一行で片付けられていた「社会不安の増大」という言葉の裏に、引き裂かれようとしている若い恋人たちの、無数の悲しみがあったことを知った。彼はもはや、ただの傍観者ではいられなかった。小夜子の幸せを、心から願っていた。
第三章 百年後の答え
小夜子と健司の運命がどうなったのか。その結末を知りたい一心で、朔は憑かれたように動き始めた。かつてあれほど嫌悪した図書館に通い詰め、当時の新聞や資料を読み漁る。失われたはずの歴史への探求心が、熱を帯びて蘇っていた。
手帳の記述は、大正十二年(1923年)八月の終わりで、不穏な色合いを増していく。健司が警察に追われ、身を隠していること。小夜子が、彼を助けたい一心で、密かに連絡を取り合っていること。
そして、日記の最後の一枚。日付は、九月一日。
『健司さんに会います。今日を逃せば、もう二度と会えなくなるやもしれぬ。たとえ、この身がどうなろうとも』
その文字は、明らかに焦りと恐怖で震えていた。その日、何が起きたのか。朔は知っている。関東大震災。帝都を壊滅させた、未曾有の大災害だ。
最後のページには、インクが滲み、紙が破れかけていた。鉛筆で殴り書きされたような、絶望的な言葉。
『黒い煙。悲鳴。…ああ、健司さん、どうか、未来で笑っていて』
そこで記述は途絶えていた。
朔は、愕然とした。震災の混乱の中、官憲による社会主義者の虐殺があったことは、歴史の闇として知られている。小夜子は、健司を庇い、命を落としたのだ。そうとしか考えられなかった。未来で笑っていて、という言葉が、彼女の最後の願いだったのだ。朔の胸に、どうしようもない無力感と悲しみがこみ上げた。なんという残酷な結末だろうか。
数日後、あの手帳を売りに来た老婆が、再び店に現れた。朔は、意を決して声をかけた。
「あの手帳ですが…差し支えなければ、持ち主だった方のことを教えていただけませんか」
すると老婆は、少し驚いたように目を丸くし、それから懐かしそうに目を細めた。
「あれは、私の祖母の日記です。小夜子、という名前でした」
「……え?」
朔は、耳を疑った。
「祖母は、関東大震災で想い人を亡くしたそうです。ですが、その後、祖父と出会い、結婚して、私の母を産みました。とても気丈な人でしたよ」
老婆は、静かに続けた。
「でも、晩年はよく、窓の外の空を見上げて、ぽつりと知らない男性の名前を呼んでいました。『ケンジさん』と…。あの日記を読んで、やっと、誰のことだったのか分かりました」
朔は、雷に打たれたような衝撃で、その場に立ち尽くした。
小夜子は、生きていた。健司だけが、あの震災の日に命を落としたのだ。彼女は、最愛の人を失った絶望の淵から、それでも立ち上がり、全く別の人生を、最後まで生き抜いたのだ。朔が体験した切ない記憶は、彼女がその長い生涯、たった一人で胸の奥に封じ込めてきた、叶わなかった恋の残響だったのだ。
歴史の結末は、悲劇でも喜劇でもない。ただ、どうしようもなく続いていく、人の生の営みそのものだった。朔は、自分の価値観が根底から覆されるのを感じた。
第四章 刻の栞
朔は、丁寧に修復した手帳を老婆に返した。老婆は深く感謝し、「祖母も、喜んでいると思います」と言って店を去った。
一人になった朔は、窓の外を流れる車の群れと、行き交う人々を眺めた。何気ない現代の風景。だが、今の彼には、その風景が全く違って見えた。このアスファルトの下には、小夜子が見た土の道が埋まっている。このビルが建つ前には、彼女が歩いたであろう木造の家々が並んでいた。全ての日常は、無数の過去の上に成り立っている。
朔は、店の一番奥にある、埃をかぶった古書の山に歩み寄った。一冊一冊が、誰かの人生の断片に見えた。この歴史書を書いた学者にも、この小説を夢中で読んだ少女にも、この哲学書に救いを求めた青年にも、それぞれのかけがえのない物語があったはずだ。歴史とは、年号や事件の羅列ではない。伝えられなかった言葉、叶わなかった願い、それでも懸命に生きた名もなき人々の、声なき声の集積なのだ。
彼は、一冊の古書を手に取った。そして、かつては無造作に払っていたその表紙の埃を、まるで宝物に触れるかのように、指先で優しく拭った。彼の目には、もう以前のような冷めた光はなかった。そこには、果てしない時間への畏敬と、その中に埋もれた無数の物語への、静かで深い愛情が宿っていた。
人は皆、歴史という壮大な物語の中に挟まれた、一枚の栞なのかもしれない。朔は、そう思った。小夜子という栞が、百年という時を超えて、彼の心に物語を届けてくれたように。
いつか、自分が生きるこの時代も、誰かの心を揺さぶる「歴史」になる日が来るのだろう。朔は、窓から差し込む夕陽に目を細め、静かに微笑んだ。不知堂の澱んだ空気は、いつしか彼にとって、数えきれない魂の息遣いが聞こえる、愛おしい場所に変わっていた。