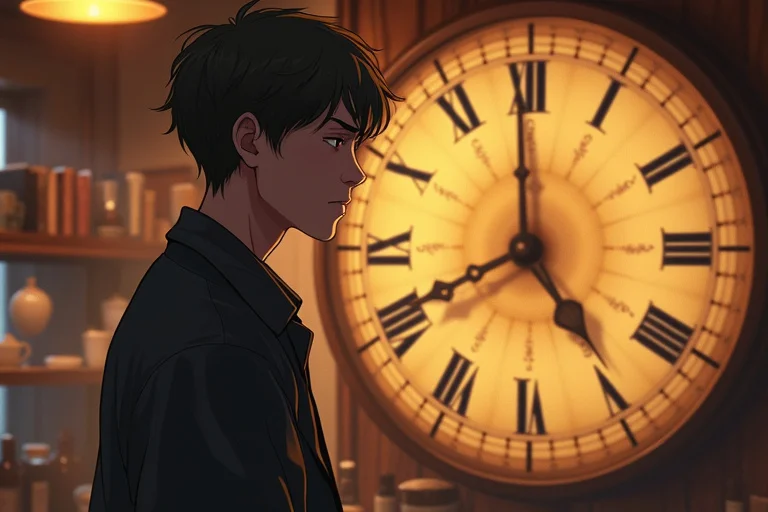第一章 郵便受けの侵入者
高槻健人にとって、日常とは完璧に調律された楽器のようなものだった。午前六時半に寸分違わず鳴るアラーム。豆のグラム数を精密に測って淹れるコーヒー。七時から三十分間の、いつもと同じ公園を巡るウォーキング。彼の世界は、予測可能で論理的なルーティンによって構築され、その堅牢な城壁の中で、健人はシステムエンジニアとして静かな安寧を享受していた。変化はバグであり、曖昧さはノイズだ。彼はそう信じて生きてきた。
その完璧な楽譜に、最初の不協和音が紛れ込んだのは、ある火曜日の朝のことだった。
いつものように郵便受けを開けた健人の目に、信じられないものが飛び込んできた。新聞と数枚のダイレクトメールに紛れて、鮮やかなオレンジ色のガーベラが一輪、まるでそこが定位置であるかのように収まっていたのだ。茎は短く切られ、誰かの手で丁寧に置かれたことが明らかだった。差出人を示すものは何もない。
健人は眉をひそめた。悪戯か、何かの勧誘か。彼はその花を指先でつまみ上げ、ゴミ箱に直行させた。非論理的な侵入者は、彼の日常から即刻排除されなければならない。しかし、その指先に残った、しっとりとした花びらの感触と、鼻腔をかすめた微かな青い香りが、妙に心に引っかかった。
翌日、そこには小さな太陽のようなひまわりがあった。
その次の日には、白いレースのように繊細なカスミソウが。
花は、一日も欠かすことなく、健人の郵便受けに届けられた。まるで静かな挑戦状のように。
健人の内なる城壁に、小さなひびが入っていく。彼は、この非合理的な現象の犯人を突き止めるべく、行動を開始した。郵便配達員が来る時間を狙って、自室の窓からそっと階下を監視した。スマートフォンのアプリで、エントランスの簡易的な監視カメラのログを確認した。しかし、そこには怪しい人影などどこにも映っていない。まるで、花だけが魔法のように郵便受けに出現するかのようだった。
「気味が悪い」
独りごちた声は、静まり返った部屋に虚しく響いた。彼の整然とした世界が、名も知らぬ誰かの気まぐれによって静かに、しかし確実に侵食されていく。その苛立ちは、いつしか得体の知れない好奇心へと変質し始めていた。健人はまだ、その変化に気づいていなかった。
第二章 花の名前と、隣の音
一週間が過ぎる頃には、健人の行動に奇妙な変化が生まれていた。彼は、郵便受けの花をすぐに捨てることをやめた。最初は空のペットボトルに、やがて近所の雑貨店で買った安物のガラス瓶に、その日の「侵入者」を挿して、殺風景な仕事机の隅に置くようになったのだ。
色とりどりの花々は、モニターの無機質な光しか映さなかった部屋に、柔らかな色彩と生命の息吹をもたらした。ある日は紫のトルコキキョウ、またある日は淡いピンクのカーネーション。健人は無意識のうちに、スマートフォンの検索窓にその花の名前を打ち込むようになっていた。
『トルコキキョウ 花言葉』――優美、希望。
『カーネーション ピンク 花言葉』――感謝。
感謝? 誰が、誰に。馬鹿馬鹿しい、と頭では否定しながらも、その言葉は小さな棘のように彼の心に刺さった。非科学的だと切り捨ててきた世界が、窓辺の小さなガラス瓶から静かに彼を手招きしているようだった。
犯人探しの過程で、健人はこれまでほとんど意識したことのなかった隣人にも目を向けた。彼の住む203号室の隣、204号室に住むのは、佐伯という物静かな老婆だった。たまに廊下ですれ違うが、深く頭を下げるだけで、会話らしい会話をしたことはない。いかにも怪しい、という先入観で観察を始めたが、彼女の生活は健人以上に単調に見えた。週に二度、決まった時間に買い物に出かける以外は、ほとんど部屋から出てくる気配がない。
ただ一つ、奇妙なことがあった。
夜、仕事を終えて静寂に耳を澄ませていると、時折、隣の部屋から微かなピアノの音が聞こえてくるのだ。それは決して流麗な演奏ではなかった。たどたどしく、時々つまずきながら、それでも繰り返し奏でられる、どこか物悲しい旋律。その音は、健人の構築した静寂の壁を、優しく叩いているようだった。彼はその音を、日常に割り込む新たなノイズとして処理しようとしたが、なぜかその悲しげなメロディーが耳から離れなかった。
第三章 空白の楽譜
その朝、郵便受けは空っぽだった。
新聞と、数枚のチラシだけ。いつもの場所に、あるはずの花がなかった。健人は一瞬、心臓が奇妙な音を立てて跳ねるのを感じた。安堵のはずだった。これで彼の日常は元に戻る。しかし、胸に広がったのは安堵ではなく、ぽっかりと穴が空いたような、冷たい喪失感だった。
翌日も、花はなかった。その次の日も。
健人は、自分がこれほどまでに、あの花を待っていたという事実に愕然とした。あれほど煩わしく、非論理的だと忌み嫌っていたはずの存在が、いつの間にか彼の日常の、なくてはならない一部になっていたのだ。窓辺で少しずつ萎れていく最後の花、赤いポピーを眺めながら、彼は言いようのない不安に駆られた。
隣から聞こえていたピアノの音も、ここ数日、ぷっつりと途絶えている。まさか。
嫌な予感が、背筋を冷たい手で撫でた。彼は生まれて初めて、自らの意思で隣の部屋のインターホンを鳴らした。応答はない。何度か呼びかけても、壁の向こうは墓場のように静まり返っているだけだった。
管理会社に連絡し、事情を話すと、すぐに担当者が駆けつけてきた。合鍵でドアが開けられた瞬間、健人は息を呑んだ。
部屋は質素だったが、塵一つなく整えられていた。そして、その静寂の中で、ベッドに横たわる佐伯さんの姿があった。眠るように穏やかな顔で、彼女はすでに息絶えていた。老衰による、安らかな孤独死だった。
警察の現場検証が終わった後、健人は許可を得て、改めて部屋の中を見させてもらった。窓辺には、彼に届けられていた花々と同じ種類の鉢植えが、愛情深く育てられている。部屋の隅には、古びたアップライトピアノ。そして、その譜面台には、一冊の大学ノートが開かれていた。
健人は、吸い寄せられるようにそのノートを手に取った。それは、佐伯さんの日記だった。そこには、彼女の秘密が、そして健人が追い求めていた謎の答えが、切なくも温かい言葉で綴られていた。
『夫は、毎日私に一輪の花をくれる人でした。庭に咲いたものを、ただ「ほら」と言って渡すだけ。でも、それが私の宝物でした。彼が逝ってしまってから、この家は音がしなくなった』
ページをめくる手が震えた。
『半年ほど前、お隣に若い方が越してきた。とても規則正しい生活をなさる方。朝のコーヒーの香り、キーボードを叩く規則的な音、決まった時間に聞こえる足音。それが、まるで昔の我が家の、夫が巻いてくれた柱時計の音のように聞こえて、私の心を慰めてくれるのです。寂しい夜も、その音を聞いていると、一人ではないような気がして』
『私の勝手な慰めのお礼です。夫が私にしてくれたように。どうか、あなたの毎日にも、ささやかな彩りがありますように。私の生活音も、あなたにはご迷惑かしら。夫が好きだった曲なのです』
最後の方のページに、しおれかけた一輪のコスモスが挟まれていた。そして、その横には、震えるような文字でこう書かれていた。
「お隣のあなたへ。いつも、ありがとう」
健人はその場に立ち尽くした。
自分がノイズだと感じていたピアノの音。非論理的だと切り捨てた花の送り主。そのすべてが、一人の人間の孤独を癒すための、ささやかで、必死の祈りだったのだ。そして、自分が無機質だと思っていた日常の生活音が、知らず知らずのうちに、誰かの心を支える「音楽」になっていた。
価値観が、音を立てて崩れ落ちていく。彼の堅牢な城壁は、跡形もなく粉々に砕け散っていた。目から溢れた熱い雫が、日記のページに小さな染みを作った。
第四章 窓辺に咲く音
佐伯さんの葬儀は、遠縁の親族によって、ひっそりと執り行われた。健人は、生まれて初めて自分の足で花屋に赴いた。色とりどりの花々が並ぶ店内で、彼は長い時間をかけて、一本一本、花を選んだ。ガーベラ、ひまわり、トルコキキョウ、そしてコスモス。それらを束ねた、不格好だが心のこもった花束を、空き家となった204号室のドアの前に、静かに手向けた。
健人の日常は、以前の静けさを取り戻した。しかし、その静寂の意味は、もはや全く違うものになっていた。
彼は毎朝、自分で買ってきた一輪の花を、窓辺のガラス瓶に挿すようになった。それはもう、誰かからの謎の贈り物ではない。彼自身の、世界に対するささやかな応答だった。
時々、彼は仕事の手を止め、隣室との間の壁にそっと耳を澄ます。もちろん、もうあの悲しげなピアノの旋律が聞こえてくることはない。けれど、その深閑とした静寂の中に、健人は確かに佐伯さんの存在を感じることができた。彼女がくれた温かさ。自分の生活音が、見知らぬ誰かと繋がっていたという、確かな手触り。
ある晴れた日の午後、健人はベランダに出て、隣の部屋の窓を見つめた。そこにはもう誰もいない。カーテンが閉ざされた窓は、ただ黙って空の色を映しているだけだ。それでも彼は、そこに佐伯さんがいるかのように、小さく、そして深く、頭を下げた。
部屋に戻り、いつものようにコーヒーを淹れる。ゴリゴリと豆を挽く音が、部屋に響き渡る。その音は、以前と同じようでいて、どこか優しく、温かい響きを帯びているように感じられた。
それはもはや、単なるルーティンが生み出す無機質な生活音ではなかった。
誰かと繋がり、誰かを慰め、そして自分自身の心を豊かに満たしていく、名もなき優しいソナタ。
健人の世界は、今も静かだ。しかしその静寂は、もう孤独の色をしてはいなかった。目には見えない無数の音と色彩で、彼の日常は豊かに、そして美しく奏でられ始めていた。