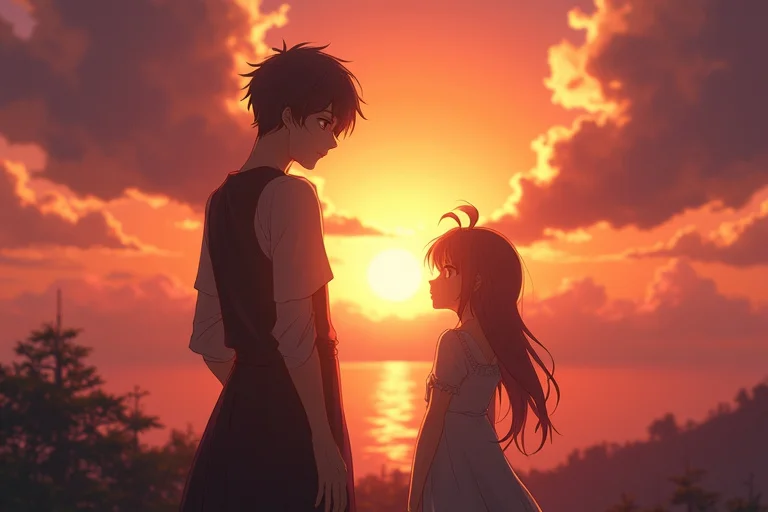第一章 玻璃の来訪者
世界は、灰色の嘆きに沈んでいた。僕、カイの知る限り、空はいつだって分厚い霧に覆われ、太陽の輪郭すらぼんやりとしか見えない。僕の仕事は、その霧の海の果て、忘れ去られた孤島に立つ古い灯台の灯りを守ること。「灯守(ともりもり)」と呼ばれる、時代遅れの役目だ。
一体誰のために、この光を灯しているのだろう。霧が深すぎて、この島の存在に気づく船など、もう何十年も現れていない。父からこの役目を引き継いで五年。僕の毎日は、巨大なレンズを磨き、油を注し、日没と共に巨大な灯火を点ける、その繰り返しのうちに虚しく過ぎていく。この光は、誰にも届かない。僕の人生と同じように。
その夜も、僕は独り、灯室の冷たい石壁に背を預け、虚空を照らす光の帯を眺めていた。回転する光が、すぐそばの霧を切り裂いては、また闇に呑まれる。無意味な営み。そう思った瞬間だった。
チリン、と澄んだ音がした。風鈴のような、しかしもっと繊細で儚い音。音のした方へ目をやると、光の帯の中に、小さな煌めきが舞っていた。虫だ。しかし、ただの虫ではない。翅はまるで極薄のガラス細工で、体は凝縮された月の光のように青白く輝いている。それは幻のように美しく、ゆっくりと僕の方へ近づいてきた。
僕は思わず手を差し伸べていた。その光の生き物は、恐れることなく僕の人差し指の先にとまった。触れた場所から、信じられないほどの優しい温もりが伝わってくる。その瞬間、僕の頭の中に、直接声が響いたのだ。それは男でも女でもなく、ただ純粋な響きだけの声だった。
『星を、見せて』
僕は息を呑んだ。星? この霧の世界で、誰も見たことのない、おとぎ話の中の存在。幻聴だろうか。しかし、指先の確かな温もりと、目の前の玻璃の生き物が放つ切ないほどの光が、これが現実なのだと告げていた。僕の孤独で色褪せた日常に、初めて異質な光が差し込んだ夜だった。
第二章 星へ還る願い
その不思議な生き物は、自らを「ルナ」と名乗った。僕の心に直接語りかけるその声は、静かな水面に落ちる雫のように、僕の孤独を震わせた。ルナの話は、およそ信じがたいものだった。自分たちは「光蟲(こうちゅう)」と呼ばれる存在で、遥か天上の星々の欠片から生まれたのだという。この世界を覆う「嘆きの霧」のせいで故郷の光を見失い、還れなくなった仲間たちが、僕の灯す灯台の光を頼りに、夜な夜な集まってくるのだと。
「あなたの光だけが、この霧を貫く唯一の道標なのです」
ルナの言葉通り、その夜から、灯台の灯りには毎夜、数えきれないほどの光蟲たちが集まるようになった。青、翠、金色と、様々な色を放つ彼らは、まるで生きている宝石の群れのようだった。彼らは灯火の周りを静かに舞い、決して音を立てることはない。ただ、その明滅する光が、言葉にならない切実な願いを訴えかけているように見えた。
これまで無意味だと思っていた自分の仕事が、誰かの道標になっていた。その事実は、僕の心に小さな、しかし確かな波紋を広げた。僕はルナと多くの時間を過ごすようになった。灯台守の仕事の合間に、僕はルナにこの世界のことを話し、ルナは僕に、彼女の記憶にある星空の美しさを語ってくれた。ダイヤモンドのように輝く無数の星々、天を横切る乳白色の川、周期的に夜空を訪れるという箒星の話。それは僕にとって、夢物語以外の何物でもなかったが、ルナの語る声の響きは、僕の胸に不思議な憧憬を灯した。
「彼らを、故郷に還してやりたい」
いつしか、僕はそう強く願うようになっていた。虚無感で満たされていた心に、初めて目的という名の熱が宿った。しかし、ルナは悲しげに光を揺らめかせる。
「この灯台の光は、仲間たちを集めることはできても、嘆きの霧を完全に晴らし、天まで届かせるほどの力はありません。星へ還る道を開くには、もっと、もっと強い光が…」
僕は決意した。この光を、もっと強くする。父が遺した書物、灯台の設計図、島の古老たちの言い伝え。僕は憑かれたように、光を増幅させる方法を探し始めた。忘れられた地下室の奥で、埃を被った一冊の古文書を見つけ出すまでは。
第三章 嘆きの霧の真実
古文書の羊皮紙は、歳月を経て硬く、インクの文字は掠れていた。そこに記されていたのは、この灯台に隠された禁断の儀式についてだった。灯台の光を極限まで高めるための、最後の手段。それは、灯守自身の「生命」を燃料として、その魂ごと灯火に捧げるというものだった。
全身の血が凍りつくのを感じた。光蟲たちを救う道は、僕自身の死と引き換えだったのだ。僕の人生は無意味だと思っていた。だが、いざその終わりを突きつけられると、足元から地面が崩れ落ちるような恐怖に襲われた。何故、僕なのだ。やっと見つけた生きる目的が、自らの死へと繋がっているなど、あまりにも残酷な冗談ではないか。
僕は数日間、灯室に閉じこもり、苦悶した。死の恐怖と、光蟲たちの無垢な光の間で、僕の心は引き裂かれそうだった。そんな僕の様子を、ルナは黙って見つめていた。僕が決心を固め、震える手で儀式の準備を始めようとした、その時だった。
「カイ、待ってください。あなたが知らなければならないことがあります」
ルナの静かな声が、僕の心を貫いた。彼女はゆっくりと、衝撃の真実を語り始めた。
「私たちが還りたいと願う『星空』は、あなたが考えているような場所ではないのです。そして、この『嘆きの霧』も…」
ルナによれば、嘆きの霧の正体は、自然現象などではなかった。それは遥か昔、この灯台の初代灯守が、嵐で愛する人を失った絶望から、自らの強大な魂と悲しみを霧に変え、世界を覆った呪いそのものだった。光を憎み、星空を隠し、世界から色彩を奪った、たった一人の男の嘆き。
そして、光蟲。彼らは星の欠片などではない。彼らこそ、その嘆きの霧の中で行き場を失い、消えていった人々の「幸せだった記憶」や「果たされなかった願い」が寄り集まって生まれた、儚い魂の残滓だった。彼らが求める「星空」とは、魂が還るべき安らぎの場所…すなわち、霧からの「解放」を意味していた。
言葉を失う僕に、ルナは最後の、そして最も重い事実を告げた。
「その初代灯守は…カイ、あなたの遠いご先祖様です。灯守の一族は代々、先祖が世界にかけた呪いを解くため、この光を灯し続けてきたのです。それは贖罪の光。彷徨う魂たちを慰めるための、鎮魂の光なのです」
僕の足が、がくりと折れた。無意味だと思っていた仕事は、僕の一族が背負わされた、途方もない宿命だった。僕が感じていた虚無感や孤独は、この血に刻まれた罪の記憶だったのかもしれない。すべてが、根底から覆された。必要なのは、僕の命ではなかった。では、一体何が、この千年の嘆きを終わらせることができるというのだろう。
第四章 夜明けの光
僕の命ではない。ならば、何が。答えを求めてルナを見つめると、彼女はそっと僕の頬にその光の体を寄せた。温かい。初代灯守が失い、そして僕が今まで知らなかった感情。
「呪いをかけたのは、深い悲しみです。ならば、それを解くことができるのは…」
その言葉に、僕はすべてを悟った。必要なのは、生命力という物理的な燃料ではない。初代灯守が絶望の果てに失ってしまった、心。憎しみや悲しみとは対極にあるもの。赦し、そして、愛。
僕はゆっくりと立ち上がった。もう恐怖も葛藤もなかった。僕は初代灯守の絶望を想った。愛する者を失った、想像を絶する悲しみを。そして、その悲しみに囚われ、彷徨い続ける無数の魂たちを想った。僕はずっと独りだと思っていた。だが、違った。この島は、この世界は、ずっと声なき声で満ちていたのだ。
僕は灯火の前に立った。目を閉じ、心を集中させる。これまでの虚しさや孤独ではない。この数週間で僕の中に育まれた、ルナや光蟲たちへの愛おしい気持ち。彼らを解放してあげたいと願う、純粋な祈り。そして、遠い先祖の犯した罪と、その深い悲しみを、僕が受け入れ、赦すという強い意志。そのすべてを、心の光として灯火に注ぎ込んだ。
すると、灯台の光が、これまでにないほど柔らかく、温かい金色の輝きを放ち始めた。その光は、もはや霧を切り裂く刃のような光ではない。霧そのものを内側から優しく照らし出し、包み込むような慈愛の光だった。
灰色の嘆きの霧が、光に触れたそばから金色に変わっていく。それはもはや呪いではなく、祝福の光の粒子となって、静かに天へと昇っていく。灯火の周りを舞っていた光蟲たちが、その金色の光に吸い込まれるようにして、次々と溶けていった。彼らの光は、消える間際に一度だけ強く輝き、まるで「ありがとう」と微笑んでいるように見えた。
ルナが、僕の指先からふわりと離れた。
『カイ。ありがとう。これで、みんな安らぎの中へ還れる』
「ルナ…君も、行ってしまうのか」
『私は、あなたの心が見せてくれた星。忘れないで』
ルナの体もまた、ひときゆわ輝きを増し、金色の粒子となって空へ溶けていった。指先に残る最後の温もりが、僕の頬を伝う一筋の涙を熱くした。
やがて、すべての霧が晴れた時。
僕の目の前には、生まれて初めて見る、夜空が広がっていた。
息を呑むほどの、無数の星々。天を貫く、乳白色の川。それはルナが語ってくれた通りの、しかし想像を絶するほどに美しい光景だった。光蟲たちが還っていった場所ではない。これは、僕がこれから生きていく世界の、新しい始まりを告げる空だった。
僕はもう、独りではない。僕が灯すこの光には、意味がある。それはもう贖罪の光ではない。この新しく生まれた世界で、誰かの道を照らすための、希望の光だ。
僕は満天の星の下、静かに微笑んだ。そして、夜が明けるまでずっと、その美しい光を見上げていた。