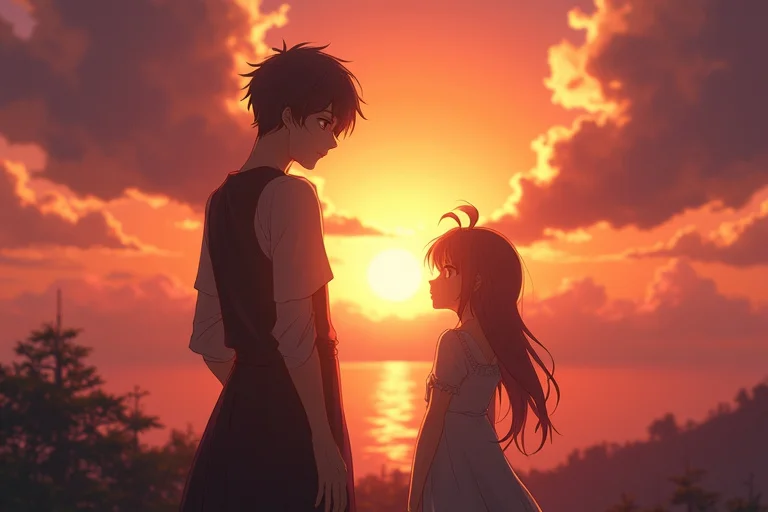第一章 売られた追憶
カイが暮らす街、アッシュダールでは、誰もが二つの影を持っていた。一つは陽の光によって地に落ちる、ありふれた黒い輪郭。そしてもう一つは、魂に結びついた「記憶の影」だ。それは感情の起伏に応じて色と形を変え、持ち主の人生そのものを映し出す、内なる輪郭だった。
そして、この街では記憶の影を売買することができた。
「カイ兄ちゃん、お水……」
か細い声が、薄暗い部屋に響く。妹のリナは、もう何か月も原因不明の熱に浮かされていた。日に日に痩せていく彼女の頬を見るたびに、カイの心臓は冷たい手で鷲掴みにされるような痛みに襲われた。医者が言うには、都にあるという高価な霊薬さえあれば、リナは助かるという。しかし、その薬価は、カイが一生働いても稼げるかどうかという額だった。
彼に残された最後の希望は、自分の「記憶の影」を売ることだけだった。
カイの記憶の影は、同年代の若者たちの間でも評判だった。幼い頃に両親を亡くし、妹と二人で肩を寄せ合って生きてきた彼の影には、苦難の中にも温かな光を放つ、美しい思い出が幾重にも織り込まれていた。特に、妹と二人で見た夏祭りの夜空を彩る花火、初めて二人で焼いたパンの香ばしい匂い、川辺で笑い合った日の木漏れ日。それらの記憶は、彼の影を琥珀色や萌黄色に輝かせ、見る者の心を和ませる力があった。
影市場は、街の最も猥雑な一角にあった。そこでは、幸福な記憶の影は眩い光を放ちながら宙に浮かび、高値で取引される。一方で、絶望や後悔に満ちた影は、アスファルトに染み付いた黒いシミのように淀み、二束三文で買い叩かれていた。富裕層は、自らの空虚な人生を彩るために美しい影を買い求め、その記憶を疑似体験して悦に入る。それは、魂の売買に他ならなかった。
カイは市場の喧騒の中、固く拳を握りしめた。リナの笑顔のためなら、どんな記憶だって差し出せる。そう自分に言い聞かせても、胸に宿る温かな光を、まるで臓器を抉り出すかのように切り離す行為に、身がすくむほどの恐怖を感じていた。思い出は、貧しい自分たちに残された、唯一の財産だったのだから。
意を決して、彼は市場の奥で店を構える、最も高値で影を買い取ると噂の仲買人、「時喰みの老婆」の元を訪れた。老婆の目は、古びた羊皮紙のように皺くちゃの顔の中で、黒曜石のように鋭く光っていた。
「ほう。これはまた……見事な輝きじゃの」老婆はカイの足元で揺らめく記憶の影を一瞥し、乾いた唇を舐めずった。「特に、あの夏祭りの記憶。妹御と二人、人混みからはぐれぬよう、固く手を繋いだ夜じゃな。打ち上げ花火がお前さんたちの顔を照らすたび、影は金色に燃え上がっておる。極上の品じゃ」
その言葉は、カイの胸に突き刺さった。あの夜の記憶は、彼にとって何よりも大切な宝物だった。
「……これを、売ります」絞り出した声は、自分のものではないように掠れていた。「妹を、助けたいんです」
老婆は満足げに頷くと、錆びた小刀を取り出した。カイが影を売るということは、その記憶を自身の内から完全に消し去ることを意味していた。曖昧になるのではない。初めから、そんな出来事はなかったことになるのだ。
老婆が小刀を振り下ろした瞬間、カイは世界から色が失せるような感覚に襲われた。足元の影の一部が、音もなく切り離され、老婆の手の中にあるガラス瓶に吸い込まれていく。瓶の中で、金色の光が狂おしく明滅していた。
第二章 空白の幸福
大金を手にしたカイは、すぐに都へ向かい、霊薬を手に入れた。薬は驚くほどの効果を発揮し、リナは日に日に元気を取り戻していった。血色の良くなった頬、鈴の音のように軽やかな笑い声。カイが何よりも望んでいた日常が、そこにはあった。
しかし、カイ自身の内側では、何かが決定的に欠けてしまっていた。
ある晴れた日の午後、リナが庭の花を見ながら無邪気に言った。
「ねえ、カイ兄ちゃん。覚えてる?去年の夏祭り、すっごく綺麗だったよね。金魚すくい、兄ちゃん下手っぴだったけど」
その言葉に、カイの心臓が凍りついた。夏祭り?金魚?彼の頭の中には、そんな光景はどこにも存在しなかった。ただ、妹の言葉を聞くと、胸の奥にぽっかりと穴が開き、そこから冷たい風が吹き込んでくるような、奇妙な喪失感が彼を襲った。
「……ああ、そうだったかな」
曖昧に微笑むことしかできない自分が、カイはたまらなく嫌だった。リナの幸福は、自分の大切な一部を犠牲にして成り立っている。その事実が、重い鉛のように彼の心を沈ませていく。彼はリナの笑顔を見るたびに、自分が何を失ったのかを突きつけられているような罪悪感に苛まれた。
幸せなはずなのに、心が満たされない。食事をしても味気なく、美しい景色を見ても感動が湧かない。彼の世界から、鮮やかな色彩が少しずつ失われていくようだった。残された記憶の影も、以前のような輝きを失い、どこかくすんだ色合いで揺らめいている。
そんなある日、カイは街の中心広場で、見覚えのある輝きを目にする。それは、見知らぬ裕福そうな男の足元に侍る、一つの記憶の影が放つ光だった。琥珀色と金色が混じり合った、温かな輝き。男は目を閉じ、恍惚とした表情でその影が映し出す幻影――カイが失ったはずの、リナと過ごした夏祭りの光景――に見入っていた。
花火が夜空に咲き、幼いリナが手を叩いて喜んでいる。その手を、若き日のカイが固く握っている。自分の知らない、しかし間違いなく自分であったはずの光景。それを見せつけられ、カイは吐き気を催した。他人の思い出を盗み、自分のものとして味わう男の姿に、激しい嫌悪感が込み上げる。
だが、それ以上にカイを恐怖させたのは、その影が時折、男から離れて周囲を彷徨うように揺らめき、何かを探しているように見えたことだった。
第三章 影の渇望
その夜、カイの家に予期せぬ客が訪れた。時喰みの老婆だった。老婆は部屋に入るなり、眠っているリナの顔をじっと見つめ、そしてカイに向き直った。
「お前さん、まだ分かっておらんようじゃな」
「何がだ……」
「影を売るということの、本当の意味を」老婆は静かに言った。「記憶を失うだけだと思っておったか?甘いのう。切り離された影は、新たな主を得る。だが、それは仮の宿に過ぎん。影は、本能的に元の身体へ戻ろうとする。自分の根源である魂に引き寄せられるのじゃ」
カイは息を呑んだ。では、あの影はいずれ自分のもとに?
「だが」と老婆は続けた。「今の影にとって、お前さんはもはや『他人』じゃ。影の核であった夏祭りの記憶を、お前さんは持っておらんからのう。戻るべき場所を失った影は、どうなると思う?」
老婆の目が、不気味な光を帯びる。
「影は、元の持ち主が最も強く心を結んだ相手……その魂の香りを嗅ぎつけ、新たな『本体』として取り憑こうとする。お前さんの影にとって、それは誰か。言うまでもないじゃろう」
カイの視線が、凍りついたようにリナの寝顔に向けられた。まさか。
「影がお嬢ちゃんに取り憑いたが最後、お嬢ちゃんは自分を失う」老婆の言葉が、とどめを刺した。「お前さんの幸福な記憶に上書きされ、お前さんの影として生きることになる。人形のようにな。あれはもう、お前さんの美しい思い出ではない。持ち主を失い、渇ききった……飢えた獣じゃよ」
その瞬間、窓の外で何かが蠢いた。カイが見ると、あの金色の影が、まるで黒いアメーバのように壁を伝い、窓の隙間から侵入しようとしていた。影はリナの放つ魂の香りに引き寄せられ、黒い触手を伸ばしている。それはもはや美しい思い出の欠片などではなかった。リナという新たな宿主を求め、渇望する、おぞましい捕食者だった。
カイは絶叫し、窓に駆け寄って固く閉ざした。ガラスの向こうで、影が静かに、しかし執拗に揺らめいている。リナを、狙っている。自分の最も美しい思い出が、今、最も大切な存在を喰らおうとしていた。
第四章 新しい地平へ
絶望がカイを打ちのめした。自分の愚かな選択が、妹を想像を絶する危機に晒してしまった。あの男から影を奪い返す?どうやって?力ずくで奪えるものではない。では、金を払って買い戻す?霊薬で使い果たし、もはや一文無しだ。
カイは眠るリナの隣で、為す術もなく夜明けを迎えた。窓の外では、影が陽光を浴びて少しだけ薄くなっているが、消えたわけではない。夜になれば、また活動を始めるだろう。
「……どうすればいい」
掠れた声で呟いたとき、ふと老婆の言葉が脳裏に蘇った。『影は、本能的に元の身体へ戻ろうとする』。
戻るべき場所を、自分が失ってしまったから、影はリナに向かうのだ。ならば。
カイの心に、一つの微かな、しかし確かな光が灯った。
影を取り戻す方法は、一つしかない。あの夏祭りの記憶以上に、もっと強く、もっと輝かしい記憶を、これから自分が作るのだ。影が「こちらこそが本当の主だ」と認めざるを得ないほどの、新しい思い出を。それは、過去の記憶を取り戻すことではない。未来を創造することで、過去を超えるという、途方もない挑戦だった。
カイはリナを優しく揺り起こした。
「リナ、旅に出よう」
「え、旅?どこへ?」
「どこへでも。誰も知らない場所へ。この街を出て、新しい景色をたくさん見に行こう。今まで見たどんな花火よりも綺麗な朝日を、二人で見つけるんだ」
リナはきょとんとしていたが、兄の真剣な眼差しに、こくりと頷いた。彼女は兄を信じている。
カイは最低限の荷物をまとめ、リナの手を固く握った。それは、夏祭りの夜に繋いだ手とは違う。過去の思い出を守るための手ではなく、未来を切り拓くための、力強い意志を込めた手だった。
二人が小さな家を後にしたとき、背後の路地から、金色の影が静かに滑り出てきた。それは獲物を見つけた狩人のように、二人の後を一定の距離を保ちながら、執拗に追いかけてくる。
カイは振り返らなかった。恐怖で足がすくみそうになるのを、リナの小さな手の温もりが支えてくれる。
これは逃避行だ。だが、同時に、失われた魂と絆を取り戻すための、巡礼の旅でもあった。前には果てしない荒野が広がり、後ろからは美しい過去の亡霊が迫ってくる。それでも、カイは前を向いた。
「大丈夫だ、リナ」彼は妹に、そして自分自身に言い聞かせた。「これから、もっとすごい思い出をたくさん作ろう。僕たちのための、本当の思い出を」
カイの記憶の影は、まだくすんだ色をしていた。しかし、その中心に、決意という名の、小さな新しい光が灯り始めていた。彼らの旅路の果てに何が待っているのか、誰にも分からない。だが、カイは歩き続ける。いつか、追いかけてくる影が振り向き、自らの足元に戻ってくる、その日まで。