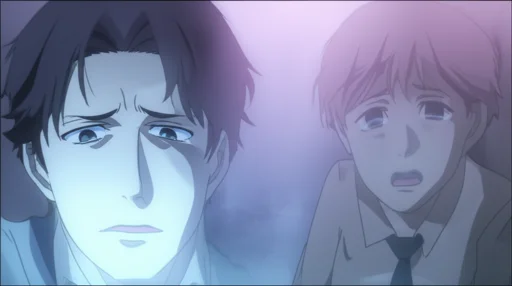第一章 腐臭の招待状
水月(みづき)には、呪いとも言うべき秘密があった。彼女は、他人の記憶の残滓を「匂い」として感じ取ることができる。それも、極度の恐怖や絶望といった、負の感情に染まった記憶だけを。
調香師の卵である彼女にとって、その類稀なる嗅覚は天賦の才であるはずだった。しかし、街を歩けば、アスファルトに染みついた事故の瞬間の焦げ付くようなパニックの匂いや、古いアパートの壁から滲み出す孤独死のじっとりとした絶望の匂いが、彼女の鼻腔を容赦なく刺した。世界は、美しい香水などでは決して上書きできない、おぞましい悪臭に満ちていた。水月は自分の能力を疎み、人との関わりを避け、香りのない無菌室のような自室に引きこもりがちだった。
そんな彼女が、自ら悪臭の渦中へ飛び込もうと決めたのは、一縷の望みを託してのことだった。新作の香水のインスピレーションが、どうしても湧かなかったのだ。スランプに陥った彼女は、藁にもすがる思いで、街外れに佇む古い洋館を訪れた。そこは、かつて天才と謳われながらも、ある日忽然と姿を消した小説家、蒼馬(そうま)レイジの旧邸宅だった。彼の作品は、読む者の魂を根こそぎ揺さぶるような、暗く美しい物語ばかりだったという。
苔むした石門をくぐり、蔦の絡まる玄関の重い扉を開けた瞬間、水月は息を呑んだ。
来た。
これまで嗅いだどんなものとも違う、圧倒的な密度の「恐怖の匂い」。それは単一の匂いではなかった。古書の乾いた匂いと、湿った土の匂いの奥から、じわりと滲み出す複数の恐怖が、複雑な和音のように絡み合っていた。錆びた鉄のような鋭い苦痛の匂い。腐りかけた果実のような甘い絶望の匂い。そして、それら全てを支配するように漂う、冷たいインクのような、静かで底知れない狂気の匂い。
全身の産毛が逆立つほどの恐怖を感じながらも、水月は奇妙な高揚感を覚えていた。これほどまでに複雑で、心を惹きつけてやまない「香り」に出会ったのは初めてだった。これは一体、誰の、どんな恐怖なのか。彼女は、この匂いの正体を突き止めずにはいられないという、抗いがたい衝動に駆られていた。それは、彼女の呪われた能力が初めて見せた、創造への誘いだった。
第二章 記憶の残香
洋館は、蒼馬レイジ記念館として一部が公開されていた。水月は閉館時間まで、まるで何かに取り憑かれたかのように、館内を彷徨い歩いた。匂いは、場所によってその表情を微妙に変えた。
一階の書斎。天井まで届く本棚に囲まれたその部屋は、「焦燥」の匂いが強かった。締め切りに追われる作家の、乾いた苛立ち。インクの匂いに混じって、神経質に掻きむしった頭皮の脂のような、生々しい匂いがする。だが、その奥にはもっと深い恐怖があった。才能が枯渇していくことへの、冷たい恐怖。真っ白な原稿用紙を前に、一文字も生み出せない苦しみが、埃っぽい匂いとなって澱んでいた。水月は、壁に飾られた蒼馬の肖像画を見上げた。神経質そうな、しかし瞳の奥に熱い光を宿した男。彼の苦悩が、時を超えて彼女の肺腑を満たした。
二階の寝室。天蓋付きのベッドが置かれたその部屋は、ひどく感傷的な匂いがした。誰かを失ったのだろうか。愛する人の不在がもたらす、底なしの孤独。それは、古いリネンに残る微かな香水の香りと混じり合い、甘くも切ない「喪失」の匂いとなって漂っていた。水月は、ここに横たわり、天井の染みを眺めながら、決して戻らない温もりを思い出しては涙したであろう作家の姿を幻視した。彼女の胸が、自分のものとは思えないほどの痛みで軋んだ。
最も濃い匂いがしたのは、地下へと続く階段の先だった。職員以外立ち入り禁止の札を無視し、軋む扉を開けると、黴と湿気が凝縮された空気が彼女を襲った。そして、あの匂い。館全体を支配する、静かな狂気の匂いの発生源はここだった。地下室はワインセラーとして使われていたようだが、その奥に、不自然なほど新しいレンガで塞がれた壁があった。
水月が壁に鼻を近づけると、匂いは極限まで純度を増した。それはもはや、人間の感情から生まれた恐怖ではなかった。もっと根源的で、名状しがたい何か。暗闇そのもの、無そのものへの畏怖。この壁の向こうに、蒼馬レイジの失踪の秘密が隠されている。彼女は確信した。この匂いを完全に理解し、自分のものにできれば、きっと誰も創り得なかった、究極の香りが生まれる。彼女の探求心は、恐怖心を凌駕していた。
第三章 物語は餓えている
数日後、水月は深夜、懐中電灯と小さなハンマーを手に、再び洋館に忍び込んだ。昼間のうちに調べておいた裏口から侵入し、まっすぐ地下室を目指す。あの壁の向こう側を、確かめなければならなかった。
レンガは意外にもろく、数度打ち付けると崩れ始めた。隙間から、澱んだ空気が濃密な匂いと共に溢れ出す。それは、彼女が追い求めてきた狂気の匂いだった。穴を広げ、身を滑り込ませると、そこには小さな隠し部屋があった。部屋の中央に置かれた簡素な机の上には、万年筆と、分厚い原稿の束が残されていた。
これだ。蒼馬レイジが最後に書いていたものに違いない。水月は、まるで聖遺物に触れるかのように、そっと原稿を手に取った。
その瞬間、世界が変わった。
これまで彼女を苛んできた、館に漂う全ての「恐怖の匂い」――書斎の焦燥、寝室の喪失、地下室の狂気――が、奔流となって彼女の中に流れ込んできた。そして、それらの匂いは混じり合い、螺旋を描きながら昇華し、全く新しい、一つの香りへと変貌を遂げたのだ。
水月は混乱した。その香りは、「恐怖」ではなかった。
それは、何かを産み出す瞬間の、凄まじいほどの「悦び」の匂いだった。脳髄が痺れるような、甘美で、官能的で、抗いがたいほどの執着の香り。それは、神が世界を創造した時に感じたであろう、万能感に満ちた芳香だった。
彼女は悟ってしまった。愕然として、原稿の表紙を見つめた。
『薫り立つ物語』
そう題された、未完のホラー小説。自分が嗅ぎ取っていたのは、蒼馬レイジという人間の恐怖の記憶ではなかったのだ。彼が創り出した「物語」そのものが放つ、魂の香りだった。書斎の焦燥は、物語の登場人物が感じていた焦り。寝室の喪失は、ヒロインが抱えていた悲しみ。そして、地下室の狂気は、この物語の根幹を成す、名状しがたい邪悪な存在そのものの匂いだったのだ。
蒼馬レイジは失踪したのではない。彼は自らが産み出した物語に魅入られ、そのあまりの美しさと恐怖に魂を捧げ、最後の登場人物として物語の中に取り込まれてしまったのだ。この洋館に漂っていたのは、彼の怨念などではない。書き手(親)を失い、未完のまま取り残された物語が、飢えと渇きに苦しみながら、新たな語り部を求めて発していた、甘美な誘いの匂いだったのだ。
「……ああ、なんて……なんて、美しい香りなの」
水月は恍惚として呟いた。恐怖は、悦びの裏返しだった。絶望は、最高の物語を生み出すための触媒だった。彼女を生涯苦しめてきた呪いは、この瞬間のためにあったのだ。
第四章 最後の一滴
水月は、自分が選択の岐路に立たされていることを理解していた。この甘美で危険な物語の香りから逃げ出し、元の灰色の日々に戻るか。それとも、蒼馬レイジの後を継ぎ、この餓えた物語の新たな語り部となるか。
彼女は、自分の両手を見つめた。この手は、世界中の美しい香りを集め、調合し、新たな香水を生み出すための手だ。しかし、彼女が本当に求めていたのは、上辺だけの華やかな香りだっただろうか。彼女の鼻が渇望していたのは、もっと根源的で、魂を揺さぶるような、生と死、歓喜と絶望が混じり合った、真実の香りではなかったか。
これまでずっと、自分の能力を呪ってきた。他人には感じられない悪臭に満ちた世界で、孤独に耐えてきた。だが、もしこの能力が、物語の魂を嗅ぎ取るためのものだったとしたら?恐怖の匂いを嗅ぎ分ける力は、最高の物語を紡ぐための、神が与えた祝福だったとしたら?
水月は、机に置かれていた万年筆を手に取った。ひやりとした感触が心地よい。インクはまだ、乾いていなかった。まるで、彼女が来るのを待っていたかのように。
彼女は原稿の、最後のページを開いた。蒼馬レイジの力強い筆跡は、ある一文でぷっつりと途絶えていた。
『そして、扉の向こう側から、懐かしい香りがした。』
水月は微笑んだ。どんな香りだったのか、今の彼女には手に取るように分かる。
彼女は万年筆のペン先を、原稿の余白にそっと落とした。新しい一文を書き始めた瞬間、奇跡が起きた。あれほど彼女を苛んでいた、館に満ちていた複雑な恐怖の匂いが、すうっと霧が晴れるように消え失せたのだ。
代わりに、彼女の鼻腔をくすぐったのは、真新しい紙の清々しい匂いと、インクが放つ知的で落ち着いた香り。そして、彼女自身の内から湧き上がってくる、創造の喜びに満ちた、温かく甘い芳香だった。
水月はもう、孤独ではなかった。彼女は、物語と共に生きる道を選んだのだ。
洋館の小さな隠し部屋で、新たな語り部を得た物語が、静かに、そして深く呼吸を始める。彼女が紡ぐ物語が、かつての主のように彼女自身を飲み込んでしまう甘美な罠なのか、それとも呪いを祝福へと変えた彼女だけの救いとなるのか。それはまだ、誰にも分からない。ただ、インクの薫りだけが、満足げに夜の闇に溶けていくのだった。