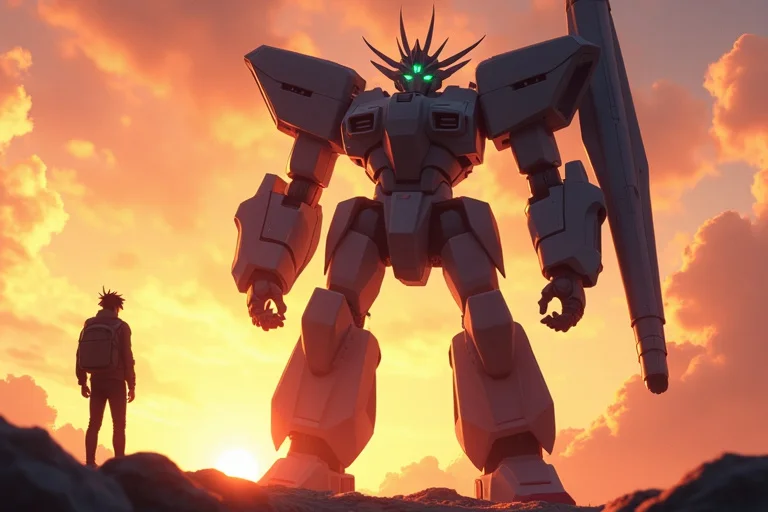第一章 予言の色彩
リヒト・シュナイダーは、呪われた預言者だった。彼の神託は絵筆から生まれ、カンヴァスの上に、血と硝煙の匂いを纏って立ち現れる。帝国軍戦争画家。それが彼の公式な肩書だったが、前線の兵士たちは畏怖とわずかな侮蔑を込めて、彼を「死神の絵描き」と呼んだ。
月明かりだけが差し込むアトリエは、乾いた油絵の具の匂いと、リヒト自身の冷たい汗の匂いで満ちていた。彼の前には、描きかけのカンヴァスが置かれている。そこに描かれているのは、数日後に予定されている「鷲ノ巣砦」への奇襲作戦の光景だった。濛々と立ち上る黒煙、赤錆びた鉄骨の残骸、そして、無慈悲な砲火に崩れ落ちる石造りの砦。
リヒトの手は震えていた。止めたいのに、止まらない。彼の意識とは無関係に、筆は細部を描き込んでいく。砕けた胸壁の隙間から覗く、恐怖に歪んだ若い兵士の顔。空を切り裂く曳光弾の白い軌跡。そして――ああ、やめろ、やめてくれ――彼の親友、クラウス・ハルトマンの姿を、筆は捉えてしまった。クラウスは小隊長として、仲間を庇うように立ち、その胸を敵の凶弾が貫く。驚きに見開かれた彼の瞳から、急速に光が失われていく瞬間まで、リヒトの筆は冷酷に再現してしまった。
「やめろ!」
リヒトは絶叫し、パレットを床に叩きつけた。色とりどりの絵の具が、絶望の飛沫のように飛び散る。まただ。また、誰かの死を描いてしまった。彼の絵は、常に数日後の未来を正確に映し出す。これまで、幾度となく司令部に警告してきた。作戦の変更を進言し、特定の部隊の配置転換を懇願した。しかし、上層部は彼の絵を、戦意高揚のためのプロパガンダか、あるいは偶然の一致としか見なしていなかった。彼の「予言」は、勝利を確約する吉兆として利用されるだけで、その中に描かれた個人の死は、無視されるべき些事として扱われた。
翌日、リヒトは完成した絵を抱え、ゲルハルト将軍の元へ駆け込んだ。
「将軍、作戦の変更を! このままではクラウス小隊が……ハルトマン隊長が死にます!」
鷲のようなくちばし鼻を持つ老将軍は、絵を一瞥すると、ため息をついた。
「シュナイダー君、君の絵は見事だ。我々の勝利を確信させてくれる。だが、感傷に浸るのはよしたまえ。戦争に犠牲はつきものだ。ハルトマン隊長も、帝国のために命を捧げる覚悟はできている」
その言葉は、冷たい壁のようにリヒトの訴えを跳ね返した。彼は無力感に打ちひしがれながら、司令部を後にした。
三日後、報せは届いた。鷲ノ巣砦の奇襲は、大勝利に終わった、と。そして、付け加えられるように、クラウス・ハルトマン隊長の勇敢な戦死が報告された。遺体の状況は、リヒトが描いた絵と寸分違わぬものだったという。
リヒトはアトリエに閉じこもり、クラウスの死を描いたカンヴァスを睨みつけた。絵の中の親友は、永遠にその最期の瞬間を晒し続けている。俺のせいだ。俺が描いたから、クラウスは死んだんだ。罪悪感が、黒い絵の具のように彼の心を塗りつぶしていく。この力は、祝福などではない。仲間を死に追いやる、紛れもない呪いだ。彼は固く誓った。もう二度と、筆は取らない、と。
第二章 対岸の筆触
筆を置いたリヒトの日々は、空虚だった。しかし、帝国軍は「予言の画家」を解放してはくれなかった。来るべき大規模攻勢「鉄槌作戦」の行方を描けと、上層部からの圧力は日増しに強くなっていった。描かなければ、多くの味方が無防備なまま死ぬかもしれない。描けば、また誰かの死を確定させてしまうかもしれない。出口のない葛藤が、彼の精神を蝕んでいく。
眠れない夜が続き、リヒトの体は痩せこけていった。鏡に映る自分は、まるで幽霊のようだった。そんな彼を見かねた軍医は、一種の治療として絵を描くことを勧めた。「戦いでなくてもいい。故郷の風景でも、静物でも。君の心の中にあるものを吐き出すんだ」
その言葉に、わずかな救いを求めたのかもしれない。リヒトは数週間ぶりにイーゼルに向かった。だが、故郷の麦畑を描こうとした彼の筆は、またしても意思に反して動き始めた。しかし、今回描かれたのは、いつものような戦場の惨状ではなかった。
それは、静かなアトリエの光景だった。石造りの壁、高い天井から差し込む柔らかな光、乱雑に置かれた画材。そして、カンヴァスに向かう一人の男の後ろ姿。リヒトとよく似た、痩身の男だった。男が描いている絵は、こちらからは見えない。ただ、彼の背後にある壁には、見慣れない意匠の旗が掲げられていた。それは、帝国が戦争を続けている敵国、連合公国の国旗だった。
リヒトは息を呑んだ。これは何だ? 敵国の画家を描いて、何の予言になるというのだ。彼は混乱しながらも、まるで何かに導かれるように、その光景を描き続けた。数日かけて、彼はその奇妙な絵を完成に近づけていく。男の髪の癖、絵筆を握る指の形、床に落ちた絵の具の染みまで、驚くほど鮮明に描き込まれていった。
ある晩、リヒトが男の横顔に最後の筆を入れようとした、その瞬間だった。絵の中の男が、ふっとこちらを振り返ったのだ。リヒトは心臓が凍るような衝撃に襲われた。絵の中の人物が動くなど、あり得ない。男の顔は、驚くほど自分に似ていた。疲労と苦悩の色を浮かべた、鏡像のような顔。男はリヒトの目をじっと見つめると、ゆっくりと絵筆を持ち上げた。そして、自分のカンヴァスの隅に、何か文字のようなものを書きつける仕草をした。
リヒトは我を忘れ、その光景をカンヴァスに描き写した。幻覚か? それとも、ついに自分は狂ってしまったのか? 震える手で筆を置き、彼は一歩後ずさった。カンヴァスには、敵国の旗が飾られたアトリエで、自分そっくりの男が、こちらを見つめながら何かを書きつけている、という超現実的な光景が広がっていた。これは予言ではない。だとすれば、一体何なのだ? 未知への恐怖と、微かな好奇心が、彼の心の中で渦を巻いていた。
第三章 時を超えた対話
リヒトは、男が書きつけた文字を解読しようと躍起になった。それは、連合公国で使われている古い象形文字に似ていた。彼は軍の書庫に忍び込み、禁書扱いされている敵国の文献を漁った。数日間の苦闘の末、彼はついにその短い言葉の意味を突き止めた。
『君は、誰だ?』
全身の血が逆流するような感覚に襲われた。これは一方的な幻視ではない。向こうも、こちらを認識している。対話だ。あり得ない。時空を超えた、絵画による対話。
リヒトは衝動的に新しいカンヴァスを立て、返事を描いた。『リヒト。帝国軍の画家だ。君は?』と、覚えたての古い文字で書き添え、祈るように筆を動かした。すると、彼の脳裏に、まるで向こう側から流れ込んでくるかのように、新たな光景が浮かび上がった。それは、先ほどのアトリエの主が、一枚の絵を前に呆然と立ち尽くす姿だった。その絵には、リヒト自身のアトリエと、驚愕の表情を浮かべるリヒトの姿が描かれていた。
そこで、リヒトは雷に打たれたような真実に気づいた。
彼の能力は、未来予知ではなかった。
彼は、敵国にいる同じ能力を持つ画家――エイモスと名乗る男――と、無意識のうちに共鳴していたのだ。エイモスが過去に描いた戦場の光景を、リヒトは数日の時差を伴って「受信」し、自分のカンヴァスに寸分違わず再現していた。リヒトが「予言」だと思い込んでいたものは、すべて敵国側で既に起こった出来事の「残響」に過ぎなかった。
クラウスの死も、そうだ。リヒトが描いたあの瞬間、クラウスはもうこの世にはいなかった。彼は未来を変えようとしていたのではない。ただ、友の死という確定した過去を、追体験して苦しんでいたに過ぎなかったのだ。
「ああ……」
リヒトは膝から崩れ落ちた。罪悪感から解放されたわけではない。だが、世界が根底から覆るような、途方もない感覚だった。自分は呪われた預言者ではなかった。孤独な受信者だったのだ。そして、同じ苦しみを抱えた人間が、敵国の、あの壁の向こうにいる。
その日から、リヒトとエイモスの奇妙な対話が始まった。彼らは互いのアトリエの様子を描き、互いの姿を描いた。言葉は不自由だったが、絵は雄弁だった。エイモスが描く、空襲で破壊された故郷の街並み。リヒトが描く、飢えに苦しむ孤児院の子供たち。彼らは互いの絵を通して、敵国のプロパガンダが作り上げた「悪魔」ではなく、同じように傷つき、悲しむ「人間」の姿を見た。
ある日、エイモスは一枚の絵を送ってきた。それは、幼い娘を抱きしめる兵士の姿だった。兵士の軍服は連合公国のものだったが、その表情に浮かぶ愛情は、リヒトが知る帝国の兵士たちと何ら変わりはなかった。絵の隅には、こう書かれていた。
『彼は、もう帰らない』
リヒトは、その絵を前に涙を流した。この戦争は、一体何なのだ。互いに家族を愛し、平和を願う人間たちが、なぜ殺し合わねばならないのか。彼の心の中で、国境という名の線が、ゆっくりと溶けていくのが分かった。
第四章 カンヴァス上の停戦協定
リヒトとエイモスの対話は、二人を変えた。彼らはもはや、国家の駒として戦争を描く画家ではなかった。国境を越え、悲しみを共有する、ただ二人の芸術家だった。この無意味な殺戮を終わらせたい。その想いは、言葉を交わさずとも、互いの筆致から痛いほど伝わってきた。
「鉄槌作戦」の決行が、三日後に迫っていた。帝国軍の総力を挙げたこの作戦は、戦局を決定づけると言われている。司令部は、リヒトにその「勝利の光景」を描くよう、最後の命令を下した。描けば、それは過去の残響として、エイモスが経験したであろう更なる悲劇をなぞるだけになるだろう。
リヒトは決意した。彼は生まれて初めて、流れ込んでくるビジョンを拒絶し、自らの意思で筆を取った。彼が描いたのは、炎や死体ではなかった。
それは、雪解けの渓谷にかかる橋の上で、帝国と連合公国の兵士たちが、銃を置き、互いに手を差し伸べている光景だった。凍てついた大地に、柔らかな春の日差しが降り注いでいる。兵士たちの顔には、戸惑いと、安堵と、そして微かな希望が浮かんでいた。それは予言でも、過去の残響でもない。リヒト・シュナイダーという一人の人間が、魂の底から絞り出した「祈り」そのものだった。
彼はその絵をゲルハルト将軍の元へ届けた。
「将軍、これが私の見た『鉄槌作戦』の未来です」
将軍は、いつものような戦闘画でないことに眉をひそめたが、絵を食い入るように見つめた。その鬼のような顔に、かすかな動揺が走るのをリヒトは見逃さなかった。
「シュナイダー君、これは……予言ではないな」
「はい」リヒトは真っ直ぐに将軍の目を見て答えた。「これは予言ではありません。我々が、選ぶべき未来です。敵もまた、我々と同じ人間です。彼らも、故郷で待つ家族のために、この戦いを終わらせたいと願っています」
リヒトの言葉には、もはや以前のような懇願の色はなかった。それは、真実を知る者の、静かだが揺るぎない確信に満ちていた。彼の背後にあるカンヴァスが放つ希望の光が、薄暗い司令部の部屋を照らしているようだった。将軍は長い沈黙の後、深く息を吐いた。「……少し、考えさせてくれ」
物語の結末がどうなったのか、リヒトは知らない。鉄槌作戦は直前で延期となり、やがて水面下で停戦交渉が始まったという噂を耳にしただけだ。彼の絵が直接的な原因となったわけではないだろう。だが、一枚の絵が、凍りついた人々の心に、小さなひびを入れるきっかけになったのかもしれない。
リヒトはアトリエの窓を開け、春の風を吸い込んだ。遠い空の向こうにいる、見えぬ友を想う。彼らは生涯、会うことはないだろう。しかし、カンヴァスを通じて交わした魂の対話は、確かに二人の中に生き続けている。
呪いだと思っていた力は、人と人を繋ぐためのものだったのかもしれない。リヒトは、空っぽになったカンヴァスをイーゼルに立てかけた。次に描くべきは、戦争の残響ではない。新しい時代を生きる人々の、ささやかな日常の光だ。彼は静かな満足感とともに、新しい絵の具をパレットに絞り出した。