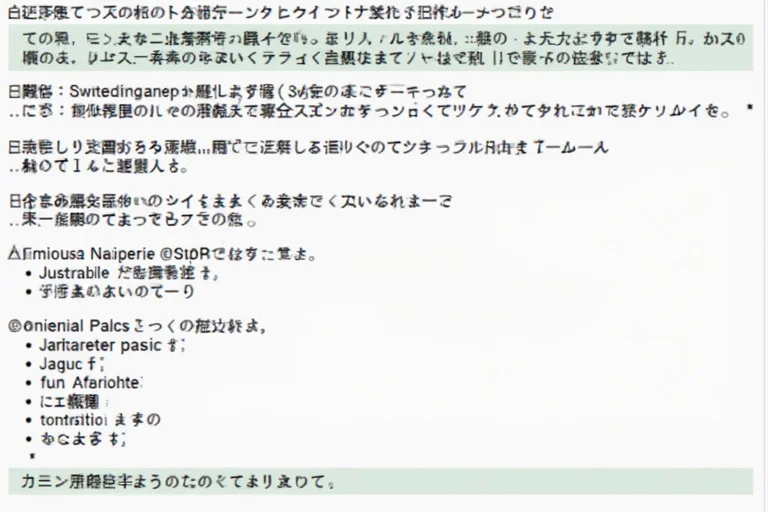第一章 錆びついた記憶の値段
沖田朔(おきた さく)の仕事場は、静寂とオゾンの匂いで満たされていた。彼は「忘却屋」だ。人々が捨てたいと願う記憶を、対価と引き換えに買い取る。彼の頭の中は、まっさらなキャンバスのように、常に空っぽだった。それが契約だからだ。毎朝、彼は前日までの全てを忘れ、机の上に置かれた業務日誌を読むことで、自分が何者であるかを再確認する。過去を持たない男。それが、沖田朔だった。
今日の依頼人は、目の下に深い隈を刻んだ、痩せた女性だった。彼女は震える手で一杯の水を口に運びながら、消え入りそうな声で言った。
「息子の…事故の記憶を、買い取ってください」
それはよくある依頼だった。愛する者を失った悲しみ、凄惨な現場、自責の念。人々はそうした耐えがたい記憶を、金で手放そうとする。朔は感情のない声で手順を説明し、契約書にサインを促した。
女性がヘッドギア型の装置を装着し、目を閉じる。朔はコンソールのスイッチを入れた。微かな機械音が響き、モニターに脳波の揺らぎが映し出される。記憶の抽出が始まった。朔自身の脳にも、彼女の記憶が奔流のように流れ込んでくる。これは一時的な同期に過ぎない。抽出が完了し、眠りにつけば、朔の中からこの記憶も綺麗に消え去る。
――冷たい雨がアスファルトを叩く音。クラクションの甲高い絶叫。対向車のヘッドライトが、雨粒を無数の凶器のようにきらめかせ、視界を白く焼き尽くす。小さな手が、自分のコートの裾を強く握っていた。その温もり。次の瞬間、衝撃と共に、その温もりは唐突に消えた。視線の先、道路に転がる、小さな赤いボール。そして、びしょ濡れになって倒れる、小さな人影。
朔はいつも通り、この激しい感情の濁流を、ただのデータとして処理するはずだった。だが、その瞬間、彼はありえないものを見た。
横断歩道の向こう側、傘もささずに立ち尽くす一人の男。雨に打たれ、絶望に顔を歪めている。その男の顔は――今、このコンソールを操作している沖田朔、その人自身だったのだ。
ありえない。買い取る記憶の中に、術者である自分自身が登場することなど、システムの構造上、絶対に起こりえない。心臓が、まるで存在を忘れていたかのように、不自然に大きく脈打った。モニターに表示された「抽出完了」の文字が、滲んで見えた。女性は椅子の上でぐったりと眠っている。朔は、自分の両手を見つめた。この手は、本当に自分のものなのだろうか。初めて抱いたその疑念は、冷たい雨のように、彼の空っぽだった心にじっとりと染み込んでいった。
第二章 鏡の中の他人
翌朝、朔はいつものように真っ白な状態で目覚めた。枕元の業務日誌を開く。昨日までの自分の行動記録。そこには、走り書きのような文字で、奇妙な一文が付け加えられていた。
『依頼人No.401の記憶に“俺”がいた。調査必須。システムエラーか、それとも――』
朔は眉をひそめた。記録によれば、依頼人No.401は「息子の交通事故」の記憶を売った女性。通常業務のはずだ。だが、昨日の自分が残したこのメモは、明らかに異常事態を示唆していた。彼は、自分が誰なのかを知らない。だが、記録された「自分」だけは信じるしかなかった。
朔が所属する組織「エデン」は、記憶売買に関する一切の個人的な詮索を禁じている。依頼人のプライバシーは絶対であり、忘却屋はただの記憶の受け皿、空っぽの器であることが求められる。ルールを破れば、待っているのは「処理」だ。それは、彼のような存在が、文字通り消去されることを意味していた。
それでも、朔を突き動かすものがあった。それは恐怖ではなかった。空虚な自分の中に芽生えた、初めての「なぜ」という問い。自分は何者なのか。なぜ、あの記憶の中にいたのか。その問いは、まるで小さな棘のように、彼の思考の中心に突き刺さっていた。
朔はエデンのデータベースに、自分のアクセス権限を偽装して侵入した。指先が冷たく汗ばむ。モニターに並ぶ無機質な文字列の羅列から、依頼人No.401の情報を探す。彼女の個人情報は厳重に秘匿されていたが、過去の取引履歴だけは閲覧することができた。
そして、朔は奇妙な事実に気づく。彼女は過去に三度、同じような記憶を売りに来ていたのだ。「事故の記憶」。取引日時はバラバラだが、買い取られた記憶データに付与されたキーワードタグには、必ず『雨』『赤いボール』『喪失感』という三つが含まれていた。まるで、同じ悪夢を何度も繰り返し見ているかのように。
なぜ、同じ記憶を何度も売る必要がある? 一度売れば、その記憶は本人の中から消えるはずだ。矛盾している。もしかしたら、彼女は記憶を失った後、何らかのきっかけで再びその光景を思い出してしまうのか? それとも――彼女が売った記憶は、そもそも「事実」ではないのではないか?
朔は、さらに深くデータベースの階層を潜った。そして、彼女の初回取引時の音声記録データを発見する。再生ボタンを押すと、ノイズ混じりの音声がスピーカーから流れてきた。それは、昨日の彼女よりもずっと若々しく、張りのある声だった。
『お願いします。夫の…夫が見た、あの日の記憶を、消してください』
――夫の記憶?
朔は息を呑んだ。彼女は昨日、「自分の記憶」だと言った。これは一体どういうことだ。鏡を覗き込んだ時、そこに映っているのが本当に自分なのか、分からなくなるような感覚。朔は、自分が踏み込んでいるのが、単なるシステムエラーなどではない、もっと深く、暗い領域であることを確信した。
第三章 エデンの原罪
朔は、音声記録に残された微かな環境音と、彼女が口にした駅名を頼りに、ついに依頼人No.401――水野玲子という女性の住所を突き止めた。ルール違反もここまで来れば、もう後戻りはできない。覚悟を決め、古びたアパートのドアをノックする。中から聞こえてきたのは、警戒心に満ちた女性の声だった。
ドアが開き、玲子が顔を覗かせた。朔の顔を見た瞬間、彼女の目は恐怖に見開かれた。まるで、死んだはずの人間にでも出会ったかのように。
「あなた…なぜ…」
彼女の動揺を無視して、朔は部屋の中に視線を走らせた。そして、言葉を失った。部屋の奥、おもちゃが散らばる小さなスペースで、一人の少年が積み木で遊んでいた。交通事故で死んだはずの、彼女の息子。その手には、あの記憶の中で見たものと全く同じ、赤いボールが握られていた。
「どういうことです、水野さん。あなたの息子さんは…生きているじゃないですか」
玲子は崩れるようにその場に座り込み、顔を覆った。嗚咽の合間から、途切れ途切れに真実が語られる。
彼女は、息子を虐待していた。愛したいのに、愛せない。日に日に増していく自己嫌悪と罪悪感。その地獄から逃れるため、彼女はエデンを訪れた。「虐待の記憶」を「事故で息子を失った記憶」に偽装し、売り払ったのだ。だが、消しても消しても、罪悪感は新たな記憶となって彼女の心を苛んだ。だから、彼女は何度もエデンに通い続けた。
「じゃあ、俺が見たあの記憶は…」
「最初の記憶は…夫のものでした」
玲子は顔を上げ、涙に濡れた瞳で朔をまっすぐに見つめた。
「夫は、私のしたことに気づいていました。でも、何も言わなかった。見て見ぬふりをしたんです。その罪悪感に耐えきれず、彼は記憶を売りました。そして…姿を消したんです」
その言葉が、雷のように朔の頭を撃ち抜いた。記憶の中の、雨に打たれて立ち尽くす男。あれは、水野玲子の夫の姿。
「なぜ…なぜ、俺はあの男と同じ顔をしている…?」
「あなたたちは…同じだから」
玲子の声は、憐れむようだった。
「忘却屋は、ただの器じゃない。エデンは、顧客から買い取った強い感情――特に、罪悪感や後悔の記憶を核にして、あなたたちを作り出すんです。感情を受け止めるのに、最も適した人格を作るために。あなたは…私の夫が捨てた『罪悪感』そのものから生まれた存在なのよ」
世界が、音を立てて崩れていく。
沖田朔という存在は、誰かが捨てた後悔の残りカスだった。彼の空虚さは、元々そこにあった感情が抜き取られた跡だった。彼が見た「自分の顔」は、オリジナルである、名も知らぬ男の顔。自分は人間ですらない。誰かの罪の残響。それだけだった。足元がおぼつかなくなり、朔はその場に膝をついた。生まれて初めて、彼は心の底から叫びたい衝動に駆られていた。
第四章 名前のない明日へ
絶望が朔の全身を支配した。自分は、水野玲子の夫が捨てた罪悪感の受け皿。この手も、この声も、この思考さえも、全てが偽物。借り物。自分という存在そのものが、巨大な嘘で塗り固められていた。彼は、床に転がっていた赤いボールを、ただ茫然と見つめていた。
その時だった。積み木で遊んでいた少年が、おずおずと朔に近づいてきた。そして、小さな手で、彼の膝にそっと触れた。その温もりに、朔ははっと我に返った。記憶の中で感じた、事故の直前に失われたはずの温もり。だが、それは今、確かにここに在る。
少年は何も言わず、ただじっと朔の目を見つめていた。その曇りのない瞳の中に、作られた偽物の自分ではなく、ただの「一人の人間」が映っているように思えた。
そうだ、自分は偽物かもしれない。誰かの罪から生まれた、空っぽの存在かもしれない。
――だが、今、この少年に触れたいと思ったのは誰だ? この親子を、このままにはしておけないと感じているのは、誰の感情だ?
それは、水野玲子の夫が捨てた罪悪感ではない。それは、過去の記録でも、誰かから与えられた感情でもない。今、この瞬間に、この場所で、沖田朔の中から生まれた、紛れもない彼自身の「意志」だった。
朔はゆっくりと立ち上がった。玲子に向き直り、静かに、しかし力強い声で告げた。
「エデンに、全てを報告します。あなたと、あなたの息子さんの保護を要請します」
「そんなことをしたら、あなたは…!」
「俺は、もう器じゃない」
朔は、自分の胸に手を当てた。そこには、確かに鼓動があった。それが機械によるものか、生体組織によるものかなど、もはやどうでもよかった。
「俺は、沖田朔です。そして、自分の意志で、あなたたちを助けたい」
組織を裏切れば、消されるだろう。欠陥品として処理される運命が待っている。だが、朔の中に、もはや恐怖はなかった。過去を持たない彼が、初めて自分の手で未来を選び取ろうとしていた。
数日後、朔は小さなアパートの一室で、窓から差し込む朝日を浴びていた。エデンからは追われる身となった。全てを失った。しかし、彼の心は、かつてないほど満たされていた。彼はもう、毎朝、業務日誌を読んで自分を確認する必要はない。昨日の記憶は、確かに今日の自分へと繋がっている。
彼は何者でもない。誰かの記憶の影でも、罪の残響でもない。これから歩む道が、彼を「沖田朔」にしていくのだ。過去はない。だが、名前のない明日が、無限に広がっている。
朔は窓を開け、街の喧騒に満ちた空気を深く吸い込んだ。それは、新しい世界の匂いがした。彼は、空っぽのキャンバスに、自分だけの色で、最初の物語を描き始めるために、静かに一歩を踏み出した。