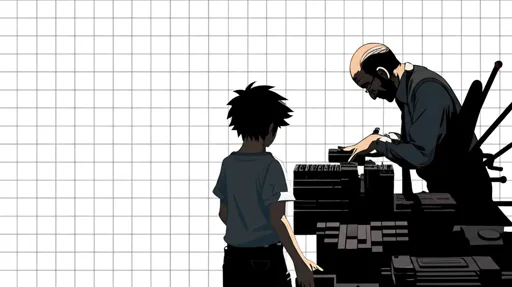第一章 色褪せたインクの依頼
柏木湊(かしわぎ みなと)の事務所は、路地裏の古い雑居ビルの二階にあった。階段を上るたびに軋む音が鳴り、ドアを開ければ、古紙と埃の混じった独特の匂いが鼻をつく。彼は「遺品鑑定士」という、少々変わった肩書を名乗っていた。しかし、彼が本当に鑑定しているのは、品物の金銭的価値ではない。その品物が持つ、最後の持ち主の「記憶」だった。
湊には、物に触れるとその持ち主の最期の瞬間の光景と感情を追体験できる、という呪いのような能力があった。強烈な死の苦痛、後悔、絶望。それらは洪水のように湊の精神を削り、彼を人間嫌いの皮肉屋へと変えていった。だから、彼は依頼を選ぶ。死の匂いがしない、穏やかな記憶だけを求めて。
その日、ドアベルを鳴らしたのは、背筋をしゃんと伸ばした小柄な老婆だった。上質な、しかし着古された和服を身にまとい、その顔には深い皺が、まるで美しい地図のように刻まれている。
「柏木先生でいらっしゃいますか」
「……ええ。まあ」
老婆は深々と頭を下げ、風呂敷包みを丁寧にテーブルの上に置いた。名は、藤堂千代(とうどう ちよ)と名乗った。
「先日、夫が亡くなりまして。主人が長年愛用しておりました万年筆を、鑑定していただきたく参りました」
風呂敷の中から現れたのは、黒檀の軸を持つ、使い込まれた万年筆だった。金色のペン先は摩耗し、持ち主の手の形に馴染んでいる。湊は無感動を装い、それを手に取ろうとした。だが、千代が続けた言葉に、彼の指が止まる。
「価値が知りたいのではございません。あのお人が、最後に何を見て、何を想って逝ったのか……それを、どうしても知りたくて」
湊の眉がぴくりと動いた。またこの手の依頼か。感傷的な遺族が、死者の心を覗きたがる。湊にとって、それは最も避けたい依頼だった。他人の死の淵を覗き込み、その感情の残滓を啜る行為は、魂をすり減らす。
「奥さん、うちは探偵事務所じゃない。モノの価値を測るのが仕事でして」
冷たく突き放す湊に、千代は静かに微笑んだ。その瞳は、まるで全てを見透かしているかのように澄んでいた。
「ええ、存じております。ですが、あなた様なら、この万年筆が語る言葉を聴いてくださる。そう、直感が申しておりますの」
湊はため息をついた。この老婆の揺るぎない眼差しは、彼が築き上げた心の壁を、いとも容易くすり抜けてくる。彼は渋々万年筆を手に取った。ひんやりとした感触が、指先からゆっくりと腕を這い上がってくる。目を閉じると、意識が冷たい水底へと沈んでいくような、あの不快な感覚が始まった。
第二章 桜並木の静寂
湊の意識は、見知らぬ書斎にいた。窓の外には、まるで燃え立つような満開の桜並木が広がっている。風が吹き、薄紅色の花びらが雪のように舞い散っていた。陽光が埃をきらきらと照らし、部屋は信じられないほどの静寂に満ちている。
これが、藤堂健一という男の最後の光景。
湊の全身を包んだのは、苦痛でも後悔でもなかった。ただ、深く、穏やかな感情。まるで長い旅を終えた旅人のような、安堵にも似た諦観。彼はゆっくりと息を吐き、桜吹雪から目を離さずに、その時を迎えた。何の波乱もない、あまりにも静謐な最期だった。
「……ご主人は、窓から見える桜を見ていました」
現実に戻った湊は、額に浮かんだ冷や汗を拭いながら千代に告げた。「とても、穏やかな最期でしたよ。苦しみも、悲しみもなかった」
それを聞いた千代の目から、一筋の涙がこぼれ落ちた。しかし、その表情は安堵に満ちていた。「そうですか……あのお人らしい、静かな最期でございましたね。ありがとうございます、先生」
彼女は深々と頭を下げ、万年筆を大切そうに風呂敷に包み直すと、静かに事務所を去っていった。
一件落着。のはずだった。だが、湊の心には、小さな棘が刺さったままだった。
あまりにも、静かすぎる。
湊がこれまで体験してきた死の記憶は、多かれ少なかれ、生への執着や、やり残したことへの無念が混じっていた。たとえ老衰による穏やかな死であっても、そこには微かな揺らぎがあるものだ。しかし、藤堂健一の記憶には、それが一切なかった。まるで、この世の全てを受け入れ、自らスイッチを切るかのように、完璧に凪いでいた。
死因は書斎での心臓発作と聞いた。それならば、多少の苦痛があってしかるべきだ。なのに、あの記憶には一片の苦しみもなかった。まるで、美しい絵画を眺めているかのような、客観的でさえある静けさ。
その違和感は、数日経っても湊の心を蝕み続けた。彼は夜ごと、あの桜並木の夢を見た。夢の中では、自分自身が藤堂健一となり、ただひたすらに舞い散る桜を眺めている。そのたびに、あの奇妙な諦観が胸に広がり、息が詰まるような感覚に襲われた。
このままではいけない。湊は、もう一度あの記憶に触れることを決意した。真実が何であれ、この正体不明の感情の残滓から、自分を解放しなければならなかった。彼は千代の連絡先を調べ、受話器を取った。
第三章 あなたが見ていた光
「申し訳ありません、藤堂さん。もう一度、ご主人の書斎を拝見できませんでしょうか。鑑定で、少し気になることがありまして」
千代は何も問わず、湊を快く家に招き入れた。手入れの行き届いた庭を抜け、案内された書斎は、湊が記憶の中で見た光景そのものだった。そして、窓の外には葉桜になりかけた桜並木が、初夏の日差しを浴びていた。
「どうぞ、ごゆっくり」
そう言って千代が部屋を出ていくと、湊は机の上に置かせてもらった万年筆を、再び手に取った。今度はもっと深く、意識の奥底まで潜る。あの静寂の源泉を探るために。
再び、満開の桜並木の光景が広がる。しかし、今度は違った。湊はただの傍観者ではなかった。健一の感情のさらに奥、その視線の先に意識を集中させる。すると、桜並木の手前に、ぼんやりと人影が浮かび上がった。
それは、着物姿の若い女性だった。黒髪をなびかせ、屈託なく笑っている。湊は息を呑んだ。若い頃の千代だ。彼女の幻影は、桜吹雪の中で、健一に向かって優しく手を振っている。
その時、湊の脳裏に、健一の心の声が直接響いてきた。それは言葉というより、純粋な想いの奔流だった。
『千代。すまない。もう、限界だ。私のせいで、お前の時間をこれ以上奪うわけにはいかない』
『これでいい。これで、お前は自由だ。先に逝って、お前が愛したこの桜の下で待っている』
湊は、まるで殴られたかのような衝撃で現実世界に引き戻された。ぜえぜえと肩で息をし、全身は汗でぐっしょりと濡れている。
そういうことだったのか。
藤堂健一の死は、穏やかな自然死などではなかった。彼は、長年自分の介護を続けてきた妻を解放するために、自らの意思で、人生の幕を引いたのだ。あの静寂は、全てを覚悟した者の、究極の愛情の形だった。
湊は呆然と立ち尽くした。これを、千代に伝えるべきなのか?
夫が自ら死を選んだという事実は、彼女の心を深く傷つけるだろう。穏やかな最期だったという美しい嘘のままでいれば、彼女は安らかに余生を送れるかもしれない。しかし、夫が命を懸けて伝えようとした最後のメッセージを、自分の判断で握りつぶしてしまっていいのか。それは、彼の魂への裏切りではないのか。
これまで他人の死に無関心でいることで自分を守ってきた湊は、初めて、死者の想いを「どう伝えるべきか」という重い責任に直面していた。
彼の視線が、机の隅に置かれた一枚の写真立てに吸い寄せられた。そこには、若い健一と千代が、あの桜並木の下で、満面の笑みを浮かべて寄り添っていた。健一が見ていたのは、ただの桜ではない。桜の下にいる「若き日の妻」の姿であり、彼女と共に生きてきた幸福な記憶そのものだったのだ。
湊は、覚悟を決めた。
第四章 残された者のための言葉
湊は縁側で茶を淹れていた千代の前に、静かに座った。何を切り出すべきか、言葉が喉につかえる。その沈黙を破ったのは、千代の方だった。
「先生。何か、お分かりになりましたのね」
その声は、全てを受け入れる覚悟を決めた者のように、穏やかだった。
湊はゆっくりと頷き、視た光景を、そして聴こえた想いを、一言一言選びながら、丁寧に伝えた。健一が見ていたのは、ただの桜ではなく、桜の下で笑う若い頃の千代の姿であったこと。そして、彼女を深く愛するがゆえに、彼女を介護という重荷から解放したかったのだ、という最後のメッセージを。
話が終わると、長い沈黙が流れた。千代はただじっと、庭の木々を見つめていた。やがて、その皺の刻まれた目から、大粒の涙が静かにこぼれ落ちた。しかし、その表情に絶望の色はなかった。
「……あのお人は、どこまでも勝手な人。最後まで、私に相談の一つもしてくれない」
震える声でそう言うと、彼女はふっと、寂しそうに、しかしどこか嬉しそうに微笑んだ。
「でも、これで良かったのかもしれません。あのお人の最後の想いを知ることができて……。先生、本当にありがとうございました。これで私も、心置きなく、あのお人のところへ旅立てます」
その微笑みは、深い愛情を受け取った者だけが浮かべられる、安らかで、美しいものだった。
数ヶ月後、湊の元に、千代の訃報を知らせる葉書が届いた。親族によると、眠るように安らかに、大往生だったという。
湊はあの日以来、初めて藤堂家のあった場所を訪れた。家は既に取り壊され、更地になっていたが、その向こうには、変わらず美しい桜並木が、夏の強い日差しを浴びて力強く枝を伸ばしていた。
これまで、他人の死の瞬間に触れる能力を、湊は呪いだと感じてきた。それは彼の心を蝕み、世界から孤立させるだけのものだった。
だが、藤堂夫妻の愛の形に触れた今、彼は違う考えを抱き始めていた。死は、必ずしも断絶や終わりだけを意味するわけではない。それは、残された者の心の中で、記憶として、愛として、永遠に生き続ける物語の始まりでもあるのかもしれない。そして自分のこの能力は、その目に見えない繋がりを拾い上げ、残された者のために言葉を紡ぐ、尊い役割を担っているのではないか。
湊はポケットから、彼自身が長年愛用している万年筆を取り出した。そして、真新しい手帳の最初のページを開く。
彼はそこに、藤堂健一が見た最後の光景を、舞い散る桜の花びらの一枚一枚まで思い出しながら、書き留め始めた。それは誰かに見せるための記録ではない。彼が鑑定した「魂の物語」を、決して忘れずに、自らの心に刻み込むための、新しい誓いだった。
風が吹き抜け、まるで喝采のように、緑の葉を揺らした。湊は顔を上げ、空を見つめる。その表情は、もうかつての皮肉屋のものではなかった。