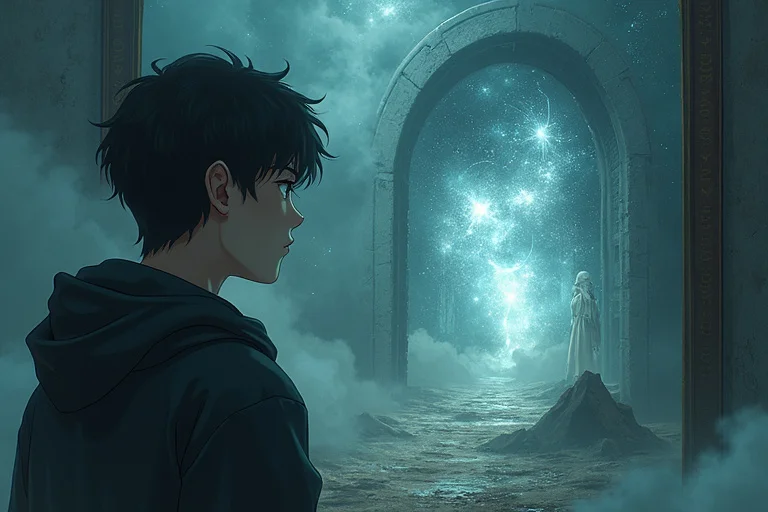第一章 澱む甘味と金属の予感
その日、私の世界は、いつものように甘く澱んだ嘘の匂いに満ちていた。喫茶店の喧騒の中、隣の席で繰り広げられる恋人たちの甘言、テレビから流れる政治家の建前、そしてSNSの画面に映し出される偽りの幸福。それら全てが、私、桜井ユイの舌の上で、それぞれの不快な味覚として立ち現れる。砂糖の塊を溶かしたような吐き気を催す甘さ、酸っぱく胸焼けするような後悔の味、あるいは錆びた釘を舐めたような金属的な感覚。生まれつきの共感覚、「嘘の味」は、私を常に真実の断片と偽りの層の狭間に置き、人との間に透明な壁を築き上げてきた。
そんな私の唯一の拠り所であり、壁の向こう側から手を差し伸べてくれる存在だったのが、親友のミキだった。彼女は私の能力を理解しようと努め、無遠慮な質問をすることも、安易な同情をすることもなかった。ただ、そばにいてくれる、それがミキだった。だが、そのミキが、突然姿を消した。
連絡が途絶えて三日目の夜、ミキの恋人であるタカシが、私の住むアパートのドアを叩いた。彼の顔には疲労と不安が色濃く刻まれていたが、その言葉の端々から、私は微かな、しかし明確な「金属のような」嘘の味を感じ取った。
「ユイさん、ミキがどこにもいないんだ。警察にも届けたけど、手がかりがなくて……」
彼の声は震えていたが、その金属味は、「嘘」というよりは「隠蔽」に近い、何かを覆い隠そうとする冷たい膜のようだった。ミキを捜しているという言葉そのものには嘘はない。だが、その背後にある、言葉にならない何か。私はタカシの目を見つめたが、彼の瞳は怯えと、そして微かな動揺を孕んでいた。
「何か、心当たりは?」私は問いかけた。
タカシは首を横に振った。「いや、全然。ケンカもしてないし、急に……」
その否定の言葉の裏にも、やはり金属味がまとわりつく。私は言葉を飲み込んだ。タカシが何を隠しているのか、その時点では皆目見当がつかなかった。しかし、この味は、ミキの失踪と無関係ではないと直感した。
警察の捜査は難航していた。ミキの部屋には争った形跡はなく、物色された様子もない。ただ、彼女がいつも持ち歩いていたスケッチブックと、最近まで肌身離さず持っていたノートパソコンが消えていた。
私は警察の許可を得て、ミキの部屋に入った。家具はきちんと整頓され、日用品もそのまま。しかし、その整然とした空間に、私は奇妙な違和感を覚えた。生活感が、唐突に途切れたような、そんな静寂が漂っていた。
その時、ベッドサイドの小さなテーブルの端に、一枚の折り畳まれたメモがあるのに気づいた。何かの下に隠されていたわけではなく、ただ無造作に置かれているように見える。私はそれを広げた。そこには、走り書きのような文字で、不規則な英数字の羅列が記されていた。
「R3N@I-K@9U-0S@0」
私はその文字列を指でなぞった。すると、舌の奥に、「焦げ付いたような、辛い」味が広がった。それは、強いメッセージ性を持つ嘘、あるいは、真実を巧妙に隠蔽するための偽りの痕跡から立ち上る味だった。このメモは、ただの暗号ではない。ミキからの、何らかの信号だ。私の胸に、新たな不安と、しかし同時に微かな希望が芽生えた。この味は、ミキがまだどこかにいて、私に何かを伝えようとしている証拠のように思えた。
第二章 偽りの糸、追憶の香り
ミキの失踪から一週間が経過し、世間の関心は薄れ始めていた。警察の捜査も定型的なものになり、私は焦燥感に駆られていた。タカシの言葉の裏にあった金属味、そしてミキのメモから感じた焦げ付くような辛い味。これらが私を突き動かした。私は自分の能力を、初めて誰かのために使いたいと思った。
私はまずタカシを調べることにした。彼の日常を観察し、行動パターンを探る。数日後、私は彼の裏切りを目撃した。彼はミキの失踪を悲しむふりをしながら、別の女性と密会していたのだ。待ち合わせのカフェで、二人は親密そうに話していた。その女性の言葉から、私は「甘ったるい」嘘の味を感じ取った。それは、タカシに向けられた、媚びたような、しかし偽りのない愛情を装った嘘だった。一方、タカシの言葉からは相変わらず金属味がした。彼が隠しているのは、ミキとの関係の終わりや、この女性との関係だけではない。もっと深く、暗い何かがある。
私は次に、ミキの行動範囲を探ることにした。彼女は最近、環境保護を謳う新興宗教団体「アース・ブレス」に傾倒していたと、共通の友人が教えてくれた。私は半信半疑ながらも、団体の集会へと足を運んだ。壇上で熱弁を振るう教祖の言葉からは、大量の「シロップのような、ねっとりとした甘い」嘘の味がした。それは、聞く者の心を癒やし、安心させるように巧みに調合された、危険な甘さだった。信者たちの熱狂的な眼差しの中、私は団体の幹部の一人に接触を試みた。彼はミキの入信を認め、「彼女は真理を求め、この世界に救いの手を差し伸べる使命を感じていました」と穏やかに語った。しかし、彼の言葉の端々からは、「薬のような、鈍い苦味」がした。それは、意図的に感情を抑制し、作り上げられた平静さの裏に隠された、冷たい計算の味だった。ミキが本当に彼らの真理を信じていたのか、それとも何かに利用されていたのか、分からなくなった。
夜、自分のアパートに戻ると、私はミキの残した暗号メモを改めて見つめた。「R3N@I-K@9U-0S@0」。焦げ付くような辛い味を思い出しながら、私は頭を捻った。英数字の羅列。何かのパスワードだろうか。ミキは昔から、変わった記号の使い方をするのが好きだった。特に、数字をアルファベットに見立てることが多かった。
R3N@I → RENAI(恋愛)
K@9U → KAGU(家具)
0S@0 → OSATO(砂糖?)
「恋愛」「家具」「砂糖」……何の意味がある?ミキらしくない無関係な単語の羅列に思えた。
しかし、ふと私は、ミキが最近開発していたアプリのことを思い出した。彼女は「真実の断片」という、人の言葉の真偽をAIが判定するプロトタイプアプリを作っていた。冗談めかして「ユイの能力を再現するアプリ」だと笑っていたのを覚えている。そのアプリには、強固なセキュリティがかかっていると言っていた。
「もしかして……」
私は、ミキが昔から好きだったある作家の作品名を思い出した。その作家は、作品のタイトルに「恋愛」という言葉をよく使っていた。そして、ミキはその作家の作品を読んだ後、必ず「家具」について語っていた。最後に、「砂糖」は彼女がコーヒーに入れる際の口癖だった。
恋愛、家具、砂糖。これらは、彼女の人生の節目や興味の対象と密接に結びついていた。これらを組み合わせたパスワードなのではないか。私は急いでパソコンを立ち上げ、ミキが使っていたと思われるアカウントにログインを試みた。
第三章 恩師の計画、血の味の真実
ミキのアプリにアクセスすることは、予想以上に困難を極めた。彼女が残した断片的なヒントを組み合わせ、試行錯誤を繰り返すこと数十回。ようやく私は、パスワードを特定し、ミキのタブレットにインストールされていたその「真実の断片」アプリの奥深くへと足を踏み入れた。画面いっぱいに広がる、ミキが収集した膨大なデータ。様々な人の会話の記録、ニュース記事の真偽判定、そして、最終的に私は、彼女が失踪する直前に残したと思われる音声ファイルを発見した。
再生ボタンを押す。スピーカーから流れ出したのは、ミキの声だった。
「タカシ、なぜ邪魔するの?これはユイのためだと言ったでしょう!」
焦燥感に満ちたミキの声に続き、男性の声が聞こえた。それは、まさしくタカシの声だ。
「ミキ、もうやめよう。こんなこと、ユイが知ったらどう思うか……。危険すぎる」
金属味がしたタカシの言葉は、このことだったのか。しかし、彼の次の言葉で、私の脳裏に雷鳴が轟いた。
「サエキ教授は、本当にユイのためだと……」
サエキ教授。その名を聞いた瞬間、私の全身から血の気が引いた。サエキ教授は、私が大学時代に師事した文学部の教授で、私の共感覚能力を唯一、頭ごなしに否定せず、真剣に耳を傾けてくれた人物だった。彼は私にとって、学問上の師であると同時に、精神的な支えでもあった。彼の言葉からは常に、清冽で透明な、真実の味がした。私は彼を、心から信頼し、尊敬していた。
しかし、そのサエキ教授が、なぜこの件に関わっているのか。そして、「ユイのため」とは、一体どういう意味なのか?
音声ファイルはさらに続く。ミキとタカシの口論の隙間から、もう一人の声が割り込んだ。
「計画は滞りなく進んでいる。タカシ君、君はもう役目を終えた。後は私が引き継ごう」
その声は、紛れもない、サエキ教授の声だった。私は耳を疑った。サエキ教授の声から、私はかつて感じたことのない、生々しい「血のような、鉄の味」を感じた。それは、絶対的な真実を語る彼の言葉からは決して感じられるはずのない、悍ましい味だった。
「ミキ、君もここで眠ってくれたまえ。君はユイの能力の鍵となる存在だ。そして、ユイ自身もまた、その鍵となる。」
その言葉の後に、薬物を吸引するような「シュッ」という音と、ミキの苦しげな呻き声、そして物が倒れるような衝撃音が聞こえた。そして、音声は途切れた。
私は呼吸を忘れていた。サエキ教授がミキを……?
そして、「ユイの能力の鍵」とは何だ?
私はもう一度、音声ファイルを最初から再生した。サエキ教授の言葉、ミキの焦燥。タカシの動揺。
その言葉の真の意味を理解しようと、私は必死に思考を巡らせた。
サエキ教授は、私の共感覚能力に並々ならぬ関心を示していた。彼は私の能力を「人類の未来を左右する才能」だと評し、そのメカニズムを解明したいと語っていた。しかし、それは単なる学術的探究心ではなかったのか?
音声ファイルから導き出される結論は、あまりにも恐ろしいものだった。サエキ教授は、私の能力を解明し、それを応用して「絶対的な真実を語らせるシステム」を構築しようとしていた。ミキは、その研究の協力者であり、ユイをそのシステムに組み込むための「実験」として、失踪を計画させられていた。つまり、ミキの失踪は「嘘」で、サエキ教授とミキが協力して仕組んだものだったのだ。
「ユイのため」とは、ユイの能力を世に知らしめ、その力を利用して社会を「真実」で満たす、というサエキ教授の狂信的な理想だった。
しかし、私が最大の衝撃を受けたのは、さらに奥に隠されたもう一つの事実だった。ミキがアプリの中に残した、研究資料らしきデータフォルダ。そこに、私の名前が記された古い医療カルテが紛れ込んでいたのだ。幼少期の私のカルテ。そこには、私の共感覚能力が、ある種の「脳機能活性化実験」によって「後天的に発現したもの」であることが記されていた。サエキ教授は、私の能力を「発見」したのではなく、「作り出した」のだ。私の幼少期の記憶が曖昧なのは、その実験の副作用だった。
私は、自分自身の根幹が、他者の意図によって作られたものだという事実に打ちのめされた。私が唯一信じられたはずの「真実の味」さえも、偽りの起源を持っていたのか。私の存在そのものが、サエキ教授の「嘘」から生まれた実験体だったのか?
膝から崩れ落ちる私。血の味が、私の舌を満たしていた。
第四章 虚構の淵、そして夜明け
私の心は、根底から揺さぶられていた。これまで私自身を定義してきた能力が、尊敬する恩師によって「作られた」ものだという事実。そして、その恩師が、私の親友を巻き込み、私を欺いていたこと。目の前の世界が、一瞬にして虚構と裏切りの淵に沈んだようだった。しかし、ミキの最後のメッセージが、私の心に僅かな光を灯した。彼女が残したパスワードとアプリの奥に、もう一つのファイルがあった。そこにはミキの自撮り動画が保存されており、彼女は意識が朦朧としながらも、私に語りかけていた。
「ユイ……ごめんね。サエキ教授は、あなたの能力を『進化』させるつもりだった。でも、私は知ってしまったの。教授の本当の目的は、あなたの能力を……ある強力な組織に『提供』することだった。彼らは、あなたの能力を解析し、量産しようとしている。私たちが思っている以上に、あなたの能力は危ないのよ」
ミキの顔は青ざめ、息も絶え絶えだった。「私は、教授の計画を妨害するために、協力するふりをしていた。あなたの能力が、誰かに奪われることだけは阻止したかった。このデータは……あなたが生きるための、唯一の道。信じて……」
動画はそこで途切れた。私の能力は、サエキ教授によって作られたものではなかった。正確には、サエキ教授が私に「植え付けた」能力は、別の研究機関が目を付けていた私の潜在的な資質を「引き出す」ための装置だったのだ。ミキは、私がその「装置」として利用されることを防ぐため、サエキ教授の計画に乗ったふりをして、私に真実を伝えようとしていた。彼女は、私を守るために、自らを危険に晒していたのだ。その動画からは、私への深い愛情と、純粋な自己犠牲の味がした。それは、私の人生で初めて感じた、全く濁りのない、透き通るような真実の味だった。
私はミキの残したヒントと、アプリの真実から、サエキ教授が隠していた秘密の研究所の場所を特定した。そこは大学の地下に広がる、無機質な実験施設だった。薄暗い廊下を進むと、ガラス張りの部屋に、拘束されたミキの姿があった。彼女は意識を失っており、胸には複数の電極が付けられている。
その時、背後からサエキ教授の声がした。「よく来たね、ユイ。君は私の最高の傑作だ。そして、ミキは、その傑作をさらに完璧にするための最後のピースだった」
私は振り返った。教授の顔には、狂信的なまでの使命感が宿っている。彼の言葉からは、かつてないほど「純粋だが、しかし冷たい、無機質な」味を感じた。それは、一切の私欲や感情が排された、歪んだ「真実」の味だった。彼は、本当に人類のためだと信じている。しかし、その「真実」は、他者の尊厳を踏みにじる、あまりにも傲慢なものだった。
「あなたの言う真実とは、人の心を無視した、ただのデータですか」私は問いかけた。
「データこそが真実だ。感情はノイズに過ぎない」教授は断言した。
その瞬間、私はミキの言葉を思い出した。「あなたの能力は、誰かに与えられたものではない。私たち自身のものだ。信じて」。
私は気づいた。私の共感覚能力は、たとえその起源が他者の介入によるものだったとしても、今や私自身のものだ。それをどう使うかは、私自身が選ぶべきものだ。サエキ教授の目指す「真実」は、人間性から切り離された冷たい概念だ。だが、私の感じる「嘘の味」は、人間の感情、意図、葛藤が生み出す複雑な匂いだ。それは、善悪では割り切れない、人間らしさそのものなのだ。
私はミキを救い出すために、そして、自分自身の真実を見つけるために、サエキ教授の計画を阻止することを決意した。私は彼に真正面から向き合い、彼の「真実」が、いかに多くの嘘の上に成り立っているかを、私の「嘘の味」を頼りに言葉で突きつけた。私の言葉は、教授の揺るぎない確信に、微かな亀裂を入れたようだった。
騒ぎを聞きつけた警備員と、通報を受けて駆けつけた警察によってサエキ教授は逮捕された。ミキは一命を取り留めたものの、長期の入院が必要となった。私はミキの病室で、彼女の握りしめていた一枚の紙を見つけた。そこには「世界は、真実だけでできているわけじゃない。嘘の中にも、愛はある」と、震える文字で書かれていた。
私は、自身の能力とミキの自己犠牲を通じて、「真実」とは何か、そして人間関係における「嘘」の持つ複雑な意味について深く考えるようになった。完全な真実が常に幸福をもたらすわけではない。時には、優しい嘘が、人を救うこともある。そして、真実を求めるあまり、人間性を失ってはならない。
私の世界は、これからも「嘘の味」に満ちているだろう。だが、それはもはや、私を苦しめるだけの不快なものではなかった。それは、人々の心の機微を、複雑な感情の織りなす綾を、私に教えてくれる羅針盤となったのだ。私は嘘を恐れるのではなく、それを理解し、人との繋がり方を模索する。ミキの残した言葉が、私の心の中で、新しい夜明けの光のように輝いていた。