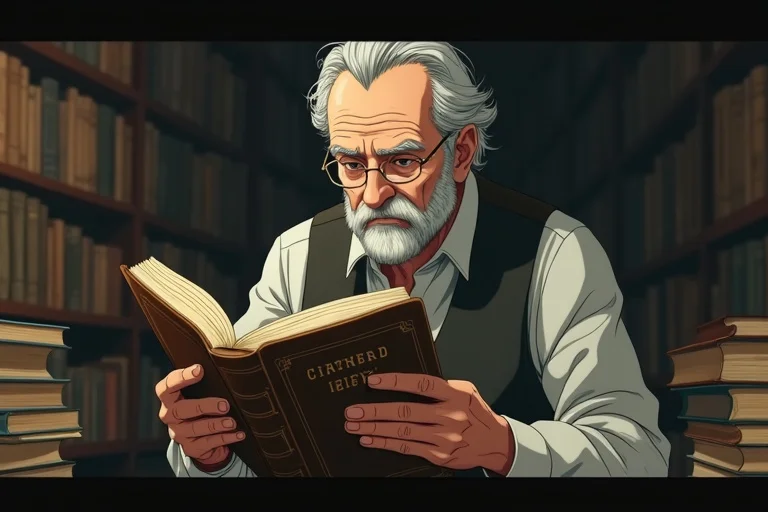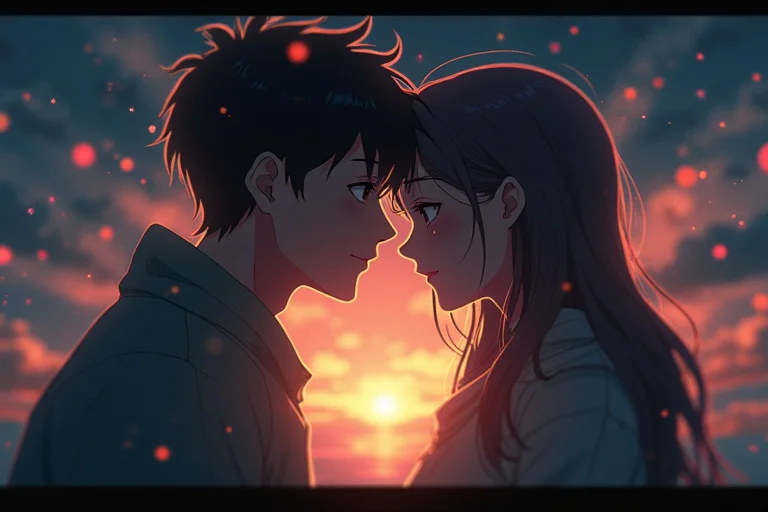第一章 偽りの和音
廃工場の鉄錆と、腐った雨の臭い。
私は遺体の前でしゃがみ込み、革手袋を噛んで外した。
「三分だ」
背後で硬質な音が鳴る。
ケイがジッポライターの蓋を弾いたのだ。
それが、私たちが「境界線」を越える合図。彼はいつも、私の意識が戻るまでの時間を、正確に計測して見守っている。
「頼む」
私は素手を、血の海に沈む被害者のこめかみに押し当てた。
粘ついた感触。瞬時に、他人の人生が脳髄へとなだれ込む。
――温かなシチューの湯気。
――祝日の食卓。
――『ねんねん、ころりよ』と歌う、優しい母の声。
幸福な記憶だ。あまりにも、完璧すぎる。
だが、違和感が走った。
視界の端で、母の顔がノイズのようにざらついた瞬間、シチューの匂いが、鼻を突く「焦げ臭さ」に変質したのだ。
(……なんだ、この混線は?)
被害者の記憶じゃない。
これは、私の記憶だ。
炎。悲鳴。そして、その地獄絵図の中で、オルゴールを回し続ける誰かの手。
激痛がこめかみを貫く。
私は弾かれたように手を離し、泥水の中へ倒れ込んだ。
「アオイ!」
ケイが滑り込み、私の頭を抱え込む。
馴染み深いタバコの香り。
その匂いに安堵した瞬間、私の視界がぐにゃりと歪んだ。
目の前の看板。
そこに書かれているはずの『立入禁止』という文字が、ただの棒線の集合体に見える。
読めない。意味が、滑り落ちていく。
「……ケイ」
私は震える手で、彼の襟を掴んだ。
「私の、名前」
「何言ってるんだ、アオイだろ」
「アオイ……アオイ……」
その音の響きが、ゲシュタルト崩壊を起こして砂のように散る。
自分の名前が、記号にしか思えない。
記憶の欠落は、静寂ではなく、生理的な不快感を伴って私の一部を削ぎ落としていった。
ケイの視線が、泳いだ。
彼は私が掴んだ襟の手を、優しく、けれど拒絶するように剥がした。
「……戻ろう。今日の仕事は終わりだ」
第二章 真鍮の懺悔
アジトの静寂を、ゼンマイの軋む音が支配している。
私は証拠品のオルゴール――真鍮製の『揺り籠』をテーブルに置いた。
現場で聴こえた歌。
私の深層意識にこびりついているメロディ。
「ねえ、ケイ。変だと思わないか」
私は彼に背を向けたまま、オルゴールのストッパーを外した。
『ねんねん、ころりよ……』
調子の外れた旋律が、部屋の空気を凍らせる。
「被害者たちは全員、過去に凄惨なトラウマを持っていた。なのに、彼らの記憶は一様に『幸福な食卓』に上書きされている。この曲と共に」
振り返ると、ケイが銃を構えていた。
銃口は私に向けられている。
だが、その引き金にかかった指は、白くなるほど震えていた。
「……やめろ、アオイ。それ以上、深く潜るな」
彼の瞳。
いつも私を導いてくれた冷静な瞳が、今は懇願するように潤んでいる。
その表情を見た瞬間、私の脳内でパズルのピースが噛み合った。
現場での、不自然なほど早い到着。
私の記憶がフラッシュバックするたびに、彼が見せた微かな安堵と、深い罪悪感。
「お前だったのか」
私の問いに、ケイは答えなかった。
ただ、銃口が僅かに下がる。
私の脳裏に、封印されていた映像が焼きつく。
燃え盛る家。
泣き叫ぶ私に、このオルゴールを聴かせ、「忘れろ」と囁き続ける少年の姿。
その少年の手の甲には、ケイと同じ火傷の痕があった。
「お前が、私の記憶を改竄した。……私を守るために?」
「……お前が壊れそうだったからだ!」
ケイが吼えた。
初めて聞く、悲鳴のような声。
「耐えられなかったんだ。お前が、自分の力で両親を焼き殺した事実に気づくのが。だから俺は、お前の能力を逆流させて、偽りの記憶を植え付けた。……だが、その『蓋』は、他の人間には猛毒だったようだ」
私の罪を隠すための『揺り籠』が、他人を狂わせ、死へ追いやった。
それが、連続不審死の真相。
「アオイ、俺を撃て。そうすれば、お前の記憶は永遠に戻らない。お前は『被害者』のままでいられる」
ケイは銃を床に捨て、両手を広げた。
その姿は、十字架に張り付けられた罪人のようだった。
第三章 空白の朝
「馬鹿な奴だ」
私はケイの胸倉を掴み、彼を壁に押し付けた。
殴りかかるのではない。
私は手袋を脱ぎ捨て、彼の額に自分の額を押し当てた。
「アオイ、何を……!?」
「お前の記憶も、私の記憶も。諸共、消し飛ばす」
「やめろ! それをすれば、お前の自我が……!」
「構わない!」
私は能力を解放する。
視るのではない。喰らうのだ。
ケイの中に根付く「私への献身」と、私の中に巣食う「偽りの幸福」。
その二つが複雑に絡み合った『共依存』の回路を、無理やり引きちぎる。
激痛。
脳を直接、火箸で掻き回されるような感覚。
――アオイ、今日はパスタだ。
――うるさいな、ケイ。タバコ吸わせろよ。
――背中は任せたぞ。
――ああ、信じてる。
数え切れないほどの「日常」が、走馬灯のように駆け巡り、そして燃え尽きていく。
どれだけ大切でも。
どれだけ愛しくても。
それが、罪の上に築かれた砂上の楼閣なら、私は瓦礫の下敷きになって死ぬことを選ぶ。
「ぐ、ああああああッ!」
ケイの絶叫が鼓膜を打つ。
彼の記憶から、私の存在が消えていく手応えがあった。
同時に、私の中からも「ケイ」という概念が剥落していく。
目の前にいる男の顔が、急速に「知らない他人」へと変わる。
親密さが消え、色彩が褪せ、ただの「肉の塊」として認識される。
怖い。
独りになるのが、たまらなく怖い。
私は縋るように、目の前の他人の服を握りしめた。
指先から感覚が失われる。
言葉が、意味をなさなくなる。
最後に残ったのは、焦げ付くような哀しみだけ。
それさえも、白い闇が飲み込んでいった。
終章 残響
小鳥のさえずりで、目が覚めた。
白い天井。消毒液の匂い。
私はベッドの上で身を起こし、サイドテーブルの水を飲んだ。
喉が渇いていたことすら、水を飲むまで気づかなかった。
「気分はどうですか? 402号室さん」
看護師の女性が、朗らかに声をかけてくる。
私は曖昧に頷いた。
言葉を発そうとしたが、喉の奥で音が詰まる。
自分には、名前がない気がした。
過去もない。
ただ、ここに「在る」という事実だけが、奇妙に重い。
ふと、窓の外を見る。
中庭のベンチに、一人の男が座っていた。
猫背で、虚空を見つめながら、右手の親指でカチ、カチと何かを弾く仕草をしている。
ライターの蓋を開閉するような動作だ。
だが、その手には何も握られていない。
見知らぬ男だ。
なのに、胸の奥が焼けるように痛んだ。
理由もわからず、涙が溢れた。
私は窓ガラスに手を当てる。
冷たい感触。
男がふと、こちらを見上げた気がした。
目が合った瞬間、彼もまた、怪訝そうに自分の頬に触れている。
私たちはガラス越しに、互いの涙を見つめ合った。
失ったものが何なのかさえ、もう二度と思い出せないまま。