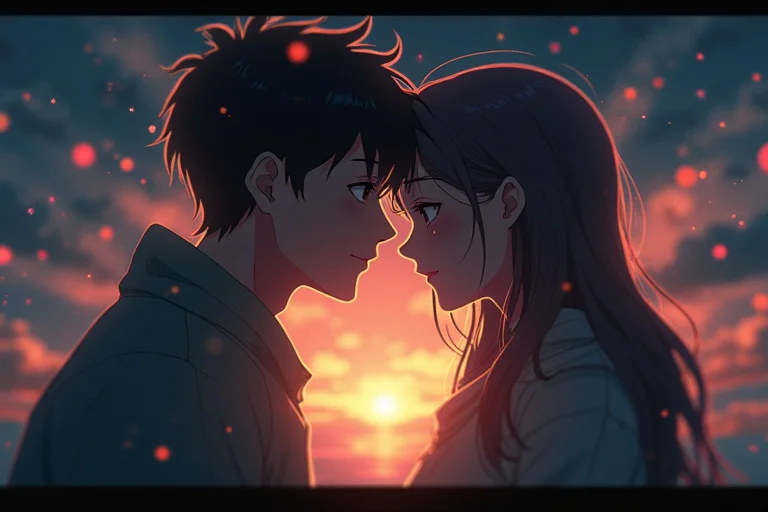第一章 後悔の残響
夜明け前の静寂を、耳鳴りのような鋭い感情が引き裂いた。
それは音ではない。匂いでも、肌触りでもない。だが、音響設計士である水上漣(みなかみ れん)の全感覚を麻痺させるほどに強烈な「後悔」の奔流だった。
息が詰まる。心臓が氷の手に鷲掴みにされたように軋み、過去のどんな失敗も比較にならないほどの絶望的な喪失感が、彼の精神を根こそぎ揺さぶった。漣はベッドから転げ落ち、冷たいフローリングに蹲ったまま、見えない敵に耐えるように身を固くした。
これは、未来の自分が体験する感情だ。
理屈では説明できない。だが、漣には確信があった。彼には時折、未来に起こる出来事の「感情の断片」が、予兆として流れ込んでくることがあった。それは、プロジェクトが成功する際の高揚感であったり、乗り遅れる電車の焦燥感であったり、ごく些細なものだ。だが、今感じているこれは、桁が違った。魂が削り取られるような、取り返しのつかない過ちを犯した者の慟哭。
窓の外が白み始め、鳥のさえずりが聞こえてくる。日常の音が、漣の内の異常を際立たせた。ようやく荒い呼吸を整えた彼は、震える手でサイドテーブルに置かれた小さなベルベットの箱に目をやった。中には、恋人である茅野未散(かやの みちる)に贈るための婚約指輪が収まっている。今日、彼女にプロポーズするはずだった。一年間、この日のために完璧なプランを練り上げてきた。
しかし、この地獄のような後悔はなんだ?
この指輪を渡すことが、この後悔に繋がるのか? 未散との結婚が、彼を絶望の淵に突き落とすというのか?
漣は箱を強く握りしめた。冷や汗が背筋を伝う。わからない。何が原因で、いつ、自分がこの後悔を抱くことになるのか、全く見えない。ただ、この感情だけが、まるで未来からの呪いのように、彼の心に焼き付いていた。
彼は決めた。この後悔の正体を突き止めるまで、プロポーズはできない。未来から響いてくるこの声なき絶叫から、自分を、そしておそらくは未散をも守らなければならない。
その日から、漣の日常は、正体不明の後悔から逃れるための、静かなサスペンスへと変貌した。彼は、自らの未来を盗聴する、孤独な探偵になったのだ。
第二章 不協和音の在処
漣の世界から、調和が失われた。音響設計士として、彼は常に完璧なバランスを追求してきた。コンサートホールの残響、スタジオの吸音、そのすべてに秩序と美しさを見出してきた。しかし今、彼の内なる世界は、不快なノイズに満ちていた。あの後悔の残響が、日常のあらゆる瞬間に不意に蘇り、彼の思考をかき乱す。
疑念の矛先は、必然的に最も身近な存在である未散へと向かった。彼女の笑顔の裏に、何かがあるのではないか。彼女の優しい言葉は、何かを隠すための旋律ではないのか。
「漣、最近疲れてる? 顔色が悪いわ」
心配そうに覗き込む未散の瞳を、漣はまっすぐに見ることができなかった。彼女の気遣いすら、後悔の予兆を増幅させるスパイスのように感じられた。
漣は、探るように彼女の行動を観察し始めた。スマートフォンの画面を盗み見る。帰宅が少しでも遅れれば、その理由を執拗に問いただす。未散は最初こそ戸惑っていたが、やがてその視線に気づき、傷ついた表情を見せるようになった。二人の間にあった心地よい沈黙は、息苦しい緊張へと変わっていった。
「私、何かした…?」
そう問う彼女の声は震えていた。漣は真実を話せない。「未来のお前とのことで、俺は後悔するらしい」などと、どうして言えるだろう。彼は曖昧に首を振り、彼女を孤独に突き放すしかなかった。
決定的な疑念が生まれたのは、ある夜のことだった。未散がシャワーを浴びている間に、彼女のスマートフォンが着信を告げた。画面に表示された名前は『高遠』。漣の知らない名前だ。履歴を遡ると、その男と彼女が頻繁に、それも深夜にまで及ぶ長電話を繰り返していることがわかった。
嫉妬と裏切りへの恐怖が、漣の心を黒く塗りつぶした。これだ。これが原因に違いない。未散が自分を裏切り、その関係が破綻する。そして自分は、それに気づけなかった愚かさを生涯後悔するのだ。あまりにありきたりで、しかしあまりにリアルな筋書きだった。
後悔の残響が、嘲笑うかのように漣の耳の奥で鳴り響いた。彼は、この『高遠』という男を突き止め、すべてを終わらせることを決意した。彼の正義は、もはや未散を守ることではなく、自らが傷つく未来を回避することにすり替わっていた。
第三章 砕かれたプリズム
漣は、探偵まがいの調査の末、『高遠航(たかとお わたる)』という男の勤務先を突き止めた。都心にある総合病院の心臓外科医。経歴も見た目も、申し分ない男だった。漣は、怒りと屈辱で奥歯を噛み締めた。
アポイントも取らずに病院へ押しかけ、医局から出てきた高遠を捕まえた。
「茅野未散と、どういうご関係ですか」
単刀直入な問いに、高遠は一瞬驚いた顔をしたが、すぐに冷静さを取り戻し、漣を近くのカフェへと誘った。彼の落ち着き払った態度が、漣の苛立ちをさらに煽った。
席に着くと、高遠は真っ直ぐに漣を見た。その瞳には、憐れみのような色が浮かんでいた。
「あなたが、水上漣さんですね。未散から、いつもお話は伺っています」
「彼女と夜中に何を話しているんですか。あなたたちのせいで、俺は…!」
感情的に言葉を叩きつける漣を、高遠は静かに遮った。
「落ち着いて聞いてください。僕と未散は大学の同級生ですが、ただの友人です。彼女が僕に連絡してきたのは…相談があったからです」
高遠は少し間を置いて、慎重に言葉を選んだ。
「未散は、あなたに言えずにいたんです。彼女の家系には、若年性の拡張型心筋症の遺伝的素因がある。最近、彼女自身にも初期症状と見られる動悸や息切れが起き始めた。だから、専門である僕に相談を…」
その言葉は、漣の頭を鈍器で殴りつけたような衝撃を与えた。心筋症? 遺伝? 未散が?
目の前が真っ白になる。漣が描いていた陳腐な不倫劇は、音を立てて崩れ去った。
「彼女は、あなたに心配をかけたくない一心で、ずっと一人で悩んでいた。病気が確定すれば、あなたの重荷になる。結婚の話だって、白紙に戻さなければならないかもしれないと…」
高遠の言葉が、漣の鼓膜を通り抜け、心臓に突き刺さる。
その瞬間、漣は理解した。
未来から響いてきていた、あの地獄のような後悔の正体を。
それは、未散の裏切りに対する後悔などではなかった。
それは、病に怯え、たった一人で絶望と戦っていた彼女の苦しみに気づけず、あろうことか彼女を疑い、その繊細な心を無神経に傷つけ、孤独の闇に置き去りにしてしまった、未来の自分自身に対する、万死に値する後悔の叫びだったのだ。
後悔を避けようとする彼の行動そのものが、後悔そのものを完璧に作り上げていた。未来の予兆は、彼を救うための警告ではなかった。それはただ、彼が犯す過ちの大きさを、残酷なまでに正確に映し出す、ただの鏡だったのだ。
漣はテーブルに突っ伏した。涙も出なかった。ただ、砕かれたプリズムのように散乱した光の中で、自分の愚かさの輪郭だけが、はっきりと見えていた。
第四章 未来を聴く者
カフェを飛び出した漣は、狂ったように走った。街の騒音が遠のき、彼の耳には、未来の後悔の残響ではなく、今この瞬間の未散の心の音が聞こえるような気がした。ドアを乱暴に開けると、ソファで膝を抱えていた未散が、驚いて顔を上げた。その瞳は赤く腫れ、憔悴しきっていた。
漣は彼女の前に崩れるように膝をつき、その冷たい手を握りしめた。
「ごめん…未散、本当にごめん…」
言葉が続かない。ただ、謝罪の気持ちだけが、嗚咽となって漏れた。
「俺は、君が病気のことも知らずに…君を疑って、追い詰めて…最低だ」
すべてを話した。未来の後悔の予兆のこと、高遠医師のこと、そして自分の愚かな疑念のこと。
未散は静かに彼の告白を聞いていた。やがて、彼女の瞳から大粒の涙が零れ落ち、漣の手に滴った。
「私も、ごめん…なさい。あなたに言えなくて。怖かったの。あなたに嫌われるのが、あなたの人生の足手まといになるのが…」
二人は、互いの弱さと過ちを曝け出し、子供のように泣いた。隔てていた不信の壁が溶け、ようやく本当の意味で向き合うことができた。どれほどの時間が経っただろうか。漣が顔を上げると、未散は微かに微笑んでいた。それは、嵐が過ぎ去った後の、儚くも美しい虹のような笑顔だった。
漣は、彼女の手を強く握り直した。
「俺は、君のいない未来を後悔するくらいなら、君と共にいる未来の、どんな困難だって受け入れる。病気のことも、二人で乗り越えよう。だから…」
彼はポケットからあのベルベットの箱を取り出し、開いた。小さなダイヤモンドが、部屋の明かりを受けて静かに輝いた。
「結婚してください、未散」
未散は、涙で濡れた顔のまま、こくりと頷いた。
その瞬間、漣は気づいた。彼の内側を支配していた、あの忌まわしい後悔の残響が、完全に消え去っていることに。まるで、壊れたスピーカーのノイズがぴたりと止んだかのように。
未来を予知する能力が消えたのか、それとも、後悔ごと未来を受け入れる覚悟を決めた彼には、もはや聞こえなくなったのか。それは分からなかった。だが、確かなことは一つだけあった。
彼はもう、未来の音に怯えることはない。これから先、どんな不協和音が待ち受けていようとも、愛する人の隣で、そのすべてを聴き、受け止めていく。
不確かな明日へと続く扉の前で、二人は静かに手を取り合った。その先にあるのがどんなメロディーであれ、二人で奏でるならきっと、それは美しい音楽になるはずだった。