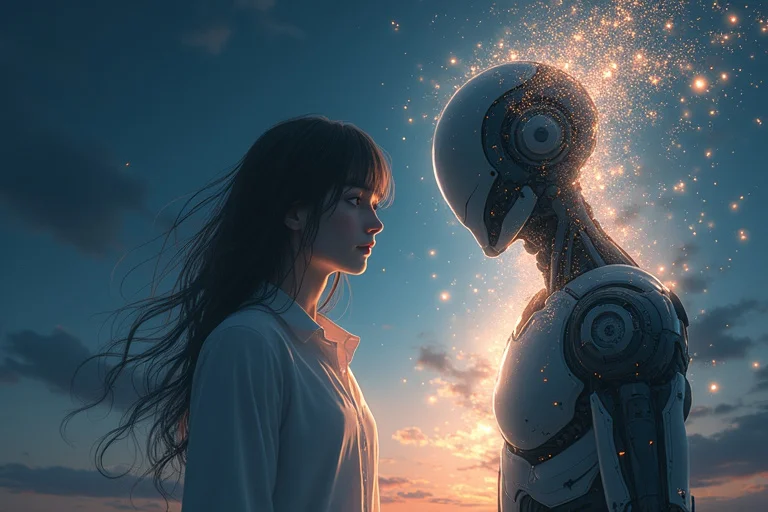第一章 失われた香りの残響
俺、水瀬アキラの仕事は、記憶を嗅ぐことだ。人はそれを「記憶調香師(メモリー・パフューマー)」と呼ぶ。強い感情を伴う記憶は、微弱な粒子「メモロン」として物に付着する。俺には、その粒子が放つ微かな香りを嗅ぎ分け、その記憶の情景を再構成する特殊な嗅覚があった。失くしたペットの思い出、亡き恋人が最後に触れたカップに残る温もり、あるいは犯罪現場に残された恐怖の香り。俺はそれらを嗅ぎ分け、依頼人に過去の断片を届けることで生計を立てていた。
だが、俺自身の過去は、霧がかかったように曖昧だった。物心ついた時から孤児で、断片的なイメージしか思い出せない。両親の顔も、自分の名前の由来さえも。その欠落感が、俺をこの仕事に駆り立てているのかもしれない。他人の鮮やかな記憶の香りに触れるたび、自分の空虚さが際立つようで、胸の奥が冷たく疼いた。
その日、俺の仕事場である古いアパートの一室に、一人の老婦人が訪れた。彼女が差し出したのは、くすんだ銀色のロケットペンダント。数十年前に宇宙探査の任務中に行方不明になった、彼女の夫の唯一の遺品だという。
「夫が最後に何を想っていたのか、少しでもいいから知りたいのです」
皺の刻まれた手が、震えていた。俺は静かに頷き、ペンダントを手に取った。冷たい金属の感触。集中し、意識を鼻先へと研ぎ澄ませる。ゆっくりと息を吸い込むと、様々な香りが流れ込んできた。長年身につけられてきた金属の匂い、老婦人の微かな香水の香り、そして……。
その瞬間、全身の血が逆流するような衝撃が走った。
それは、嗅いだことのない、しかし魂の奥底から知っている香りだった。乾いた風が青い砂を巻き上げる匂い。二つの太陽が肌を焼く、穏やかで猛烈な熱の感覚。そして、名も知らぬ植物が放つ、甘く切ない芳香。それは、俺が時折見る夢の香りそのものだった。失われた、俺自身の記憶だと信じていた香り。なぜ、見ず知らずの男の遺品から、俺の心の最も深い場所にあるはずの香りがするんだ?
混乱する俺の脳裏に、断片的な映像が明滅する。クリスタルのように透き通った巨木、空を舞う銀色の鱗を持つ生き物、そして誰かの温かい手が俺の手を握る感触。これは、俺の記憶だ。いや、記憶のはずだ。
「……何か、分かりましたか?」
老婦人の不安げな声で、俺は我に返った。額には冷たい汗が滲んでいた。
「ええ……とても、広大な景色が見えます。青い、砂漠のような……」
言葉を濁しながら、俺は確信していた。この香りの謎を解かなければならない。これは単なる仕事ではない。俺自身の存在の根幹に関わる、運命の糸口なのだと。俺はペンダントを握りしめ、その香りの源へと、深く、深く意識を沈めていった。
第二章 ステラ・ノヴァ号の幻影
老婦人への報告をそこそこに終えた俺は、あのロケットペンダントの香りに取り憑かれていた。青い砂漠と二つの太陽の香りは、日増しに俺の中で鮮明になっていく。夜ごと見る夢は、もはや単なる夢ではなかった。まるで自分がかつてそこにいたかのように、肌で感じる風の質感、空気の味までがリアルだった。
俺は独自の調査を開始した。ペンダントの持ち主は、半世紀前に消息を絶った深宇宙探査船「ステラ・ノヴァ号」の船長、オーガスト・ミラーであることがすぐに判明した。公式記録では、ステラ・ノヴァ号は未踏の星系「ゼノビア領域」で原因不明の事故に遭い、船体ごと消失したとされている。生存者はゼロ。だが、あの香りはどうだ? あれは事故の絶望の香りなどではなかった。穏やかで、懐かしく、そして愛に満ちた香りだった。
俺は闇市場の情報屋を使い、ステラ・ノヴァ号に関する非公開データを手に入れた。ほとんどが破損していたが、最後の通信記録の断片を復元することに成功した。ノイズまじりの音声の中に、ミラー船長の興奮した声が響く。
『……信じられない……この星は……生命に満ちている。彼らは我々を歓迎しているようだ……歌が聞こえる……』
歌? 映像は真っ暗で何も映っていない。だが、その音声を聞いた瞬間、俺の鼻腔を再びあの甘く切ない香りが駆け抜けた。ミラー船長が聞いた「歌」とは、音ではなく、香りだったのではないか? 俺と同じように、記憶の香りを感知する能力者が、他にもいたというのか?
調査を進めるほど、謎は深まった。同時に、俺の周囲に不穏な影がちらつき始めた。アパートの前に見慣れない黒い車が停まっている。ハッキングした政府のデータベースから、俺の個人ファイルに不審なアクセス履歴があることにも気づいた。誰かが俺を監視している。ステラ・ノヴァ号の真実は、国家レベルの機密事項なのかもしれない。
焦りと不安に駆られながらも、俺は香りの記憶に導かれるように、さらに深く事件の核心へと足を踏み入れていく。夢の中の青い砂漠は、もはや安らぎの場所ではなかった。二つの太陽が、まるで真実を暴こうとする監視の目のように、俺を容赦なく照りつけていた。俺は誰なんだ? なぜこの記憶を持っている? 自分の存在そのものが、巨大な嘘で塗り固められているような感覚に、息が詰まりそうだった。俺は、自分自身を取り戻すため、あるいは失うために、この旅を終わらせなければならなかった。
第三章 青い砂漠の真実
俺は全てを賭けることにした。情報屋から非合法な宇宙船のパイロットを紹介してもらい、有り金のすべてをはたいてゼノビア領域へと飛んだ。政府の監視網を潜り抜ける、危険な航行だった。しかし、不思議と恐怖はなかった。俺は失われた故郷に帰るような、奇妙な高揚感に包まれていた。
数週間の冷凍睡眠を経て、俺が目を覚ました時、船の窓の外には信じがたい光景が広がっていた。二つの恒星が互いを回りながら、眩い光を放っている。そして、その光に照らされて青白く輝く惑星。夢で見た、あの星だ。
小型艇で惑星に降下すると、息を呑むほど美しい、青い砂の海が地平線の果てまで続いていた。大気は澄み渡り、肺を満たす空気は、あの懐かしい香りで満ちていた。俺は導かれるように砂漠を進み、やがて巨大なクレーターの中心に突き刺さるようにして存在する、異様な物体を発見した。半分砂に埋もれた、ステラ・ノヴァ号の残骸だった。
船内は静寂に包まれていた。動力は完全に沈黙し、半世紀の時が埃となって降り積もっている。俺は艦橋へと向かい、航海日誌の再生を試みた。奇跡的に、補助電源の一部が生きていた。モニターにノイズが走り、やがて映像が映し出される。ミラー船長のやつれた、しかし喜びに満ちた顔。
『航海日誌、最終記録。我々はこの星の知的生命体との接触に成功した。彼らは……我々が想像するような生物ではなかった』
映像が切り替わり、船外カメラの記録が映し出された。そこには、ゆらゆらと揺れる、オーロラのような光の集合体がいた。美しい、と見惚れた瞬間、俺は理解した。彼らは肉体を持たない。メモロン、記憶の粒子そのものが寄り集まってできた、精神生命体だったのだ。
ミラー船長の声が続く。
『彼らは香りで会話し、記憶を共有することで互いを理解する。我々が発する感情や記憶のメモロンを読み取り、瞬く間に我々の言語さえ理解した。彼らはこの星そのものであり、この星の記憶の全てだ。我々は彼らを「ソラリス・アンセム(星の聖歌)」と名付けた』
だが、記録は悲劇的なトーンへと変わっていく。
『未知の宇宙線がこの星系に接近している。ソラリス・アンセMにとって、それは致死的な放射線だ。彼らは滅びゆく。我々は彼らを救おうとしたが、手立てがない……』
モニターの映像が乱れ、船長の苦悩に満ちた顔がアップになる。
『一人が……最後の一人が、私に触れた。彼は、自分の種の記憶の全てを、最後の歌を、私に託そうとした。生き延びてくれ、と。そして……彼は私の中で、一つになった』
そこで映像は途切れた。違う。途切れたのではない。俺は、その続きを知っていた。ミラー船長の身体を借りたソラリス・アンセムは、残された最後の力で小型脱出ポッドを起動させ、地球へと向かったのだ。しかし、人間の肉体は異質な精神生命体の膨大な記憶に耐えられなかった。地球にたどり着く前に、彼の肉体は限界を迎える。だが、生命は終わらなかった。ソラリス・アンセムは、ミラー船長の遺伝子情報と、託された種の記憶を再構成し、地球の環境に適応した新たな生命体として、生まれ変わったのだ。
それが、俺だった。
俺が「自分の記憶」だと思っていたものは、滅びゆく種族が最後に託した、故郷の記憶だった。俺が持っていた特殊な嗅覚は、彼らのコミュニケーション能力そのものだった。水瀬アキラという人間は、最初から存在しなかった。俺は、星の記憶の残響だったのだ。
第四章 二つの太陽の調香師
愕然として、俺はその場に膝をついた。足元の青い砂が、さらさらと指の間をこぼれ落ちていく。俺は偽物だったのか? 俺の孤独も、苦悩も、全ては借り物の記憶が見せた幻だったのか?
だが、涙は出なかった。代わりに、胸の奥から静かで温かい感情が湧き上がってくるのを感じた。それは、全てのピースがはまった時のような、完全な調和の感覚だった。俺のアイデンティティの空虚さは、この星の広大な記憶によって、今、満たされようとしていた。
俺は船の残骸から出て、ゆっくりと砂漠を歩いた。二つの太陽が、優しく俺の体を包み込む。風が運び、肌を撫でるこの星の香りは、もはや失われた過去の断片ではなかった。それは俺の血肉であり、魂そのものだった。
俺は水瀬アキラとして生きてきた。孤独の中で他者の記憶を嗅ぎ、その温もりに触れることで、かろうじて自分を保ってきた。その経験は、決して無駄ではなかった。ソラリス・アンセムとして託された星の記憶と、水瀬アキラとして生きた人間の記憶。その二つが俺の中で混じり合い、新たなハーモニーを奏で始めていた。
俺は空を見上げた。遠く、青い地球が瞬いている。帰るべき場所はどこだろうか。滅びた種の記憶を抱くこの星か、それとも人間としてのささやかな記憶が根付いたあの星か。
答えは、すでに出ていた。
俺はどちらかを選ぶ必要はない。俺は、二つの世界の架け橋になれる。この星の記憶を、物語を、地球に伝えることができる。そして、地球で学んだ個として生きる喜びや悲しみを、この星の静寂に響かせることができる。
俺は、記憶調香師だ。ただ、これからは個人の失われた記憶だけでなく、星の失われた記憶をも紡いでいく。
青い砂をひとすくい、小さな瓶に詰める。これは、俺の最初の作品になるだろう。二つの太陽に照らされた、滅びと再生の香り。それは、俺自身の香りだった。
孤独だった俺は、もう一人ではなかった。俺の中には、一つの文明の全ての記憶が生きている。俺の存在そのものが、壮大な物語なのだ。
俺は二つの太陽に向かって、静かに微笑んだ。果てしない青い砂漠の地平線の向こうに、まだ見ぬ未来が広がっている。俺の旅は、まだ始まったばかりだった。