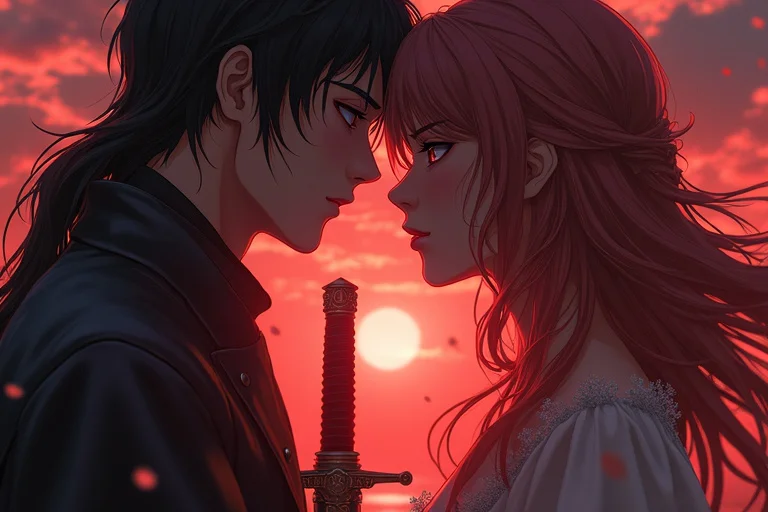第一章 灰色の残響
カイの耳には、常に死んだ言葉の囁きがこびりついていた。それは、王都の石畳に染みついた過去の恋人たちの睦言であり、古物店の隅に転がる錆びた短剣が記憶する、持ち主の最後の絶叫であった。彼は、この世界に満ちる「失われた声の残響」を聞くことができた。
その能力は、祝福とは程遠い呪いであった。声は常に持ち主の強い感情を伴い、嵐のようにカイの精神を揺さぶる。他人の喜びは彼の心を焼き、他人の絶望は彼の魂を凍らせた。だからカイは、極力他人と、そして過去と関わらぬよう、埃っぽい書庫の奥で古文書の修復師として息を潜めて生きていた。
冷たいインクの匂いが満ちる静寂の中、不意に背後から声がかかった。
「あなたが、カイさんですね。『残響聴き』の」
振り返ると、そこにいたのは王立古文書館の若き司書、エララと名乗る女性だった。彼女の瞳は、まるで磨かれた黒曜石のように深く、カイの魂の奥底まで見透かしているかのように澄んでいた。
「王家の秘匿書庫に、あなたに聞いていただきたい『声』があります」
彼女の言葉は、拒絶を許さない響きを持っていた。カイは、錆びついた運命の歯車が、軋みを上げて回り始めるのを感じていた。
第二章 濁った雫
王家の秘匿書庫は、時間の澱が溜まった湖の底のようだった。黴と古い羊皮紙の匂いが鼻をつく。エララが指し示したのは、硝子ケースに収められた、壮麗な一振りの長剣。建国の英雄、初代将軍アークライトが佩いていたとされる『黎明の剣』だ。
「この剣には、将軍の最後の言葉が宿っていると伝えられています。ですが、誰にもその声は聞こえません」
カイがおそるおそる硝子に指を触れる。途端に、脳を直接殴りつけるような激しい幻聴が迸った。
――偽りの礎に、栄光はない。
――この世界は、あまりにも……脆い。
絶望と、諦観。そして、底知れぬほどの深い愛情。矛盾した感情の奔流がカイを襲い、彼は思わず後ずさった。
「何か、聞こえましたか?」
エララの問いに、カイはかろうじて頷く。
「断片的ですが……。しかし、何かおかしい。この声、途切れすぎています。まるで、大切な部分がごっそりと抉り取られたように」
エララは懐から、白銀の細工が施された小さな懐中鏡を取り出した。
「これは『言霊を映す懐中鏡』。残響を、言葉の幻影として映し出します」
彼女は鏡を剣にかざした。すると、鏡面に淡い光が揺らめき、文字の断片が浮かび上がる。しかし、そのほとんどはインクが滲んだように濁り、判読できなかった。
「これが、今の歴史の姿です」とエララは静かに言った。「建国史における、ある特定の時期。アークライト将軍の最期を巡る時代の言霊の雫だけが、全て濁り、消失しかけているのです。何者かによって、歴史が『改竄』されたかのように」
第三章 記憶という代償
カイとエララの奇妙な調査が始まった。彼らは正史から抹消された古戦場や、打ち捨てられた祠を巡り、失われた言霊の雫を探した。
「忘れられた谷」と呼ばれる霧深い盆地で、カイは朽ちた石碑に手を触れた。そこには、将軍に最後まで付き従ったという無名の騎士たちの名が刻まれている。懐中鏡をかざすと、カイは鏡に自らの記憶を捧げる覚悟を決めた。幼い頃、雨上がりの虹を初めて見た日の感動。その記憶が意識の底に沈むのと引き換えに、鏡面に鮮やかな言葉が浮かび上がった。
『星が、落ちる』
『我らの王は、世界を憂いていた』
言葉と共に、騎士たちの深い忠誠心と、どうしようもない哀しみが流れ込んでくる。カイは膝から崩れ落ちた。記憶を失う痛みよりも、彼らの純粋な想いが胸を締め付けた。
「大丈夫ですか、カイさん」
エララが駆け寄る。彼女の横顔には、いつも使命感とは異なる、個人的な痛みの色が滲んでいるように見えた。カイは霞む意識の中で、誰かの顔を思い出そうとしていた。笑いかけてくれる、温かい誰かの顔を。だが、その顔には靄がかかっていて、どうしても思い出せなかった。
第四章 空白の祭壇
数多の記憶を代償に、カイたちはついに謎の中心地へと辿り着いた。初代将軍アークライトが、その生涯を閉じたとされる『始まりの祭壇』。王都を見下ろす断崖絶壁に、その祭壇は静かに佇んでいた。
しかし、そこは完全な『無』の空間だった。
言霊の雫一つ、残響の欠片一つ感じられない。歴史が改竄された痕跡である濁った雫すらない。まるで、最初から何も存在しなかったかのように、そこだけが時間の流れから切り取られていた。
「……どうして」カイは愕然とした。「ここには、何もない」
絶望が空気を満たしたその時だった。
「いいえ。最後の雫は、ここにあります」
エララは静かにそう言うと、カイの手から懐中鏡をそっと取った。そして、信じられない行動に出た。彼女は鏡の縁に付いた鋭い装飾を、躊躇いなく自らの胸に突き立てたのだ。
「エララさん!?」
赤い血が彼女の白い衣服に滲む。しかし彼女は、痛みを感じさせない穏やかな笑みを浮かべていた。
「この鏡は、持ち主の記憶だけではなく……その『存在』そのものを捧げることで、消失した言霊すら呼び覚ます禁断の鍵なのです」
彼女の足元から、眩い光が溢れ出す。
「我が一族は、王家の分家。歴史の改竄を主導した者たち。ですが、その血脈の中には、いつか真実を取り戻す者が現れることを願い、この鏡と真実の鍵を密かに受け継いできた者たちもいました。私が、その最後の番人です」
エララの身体が、徐々に光の粒子となって崩れていく。
「カイさん……あなたなら、真実に辿り着ける。この世界の……本当の姿に」
彼女の言葉を最後に、懐中鏡は太陽のように輝き、祭壇全体が巨大な光の渦と化した。カイは抗う間もなく、その光の中へと吸い込まれていった。
第五章 夢の終わり
光の中で、カイは見ていた。初代将軍アークライトの最後の記憶を。
彼は、荒廃した世界を統一し、人々が笑い合える平和な国を創り上げた。それは彼の理想そのものだった。しかし、ある日、彼は世界の真理に気づいてしまった。この世界は、あまりにも脆い。人々の強い『願い』や『想い』が物理的な法則に干渉し、世界を形作っている。そして、その最も強大な力の源は、彼自身――初代将軍アークライトの「平和であれ」という、あまりに強大な願いそのものだった。
この世界は、彼が見ている壮大な『夢』に過ぎなかったのだ。
彼の最後の声が、カイの魂に直接響き渡る。
『この偽りの平穏は、いつか必ず綻びる。人々が真に生きるべき未来を、私の夢が奪っている。ならば、私がすべきことは一つ』
祭壇の上で、アークライトは天を仰いだ。
『この夢を終わらせよう。この世界の創造主である、私自身と共に。――誰か、いつかこの残響に辿り着く者がいるのなら、君に託す。本当の世界の扉を、開けてくれ』
アークライトは自らの存在を抹消し、夢の世界を終わらせようとした。それが彼の『真の最期』。しかし、彼の夢の残響はあまりに強く、世界は完全には消えなかった。彼の死という事実だけが歴史から消え、残された人々――後の王朝は、その不都合な真実を隠蔽し、将軍は偉大な英雄として死んだという『偽りの歴史』を創り上げたのだ。
第六章 目覚めた存在
意識が現実に戻った時、カイの周りの世界は静かに崩壊を始めていた。始まりの祭壇が、王都の街並みが、空の色さえもが、光の粒子となって風に溶けていく。エララが立っていた場所には、ただ温かい光の余韻だけが残っていた。全てが、偉大な一人の男が見た、長過ぎる夢の残滓だった。
孤独が胸を刺す。だがその時、カイの脳裏に、捧げたはずの記憶が鮮やかに蘇った。
病弱だった妹の手を握り、「お兄ちゃん、いつか本物のお空が見たいな」と囁いた声。
世界の法則が崩れる中で、彼の核として失われずにいた、最も大切な記憶。
彼は理解した。自分はもはや、この夢の登場人物ではない。初代将運が、そしてエララが命を賭して真実を託した、唯一の『目覚めた存在』なのだと。
目の前の空間が、まるで水面のように揺らめいた。そして、その中心に小さな光が灯り、やがて人一人が通れるほどの大きさの、光でできた扉が現れた。初代将軍が遺した、最後の道標。
カイは消えゆく夢の世界に、一度だけ深く頭を下げた。感謝と、訣別のために。そして、迷いのない足取りで、その扉へと歩みを進める。
扉の向こうには、まだ知らぬ風の匂いと、本物の陽の光が満ちている。彼がこれから紡ぐべき、新しい『現実』が始まろうとしていた。