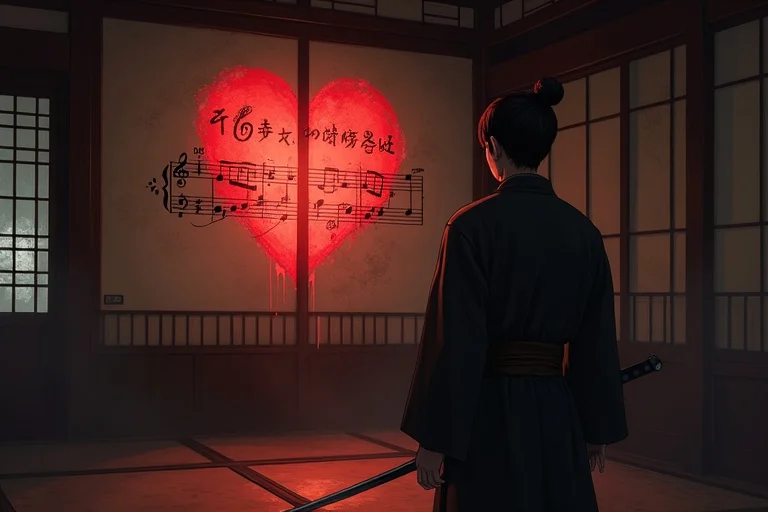第一章 漆黒の静寂
江戸の片隅、日がな一日絵筆を握る響(ひびき)にとって、世界は絶え間ない色彩の洪水だった。彼の目には、常人には聞こえるはずの「音」が、鮮やかな「色」として映る。赤子の泣き声は空を引き裂くような真紅の稲妻に、行き交う人々の下駄の音は石畳に散らばる小気味よい黄土色の斑点に、そして商人の呼び込みは、粘りつくような緑青(ろくしょう)の靄(もや)に見えるのだった。この生まれ持った奇異な才のせいで、響は言葉を交わすことが不得手だった。言葉は、相手の感情の色と混じり合い、彼の心をかき乱す。故に、彼は黙して絵を描く。見たものを、感じた色を、和紙の上に写し取ることで、ようやく世界との折り合いをつけていた。
懇意にしている版元『文林堂』の主人・惣兵衛(そうべえ)は、そんな響の数少ない理解者だった。彼の朴訥とした声は、響の目には温かい土の色に見え、心を安らがせた。その惣兵衛が、死体となって発見されたのは、木犀の香りが夜気に溶け込む、そんな秋の晩のことだった。
報せを受け、響が文林堂の仕事場に駆けつけた時、そこは異様な静寂に包まれていた。同心や野次馬の声が、彼の周りでけばけばしい原色の渦となって明滅する。だが、響の目は仕事場の奥、惣兵衛が倒れていた一点に釘付けになった。そこには、何もない。音がない。しかし、彼の目には見えていた。他のどんな色をも飲み込み、光さえも吸い込むような、底なしの「漆黒」。それは単なる無音ではなかった。まるで、そこにあったはずの全ての音を喰らい尽くしたかのような、暴力的なまでの静寂の色だった。人の絶命の際に放たれるであろう、悲痛な叫びの色も、凶器が振り下ろされる残忍な金属の色も、何もかもがその漆黒に塗り潰されていた。
震える手で、響は懐から画帳を取り出した。誰もが惣兵衛の亡骸と物色された箪笥に気を取られる中、彼は一心不乱に筆を走らせる。同心たちの訝しげな視線も意に介さず、ただ、目に焼き付いた常ならざる「漆黒の音」を、紙の上に描き留めた。それは、見る者が見ればただの墨の染みにしか見えないだろう。だが、響にとっては、これが唯一無二の、犯人が残した声だった。
第二章 語らぬ絵師と色の欠片
惣兵衛の一人娘である小夜(さよ)は、父の突然の死に気丈に振る舞いながらも、その瞳の奥には深い藍色の悲しみが澱んでいた。響が弔問に訪れると、彼女はやつれた顔で無理に微笑んだ。その声は、かつての鈴を転がすような銀色を失い、か細く震える灰色の糸となっていた。
「響様。父が、いつもお世話に……」
響は言葉を返せず、ただ黙って頭を下げた。何かを伝えなければならない。あの夜に見た、おぞましい漆黒の静寂のことを。彼は懐から、あの夜に描いた絵を取り出し、小夜に差し出した。和紙に広がる、渦を巻くような墨の染み。小夜はそれを受け取ると、怪訝な表情を浮かべた。
「これは……?」
「……」
響は必死に何かを伝えようと、絵の中の漆黒を指さし、次いで自分の耳を指した。だが、その意図が伝わるはずもない。小夜の瞳に浮かんだのは、理解ではなく、当惑と、かすかな怯えの色だった。父を亡くしたばかりの娘にとって、言葉も発さずに不気味な絵を見せる男は、不審な存在でしかなかったのだろう。響は、人と自分とを隔てる、どうしようもない壁の厚さに唇を噛んだ。
事件は、押し込み強盗の犯行として処理されようとしていた。帳場が荒らされ、金子がいくらか盗まれていたからだ。だが、響には確信があった。あれは、ただの物盗りの仕業ではない。あの「音を喰らう漆黒」は、もっと深く、歪んだ意思を持った色だった。
それから数日、響は江戸の町を彷徨った。事件があった時刻、文林堂の周辺にいた人々の声を、色として拾い集めるために。物売りの声、酔漢の怒声、恋人たちの囁き。それらは全て、彼の画帳の中で色とりどりの絵の具となっていく。だが、どれも決め手にはならなかった。どの色も、あの夜の漆黒とはあまりにも異質だった。
孤独な探索の中、響の脳裏には、惣兵衛との最後の会話が蘇っていた。一月ほど前、惣兵衛は興奮した様子で、ある笛師の噂をしていた。
「響、聞いたことがあるかい。時雨(しぐれ)という若き笛師の名を。奴の笛の音は、天人の奏でる音楽だ。聞く者の魂を震わせるという。今度、うちで奴の楽譜を版木に起こすんだ」
その時の惣兵衛の声は、新しい才能を見出した喜びに、輝かしい黄金色に染まっていた。その笛師、時雨は、小夜が密かに想いを寄せている相手でもあることを、響は知っていた。
第三章 音を喰らう笛
響は、噂の笛師・時雨の演奏会に足を運んだ。舞台に現れた時雨は、柳のようにしなやかな体躯の、憂いを帯びた美青年だった。彼が静かに横笛を唇に当てた瞬間、会場のざわめきがすっと消えた。それは、響の目には、様々な色がふっと白色に浄化されるように見えた。
そして、最初の一音が放たれる。
その瞬間、響は息を呑んだ。時雨の笛から紡ぎ出されたのは、旋律ではなかった。それは、他のあらゆる音を打ち消し、吸収していく「無音の音」だった。彼の目に映ったのは、あの夜、文林堂で見たものと寸分違わぬ、全てを飲み込む漆黒の渦。観客たちは、その神がかり的な音色にうっとりと聴き入っている。彼らの耳には、それがどれほど美しい旋律に聞こえているのだろうか。だが、響には、その音が持つ本質が見えていた。これは、世界から色を奪う、冒涜的な音だ。
全身が粟立った。間違いない。犯人は時雨だ。
演奏会が終わり、響は時雨の楽屋を訪ねた。楽屋には、小夜も祝いに駆けつけていた。彼女の時雨に向ける眼差しは、淡い桜色に染まっており、響の胸をちくりと刺した。
「時雨様、素晴らしい音色でございました」
小夜がうっとりと言うと、時雨は優美に微笑んだ。
「君に聴いてもらえたのなら、本望だよ」
響は、二人の間に割って入るように、一枚の絵を突きつけた。それは、あの夜に文林堂で描いた「漆黒の音」の絵だった。時雨の表情が、初めて凍りついた。彼の瞳の奥で、一瞬、鋭い硝子のような色が閃くのを響は見逃さなかった。
「……ただの墨絵か。何のつもりだ、絵師殿」
時雨の声は平静を装っていたが、その色の輪郭は微かに乱れていた。
「この方は響様。父が大変お世話になった絵師ですの」
小夜が慌てて取りなすが、響は時雨から目を離さない。そして、もう一枚の絵を見せた。それは、文林堂の周辺で拾い集めた様々な音の色と、惣兵衛が最後に語った時の「黄金色の声」を描き加えたものだった。そして、その全ての色彩が、中央の漆黒に吸い込まれていく構図になっていた。
時雨は、その絵の意味を正確に理解した。彼の顔から血の気が引いていく。
惣兵衛は、時雨の才能の秘密に気づいてしまったのだ。時雨の作る曲は、全て古今東西の様々な旋律を巧みに盗み、組み合わせたものだった。その盗作の証拠を掴んだ惣兵衛を、時雨は口封じのために殺害した。そして、凶行の際に発せられる物音を、己が持つ特異な笛の音――他の音を相殺し、打ち消す「無音の旋律」――で掻き消したのだ。完全犯罪のはずだった。音さえ消せば、証拠は何も残らない。だが、彼には計算外のことが一つだけあった。その消された音を「色」として見ることのできる絵師が、この世に存在したことを。
第四章 魂の彩声
「……化け物め」
時雨が絞り出すように呟いた。その声は、もはや優美な色を失い、どす黒い泥の色をしていた。彼は懐から短刀を抜き放ち、証拠を知る唯一の人間である響に襲いかかった。悲鳴を上げる小夜。だが、響は動じなかった。
彼は、最後の絵を時雨と小夜の前にかざした。それは、つい今しがた、この場で描き上げたものだった。
中央には、時雨が奏でたおぞましい「漆黒の笛の音」。その漆黒を切り裂くように、一本の鮮烈な「緋色の叫び」が描かれていた。それは、惣兵衛が最期に上げたであろう、娘の名を呼ぶ声の色だった。そして、その緋色の周りには、惣兵衛が響に語った時の「温かい土色の声」や、小夜を想う「優しい黄金色の声」が、守るように寄り添っていた。
それはもはや、単なる絵ではなかった。言葉を発することのできない絵師が、魂の全てを込めて描き上げた、声の肖像画だった。
その絵を見た瞬間、小夜は全てを悟った。絵から伝わってくる、父の無念と愛情。そして、時雨の音の裏に隠された、冷たい虚無。彼女の瞳から、大粒の涙が溢れ落ちた。その涙は、透き通った水晶の色をしていた。
「……父様……」
小夜の嗚咽が、時雨の動きを止めた。彼の足元から、力が抜けていく。短刀が床に落ち、乾いた金属音――鈍い灰色の色が響いた。
事件は解決し、時雨は捕らえられた。だが、響の心に喜びはなかった。自分の特異な才が、一人の人間の罪を暴き、一人の少女の淡い恋心を打ち砕いたのだ。世界の色は、なんと悲しく、複雑なのだろう。
数日後、響は文林堂を訪れた。店を継ぐ決意をした小夜が、一人で帳面をつけていた。
「響様」
彼女は顔を上げ、静かに微笑んだ。その声は、まだ悲しみの藍色を帯びてはいたが、その奥に、凛とした藤色の光が宿っていた。
「ありがとうございました。あなたの絵がなければ、私はずっと偽りの音色に惑わされたままでした。……あなたの目には、私の声は、今、どんな色に見えますか?」
響は、初めて自分の能力について話してみようと思った。言葉は、うまく色に変換できないかもしれない。それでも。
彼は、小夜の前に座ると、ゆっくりと口を開いた。彼の発した声がどんな色をしていたのか、彼自身には分からない。
だが、それを聞く小夜の瞳が、ふわりと温かい光を灯した。彼女の穏やかな声が、響に返ってくる。
「ひだまりのような、黄金色です」
その声の色に包まれた時、響は、自分の呪われた才が、初めて救われたような気がした。世界は音と色に満ちている。その美しさも、醜さも、悲しさも、全て描き留めていくのが自分の役目なのだ。
響は和紙を広げ、筆を取った。彼が描き始めたのは、絶望の漆黒ではない。目の前にいる少女の声が放つ、希望に満ちた、ひだまりの黄金色だった。その絵には、まだ音も言葉もなかったが、確かな温もりが満ちていた。