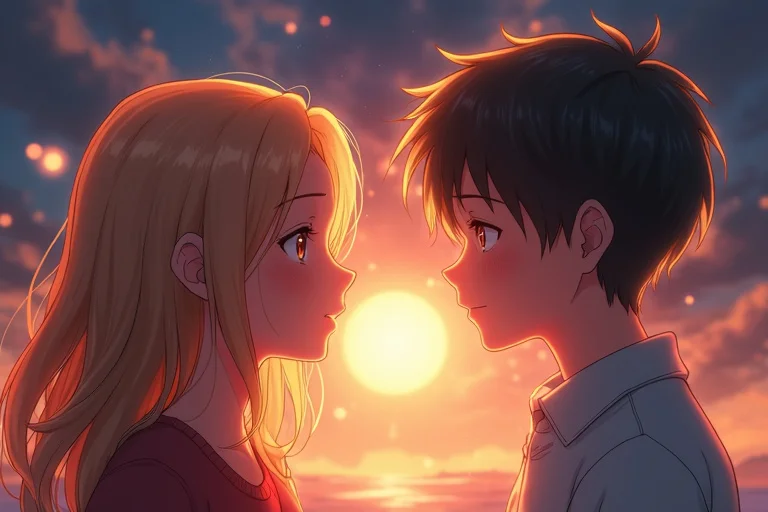第一章 色褪せる時間
僕、水上蒼(みなかみあおい)の目には、世界が少しだけ違って見えている。時間の流れが、色彩を伴う帯として網膜に映るのだ。遥かな過去は深海のような藍色に沈み、すぐ過ぎ去った昨日は淡い空色を留める。僕たちが「現在」と呼ぶ瞬間は、芽吹いたばかりの若葉のような鮮烈な緑色だ。そして、まだ見ぬ未来は、地平線の彼方で揺らめく、おぼろげな金色の光として存在する。
他人の時間も同じように見える。だから、誰かが人生のどの季節を生きているのか、僕には一目でわかった。とりわけ、「青春」と呼ばれる時期を生きる人々が放つ光は格別だった。それは固定された色ではなく、感情の波に合わせて明滅する虹色のオーラ。希望、不安、焦燥、そして恋。あらゆる感情が混ざり合い、万華鏡のようにきらめく、儚くも美しい輝きだ。
この世界には、もう一つの時間の指標がある。十二歳を過ぎた頃から、すべての人の手の甲に、己の「青春の時間」の残量が四桁のデジタル数字で浮かび上がるのだ。その数値は時計の秒針のように着実に減り続け、やがてゼロになる。ゼロになった者は、青春の終わりを迎える。感情の起伏は凪のように穏やかになり、思考は澄み切った水のように論理的になる。まるで、熱を失った恒星のように。
僕の親友、月島陽奈(つきしまひな)の虹は、誰よりも鮮やかだった。彼女が笑うと、真夏の太陽みたいなオレンジが弾け、夢を語る時には、夜明けの空のような紫が滲んだ。彼女の手の甲に浮かぶ数値は「3155」。まだたっぷりと残された、輝かしい時間の証。
だが、異変は静かに始まった。ある日の放課後、教室の窓から差し込む西日が、生徒たちの手の甲を照らし出していた。僕はふと、陽奈の隣の席の男子生徒の数値が、昨日より三十も減っていることに気づいた。通常、一日に減るのは五か六のはずだ。見渡せば、クラスのあちこちで、時間の帯が不安定に揺らぎ、虹色の輝きが急速に色褪せている。まるで、見えざる何者かに、彼らの最も輝かしい時間を奪われているかのように。
そして、その現象は陽奈にも及んでいた。彼女の数値は「2980」。数日で百以上も失われている。彼女が愛用していたスケッチブックは開かれなくなり、その瞳から、かつて宿っていた虹色の光が少しずつ消えていくのを、僕はただ見ていることしかできなかった。
第二章 0と1の境界線
街全体が、目に見えない焦燥感に包まれていった。ニュースは連日、世界規模で発生している「青春時間加速現象」を報じているが、どの専門家も首を傾げるばかりだった。人々は失われゆく時間を惜しむように、刹那的な楽しみに身を投じるか、あるいはすべてを諦めたように無気力になっていった。
陽奈もまた、その渦に呑まれつつあった。
「ねえ、蒼。絵本作家になるって夢、なんだかもう、すごく遠いことみたいに感じるんだ」
ある日、河川敷のベンチで、彼女は力なく呟いた。その声は乾いていて、風に溶けて消えそうだった。彼女の手の甲の数値は、もう三桁にまで落ち込んでいた。かつて彼女を包んでいた虹色のオーラは、今はまるで陽炎のように揺らめくだけだ。
僕は何も言えなかった。慰めの言葉は虚しく、励ましは残酷に響く気がした。僕にできるのは、ただ彼女の隣に座り、彼女の時間が刻一刻と失われていく様を、この呪われた目で見つめることだけだった。
そんな時、奇妙な噂が流れ始めた。青春の時間がゼロになり、感情を失ったはずの人々が、再び感情を取り戻し始めている、と。まさか、と思った。一度ゼロになった数値が戻るなど、ありえない。それは、死者が蘇るのと同じくらい、この世界の法則に反する出来事だった。
しかし、僕は見てしまったのだ。卒業したバスケ部の先輩が、体育館裏で一人、肩を震わせているのを。彼は半年前、誰よりも早く数値がゼロになり、部の引退にも一切涙を見せなかった男だ。その冷静沈着さで「氷の男」とまで呼ばれていた。
僕は思わず声をかけた。「先輩……?」
彼はゆっくりと顔を上げた。その目には涙が浮かび、頬を伝っていた。そして、僕が息を呑んだのは、彼がおもむろに差し出した、その手の甲だった。
そこには、微かな光で「0001」という数字が、明滅していた。
「……わからないんだ」先輩は掠れた声で言った。「急に、思い出した。最後の大会で負けた時の、あの悔しさを……。胸が、張り裂けそうだ」
失われたはずの感情の奔流。ゼロと一の境界線で、一体何が起きているのか。世界を覆う謎は、さらに深く、暗くなっていくようだった。
第三章 クロノスグラスの囁き
自宅に戻った僕は、自室の机に置かれた古びた砂時計を手に取った。祖父の形見である「時の砂時計(クロノスグラス)」。くびれたガラスの中で、銀色の砂がさらさらと静かに流れ落ちる、ただそれだけのアンティークだ。祖父は「これはただの時計じゃない。世界の涙を映す鏡だ」と、よくわからないことを言っていた。
最近、この砂時計に奇妙な変化が起きていた。時折、流れ落ちる砂粒が、まるでホタルか何かのように、淡い虹色に明滅することがあるのだ。先輩の涙を見た夜、僕は初めて、その現象に明確な意味があるのかもしれないと感じ始めていた。
僕は砂時計をじっと見つめた。中の砂は相変わらず静かだ。僕は無意識に、指先でその冷たいガラスに触れた。その瞬間、足元から何かが這い上がってくるような、奇妙な感覚に襲われた。時間の流れが乱れている。僕の目に映る現在(いま)を示す緑色の帯が、まるで強風に煽られたリボンのように、激しく波打っているのが見えた。
同時に、クロノスグラスの砂粒が一斉に、眩い虹色の光を放った。
「うわっ……!」
驚いて手を離そうとしたが、ガラスが指に吸い付くように離れない。そして、信じられない光景が目の前で繰り広げられた。
流れ落ちていた砂が、まるで引力に逆らうように、ゆっくりと、しかし確実に、上へと昇り始めたのだ。
逆流。
時間が、物理的な形を持って、過去へと遡っていく。祖父の言葉が脳裏をよぎる。「世界の涙を映す鏡」。これは単なる比喩ではなかったのかもしれない。この砂時計は、この世界の異常な時間の歪みを感知し、反応しているのだ。僕はゴクリと唾を飲み込み、再びそのガラスに、今度は両手でそっと触れた。
第四章 逆流する砂、甦る過去
陽奈の数値は、ついに一桁になった。「0009」。それはもはや、風前の灯火だった。
「もう、いいんだ」彼女は、僕が何かを言う前に、そう言った。「なんだか、すっきりした。夢とか、希望とか、そういう熱いものって、疲れちゃうね。これからはきっと、もっと楽に生きられる」
彼女は微笑んでいた。だが、その瞳には何の光も宿っていなかった。虹は完全に消え失せ、ただ空虚な色が広がっているだけだった。僕たちの間に、冷たくて透明な壁ができたように感じた。触れることさえ、もうできない。
その夜、僕は半ば自暴自棄になって、クロノスグラスを掴んだ。どうにでもなれ、と。
すると、砂時計はこれまでで最も激しい光を放ち、僕の手の中で震えた。逆流する砂は、ただ昇るだけではなかった。一つ一つの砂粒がプリズムのように光を乱反射させ、ガラスの内壁に、無数の映像を万華鏡のように映し出し始めたのだ。
―――そこは、僕の知らない世界だった。
空は赤黒い塵に覆われ、崩れかけたビル群が墓標のように突き立っている。荒廃した大地。絶望の色。
映像は切り替わる。薄暗いシェルターのような場所。そこにいたのは、深く皺の刻まれた老人たちだった。だが、僕の目は、その中の二人を捉えて離さなかった。
年老いた、僕。そして、陽奈。
未来の彼らは、ひどく疲弊し、やつれていた。しかし、その瞳には諦めではない、強い意志の光が宿っていた。彼らは巨大な機械を囲み、何かを必死に操作している。未来の僕が、何かを呟いた。声は聞こえない。だが、唇の動きでわかった。
「間に合ってくれ……」
次の瞬間、未来の陽奈が苦しそうに胸を押さえ、その手の甲が映し出される。そこには、青春の時間を示す数値などなかった。代わりに、彼女の身体そのものが淡い光の粒子となって、目の前の機械に吸い込まれていく。それは、命の輝きそのものだった。
未来の僕もまた、自らの身体が崩れていくのを構わずに、機械のレバーを押し込んだ。彼が最後に僕(過去の僕)に向かって、何かを訴えるように手を伸ばしたところで、映像は途切れた。
僕は呆然と、手の中の砂時計を見つめていた。砂は静かに流れ落ちる、いつもの姿に戻っていた。
全てを、理解した。
第五章 未来からの贈り物
この世界の時間の流れは、巨大な渦に巻き込まれていたのだ。未来に起こる、何か破滅的な出来事。その余波が過去にまで及び、僕たちの時間を不安定にさせていた。青春の時間の異常な減少は、その副作用だった。
そして、ゼロになった人々に再び灯った微かな光。あれは、未来からのメッセージだった。
いや、贈り物だ。
破滅の未来を生きる彼らが、その運命を変えるために。僕たちが、彼らと同じ過ちを繰り返さないように。自らの残り少ない生命――かつて「青春」と呼ばれた輝きの残滓――をエネルギーに変え、時空を超えて過去の僕たちに送り込んでいたのだ。
僕たちが今、感じているこの焦りも、不安も、そしてまだ微かに残っている希望のきらめきさえも。それはすべて、未来の僕たちからの、血を吐くような祈りだった。
僕の頬を、熱いものが伝った。これは僕自身の涙なのか、それとも、時を超えて届いた、未来の僕の涙なのか。もう、わからなかった。
第六章 託された現在(いま)
僕は夜の街を走った。陽奈の家へと向かう。彼女に伝えなければならない。僕たちが失いかけているこの時間は、決して無価値なものではないと。未来の自分たちが、その命と引き換えに、僕たちに託した最後の光なのだと。
陽奈の部屋の窓には、明かりが灯っていた。僕が窓を叩くと、彼女は驚いた顔でこちらを見た。
「蒼……? どうしたの、こんな時間に」
僕は窓を乗り越えて部屋に入り、息を切らしながら彼女の腕を掴んだ。彼女の手の甲では、「0001」という数字が、消え入りそうに点滅していた。
「聞いてくれ、陽奈」
僕は見たことのすべてを話した。クロノスグラスが見せた、荒廃した未来。年老いた僕たちの姿。そして、彼らが命を賭して僕たちに託したものの正体を。
陽奈は黙って聞いていた。僕の話が終わっても、彼女は何も言わず、ただ窓の外の闇を見つめていた。
やがて、彼女はゆっくりと僕の方を向いた。その瞳が、微かに潤んでいるように見えた。
「……未来の私、ちゃんと笑ってた?」
予想外の質問に、僕は言葉に詰まる。
「笑ってはいなかった。でも……すごく、強い顔をしてた。君も、僕も」
「そっか」
陽奈はふっと息を吐くと、僕の手を握り返した。その手は、少しだけ震えていた。
「私たちの青春って、借り物だったんだね」
「違う」僕は強く首を振った。「借り物じゃない。託されたんだ。未来から、この現在(いま)を」
具体的な破滅の原因はわからない。僕たちがどんな過ちを犯すのかも。でも、一つだけ確かなことがある。未来の僕たちは、感情を失い、論理的になった世界の果てに、後悔したのだ。青春の輝きを失ったことを、そして、その輝きでしか変えられない未来があったことを。
僕の目に映る時間の帯が、変わった。未来を示す金色の光が、これまで見たこともないほど力強く、明確な意志を持って輝き始めた。それはもう、おぼろげな光ではない。僕たちがこれから創り上げていくべき、道標そのものだった。
陽奈の瞳の奥に、小さな、本当に小さな虹色の光が再び灯るのが見えた。それは、未来の彼女が送ってくれた最後の贈り物であり、現在の彼女が自ら取り戻した、最初の希望だった。
僕たちは、夜が明けるまで語り合った。僕たちの手の中には、残りわずかな青春の時間しかない。だが、それはもはや、終わりを告げるカウントダウンではなかった。未来からの祈りであり、僕たちが果たすべき約束の証だった。この輝きを、ただ消費するのではなく、未来を変える力に変える。それが、僕たちに託された、本当の意味だった。
東の空が白み始め、朝焼けが街を染めていく。僕と陽奈は、言葉もなくその光景を見つめていた。手の甲の数字は、まだ少ないままだ。でも、僕たちはもう、それを恐れてはいなかった。