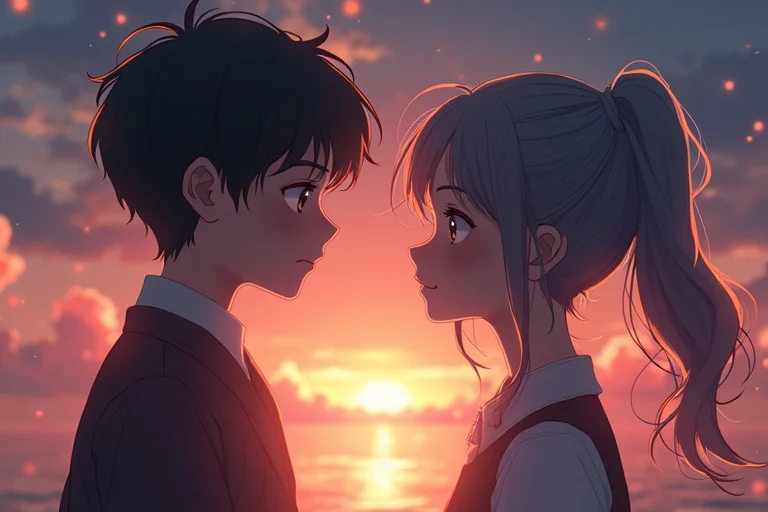第一章 色彩の教室
五限目の世界史。
僕は瞼の裏が焼けつくような眩しさに、思わず顔をしかめた。
窓際、サッカー部のエースの背中から立ち昇る真紅の揺らめきが、視界の端で暴れている。
前の席の女子生徒からは、冷徹なサファイア色の粒子が降り注ぎ、ノートの上で静かに明滅している。
教室中が、極彩色の光で溢れかえっていた。
誰も気づいていない。僕だけが、このうるさいほどの輝きに晒されている。
ふと、視線を自分の胸元に落とす。
ワイシャツの白い布地の上には、アスファルトに落ちた染みのような、濁った灰色がへばりついているだけだ。
「……眩しいな」
誰の耳にも届かない声で呟き、僕は机に突っ伏した。
僕には色がない。
焦がれるような赤も、澄み切った青も。
ただ、他人の溢れんばかりの生命力を、サングラスなしで直視させられるだけの傍観者。
チャイムが鳴り、極彩色の光たちが一斉に動き出す。
「ねえ、陽(よう)」
背後から声をかけられ、僕は気怠げに体を起こした。
幼馴染の春野美月だ。
振り返った瞬間、僕は息を止めた。
「……ノート、見せてくんない?」
美月が笑っている。
唇の端を無理やり吊り上げたような、ひび割れた笑顔。
かつて彼女は、誰よりも鮮烈だった。
キャンバスに向かう彼女の身体からは、直視できないほどの黄金色が溢れ出し、周囲の空気さえも熱狂させていたはずだった。
なのに、今の彼女は――透明だ。
光がないどころか、輪郭さえも教室の空気に溶けて消えてしまいそうなほど、希薄。
「美月、お前……絵は?」
僕の問いかけに、彼女の笑みが凍りついた。
視線が泳ぎ、自分の指先へと落ちる。その指はささくれ立ち、爪は深爪になるほど噛みちぎられていた。
「ああ、それ」
彼女は右手を、汚いものでも隠すようにスカートのひだに押し付けた。
「辞めた」
「は?」
「筆を持つとね、吐き気がするの」
美月の声が震えだした。
「色が、泥に見えるんだ。自分が何を描きたかったのか、何が好きだったのか……全部、真っ白になっちゃった」
彼女の瞳孔が開いている。
そこに映っているのは僕ではなく、底のない虚無だ。
僕はブレザーのポケットに手を突っ込み、ある冷たい金属を握りしめた。
錆びた真鍮の感触。
指の腹に食い込む、無骨な蝶番の突起。
かつて美月がくれた、壊れたコンパスだ。
その針が今、ポケットの中で狂ったように暴れ、僕の太腿を小刻みに叩いているのを、僕は感じていた。
第二章 錆びついた羅針盤
放課後の美術室は、墓場のように静まり返っていた。
本来なら鼻を突くはずの油絵具の匂いも、今は埃っぽい乾いた空気に塗り潰されている。
美月が放置した描きかけのキャンバスが、部屋の隅で白い布を被ったまま死体のように佇んでいた。
「ここに来ると、息が詰まる」
美月が窓枠に腰掛け、弱々しく呟く。
夕焼けが彼女の背中を茜色に染めているのに、その光は彼女をすり抜け、床に長い影だけを落としていた。
「あんなに熱かったのにね。陽と美術館に行った日も、夜通しデッサンした日も……全部、他人の記憶みたいに遠い」
彼女が自分の胸を叩く。ドン、と鈍い音がした。
「空っぽなの。中身を全部くり抜かれたみたいに、軽いんだ」
世界は残酷だ。
熱量は無限じゃない。注ぎ込んで、注ぎ込んで、それでも世界に拒絶された時、人は中身を失って抜け殻になる。
美月は、夢に喰い殺されたんだ。
僕はポケットの中で、熱を帯び始めたコンパスを強く握った。
汗ばんだ掌の中で、金属が生き物のように脈打っている。
取り出して、蓋を開く。
ガラスの向こうで、磁針が痙攣していた。
「あ、それ」
美月の目が、一瞬だけ懐かしさに細められる。
「まだ持ってたんだ。小学生の時にあげたガラクタ」
「ガラクタじゃねえよ」
普通なら北を指す針。
だが、この壊れたコンパスは、常に「僕」を指し続けてきた。
僕がどこを向いても、針は執拗に、僕の心臓にある灰色の染みを狙い続けていたのだ。
だが、今は違う。
チチチチチ……。
針が異常な速さで回転し、ガラスにぶつかって微かな音を立てている。
まるで、出口を求めてのたうち回る虫のように。
「陽? なんか変だよ、それ」
美月が身を乗り出した、その時だ。
キィン、と耳鳴りが脳髄を貫いた。
視界が歪む。
いつもの澱んだ灰色じゃない。
もっと重く、粘り気のある、タールのような何かが視界の端から滲み出してくる。
心臓が早鐘を打つ。
僕の空っぽの器の中で、何かがとぐろを巻き始めた。
熱い。
いや、痛い。
美月の身体から抜け落ちたはずの「黄金」の残滓。
それが消滅したのではなく、見えないへその緒を伝って、僕の胸の中へ流れ込んでいたことに気づいた時には、もう遅かった。
第三章 灰色の器
「ぐ、あああああッ!?」
僕は喉の奥から悲鳴を絞り出し、床に膝をついた。
「陽!?」
駆け寄る美月の足音が遠い。
視界が弾け飛び、物理的な質量を持った「情報」が、僕の脳内に雪崩れ込んでくる。
痛い、熱い、苦しい。
――徹夜明けの目の渇き。
――絵の具が混ざり合う瞬間の、背筋が粟立つような快感。
――落選通知を見た時の、内臓が凍りつくような吐き気。
他人の人生が、感情が、泥水のような奔流となって僕の自我を浸食していく。
僕の記憶じゃない。美月の痛みだ。美月の歓喜だ。
(違う、燃え尽きてなんかいない!)
彼女の情熱は死んでいなかった。
行き場を失い、溢れ出した熱量が、一番近くにいた「空っぽの器」である僕に流れ込んでいたんだ。
僕の心臓が、ハンマーで殴られたように跳ねる。
コンパスが火傷しそうなほど発熱している。
わかった。いや、わからされた。
僕の色が「灰色」だった理由。
色が混ざって濁っていたんじゃない。
まだ何色でもなかったからだ。
他人の行き場のない情熱を受け止め、保存し、腐らせないための「保存容器」。
それが、灰崎陽という人間の正体。
「陽、しっかりして! 先生呼んでくる!」
美月が立ち上がろうとする気配。
僕は霞む視界の中で、彼女の手首を死に物狂いで掴んだ。
「待て……っ!」
顔を上げる。
視界の明滅が収束し、世界が研ぎ澄まされた刃物のような鮮明さを取り戻す。
僕の胸元から、猛烈な光が噴き出していた。
灰色じゃない。
あらゆる色を飲み込み、反射し、決して染まることのない、プラチナのような銀色の輝き。
その光の核に、大切に守られた「黄金」の種火が見えた。
「な、に……これ……」
美月が目を見開き、腰を抜かす。
彼女の網膜にも、この光景が焼き付いているのだ。
「俺も知らなかった」
僕は震える手で、熱を持ったコンパスを彼女の胸に向けた。
狂ったように回転していた針が、ピタリと止まる。
針先が、美月の心臓を真っ直ぐに指し示していた。
「お前の情熱は、消えてなんかいない。俺が預かってたんだ」
「預かってた……?」
「一回折れたくらいで、終わりになんかさせてたまるかよ」
僕は立ち上がり、彼女の肩を掴んだ。
掌を通して、僕の中で純度を増した熱が、奔流となって彼女へと逆流していく。
それは単なる返却ではない。
僕というフィルターを通し、不純物を削ぎ落とし、より強靭に練り上げられたエネルギー。
ドクン。
美月の心臓が大きく鳴ったのが聞こえた。
彼女の虚ろだった瞳に、色が戻る。
かつての暴力的で不安定な黄金ではない。
夜明け前の空のような、静謐で、しかし何物にも侵されない、透き通った暁色(あかつきいろ)。
「……あたたかい」
美月が涙を溢れさせながら、自分の胸を強く抱きしめた。
指先の震えが止まっていく。
「聞こえるよ、陽。……描きたい色が、頭の中で爆発してる」
最終章 光の番人
完全に陽が落ちた美術室。
頼りない街灯の明かりだけが、窓から差し込んでいる。
美月はキャンバスの前に立っていた。
手にはパレットナイフ。
迷いなく振り上げられたその腕から、暁色の光が燐光のように舞い散る。
ザッ、と鋭い音が静寂を切り裂いた。
真っ白だった布に、鮮烈な「意志」が刻まれる。
その背中は、以前よりもずっと大きく、頼もしく見えた。
僕は壁に寄りかかり、その様子を眺めながら、ポケットの中で冷え切ったコンパスを弄ぶ。
錆びついた針は、また僕の心臓を指していた。
けれど、その先端は微かに発光し、暗闇の中で蛍のような淡い明かりを灯している。
僕の胸の光は、再び静かな灰色に戻っていた。
けれど、もう空虚だとは思わない。
この灰色は、何もない色じゃない。
これから出会う誰かの、行き場をなくした情熱を受け止めるための、準備の色だ。
「陽、見て」
美月が振り返る。顔中に絵の具をつけ、子供のように笑っていた。
キャンバスの上では、まだ形を成さない色が、生命のスープのように渦巻いている。
「これ、陽の色だよ」
彼女が指差した絵の具は、全ての光を吸い込み、優しく照り返すような銀色だった。
「ありがとう。……私の、一番のファン」
「……バカ言え」
照れ隠しに視線を逸らすと、灰色の奥底がじんわりと熱を持った。
共鳴しているのだ。彼女の新しい情熱と、僕の器が。
僕はコンパスの蓋を、パチンと閉じた。
僕には自分だけの物語はないかもしれない。
世界を変えるような大それた夢も、身を焦がすような恋もないかもしれない。
それでも。
誰かの消えかけた火を掌で囲い、嵐が過ぎるまで守り抜くことができるなら。
この「灰色の光」も、そう悪くはない。
「最高の絵になりそうだな」
「うん。……絶対になるよ」
終わらない青春のただ中で、僕たちは共犯者のように笑い合った。
ポケットの中で、コンパスがチチ、と小さく鳴く。
まるで、次に行くべき場所を探り当てたかのように。